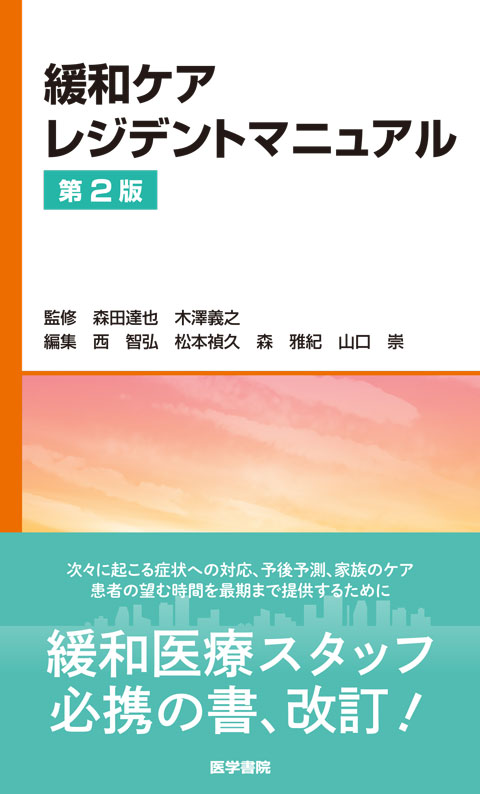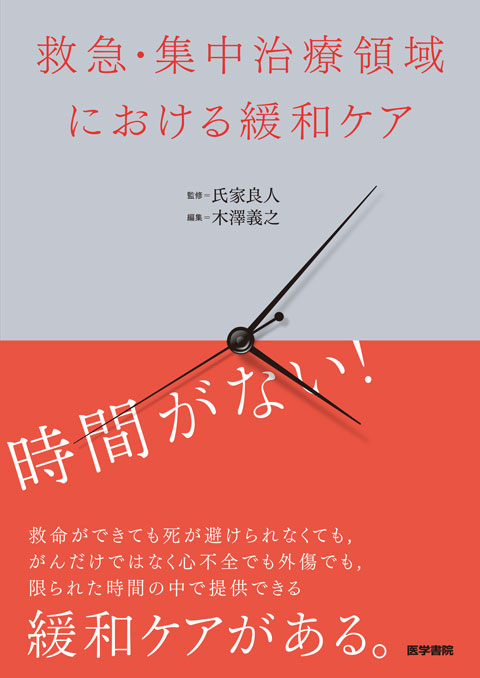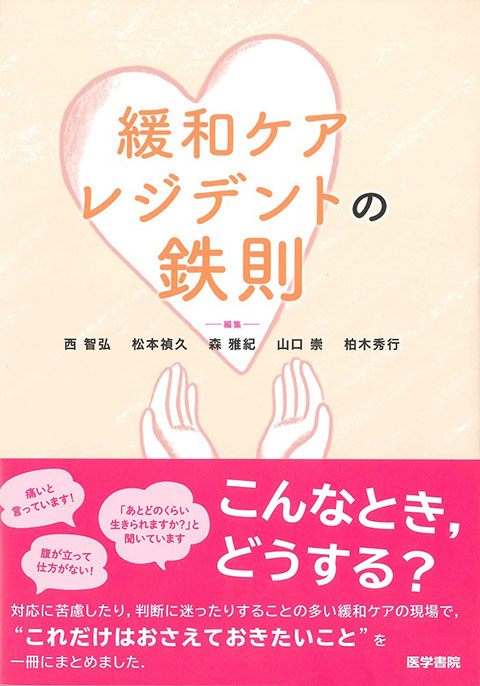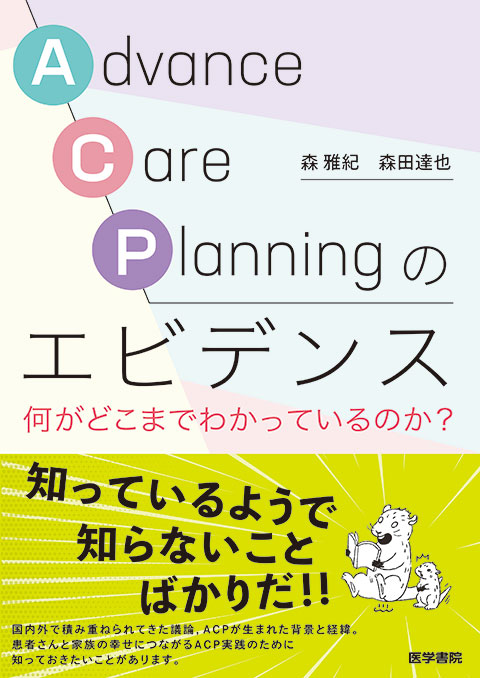踊り場に立つACP,いま何が求められるのか
寄稿 西川満則,紅谷浩之,平岡栄治
2022.11.07 週刊医学界新聞(通常号):第3492号より
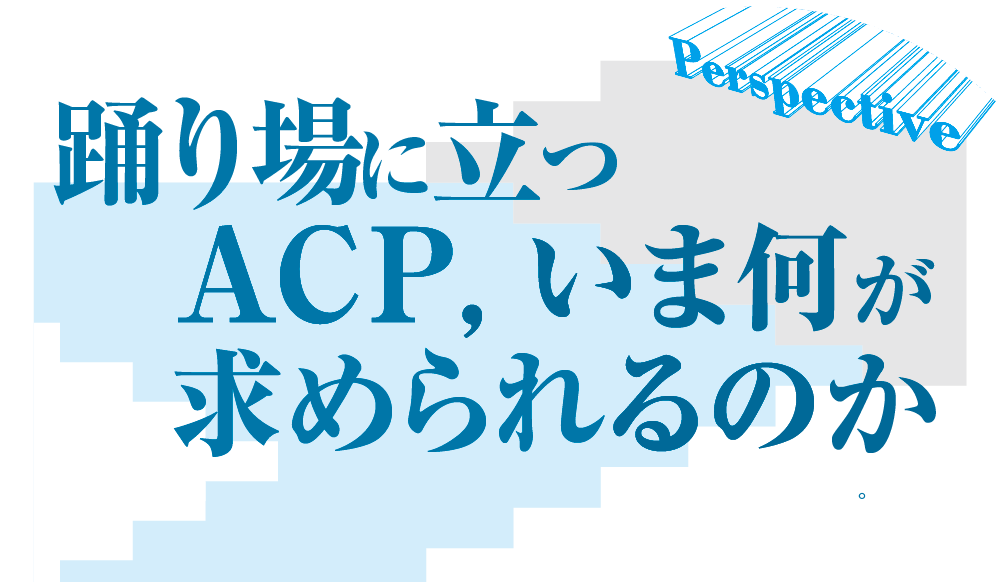
ACP(Advance Care Planning)とは,年齢や病期にかかわらず,本人の価値観や今後受けたい医療・ケアを共有するプロセスである。緩和ケア領域だけに限らず,全ての医療者のACP実践への参画が重要であろう。さまざまな領域において,「踊り場」に立つACPにいま何が求められるのか。老年医療・ケア,在宅医療,救急・集中治療,それぞれの視点から考える(同特集の座談会記事)。
【老年医療・ケア】いま思うこと,これから願うこと
西川 満則氏
国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部医長
第一は,ACPの実践者に本人が含まれているのに,本人の意思が反映されない現状がある。日本老年医学会によるACP提言には,「意思表示が困難な状態の場合もACP開始を考慮すべき」とある。意思決定能力が低下した人のACPにフォーカスすべきと思う。
第二は,家族らに「代弁者」としての役割が期待されるが,代弁者に「代理決定」を強いる傾向にあることが問題だ。自己表現を避けがちな国柄もあり代弁者の役割は大きい。本人の意思決定能力がなくなった後,代理決定する場合もあるが,老年医療・ケアでは,本人が意思決定できる時期から本人の声を代弁するかかわりが望ましい。
第三は,医療・ケア従事者の範囲だ。ACPは医療選択に違いないが,それには人生や生活の中にちりばめられた想いのかけらが影響する。医療職に比し,生活支援職の役割にフォーカスされていない。例えば老年医療・ケアでは,病院ソーシャルワーカーや地域の介護支援専門員の役割が重要だ。
もし,我々がいま階段の「踊り場」にいるなら,次は「緩やかならせん階段」を上るイメージがよい。ACP実践だけが急勾配の直線階段を選んだところで,恩恵は得られない。意思決定能力の低下した人の思いをくみ,代弁者に意思決定を強いらず,人生や生活の中の想いのかけらをキャッチしつなぐ心構え――これらの基本が重要である。日々のケアにACPを含めるのだ。救急医療ではこのようなアプローチが適さないこともあるだろうが,老年医療・ケア領域では,周囲を見渡し緩やかならせん階段を上るイメージでのACP実践を願う。
Morrison氏の主張のように,エンド・オブ・ライフの質がACPで向上するわけではないという見方もあるだろう。確かに,ACPごときで最期に人生を全うできたような気持ちにはなれないと個人的には思う。一方,医療・ケア従事者との関係性,望んだ場所での最期など,人生の最終段階の生活の質にACPはある程度の効果があるとも思う。過度に予見せず,信じるままにACPを実践し,時に我々は「踊り場」でその実践を振り返るのだろう。
【在宅医療】生活と医療の垣根を越えた取り組みと対話を
紅谷 浩之氏
オレンジホーム ケアクリニック理事長
病気を抱えたり悪化したりした時にどのような生き方を望むかを日頃から繰り返し話し合う場として,在宅療養の現場ほどふさわしい場所はないと筆者は考える。住まいには患者の生活があり,人生がある...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。