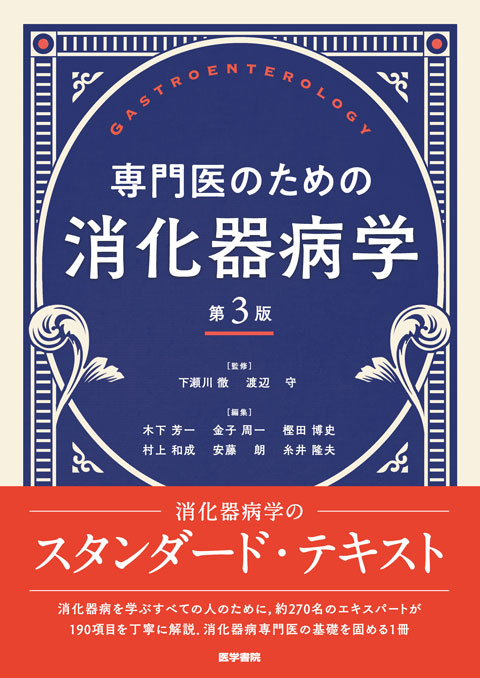MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.02.07 週刊医学界新聞(通常号):第3456号より
《評者》 菊地 臣一 一般財団法人脳神経疾患研究所常任顧問/福島県健康医療対策監
「臨床研究を巡る常識のウソ」に気付かせてくれる
昔日,己の臨床研究デザインの拙さをイヤと言うほど突き付けられたことがありました。臨床研究デザインの基本を学ばなければ世界で闘うことはできないと思うきっかけになった,恥ずかしい,そして悔しい痛切な経験でした。この本を手にした時,わが国の臨床研究の水準もここまできたのかと,万感胸に迫るものがありました。今の私には,わが国における臨床研究の現状がどのくらいかわかりません。したがって,以下に記すことが見当違いであれば見逃してください。
病院に勤務しながら独りで臨床研究をしていた頃の話です。当時,回帰曲線の作成をコンパス,糸,そして手計算でやっていました。自ら理解して実践しないと論文作成は不可能でした。今は,キーボードに触れるだけで,一瞬でできてしまいます。
痛切な経験とは,海外誌へ投稿した際のことです。臨床研究の基本を知らなかったがゆえに,査読者からのコメントが私には全く理解できませんでした。それは,計測値の信頼性,再現性に対する指摘でした。今なら当たり前の話です。海外の友人を頼り,紹介された専門家の助言を受けながら論文に加筆し,何とか受理されました。
本書を通読してみると,目次の半分は己がかつて経験した無知や誤解に基づく勘違いでした。この本は,私のような臨床家にとっては,「臨床研究を巡る常識のウソ」に気付かせてくれます。EBM(Evidence Based Medicine)では,RCT(Randomized Controlled Trial)以外は研究ではないと,臨床家が蓄積してきた資料が否定された時代もありました。そのこともあって,当時,臨床研究デザイン=マニアックな人たちの仕事と,距離を置く空気がありました。「序」で指摘されているように,臨床研究=統計解析ではありません。臨床研究デザインの目的は,第三者に理解してもらうことであって,統計解析はその手段にすぎません。ただし,基本的な知識を持っていないと質の高い臨床研究はできません。「医師が居なくては医療はできない。しかし,医師だけでは医療はできない」という箴言に通じることです。臨床研究デザインとは,臨床研究を行う上での基本的な概念です。一方,近年,EBMの手法自体に批判的な眼が向けられています。「統計は嘘を吐かないが,嘘を吐く人は統計を用いる」という警句がよみがえります。私は,目的と手段がひっくり返って,統計解析がしてあれば正しい結論という風潮があった時代を知っています。それを考えると,この本の刊行は時の流れをも感じさせてくれます。
本書は,通読するのではなく,仕事の合間に一項目ずつ拾って読むことを勧めます。己の臨床研究の計画を見直すきっかけになります。そして,キーボードで一瞬で結果を出し,それが臨床研究だという思い込みに疑問が生まれます。有名雑誌に掲載される論文の中には,素人の私からみても,解析手法や有意差の解釈が間違っているものが見受けられます。
まずは,本書を読んで,臨床研究を行う際の基本的な知識を得ることです。それにより,「臨床研究を巡る常識のウソ」に気付きます。買って,読んで損はない本です。
《評者》 吉尾 雅春 千里リハビリテーション病院副院長
脳卒中の歩行障害の専門家に一石を投じる良書
『脳卒中の装具のミカタ』という意味深なタイトルの書籍が出版されました。編者の松田雅弘氏・遠藤正英氏の序文にわざわざ「ミカタ」とカタカナ表記されたその意味が書かれていました。装具の見かた・診かたということに加えて,装具難民の味方になりたいという思いだそうです。装具難民とは,装具が処方された後に適切なフォローがなく,装具の不適合や相談先などに困っている対象者のことを指します。厚生行政の都合で,対象者となる脳卒中者が急性期,回復期,生活期へという展開の中で全く違った病院,施設,およびスタッフたちがかかわることで,十分な連携がとられないがために生じる代表的な社会現象です。その装具難民のミカタになり,卒前教育で装具に関する有意義な講義を受けていないように思える若いセラピストたちのミカタになり,そして今さら聞けないよというベテランのセラピストのミカタになり,さらには装具について学ぶ機会のなかった看護師・介護福祉士・ケアマネジャーらのミカタになりたいという熱い思いで装具の見かたについて著されています。
時流になってきたWeb動画付きで,57のQ&Aを軸に構成されています。脳卒中の病態や歩行,装具の基礎知識,装具調整の基礎知識,装具と運動療法,体幹装具・上肢装具と歩行との関係,入院中の装具の管理とその指導の方法,装具療法に必要な連携,生活期における装具,各病期における装具療法代表例についてまとめられ,具体的なQuestionに対してAnswerおよび解説,ポイントが述べられています。さらには随所にあるMEMOやcolumnが目を引きます。19人に及ぶ執筆者は装具に長けたそうそうたる顔ぶれで,実際の場面で多くの問題に取り組んでいる理学療法士・義肢装具士だからこそ解説できる内容です。初学者に限らず,多くの人たちに目を通していただきたい書籍です。
あえて注文をつけさせていただくとすると,装具になじんでいない人たちを対象にする書籍だからこそ,具体的な写真をより大きくしていただくとよかったのではないかと思いました。モノクロの写真ですから,なじんでいない人たちにはもしかしたら判断しにくいかもしれません。思いっきり文字を少なくしてでも,その工夫があってもよかったかもしれません。
対象者に適切な装具を選択できない理由の一つに,そもそも医師やセラピストが個々の脳卒中者の病態や歩行障害を正しく理解,あるいは把握できていない現状があると私は考えています。すなわち適切な教育がなされていないということになります。そういう意味では脳卒中者の歩行障害にかかわる私たち専門家こそが難民といえるのではないでしょうか。このことを考えますと,私たちが抱えているこの根本的な課題に本書『脳卒中の装具のミカタ』は大きな一石を投じてくれたと思っています。
《評者》 寺野 彰 学校法人獨協学園名誉理事長/獨協医大名誉学長
消化器病学論文の集大成
『専門医のための消化器病学 第3版』が,2021年11月に上梓された。8年ぶりの改訂である。2005年4月に,小俣政男教授,千葉勉教授によって編さんされた初版は,「専門医」を対象にしたものであったから,初めからかなり高度な内容をめざしていた。その初心は,第2版そして今回の第3版へと受け継がれ,いわば消化器病学論文の集大成とでもいうべき記述で構成されている。
執筆者も若手消化器病学者を核として,われわれのようないわば高齢消化器病学者の名はほとんど見られず,新鮮な雰囲気を醸し出している。構成も,通常見られる全体としての総論,各論ではなく,いきなり食道疾患から入っている。そのいわば各論の中で,総...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

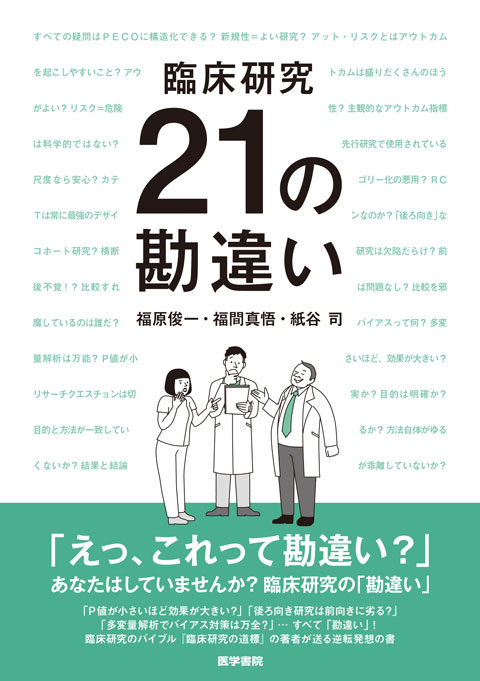
![脳卒中の装具のミカタ[Web動画付]](/application/files/1016/3454/1444/108356.jpg)