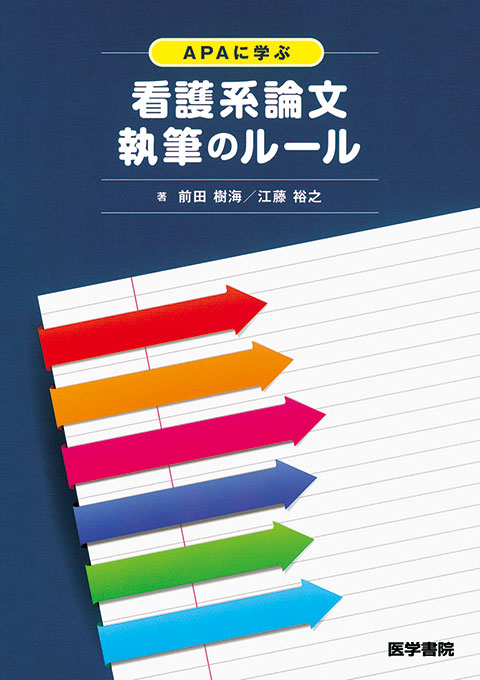誰も教えてくれなかったオーサーシップ
[第2回] 不適切なオーサーシップをめぐる話題
連載 前田樹海
2021.12.13 週刊医学界新聞(看護号):第3449号より
考えてみよう
その研究は学部生の何気ないアイデアから生まれた。私は指導教員として学生のアイデアを形にすべく,さまざまな助言を提供した。データ収集とスクリーニングはもっぱら学生が行い,分析とデータの解釈は学生と十分にディスカッションしながら進めた。論文のドラフトは学生が執筆し,私はそのドラフトを推敲した。投稿先は研究テーマに適したX看護学会誌に決め,執筆要領に沿って原稿が作成された。学生からは,その学会の会員になるための承諾も得ていた。しかし,学生が申請手続きをしたところ,「会則により,学部学生は本学会の会員になれない」との返答を得た。そこでやむなく自分が著者として投稿し,学生の名前は謝辞の中で述べることにした。この判断は適切だろうか?
連載第1回(3430号)では,論文投稿に際して「不適切なオーサーシップ」というものが存在することを紹介しました。では,具体的にどのような例が「不適切」と評価されるのでしょうか? 実例を基に考えます。
文科省は,『研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン』(以下,ガイドライン)に基づき,科学研究費等で行われた研究活動に関して,研究機関から特定不正行為(捏造,改ざん,盗用)の報告を受けた時は,ウェブサイトで公表しています。本来,「不適切なオーサーシップ」は特定不正行為には分類されていないものの,研究機関から報告を受ければ公開するスタンスです。
同サイトには2015年から本稿執筆時点までに64件の特定不正行為が挙げられており,うち「不適切なオーサーシップ」について言及された事案は10件ありました。その中から主なものを以下に抜粋します。
①論文作成に全くかかわっていない研究メンバーを著者に加えた
②研究に全く関与していない他者を著者に加えた
③研究を実質的に行い本来著者となるべき者が著者から外れていた
オーサーシップの基準が,当該学問コミュニティや学会のポリシーに依存する点は第1回で述べた通りです。①は,それらの基準に照らしてオーサーシップが認められないケースです。対して②は研究に関与していない時点で,学問領域にかかわらず「アウト」と言えましょう。反対に③は,本来オーサーシップを有する者が著者として名を連ねていないケースで,これも不適切とされています。
このように「不適切なオーサーシップ」は,オーサーシップを持たない者が著者になっている場合(①,②)と,オーサーシップを持つ者が著者になっていない場合(③)の2種類に大別されます。前者は「ギフト(ゲスト)オーサーシップ」,後者は「ゴーストオーサーシップ」と称されます。本事例の学生は後者に当たります。
研究の系譜を狂わせてしまう危険性
そもそも,どうして「不適切なオーサーシップ」はいけないのでしょう。ガイドラインには「科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる」としかその理由が明記されていません。しかし不適切なオーサーシップが「正常な科学的コミュニケーションを妨げる」メカニズムについて,僕の頭ではうまく像を結ばないのです。そこで,この論理を著作物のアナロジーで考えてみます。
文学作品には著者がいます。多くの作品は1人の作家によって執筆されているため,「誰がこの作品の著者か」と悩むことはほぼありません。一方で研究は共同制作をする場合が多く,論文の著者の線引きが難しい。そのための基準がオーサーシップとなります。もちろん,文学作品においても専門家や友人等からの聞き取りを基に作品を構築する作家はいますが,それらの情報提供者が共著者になることはありません。情報提供者の語り,すなわちデータではなく,データ(材料)を情報(作品)に変換する人物こそが著者として認められるのです。
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。