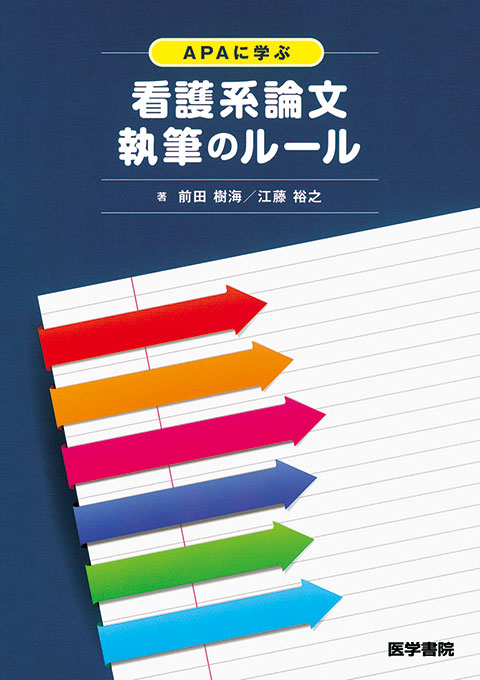誰も教えてくれなかったオーサーシップ
[第1回] 日本のオーサーシップ基準の現状
連載 前田 樹海
2021.07.26 週刊医学界新聞(看護号):第3430号より
考えてみよう
現任教育の一環で,看護経験2~3年の同僚と共に3人で看護研究を行った。時間の制約もある中で研究を進めるのは大変だったが,入職時から自分が感じていた疑問に答える可能性の高い結論を導くことができたので,全国的な学会で発表することにした。
ところが,学術集会の演題登録の直前,病棟師長から「その著者リストに私の名前も入れておいて」と言われた。師長は研究に必要な資材を経費で落としてくれたり,演題登録に必要な抄録の推敲をしてくれたりしたものの,計画から学会発表までずっと研究にかかわってきたのはメンバーの3人だけなので合点がいかない。この場合,師長は共著者に当たるのだろうか?
看護研究を含むあらゆる研究は1人で遂行できるわけではなく,多くの人の協力のもと達成されます。研究成果を学会発表や論文執筆などの形で公表する際には,執筆者のほか研究協力者たちを「共著者」として記載します。しかし実際には「研究にはかかわっていないけどあの人の名前も共著者に入れておこう」「病院の規則でラストオーサーには必ず〇〇の名前を入れなさいと言われた」といった事例に心当たりがある読者も多いのではないでしょうか。共著者やその記載の順番は,成果を発表するに当たり軽視されがちですが,実は落とし穴もあるのです。
このように,「誰が共著者にふさわしいのか」を「オーサーシップ(著者資格)」と言います。そこで本連載では,看護研究を行う皆さんが迷いやすい事例を取り上げ,オーサーシップの落とし穴や適切なオーサーシップの在り方を考えます。
「不適切なオーサーシップ」の位置付け
僕は四半世紀以上,看護系大学の教員として研究活動に携わっています。四半世紀なんて,人類の研究活動の歴史の中ではほんの一瞬に過ぎません。それでもこの短い期間の中で,研究倫理審査委員会による研究計画書の審査,研究倫理を学ぶためのeラーニングの受講,利益相反の申告等々,研究に必要な手続きが増えました。正直言って面倒なものばかりです。それらの手続きのほとんどは,過去のごく一部の「悪い研究者」による不正行為のしわ寄せですから少々納得できない部分もあります。ただ,そういった「悪い研究者」のおかげで,不正を防止するためのさまざまな環境や仕組みが整備されたと考えれば,ある意味社会貢献度は大きいと言えるのかもしれません。
さて,研究活動における不正行為の定義は,国が2014年に発行した『研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン』(以下,ガイドライン)に次の通り記載されています。
得られたデータや結果の捏造,改ざん,及び他者の研究成果等の盗用が,不正行為に該当する。このほか,他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿,論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになってきている。
中でも,捏造(fabrication)・改ざん(falsification)・盗用(plagiarism)は,特定不正行為と呼ばれていて,研究不正行為の中でも特に悪質とされています。これらの特定不正行為は,頭文字をとって「FFP」と呼ばれる場合もあります。
ガイドライン発行当時に「不正行為として認識されるようになってきてい」たとされる,特定不正行為以外の研究不正は,「好ましくない研究行為 (Questionable Research Practice:QRP)」と呼ばれています。本稿で取り扱うオーサーシップにかかわる不正は,特定不正行為ではなくQRPとして分類されます。
わが国のガイドラインを読み解いてわかること
では本事例の病棟師長にオーサーシップはあるのでしょうか。
ガイドラインによれば「論文著作者が適正...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
前田 樹海(まえだ・じゅかい)氏 東京有明医療大学看護学部 看護情報・管理学 教授
1989年東大医学部保健学科卒業後,ソニー株式会社,長野県看護大講師,同大准教授を経て,2009年より現職。04年長野県看護大大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。共著に『APAに学ぶ看護系論文執筆のルール』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。