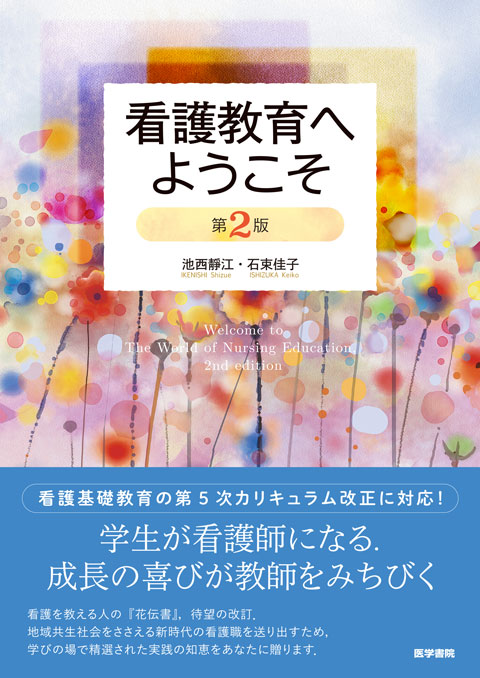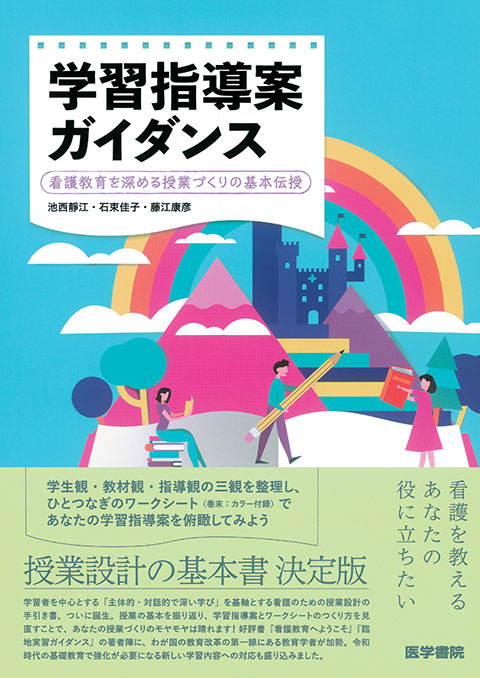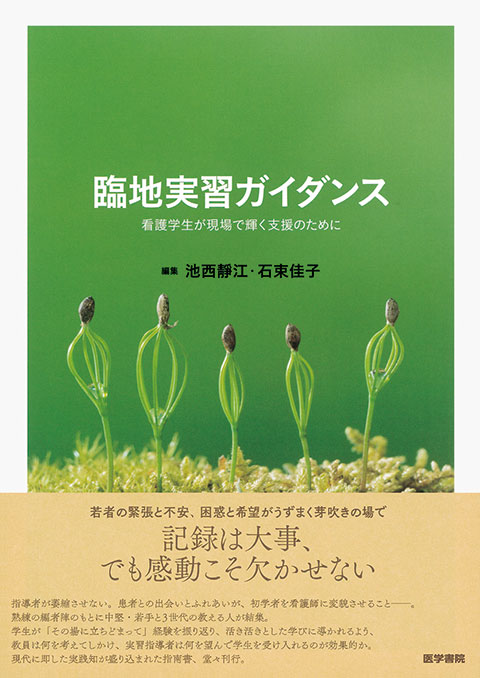コロナ禍での看護教員の奮闘に迫る
対談・座談会 池西 靜江,西村 礼子
2021.11.22 週刊医学界新聞(看護号):第3446号より

池西 2020年1月に端を発する国内のコロナ禍により,臨床現場はもちろん,基礎教育の現場も様変わりしました。最大の変化はICT教育の急速な導入でしょう。日本看護学校協議会が休校時の対応に関する計画について2020年4月末に調査をしたところ,65.2%の学校がオンライン授業を予定していると回答しました3)。私自身,コロナ禍で初めてICTの活用を積極的に考え始めました。
西村先生はコロナ禍以前より基礎教育の場でのICT活用を進められていますよね。導入を検討する養成所から多数の相談があったのではないですか。
西村 ええ。2009年頃から学習管理システムのLMS(Learning Management System,註1)を活用した教育を行ってきたことから,ICT活用時の困り事に関して多くの看護教員から相談を受けました。内容を詳しく聞いてみると,操作方法といったコンピューターリテラシーに関する単純な相談ではなく,「対面で行っていた授業をいかに構造化してシステムに当てはめるか」に苦戦されているように見えました。
池西 私も同じように不安を抱いた1人です。初めはうまく行えるのかと疑問でした。しかしいざやってみると,取り組みたかった授業に近い形になったことで,教育の幅が広がったと感じましたね。
「臨地実習でしかできないこと」とは何か
池西 コロナ禍での基礎教育の最大の課題は,臨地実習をどう実施すべきかという点でした。臨床現場での体験は何物にも代えがたい経験ではあるものの,感染拡大の状況に鑑み臨地実習自体の中止や日程短縮が続々と決まる中で,学生と学校をつないだり,学生と病院をつないだりするオンライン実習が,試行錯誤しながらも2020年夏頃から徐々に取り入れられていきました。
そうした流れの中で,私が当時会長を務めていた日本看護学校協議会でも,オンライン実習を前提とした学習補完教材(医学書院「eナーストレーナー」)を開発することになりました。開発に取り掛かった当時は,9月からの臨地実習を実施できるかどうかが不透明な状況であったため,臨地実習の形に少しでも近付けられる教材を作ろうと皆必死でした。現場での経験を積めないままに卒業していくのはあまりにもかわいそうだと思ったからです。
西村 私もオンライン実習案を作成した当初は手探り状態でした。前例がないことは教員にとって大きな負担です。そのため,「私は実習期間中,この目標に対してここまでの到達を期待しているのですが,内容はどうですか?」と,学生や担当教員,模擬患者さんと率直に話し合う機会を設けて,改善をし続けました。
池西 西村先生の施設ではどのような実習形式となったのでしょうか。
西村 当校の臨地実習は,期間短縮や午前中だけの時間短縮,全面中止となるケースもありました。それゆえ実施に際して最も考えたのは,「限られた臨地実習期間で何を学んでもらいたいか。臨地実習でしか学べないことと,オンライン実習でも学べることは何か」です。オンライン実習で代替できないのは,患者さんの背景にあるナラティブな部分を自身の五感を用いて引き出すことなのではと考えました。そうした考えを基に臨地実習と代替実習案を作成し,学内のシミュレーション等で補える部分は代替をしていったのです。
池西 教材開発をする際,私も同じことを考えました。やはり患者さんとの対話でしか得られない経験が多分にあるはずだと。これまでは,臨地実習に行けることが当たり前だったからこそ,「臨床現場でなければできないことは何か」との議論が抜け落ちていた気がします。コロナ禍を機に,改めて検討する機会ができたのは,不幸中の幸いだったのかもしれません。臨地実習の意義を再認識しました。
看護職との密な連携が教材のブラッシュアップにつながる
池西 では反対に,シミュレーション教育をはじめとするオンライン実習の強みはどんな点にあると考えますか。
西村 卒業時到達目標に基づく科目としての到達目標に対して,①安心・安全かつ忠実性がコントロールされた環境で繰り返し取り組めること,②診断的・形成的・総括的評価ができること,③レディネスの担保ができること,という点でしょうか。
例えば,脳梗塞患者さんの再梗塞を想定し「この部分に気付いてほしい」と考えた時,その部分を切り取って教材化することで何度も復習できます。これは患者さんの状態をコントロールできない臨地実習では経験しにくいと言えます。さらに,「今,何を考えてその行動に至ったのか」という思考過程と行動の言語化も併せて確認できることは大きなメリットでしょう。
池西 できるまで取り組んだ経験は,卒業後に自信となるはずですよね。
西村 そうだと思います。またコロナ禍では,臨地実習の中止を案じて看護職の方が教材開発に積極的に協力してくださったことがとてもありがたかったです。もちろん授業の目標・評価を作るのは教員なのですが,「この部分は教科書にはAと書いてありますが,実践ではBというケースも多いから,教材に取り入れたほうがいいかもしれません」と数多くのアドバイスをいただきました。教員だけで作成すると,実習での学びを促す教材なのにもかかわらず臨床の場での看護実践とはどうしても異なる部分が出てしまうために,この差を埋める良い教材ができたと考えています。
池西 確かにコロナ禍になって,現場の看護職の方と協働して教材を開発するという話をよく聞きます。在宅看護の教材を作成する際には,訪問看護師の方が現場を撮影して学生たち...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

池西 靜江(いけにし・しづえ)氏 Office Kyo-Shien代表
国立京都病院附属看護助産学院(当時),京都府立保健婦専門学校(現・京都府医大)卒。国立京都病院での臨床経験後,京都府医師会看護専門学校,(専)京都中央看護保健大学校に勤務。37年間の看護教員生活を経て,2013年にOffice Kyo-Shien開設。鹿児島医療技術専門学校学科顧問。専任教員・教務主任養成講習会の講義,看護教員向けの講演,看護学校運営のアドバイス,看護学校での講義などの活動に携わる。『看護教育へようこそ(第2版)』『学習指導案ガイダンス』(いずれも医学書院)など著書多数。前日本看護学校協議会会長。

西村 礼子(にしむら・あやこ)氏 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科准教授
名大医学部保健学科看護学専攻卒。東京医歯大大学院保健衛生学研究科博士前期課程・博士後期課程修了。博士(看護学)。順大附属順天堂医院で看護師として勤務。東京医歯大大学院保健衛生学研究科非常勤,東京医大医学部看護学科助教を経て,2019年より現職。『看護教育』誌で「看護教員のICT活用教育力UP講座」を12回にわたって連載するなど,ICTを活用した授業設計や学習効果について全国に発信を行う。現在は,文科省「大学教育のデジタライゼーション・イニシアティブ(スキームD)」にて「看護実践能力(コンピテンシー)基盤型システムによる学習・教育の構造・過程・成果の可視化」をめざす。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。