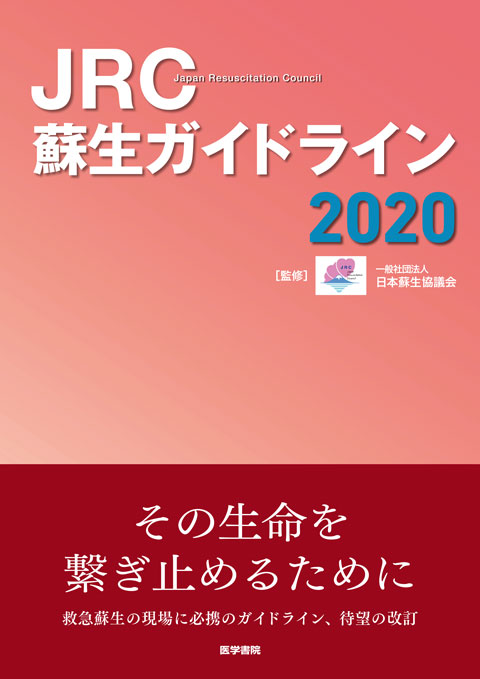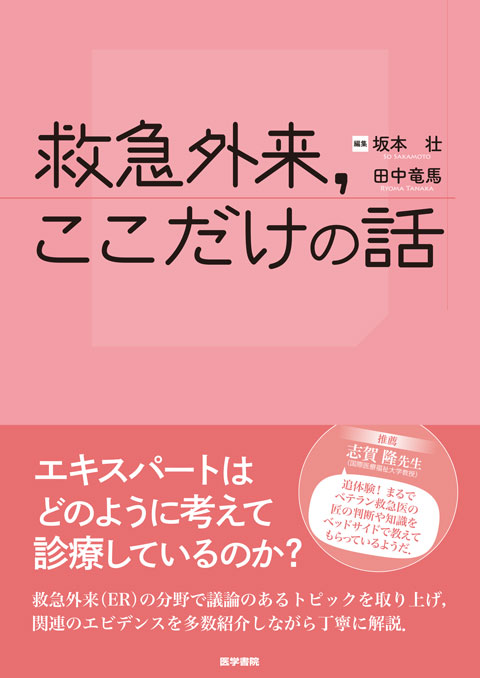MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.11.15 週刊医学界新聞(通常号):第3445号より
《評者》 小林 欣夫 千葉大大学院教授・循環器内科学
心肺蘇生のバイブル
心肺蘇生は待ったなしです。心肺蘇生の開始が1分遅れるごとに救命率が10%低下すると報告されています。このために的確な心肺蘇生を行い,命を救わなくてはなりません。しかしながら,それだけでは不十分です。命を救うとともに,高次脳機能障害などを起こさせない,またはなるべく軽くしなくてはなりません。このために心肺蘇生を行う人の技量・知識が非常に重要です。
日本蘇生協議会(JRC)は,医学系の18の学術団体と救急・蘇生教育を推進する関連5団体の計23団体で構成されている救急蘇生科学に関するプロフェッショナル集団です。2002年に設立され,心肺蘇生法に関する世界的なガイドライン作成の日本の窓口として,国際蘇生連絡委員会に参画しています。国際蘇生連絡委員会は蘇生関連のトピックに関してエビデンスを網羅的に検索・解析し,国際的なガイドライン作成方法であるGRADEシステムを用いてガイドラインを作成しており,これは国際標準となっています。JRCもこれに基づいて2010年,2015年にガイドラインを作成し,この度5年ぶりの改訂版の出版となりました。
一次救命処置(BLS),二次救命処置(ALS)はもちろんのこと,一般の医療者においてはなじみの少ない新生児,小児,妊産婦の蘇生も詳細に記されています。蘇生領域で非常に重要な急性冠症候群,脳神経蘇生の項目も充実しています。また,ファーストエイド,普及・教育のための方策,さらには昨今問題となっている新型コロナウイルス感染症への対策まで,蘇生領域の全てが網羅されています。
本書は一目でわかる非常に実用的な蘇生のアルゴリズムが,それぞれの状況ごとに示され,アルゴリズム内の項目ごとに詳細な解説がなされています。また,臨床の現場で問題となることがクリニカルクエスチョンとして提示され,これに対する推奨と提案が記載され,引き続きエビデンス,JRCの見解,今後の課題が示されています。救急蘇生の全てが理解できる,最新の国際標準の蘇生ガイドラインです。
本書は蘇生のバイブルとして,初学者からエキスパートまで幅広く役立つものであります。わが国における救命率の向上のために,そして一般市民,医療関係者における心肺蘇生の標準化・普及啓発のために,多くの方に本書を活用していただけることを望んでいます。
-

ソーシャルマーケティング:行動変容の科学とアート 健康,安全,環境保護,省資源分野等への応用の最前線
- 木原 雅子,小林 英雄,加治 正行,木原 正博 訳
-
B5・頁552
定価:7,480円(本体6,800円+税10%) MEDSi
https://www.medsi.co.jp
《評者》 三石 祥子 国際高等研究所・研究支援部長
個人の行動変容が社会を変える,21世紀の学問の力
訳者の木原正博先生から本書の存在を教わったとき,なぜ医学者の木原先生がソーシャルマーケティングに注目されるのだろう,と不思議であった。先生は1990年代前半からエイズの疫学研究に本格的に取り組まれた。当時のエイズ疫学は,どう予防するかが鋭く問われており,予防の方法論を探っていくうちに,ソーシャルマーケティングに行きついたという。
本書の著者であるPhilip Kotlerはマーケティングの世界的大家であり,1970年代に「ソーシャルマーケティング」という言葉とアプローチを提唱した。その後,ソーシャルマーケティングはその実用性の高さから,さまざまな分野に応用が広がった。同時に,定義,内容,用語が多様化することとなり,2010年代前半から,国際ソーシャルマーケティング協会などによって,標準化が行われてきた。Kotlerはその中心的役割を果たした人物でもある。
ソーシャルマーケティングは,商業マーケティングの概念と技術を社会的課題に応用し,個人と社会の利益に資する行動変容を導くアプローチのことである。
このアプローチは,生態学的視点と人の行動原理を踏まえた系統的介入プログラムの企画・実施・評価により実践される。本書で詳しく解説される「10ステップ」は,新たなプロジェクトの構築や既存のプロジェクトの改善に役立つ,一般性の高いアプローチである。
それゆえ,ソーシャルマーケティングは,健康,安全,環境保護,社会貢献など,人の行動がかかわるあらゆる社会的課題に応用されている。健康分野においては,米国の「Healthy People 2020」の中で,ヘルスプロモーションの中核的方法論とされている。わが国でも,厚生労働省の「健康日本21」の総論でその重要性が言及されている。
ソーシャルマーケティングには,一貫して,オーディエンス中心という考え方が存在する。木原先生はソーシャルマーケティングの特徴を,「通常の」プログラム策定のアプローチを「逆さま」にしたボトムアップ(=オーディエンス中心主義)のアプローチで,そこから論理的に立ち上がる体系のこと,と表現する。
本書に,健康信念モデル,行動段階理論,イノベーション拡散理論,行動経済学,ナッジ,仕掛け学などの行動に関する理論やモデルが紹介されているのは,ソーシャルマーケティングが「オーディエンスとその行動」の理解に重きを置いているゆえんであろう。
本書は,多数の実践事例と,行動変容を起こすための個人や集団の理解の方法に,多くのページが割かれている。「心」と「感情」を持つ人間を学問として理解すること。個人から社会までを視界に入れた,実践の学問であり続けること。500ページ以上にわたる本書には,この二つを根気強く追究する学問の力が宿っている。
《評者》 福田 龍将 虎の門病院救急科部長
カリスマ指導医から指導を受けたかのような体験を
救急外来診療をしていると,いつになっても臨床的疑問が尽きることはありません。その度に最新の知見を調べる余裕があればよいですが,現実には多忙を極める救急外来で一つひとつの疑問に向き合う時間を十分には取れないことがほとんどです。本書はそのような状況で,われわれの強い味方になる一冊です。「ここだけの話」というタイトルからは,救急診療におけるマニアックな部分を追求したものを想像されるかもしれませんが,実際には基本的な部分からcontroversialな部分まで幅広い臨床的疑問が扱われています。ばらばらの疑問ではなく,系統立てて構成が行われているため,教科書のように使いながら各病態や疾患についての最新の知識を深めることも可能な一冊となっています。
本書の編集を担当された坂本壮先生・田中竜馬先生は,これまでにも救急・集中治療領域でベストセラーとなるような名著を数多く出版されてきましたが,本書も間違いなくお二人の代表作の一つになることと思います。私は以前,シリーズ第1作目となる田中竜馬先生の編集による『集中治療,ここだけの話』で,私自身が専門とする蘇生に関する項目の執筆を担当させていただきましたが,その編集過程において妥協を許さず読者にとってよりよいものを提供するための努力を惜しまない編集者の姿勢を垣間見る機会がありました。今回の『救急外来,ここだけの話』でもお二人の編集の下,執筆陣には各領域のエキスパ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。