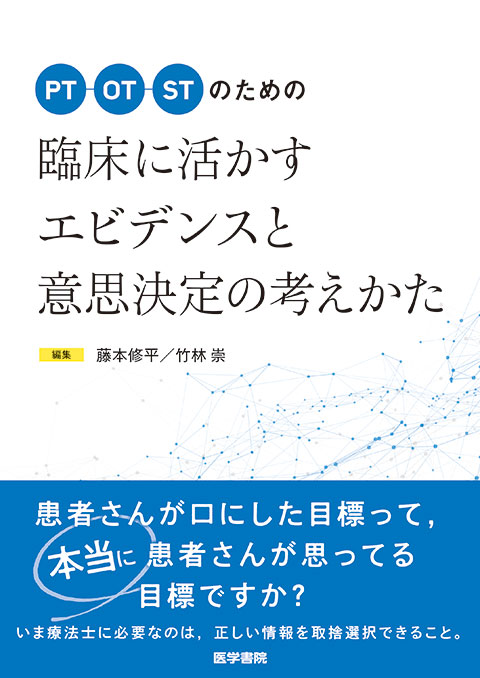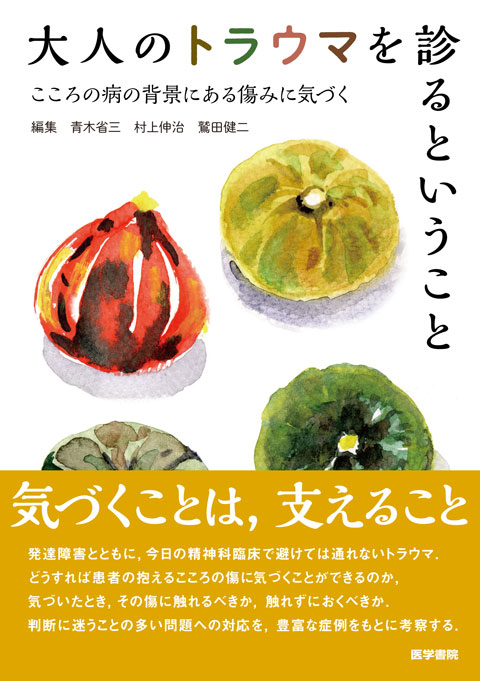MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.05.10 週刊医学界新聞(通常号):第3419号より
《評者》 森岡 周 畿央大教授・理学療法学
情報の取捨選択能力の育成に不可欠な書
情報入手から情報共有時代へ。これは科学のパラダイム転換でもある。それは情報を惜しげもなく公開し,多角的知識を総動員し,情報改訂することが人類の発展につながると判断したからである。しかし,それは共有する者同士の情報取捨選択能力とモラルに依存するため危険性と共存している。それらを持ち得ない場合,誤情報が共有され社会混乱を招いてしまう。
情報入手能力と取捨選択能力は異なる。後者はクリティカルな視点が必要である。つまり研究能力そのものであり,発信内容に批判的吟味を加える認知能力が求められる。生命や健康に携わる職種においては,その能力は極めて重要である。PT/OT/ST(専門職)の養成課程においては,実践を中心にカリキュラム構成されている。上記視点の重要さを説く科目が欠落している学校も少なくない。情報氾濫社会において,医療教育の一丁目一番地は情報取捨選択能力の育成であると思う。
本書は4章(第1章 エビデンス,第2章 患者の価値観,第3章 目標設定とコミュニケーション,第4章 ケース)で構成されている。第1,2章を冒頭に配置したところに意味がある。両者は一見矛盾するが,最適な医療実践には疫学によって得られた一般論(エビデンス),患者の価値観・希望,患者の個別性・多様性,環境を包含し,それらに個人の経験による技能・直感的判断力を合わせる過程が求められる。これがEBMであり,エビデンスのみから判断しない。多くの専門職は誤解し,誤解により結局は旧体系の個人の経験・技能による判断に退行している傾向がある。本書は読めばその誤解が解けるであろう。一方,百花繚乱のように介入法が開発され,その支持情報ばかりを集め,反証内容を無視するバイアス情報が講習会で提示されていることがある。3た論法(使った,治った,効いた)が医療においてつきまとい,(偽)相関であるにもかかわらず,ただちに因果とみなすミスリーディングが生まれる。中間・交絡・修飾因子の理解なくして手段を思慮深く決定できない。本書はその意味を理解させてくれる。
本書はWeb情報の信憑を考える上でSEOまで踏み込み記述している。現代では,“ググる”という造語があるように検察エンジンで調べることが反射化されている。本書は専門書ではあるもののそのことに踏み込んだことは,平均年齢が低い専門職に対する警告ととらえることができる。さらに意思決定の合理性について記述しているところに意味がある。行動経済学では当たり前となった感情が意思決定に入り込むことを専門職に向けて平易に解説している点は価値がある。
最終章はケース供覧となっており,どのような手続きによって意思決定するか身近にとらえることができる。この章については今後改訂されることで,それまでの総論との整合性を意識されたいと願っている。
いずれにしても,Society5.0において,医療者はAIと共存し意思決定することが求められる。まずは本書を読み,すぐそこの未来に備えていただきたい。
《評者》 小林 桜児 神奈川県立精神医療センター副院長/医療局長
症状の背景に隠れたトラウマへの気付きを促す一冊
「トラウマ」という用語は,ある種のリトマス試験紙である。精神科や臨床心理に従事している者は,その用語に対する反応によって2種類に大別される。精神症状を遺伝負因や神経伝達物質の異常から説明することを好む臨床家は,トラウマと聞くと「あまり触ってはならないパンドラの箱」といった苦手意識を感じるか,あるいは「自己責任を取らずに何でも周囲の人や環境のせいにするための口実」,などといった嫌悪感を隠し切れないかもしれない。他方,精神分析や力動的精神医学の影響を受けた臨床家は「トラウマ」を幅広く解釈し,診断や治療上不可欠な要素,と主張するであろう。
かくもトラウマという用語は,人間に対極的な反応を引き起こす。女性の性的トラウマから研究を始めたはずのFreud自身,やがてトラウマ体験は本人の空想,と解釈するに至った。第一次世界大戦中に戦争神経症を発症した兵士たちは臆病者とみなされ,イギリスの精神科医Lewis Yeallandは電気ショックで治療しようとした。トラウマ体験が心の病を引き起こすことを私たちが認めることが難しい理由の一つは,それを認めてしまうと,患者は「炭鉱のカナリア」に過ぎず,患者を取り巻く他者が,社会が,つまりはその社会に属する私たち一人ひとりが変わらなければならない,という現実と向き合うことになってしまうからではないだろうか。
本書はトラウマに関する疾病教育的な解説から始まり,その後は多彩で豊富な症例が次々と提示されて,症状の背後に隠れたトラウマ体験への気付きを読者に促していく。私たちは気付かなければ,変わることができない。狭義のPTSDにとどまらず,知的障害から統合失調症,そして認知症に至るまで,トラウマ体験が精神障害全般に与える影響について,専門家でなくともわかりやすい言葉で解説されている。語り口は優しく謙虚で,病状の理解の仕方も極端に心因に寄り過ぎることなく,非常にバランスが取れている。さらに患者を取り巻く家族や援助者たちへの目配りも忘れず,豊富な経験に裏付けされた助言も随所にちりばめられている。トラウマという用語に苦手意識や懐疑心を抱えている一般の方々や第一線の臨床家に,特に本書をお薦めしたい。
2012年にはハーバード大児童発達センターのShonkoffらがtoxic stressの概念を発表し,生育環境におけるトラウマが子どもの発達に与える影響について,一段と注目が集まっている。さらに近年エピジェネティクスの研究が進んで遺伝子の発現が環境因子によって変わり得ることも次々と明らかになり,もはやnatureとnurtureは対立用語ではなくなった。今後はトラウマが精神症状を生み出す神経生物学的機序も,より精緻に語られるようになっていくであろう。そのような時代の分水嶺に,トラウマという視点の大...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。