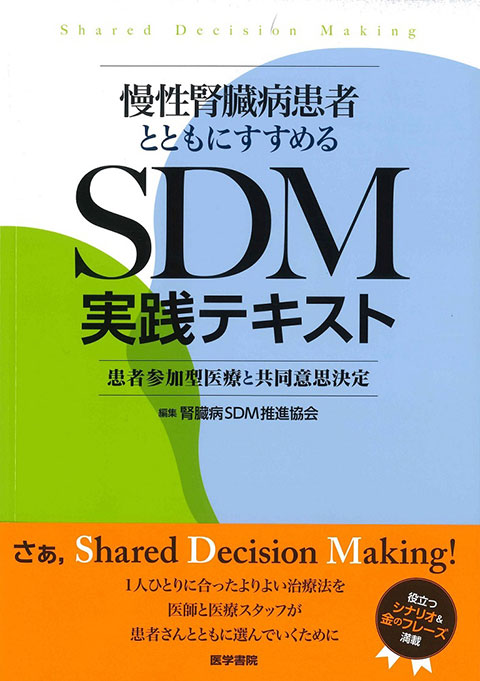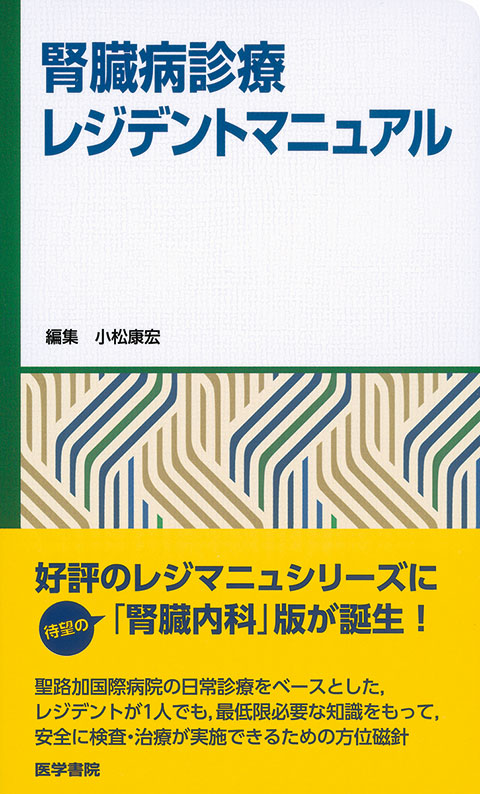効果的なSDM実践のために
小松 康宏氏に聞く
インタビュー
2021.01.18 週刊医学界新聞(通常号):第3404号より
共同意思決定(Shared Decision Making:SDM)は「New England Journal of Medicine」誌に取り上げられた2012年1)以降,その役割が広く注目されるようになった。しかし,医師と患者双方が情報を共有しながら治療方針を決定する考え方であるSDMの具体的な実践方法に悩む医師は多いのではないか。本紙では,腎臓病SDM推進協会を設立し,セミナーなどでSDMの普及に向けた活動を行う小松氏に,SDMを進める際に知っておきたい理論や求められる実践,医療チーム内で取り組むための工夫を聞いた。
――治療方針決定の代表的なアプローチとしてSDMのほかに,パターナリズムとインフォームド・モデルが挙げられます2)。初めにこの2つの特徴について教えてください。
小松 医師に判断を全て任せる医療,すなわちパターナリズムは「医師は患者にとって最善の判断ができる」との前提に立つアプローチです。日々の診療に際し,医師が血液検査項目などの選択を決定することに問題はありませんが,手術など侵襲度やリスクが高い処置を行う場合に,医師の判断だけで治療方針を決めるパターナリズムは患者さんの自己決定権尊重に反してしまいます。このような場面では,医師が提供した医療情報を基に患者さん自身が治療方針を決定するアプローチ,すなわちインフォームド・モデルが広まってきました。
―― 一見すると,インフォームド・モデルによる治療方針決定が患者さん自身の意見を反映しているため,最適と感じられてしまいます。なぜSDMが求められるのでしょう。
小松 医療技術の発展,社会の高齢化,多疾患併存患者の増加により,医療の目的が患者中心志向となったことと,治療選択肢が多様化したことが背景にあります。選択する治療方針次第で生命予後や生活,QOLが変化するケースが増えたのです。そのため,患者さんにとって最善の決定を行うためのプロセスとして,医師はエビデンスに基づく医学的情報を,患者さんは自分にとって大切なこと,健康観,価値観をそれぞれ共有の上,協働して治療方針を決定する考え方,つまりSDMが求められるようになりました。
――どのような場合にSDMは有効なのですか。
小松 例えば,腎不全が進行し尿毒症によって命の危険が迫っている場合,患者さんの生活と生命の質を向上させ維持させるには,透析療法,腎臓移植などの腎代替療法が必要になります。透析療法のうち血液透析では週3回の通院治療が必要になり,腹膜透析では自宅で患者自らが治療を行う必要があります。両治療法ともに5年生存率には大きな差がないものの,生活に与える影響や患者の負担が異なるので,医師だけの判断ではどちらがベストな治療なのかを断言できないのです。腎臓・透析領域をはじめ,精神科,神経内科,緩和ケア,がん医療など,治療選択肢の多い分野では特にSDMが欠かせません。
“Ask-Tell-Ask”で患者さんの「思い」を引き出そう
――確かに,それらの分野ではSDMの必要性が特に叫ばれています。ただ,実践に悩む医師も多いのではないでしょうか。適切なSDMの実践が難しいのはなぜですか。
小松 治療方針にかかわる情報を患者さんと共有する際,多くの医師が,医学的な説明を中心に行ってしまうことが要因として挙げられるでしょう。説明の内容が高度であればあるほど患者さんは戸惑い,疑問を抱いたとしても質問がしづらかったり自身の希望を伝えにくかったりする可能性があります。一方的な説明にならないよう,患者さんが知りたいこと,大切にしたいこと,不安なことを尋ね,そ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小松 康宏(こまつ・やすひろ)氏 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授
1984年千葉大医学部卒。97年東京女子医大博士(医学)。2010年米ノースカロライナ大チャペルヒル校公衆衛生学修士(MPH)。聖路加国際病院腎臓内科部長,副院長などを経て,17年より現職。編著に『慢性腎臓病患者とともにすすめるSDM実践テキスト』『腎臓病診療レジデントマニュアル』(いずれも医学書院)。「患者にとっても医療者にとっても満足できる医療を実現したい」。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。