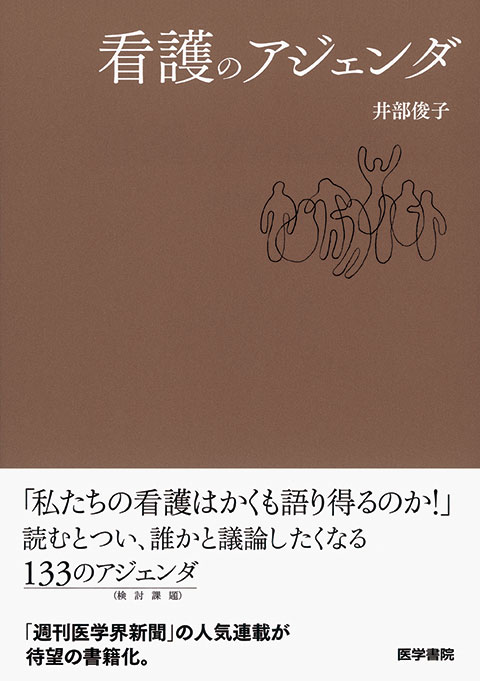看護のアジェンダ
[第191回] バーチャル・ユーラシア紀行
連載 井部 俊子
2020.11.23
| 看護のアジェンダ | |
| 看護・医療界の"いま"を見つめ直し,読み解き, 未来に向けたアジェンダ(検討課題)を提示します。 | |
| |
井部 俊子 長野保健医療大学教授 聖路加国際大学名誉教授 |
(前回よりつづく)
新幹線通勤で心待ちにしていることがある。それは車内誌「トランヴェール」の巻頭エッセイ「旅のつばくろ」に載る,沢木耕太郎の見開き2頁の文章である。毎回1枚の写真が添えられる。几帳面に,座席ポケットに入っているこの雑誌は毎月1日に入れ替わっている。どなたの担当なのであろうか。たまに,前月の最終日に真新しい翌月号が入っていると,得をした気分になる。
ミッドナイト・エクスプレス
沢木耕太郎が新刊を出すという広告をみて,喜び勇んで書店に行ったのが2020年3月である。タイトルは『沢木耕太郎セッションズ――訊いて,聴く』(岩波書店)で,4巻で構成される。2巻までは出版されていたのだが,3巻と4巻は未刊でしばらく待たされたのを覚えている。待ち遠しかった。ジャズのジャム・セッションをイメージしているというセッションズの書き出しが気に入っている。「私の幼い頃の最も甘美な記憶のひとつに,日曜日の夕方,縁側で弱い西日を浴びながら父親の朗読する声を聞いているという情景がある。父親は,新聞に連載されていた子どものための冒険活劇の読み物を切り抜き,毎週日曜になるとそれらをまとめて読んで聞かせてくれていたのだ。私は耳を澄ますようにして聴きながら,次の展開を早く知りたくて,“それで,それで”と心のうちでつぶやいているような気がする」。この光景は,セッションズの次の刊行を待ちわびる読者と筆者の関係に似ている。
セッションズIのテーマは「あう」であり「達人,かく語りき」として,多様な分野の先駆者10人が登場する。セッションズIIは「きく」であり,「青春の言葉たち」として,10人の青春の記憶と軌跡を語る。セッションズIIIは「みる」という「陶酔と覚醒」であり,旅と冒険とスポーツをたどる10人のセッションである。セッションズIVは「かく」であり,「星をつなぐために」としてフィクションとノンフィクションをめぐる緊張感のある10のセッションである。
各巻に書き下ろしエッセイが収録されており,「あう」「きく」「みる」「かく」ということが論じられる。そのころ私は学生の「観察」実習を検討していた時期であり,『「みる」の対語は「する」であるような気がする。そして,その「みる」という動詞を人と結びつけるとするなら,「みる者」と「みられる者」ではなく,「みる者」と「する者」になるのではないかと思うのだ』(『セッションズIII』303頁)という文章に私の思考は立ち止まった。...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
サルコペニアの予防・早期介入をめざして
AWGS2025が示す新基準と現場での実践アプローチ寄稿 2026.03.10
-
寄稿 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療を楽しく知る・学ぶ社会をめざして
おもちゃAED「トイこころ」開発への思い
坂野 恭介氏に聞くインタビュー 2026.03.10
-
寄稿 2026.03.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。