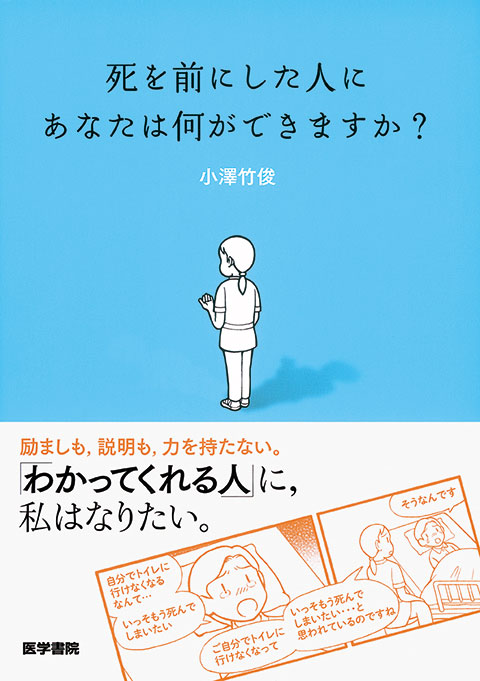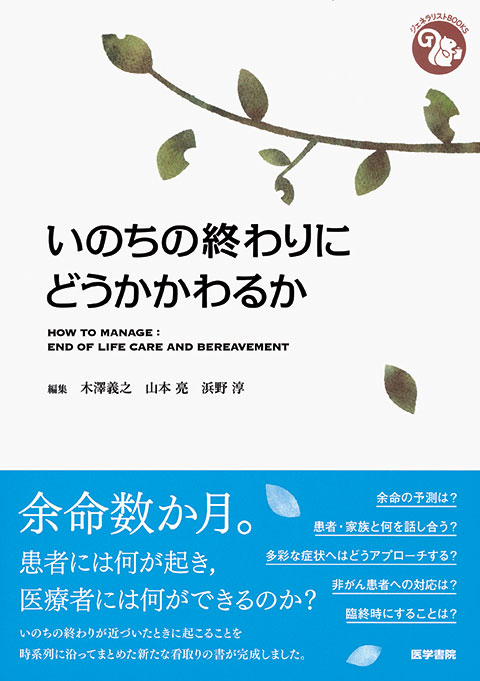小澤 竹俊氏(めぐみ在宅クリニック院長 / エンドオブライフ・ケア協会理事)に聞く
人生の最期にどう向き合うか
苦しみの中でも“穏やかになれる”援助の在り方とは
インタビュー 小澤 竹俊
2017.10.30 医学界新聞(通常号):第3246号より

超高齢多死時代を迎えた今,国は地域包括ケアシステムの構築を掲げて在宅での看取りを推進している。各医療機関においても在宅医療との連携が求められる中,回復の見込みのない患者とのかかわり方に不安を持つ医療者は多いのではないか。本紙では,横浜市で24時間365日の訪問診療体制を整え,年間300人以上の在宅看取りに携わる小澤氏に,全ての医療者が心得るべき「穏やかな看取り」についてのヒントを聞いた。
――「住み慣れた場所で最期を迎えたい」という地域住民の希望をかなえるために今,必要なことは何でしょうか。
小澤 多死時代を前に,看取りのできる環境整備や人材育成は喫緊の課題です。年間死亡数は,最も多くなるとされる2040年には166万人を超え,2015年と比べて約36万人の増加が見込まれます。
当院では常勤6人,非常勤11人の医師により,半径約5 km圏内に対して訪問診療を行っており,地域の看取りをカバーしています。しかし,国内全体ではまだ十分な体制はできていない状況です。
――2018年度に実施される診療報酬・介護報酬同時改定や第7次医療計画でも,在宅医療の拡充が重要な柱となりそうです。
小澤 医療・介護が連携した在宅医療推進の流れは,在宅医療に現在携わっている人はもちろん,急性期病院を含めた全ての医療者に大きな影響を及ぼすと思います。
これからの時代,医療には病気を治すことの追求だけでなく,「回復の見込みのない患者さんに対して何ができるか」という視点も重要です。たとえ患者さんを治す手だてがなくても,見放さずにしっかりと向き合える。地域から高く評価され,選ばれ続ける医療には,Best Supportive Careの力が今まさに必要とされているのです。
苦しむからこそ見える,“支え”の存在
――小澤先生は救命救急センターや医療過疎地などでも働いてこられたそうですね。どのようなきっかけでホスピスの道に進んだのでしょう。
小澤 医師を志した高校生のころから全く変わらない思いがあります。それは「世の中で一番苦しむ人の力になりたい」ということです。さまざまな現場を経て,最も苦しむのは「死を前にした人」ではないかと考え,31歳のときにホスピス病棟で働き始めました。
――ホスピス以外の経験で,今につながっていることはありますか。
小澤 救命救急センターでの経験から,「在宅医療は急性期病院の役割を守るためにある」という思いを持っています。自宅や介護施設では看取りに対応できないという理由で安易に救急搬送することは,救急医療を疲弊させる恐れがあるからです。
――看取りに携わるようになって,戸惑いはありましたか。
小澤 回復の見込みのない患者さんに対し,医師として何ができるか悩みました。身体的な痛みは緩和ケアで取り去ることができても,苦しみの全てを解決することはできないからです。そこで私は,対人援助やスピリチュアルケア,そして「哲学」を学びました。
――哲学ですか。
小澤 「現象学」という分野から,1つのものに対していろいろな見方があることを学びました。つまり,死というものを普通は「怖い」「不安だ」などととらえますが,見方を変えれば「穏やかだ」「幸せだ」と感じられる可能性もある。苦しみの中でも,人は穏やかになれるのです。
――どうすれば見方を変えられますか。
小澤 苦しむからこそ見える,“支え”の存在に気付くことが大切です。死が近づくと,ご飯を食べる,トイレに行くといった当たり前のことが,だんだんとできなくなってきます。すると,病気になる前は見えなかった「当たり前の生活の素晴らしさ」に気付くようになる。そうすると,傍らに家族がいる,窓から美しい花が見えるといった何気ないことに心を打たれるのです。
何が支えになるのかは人によってさまざまですが,支えに気付いた患者さんは不思議と穏やかになっていきます。「こんなに苦しい思いをするなら,いっそ早くお迎えが来てほしい」と思っていた人でも,「今,穏やかに生きていて幸せだ」と感じることができるのです。
必要なのは“わかってくれる人”
――支えに気付き,穏やかな最期を迎えるために,周りの人はどうかかわればよいのでしょう。
小澤 苦しんでいる人は自分の苦しみを“わかってくれる人”がいるとうれしい。これが大事なキーワードです。それには資格の有無は関係ありません。たとえ実習に来た学生さんでも“わかってくれる人”になれたら,素晴らしい援助者だと言えます。
――どうすれば患者さんの苦しみを理解できるようになるのでしょうか。
小澤 自分が相手を理解できたかどうかは重要ではありません。大事なことは,患者さんが「この人は私の苦しみをわかってくれた」と思うかどうか。つまり,「わかります,その気持ち」と声を掛けても駄目なのです。“わかっ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

小澤 竹俊(おざわ・たけとし)氏 めぐみ在宅クリニック院長 / エンドオブライフ・ケア協会理事
1987年慈恵医大卒。91年山形大大学院医学研究科博士課程修了。救命医療や農村医療に従事した後,94年より横浜甦生病院内科・ホスピス勤務。2006年にめぐみ在宅クリニックを開院。15年にエンドオブライフ・ケア協会設立。17年にはNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演した。『死を前にした人にあなたは何ができますか?』(医学書院),『今日が人生最後の日だと思って生きなさい』(アスコム),『小澤竹俊の緩和ケア読本――苦しむ人と向き合うすべての人へ』(医事新報)など著書多数。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。