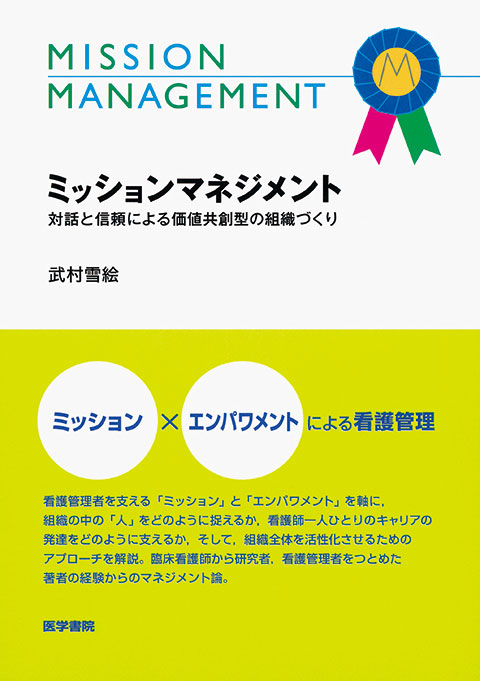新しいルールと意味の創出(3)(武村雪絵)
連載
2012.04.23
看護師のキャリア発達支援
組織と個人,2つの未来をみつめて
【第13回】
新しいルールと意味の創出(3)
武村雪絵(東京大学医科学研究所附属病院看護部長)
(前回よりつづく)
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
前回までに,「新しいルールと意味の創出」を構成する2つの変化,「境界の問い直し」と「意味の深化」を紹介した。私がこの研究テーマに関心を持ったきっかけでもあるが,「新しいルールと意味の創出」を経験した看護師らは共通して,「昔より楽になった」「看護が楽しくなった」と話し,心から楽しそうに仕事をしていた。今回は,その“楽さ”と“楽しさ”,そして彼女らに共通していた“柔軟性”について考察したい。
絶対の正しさを求めない等身大の自信
「新しいルールと意味の創出」を経験した看護師は,「自信がある部分とない部分を自分で理解できているかな」というように,過大でも過小でもない等身大の自信を有しているという特徴があった。また,自分の感性を信じて行動するだけの自信は持っているが,その判断が正解でなければならないという固執がなかった。そのため,自身の判断を修正することにもためらいがなかった。
例えば,第11回(第2966号)で,境界を問い直し,患者に最善を尽くす方法を考えるようになった例として紹介したCさんは,「ある意味自信を持って自分の感性を信じなければ,主張できない」と,自分の感性を信じていると話した。しかし,その一方で,自分の感性が絶対に正しいと思っているわけではなく,正しいかどうかにはこだわっていなかった。Cさんは以下のように話した。
|
また前回(第12回,2970号),患者の話の聞き方が変わった例として紹介したWさんも,以前は「自分が正しい」と思っていたが,正しさへのこだわりがなくなり,「私がいちばん正しいわけじゃなくて,本当に考え方ってばらばらなんだと気づいた」と話した。
|
同様に前回,日常的な援助にあらためて意味を見いだすようになった例として紹介したUさんは,自分の変化について説明してくれた。Uさんは「以前は変に自信があった。卒後何年目かのときは,自分のやっている看護に,“できている”っていうような印象を持っていた。でも,それはただの思い上がりだったなって,最近思うようになった」と話した。Uさんは,自分がさまざまなことを考慮して合理的に判断したとしても,それは絶対ではなく,ほかの可能性があることを常に意識するように変わったという。
|
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。