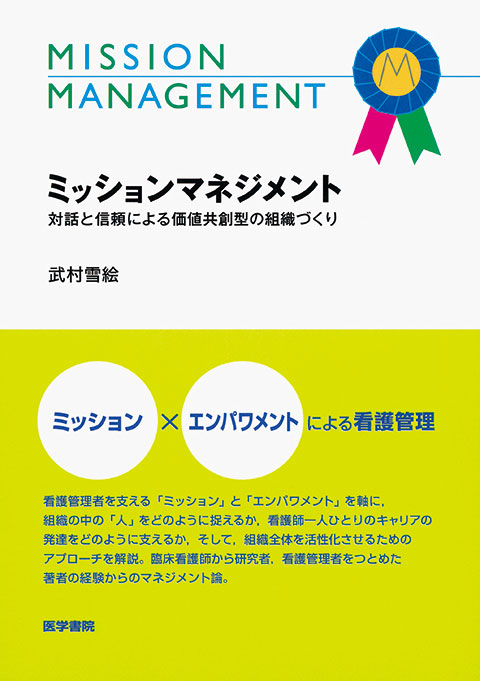新しいルールと意味の創出(4)(武村雪絵)
連載
2012.05.28
看護師のキャリア発達支援
組織と個人,2つの未来をみつめて
【第14回】
新しいルールと意味の創出(4)
武村雪絵(東京大学医科学研究所附属病院看護部長)
(前回よりつづく)
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
「新しいルールと意味の創出」を経験した看護師は,過去に,「組織ルーティンを超える行動化」によって自分なりの実践スタイルを構築し,自分の看護に自信や誇りを持っている時期,少なくとも疑問を感じない時期を経験していた。その後で,当たり前が揺らぐショック体験,あるいは,他者の言葉や姿が楔のように記憶に刻まれる経験をしたことが,「新しいルールと意味の創出」につながっていた。ただし,看護師にこれらを自らの根底を揺るがす体験として受け止める感性と,自己を揺さぶり,その揺さぶりに耐える力が備わっている必要があった。
当たり前が揺らぐショック体験
◆他者からの指摘
他者からの厳しい指摘が転機となることがあった。Yさん(第12回,第2970号)は,自分の看護に「ある程度できる」という感覚を持ち,そろそろ看護師を辞めて次のステップに進もうかと考えていた時期に事例検討会に参加した。その病院の事例検討会は,同じメンバーのグループで複数回,事例を基に議論する形式であった。Yさんが事例を紹介したところ,他病棟の先輩看護師に,「あなた,人間に興味があるの?」「ちゃんと患者さんの話を聞いてあげているの?」と言われたという。Yさんは,「どうして先輩にそんなことを言われなきゃいけないの?」と,そのとき強いショックと憤りを感じたという。
Yさんは,「もう事例検討会に参加したくない」と思いつつも,友人と参加を続け,なぜそのような指摘を受けたのかを,友人と,あるいは一人で考えたという。やがて患者の話を「ただ,すとんと落とすように聞く」方法を知り,看護が「すごく楽になった」という。Yさんは,それまでの自分の看護を,「確かに驕っていたんだよね」と振り返り,看護を続ける決意をしたと話した。
|
ただ相手を否定するだけでは相手を傷つけ,反発をまねくだけで,「新しいルールと意味の創出」を促すどころか,意欲の低下や離職につながりかねない。Yさんは,厳しい指摘をした先輩看護師らと繰り返し振り返る機会があり,最終的には先輩看護師らに変化を評価され,親しい関係を築いた。言いっぱなしで終わらず,その後本人を支え一緒に考える体制をつくれるか,本人がその指摘に耐え自己を振り返る力を持っているか,支えてくれる仲間がいるかを慎重に判断する必要があるだろう。
◆当たり前に疑問をつきつける事実
他施設の友人から自病棟と異なる陰部洗浄の方法を聞いて,「すごくショックを受けた」Sさんのように(第11回,第2966号),別のやり方の存在を知ることも,当たり前が揺らぐきっかけとなった。14年目のある看護師は,新しく配属された中途採用者からその病棟のやり方をおかしいと指摘されたことで,「結構あるつもりだった」それまでの自信が崩れる体験をしていた。彼女はそれ以来,本や文献を読む習慣が身についたと話した。
「組織ルーティンの学習」の途中など自分の実践スタイルを構築する最中では,新しい知識や実践に触れても,一つのルールの習得やルールの修正に終わることが多い。「組織ルーティンの学習」の初期段階では,別の方法の存在を知ることで混...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。