MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2011.03.07
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
北島 政樹 監修
加藤 治文,畠山 勝義,北野 正剛 編
《評 者》稲田 英一(順大主任教授・麻酔科学)
外科学における学生教育の現在のスタンダード
 最近は外科志望の医師が減少していると言われている。外科医を増やすためには,まず実技教育を含めた生き生きとした充実した学生教育を行う必要がある。ひと口に外科と言っても,消化器外科,呼吸器外科,心臓外科,乳腺外科,小児外科などその領域は広い。外科領域の臨床だけでなく,外科学に関係する遺伝子学や免疫学などを含めた基礎教育など幅広い教育も必要となってくる。さらに,臓器移植,遺伝子治療,新薬による治療などに関する倫理的な教育も必要となってくるだろう。
最近は外科志望の医師が減少していると言われている。外科医を増やすためには,まず実技教育を含めた生き生きとした充実した学生教育を行う必要がある。ひと口に外科と言っても,消化器外科,呼吸器外科,心臓外科,乳腺外科,小児外科などその領域は広い。外科領域の臨床だけでなく,外科学に関係する遺伝子学や免疫学などを含めた基礎教育など幅広い教育も必要となってくる。さらに,臓器移植,遺伝子治療,新薬による治療などに関する倫理的な教育も必要となってくるだろう。
このような幅広い要請に十分に応える外科の優れた学生向け教科書が必要なことは言うまでもない。『標準外科学』は今回で第12版となり,1976年の初版発行から30余年が過ぎた「標準」と付いていることに恥じないロングセラーである。現在,外科学の一線で活躍されている先生方の多くも使用された教科書であると思う。本書はその表紙から紙面まで大きく変貌を遂げた。真っ白な表紙は,刷新された本書の意気込みや潔さが象徴されている気がする。
評者は麻酔科医であり,外科医ではない。良書であることを知っているので気軽に書評を引き受けたものの,麻酔科医である私が適任かどうかについて悩むこととなった。そこで,学生になった気持ちで本書を読むこととした。
教科書はまず読み応えがなくてはならない。単に調べるため,あるいは記憶するためだけの本は,教科書とは呼べないであろう。ざっと章立てを眺めてみると,総論には,歴史と医療への貢献,外科的侵襲の病態生理,ショック,外科的診断法,無菌法,基本的外科手術手技や処置,出血・止血・輸血,救急外科,急性腹症,損傷,外科的感染症,腫瘍といった章が並んでいる。さらに,近年学問的進歩が著しく,臨床的にも応用が進んでいる免疫,分子生物学,臓器移植,人工臓器,再生医学,リスクマネジメントといった章が続く。次に各論では,顔面,口腔,頸部,乳腺,心臓,血管,消化管,肝臓といった部位別,臓器別の章が続いている。老人外科,小児外科は別立ての章となっている。
「外科の歴史と外科医の医療への貢献」の章では,外科専門医制度にも触れられており,学生の将来への指針となるだろう。「外科的侵襲の病態生理」では神経内分泌反応に加え,免疫系の変化や炎症,遺伝子多型にも触れられている。「ショック」の章では,液性因子に対する対策について述べられており,前章との基礎知識と結び付く。「外科的診断法」や「基本的外科手術手技」は図や写真も多く実践的となっており,OSCE対策としても役立つであろう。
各論においては,解剖,生理,検査を含む診断法,病態,診断,治療,予後というように順序立てて述べられている。このように基礎から書き起こすことにより,相互に結びついた系統的な知識体系となり,それに基づいた理論的思考を促すことになる。
本文は重要事項を赤文字ゴチックとしたり,アンダーラインを付けるなどわかりやすくなっている。とかく平板になりがちな教科書の記述がこれらの工夫により,読みやすく,また記憶しやすいものになっている。試験前の学習にも便利であろう。図表や写真も多く,理解や知識の整理を促進するようになっている。写真も白黒のものは鮮明であり,カラー写真のものも実際に近い色となっており,臨場感がある。心臓手術のところでは,QRコードを用いて術中映像が閲覧できるようになっている。本文695ページという中に,これらの事項を含めた監修者と編者の努力に敬服する。
本書は,外科学の学生教育の現在のスタンダードを示すと同時に,未来への展望も示すものである。本書は医学部学生を主たる対象としたものであるが,実地医家にとっても,外科学全般を今一度振り返りリフレッシュするのに有用な書と考えられる。
B5・頁784 定価8,925円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00865-5


渡邉 裕司 編
《評 者》植田 真一郎(琉球大大学院教授・臨床薬理学)
臨床現場で必要な感覚も身につくコンパクトな薬の本
 医学生としてベッドサイドで薬のことを勉強するのは大変である。そもそも病態生理が中心の教科書には治療学に関する記載はあまりないのに,診断が確定したあとは,診療録の記載の中心は治療に関することである。医師となればその日から担当の患者さんの処方を理解しなければならない。承認されている薬を羅列している本はあるものの,これを全て記憶することは不可能である。筆者が研修医となった頃は紙の処方箋だったが,処方をしてサインをする時は緊張した。実習では薬のことを調べたが,不思議なことに薬理学で頻出した薬剤はあまり使用されていないし,膨大な記載に劣等生だった私は,国家試験に合格した医師はなんてすごいのだろう,きっと全部覚えているのだろう,自分は駄目だと驚愕した覚えがある。しかし実は薬物療法に関してその本質的なところを理解し,患者さんに生かすためにはそう多くの薬に関する「知識」を要しないと思う。基本的な薬剤に関して,なぜその薬剤なのか,薬理作用と実際の患者さんのアウトカム改善,という2点から考える癖をつけることが必要である。そして内科系の実習の時にはこれを是非身につけてほしい。
医学生としてベッドサイドで薬のことを勉強するのは大変である。そもそも病態生理が中心の教科書には治療学に関する記載はあまりないのに,診断が確定したあとは,診療録の記載の中心は治療に関することである。医師となればその日から担当の患者さんの処方を理解しなければならない。承認されている薬を羅列している本はあるものの,これを全て記憶することは不可能である。筆者が研修医となった頃は紙の処方箋だったが,処方をしてサインをする時は緊張した。実習では薬のことを調べたが,不思議なことに薬理学で頻出した薬剤はあまり使用されていないし,膨大な記載に劣等生だった私は,国家試験に合格した医師はなんてすごいのだろう,きっと全部覚えているのだろう,自分は駄目だと驚愕した覚えがある。しかし実は薬物療法に関してその本質的なところを理解し,患者さんに生かすためにはそう多くの薬に関する「知識」を要しないと思う。基本的な薬剤に関して,なぜその薬剤なのか,薬理作用と実際の患者さんのアウトカム改善,という2点から考える癖をつけることが必要である。そして内科系の実習の時にはこれを是非身につけてほしい。
この本は上記のような,医学生のときに将来適切な薬物療法を行うためにまず知るべきこと,考えるべきことを丁寧に教えてくれる。なによりも薬を厳選していること,薬理作用は簡潔にまとめられ,読み易いこと,なぜその薬剤をそのように使うのか,という点が要諦としてわかりやすく記載されている。暗記を強要するものではなく,臨床の現場で必要な感覚を身につけられると思う。従って医学生のみならず初期研修医にとっても有益である。本書を編集された渡邉裕司教授は浜松医科大学で臨床薬理内科を立ち上げられたが,本書は内科医として,そして臨床薬理医としての医学生教育のあり方を示唆するものであると思う。
B6変型・頁344 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00834-1


藤田 尚男,藤田 恒夫 著
岩永 敏彦,石村 和敬 改訂協力
《評 者》佐藤 洋一(岩手医大教授・解剖学)
ゆとり世代の学生にはもったいない骨太の教科書
 藤田・藤田の標準組織学が改訂された。この本は,手垢の付いた表現ではあるが「深い教養と該博な知識に裏打ちされた組織学の教科書」として,初版以来,多くの解剖学・組織学の教員から絶大な支持を得てきた。その特徴は,生理学や細胞生物学の知見を織り交ぜながら生命形態を美しい写真とわかりやすい図で表していることに加え,研究のプロセスを感じさせるエピソードがここかしこにちりばめられている点にあったと言える。とりわけ日本人学者の業績を紹介している項は,われわれの励みになってきた。とはいえ,発展が目ざましい分子生物学の新知見を盛り込むために,趣味的記載は減らされたのではなかろうか,そんな不安を抱きつつ,改訂版をひもといた。
藤田・藤田の標準組織学が改訂された。この本は,手垢の付いた表現ではあるが「深い教養と該博な知識に裏打ちされた組織学の教科書」として,初版以来,多くの解剖学・組織学の教員から絶大な支持を得てきた。その特徴は,生理学や細胞生物学の知見を織り交ぜながら生命形態を美しい写真とわかりやすい図で表していることに加え,研究のプロセスを感じさせるエピソードがここかしこにちりばめられている点にあったと言える。とりわけ日本人学者の業績を紹介している項は,われわれの励みになってきた。とはいえ,発展が目ざましい分子生物学の新知見を盛り込むために,趣味的記載は減らされたのではなかろうか,そんな不安を抱きつつ,改訂版をひもといた。
杞憂であった。例えば,ランゲルハンスの写真は彼が最も充実していた若いときのものに入れ替えられ,伝記的記述も増えている。知見の追加は,主に「成り立ち」と「機能」を重視したものであり,読んでいて目から鱗が落ちる思いをすることがしばしばであった。
「……新説によってすっきり説明できる」「……であれば,当然のことである」「……この発生過程から納得できる」等の表現は,一般的な教科書では目にしないが,これこそが本書の真骨頂であり,科学的思考方法を読者に教えてくれるのである。改訂協力者の岩永敏彦教授と石村和敬教授は,それぞれ藤田恒夫教授と藤田尚男教授の愛弟子であり,本書の特質を失うことのないように改訂作業が進められたのであろう。
神経系の章は序に記されているように,寺島俊雄教授により大改訂された。新知見が過不足なく収められており,不勉強な私にとっては,今後ともかなり助けていただくことになるだろう。それ以外の個所でも,改訂に当たっては,全国の解剖学者が協力しており,日本の解剖学者のアクティビティーの高さを伺わせるとともに,いかにこの本が好まれているのかがわかる。そのせいか,いささか文献が多いような気がするが,本書を一種の総説と見なせば,文献欄の充実とも言えるだろう。
ゆとり教育のおかげか,あるいは社会環境の変化によるものなのかわからないが,医学生の気質は最近になって急激に変わっており,試験に出ないことを教えるのは悪であるかのように言ってくる学生が増えている。そんな彼らにとって,逸話はいらないし,「……についてよくわかっていないが,……という人もいる」という記述は煩わしい。それらはCBTや国家試験に出されないからである。
一方では,教科書の隅から隅まで覚えなければいけないと思い込んでいるような,極めてまじめな学生(言い換えれば,要領の悪い学生)も増えている。全体を俯瞰して軽重をつけた勉学ができない学生にとって,「ぶらぶらと散歩しながら,横道に入ってみる楽しさ」は実感できない。
そこで改訂版では,組織学の教科書としての記述と,研究者向けあるいは趣味的な記載とが,フォントサイズの違いによって示されている。ただし,教科書としての記載はもう少し簡潔に記載するか,あるいは章ごとに「まとめ」の項があれば良かったように思われる。もっとも,将来は電子書籍化することで,ジャンルやレベルを分けて呈示することが容易になるであろう。
さて,私はこの教科書を以下の方々に強く勧める。まず,既に旧版の標準組織学を買っている方である。改訂版を購入して失望することはない。また,解剖学教室はもちろん,すべての基礎医学系の若手教員には本書を通読してもらいたい。多細胞生物の生命現象は,培養皿の中ではなく,組織という場でなされていることを認識した上で,教育と研究に当たってもらいたいと強く願うからである。
さて,学生に対してであるが,これを組織学の教科書として指定したくない誘惑に駆られてしまう。こんな楽しい読み物は,学生にはもったいない。われわれ教員が密かに読んでおいて,授業や実習中に学生にさりげなく披瀝し,「教養有る学者」と学生に思い込ませるためには最適な本なのである。
B5・頁616 定価12,600円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00302-5


坂井 建雄 監訳
市村 浩一郎,澤井 直 訳
《評 者》中田 隆夫(東京医歯大大学院教授・細胞生物学)
21世紀の解剖学アトラス
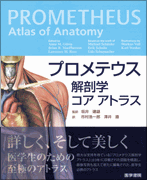 私事で恐縮であるが,外科医であった父の本棚には,父の学生時代の教科書が幾つかあった。当然その内容は古く,私が医学生になってから見てみると,内容が使えそうなのは解剖学(マクロ)だけであった。それも日本が貧しい時代の印刷の悪いものであった。私の学生時代,良いアトラスといえばPernkopfかSobottaかであった。父にPernkopf 2巻を買ってもらった。 十分使いこなせたとは言えないが,図の精緻さ,美しさは素晴らしく,今も職場の本棚にある。
私事で恐縮であるが,外科医であった父の本棚には,父の学生時代の教科書が幾つかあった。当然その内容は古く,私が医学生になってから見てみると,内容が使えそうなのは解剖学(マクロ)だけであった。それも日本が貧しい時代の印刷の悪いものであった。私の学生時代,良いアトラスといえばPernkopfかSobottaかであった。父にPernkopf 2巻を買ってもらった。 十分使いこなせたとは言えないが,図の精緻さ,美しさは素晴らしく,今も職場の本棚にある。
時代の趨勢もあり,今後,これらを超えるようなアトラスが作られることはないだろうと思っていた。実際,学習に便利であったり,安価であったりする良いアトラスは出版されても,うなるような素晴らしいアトラスは見ることはなかった。
しかし,プロメテウスの第1巻を見たとき,解剖学のアトラスにこのような進化の方向があったのかと感動した。CGを使っているからであろうか...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
