看護師と医師のあいだで(山内豊明,平林大輔)
医療者間の他者性を問い直す
対談・座談会
2008.02.25
【クロストーク】
医療者間の他者性を問い直す
看護師と医師のあいだで
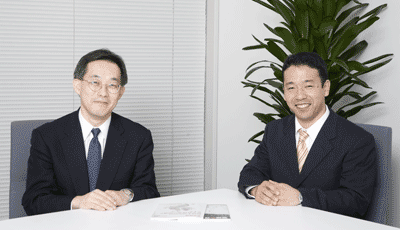
山内 豊明氏(名古屋大学医学部教授・基礎看護学)
平林 大輔氏(東京北社会保険病院 初期研修医)
月刊『看護管理』誌上で平林大輔氏による連載「医者ときどき看護師」がスタートした。初期研修医である平林氏は,看護師としての臨床経験を持つ。本紙では,同じくダブルライセンスを持つ山内豊明氏との対談を企画した。チーム医療がいわれて久しいが,看護と医学のあいだに二項対立的な意識は潜在していないだろうか。医療者がもっとわかり合うために教育や臨床の現場で求められる視点について,お二方にお話しいただいた。
山内 平林先生は看護の臨床を経て,志を新たに医学部を卒業され,現在は初期研修医になられています。この間のいきさつを教えていただけますか。
平林 大学へ進学するときには研究職をめざそうと思っていました。理学系の学部に入ってみると,研究はたしかに面白いのですが,もう少し人とかかわるような職業に就きたいと考えるようになりました。それで,大学に籍を置いたまま医学部の受験をしたのですが,うまくいかずに,改めて考えた結果,同じ領域である看護学科に進んで看護師をめざしました。臨床で看護業務に携わるなか,疾患について深く勉強したいという思いが強まり,ちょうど学士編入学の制度が始まったこともあって再度医学部をめざしました。
山内 人間は身体だけでもないし,心だけでもなく,さまざまなものが融合された存在ですが,その人を知るというベーシックな部分で,看護での学びに加えてもうひとつ,疾患からのアプローチという力強さがほしかったということでしょうか。
看護を学んだあと,医学部での学びからどのようなことを感じましたか。
平林 看護の基礎教育では,療養上の世話や退院してからの生活などを教わり,患者さんを周りから包み込んでいくような温かさ,全人的なケアという視点が通奏低音として流れていました。
しかし,病態生理や疾患構造の教育に関しては,ロジカルな部分が不足していたような気がします。たとえば「こういう状態のときには,このようなケアをすればいい」というように,起点と終点は教わるのですが,そのあいだのプロセスはあまり教わらなかったように思います。
医療行為という一連の流れのなかで,ある時点に自分が提供した医療の意味,順序性がわからないことがストレスに感じられ,消化不良な感覚が自分のなかに積もっていったように思います。それを補完してくれたのが,医学部での教育でした。
看護を裏切る?
山内 自分がものを見る場所を複数もつことによって,もとの場所からは何も見えなかったのに,違う場所から見えてくることがありますね。平林先生は「あちらから見たら,違うものが見えそうだ」ということで医学部に再入学されたのだと思います。先生に見えてきたものを教えていただけることは,医療者がものの見方に厚みをもつことができるチャンスだと思います。
その一方で先生が看護職を辞められたとき,「なぜ看護を裏切って,医者になるの?」といわれたそうですね。これは非常にショッキングな言葉です。「裏切る」という言葉は,決して上下関係を表しているのではないと思いますが,「自分の価値観を否定された」とか,対極する価値観があって「あなたは,どっちを選ぶの?」というニュアンスを感じてしまいます。
私が医学生だったときには,「看護師と比べて」というコンテクストは聞かなかったように思いますが,米国で看護学生として学んでいたときも,臨床で看護を行っていたときも,「こちらの考え方」「むこうの考え方」というように看護には,どうしても医師の業務と比べながら教育していく部分があることを感じていました。
それはやはり病院というシステム上,法律的に「医師の指示の下で」という文言が存在することで,監督する人・される人という,対峙するようなあるいは上下のような関係性が医療者のなかに刷り込まれてしまっているということなのでしょうか。
平林 医学と看護が対立するものという考えをもっている看護師もいて,そういう人にとっては,看護師が医師になることは,自分たちの側を裏切って相手の側に行ってしまうことになるのかもしれないと感じました。
山内 野球にたとえると,内野手がお互いの守備範囲に集中するために「ここで分けましょう」とぴったりと線引きをすると,ちょうどその境界線上にボールが来ると外野まで抜けていってしまうかもしれない。そうではなくて,両方が走ってきて,実際にはどちらかが球を取るのだけれども,実はもう1人横で構えている。
お互いに境界領域をカバーしようという考えが共有されていて,内野がしっかりしていると,外野は内野ゴロが出たときに「どうしよう」とうろたえなくてもよいと思うのです。その共通理解がないと,医療現場はとてもあやうい状態になってしまいます。
平林 同じようなことを私はよくサッカーにたとえます。深いコミュニケーションをとって,相手がどういう人なのか,どういう能力をもっていて,どこまで信頼できるのかということを知っておくことは,非常に大切なことだと思います。詳しくは『看護管理』2月号を読んでください(笑)。
それと,医師の側に立って感じたことですが,信頼して自分の患者さんを任せるには,やはり看護師にもたくさん勉強してほしいし,知識・技術を磨いてほしいと思うのです。勉強していない医師に患者さんのことを任せられないのと同じことだと思います。
山内先生は看護師に向けて『フィジカルアセスメント ガイドブック』を書かれましたが,医師の立場からは,看護師にもフィジカルアセスメントの技能をしっかりと身につけていてほしいと思います。基礎教育では,技術や知識に関する突っ込ん...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
