MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.12.10
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


社団法人 日本リハビリテーション医学会 監修
日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会
リハビリテーション連携パス策定委員会 編
《評 者》蜂須賀 研二(産業医大教授・リハビリテーション医学)
参考となる連携パス実践例と臨床家の必須知識を収載
 このたび,日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会リハビリテーション連携パス策定委員会の編集により本書が出版された。近年,脳卒中リハビリテーション連携パスは,日本リハビリテーション医学会や関連する研究会で教育講演やシンポジウム,あるいは医学雑誌の特集企画としてしばしば取り上げられている。しかし,すべての脳卒中医療関係者が気軽に通読でき,何時でも何処でも手軽に参照できる成書は,これまで存在しなかった。
このたび,日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委員会リハビリテーション連携パス策定委員会の編集により本書が出版された。近年,脳卒中リハビリテーション連携パスは,日本リハビリテーション医学会や関連する研究会で教育講演やシンポジウム,あるいは医学雑誌の特集企画としてしばしば取り上げられている。しかし,すべての脳卒中医療関係者が気軽に通読でき,何時でも何処でも手軽に参照できる成書は,これまで存在しなかった。
2006年4月に診療報酬の改定があり,急性期リハビリテーションの重要性が認められ,リハビリテーション訓練の算定上限が1日9単位までに拡大したが,脳卒中発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病院に転床させなければならなくなった。効果的なリハビリテーションを実施するには急性期を充実させるとともに,急性期病院と回復期リハビリテーション病院との密接な連携が必須である。さらに,回復期リハビリテーション病院とかかりつけ医,あるいは介護保険に基づくリハビリテーション施設との連携も不可欠である。これまで「連携」は「在院日数短縮」の手段であり,あたかも川の水が高い所(急性期病院)から低い所(かかりつけ医)へと流れるが如しとの批判もあった。一方,地域リハビリテーション領域ではその重要性は認知されていたが主観的麗句に終始することが多く,必ずしも医療全体に波及する具体的な方法論は提示されていなかった。
この激動期に多くの医療関係者が待望していた脳卒中診療に関する実践的な連携パスの解説書が完成した。内容は,脳卒中診療の現状と診療連携,クリニカルパスの基本,脳卒中診療におけるクリニカルパスの動向,データベースとITの活用と開発,連携パスの実践,ユニットパスの実際,連携相手に望むこと,といった7つの章で構成されており,急性期・回復期・維持期を担当する医師やコメディカルにより分担執筆されている。個々の記載は簡潔であり,図表も多く,読みやすく,読者がどのような施設に勤務していても必ず参考となる連携パス実践例を見つけることができる。さらに本書は単なるパス実例集ではなく,脳卒中リハビリテーションを適切に実施するためのヒントが得られ,診療報酬上の誘導に左右されない見識と臨床家として必要な知識を得ることができる。
今回,里宇明元担当理事のもと,委員の方々がこの時期に的を射た企画を立て出版にまでこぎ着けたことは賞賛すべきである。本書はリハビリテーション関係者ばかりではなく,脳卒中医療に関与するすべての医師とコメディカル・スタッフにぜひお勧めしたい一冊である。
A4・頁256 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00478-7


平野 和行,廣田 耕作 著
《評 者》鍋島 俊隆(名城大大学院教授・薬学研究科薬品作用学)
「百聞は一見に如かず」 adherence向上に繋がる一冊
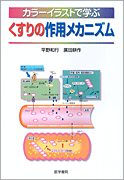 薬剤師の医療における役割はPharmaceutical care「医薬品の適正使用を介して患者の生活の質(QOL)を向上させること」である。医薬品の適正使用は医師,薬剤師,患者がお互いに信頼関係を持ち,病態,医薬品について共通の知識を持ち,それぞれが自分の役割を的確に果たすことが必要である。医師は的確な診断とそれに基づく適正な処方をしなければならない。薬剤師は処方を厳格に監査して,間違いなく調剤をし,そのうえで患者のわかる言葉で服薬指導をしないといけない。患者は病態,服薬の意義についてしっかりと理解し,医薬品を処方に従って服用しないといけない。これら一連の過程がすべて完結したときに,初めて医薬品の適正使用が可能となる。
薬剤師の医療における役割はPharmaceutical care「医薬品の適正使用を介して患者の生活の質(QOL)を向上させること」である。医薬品の適正使用は医師,薬剤師,患者がお互いに信頼関係を持ち,病態,医薬品について共通の知識を持ち,それぞれが自分の役割を的確に果たすことが必要である。医師は的確な診断とそれに基づく適正な処方をしなければならない。薬剤師は処方を厳格に監査して,間違いなく調剤をし,そのうえで患者のわかる言葉で服薬指導をしないといけない。患者は病態,服薬の意義についてしっかりと理解し,医薬品を処方に従って服用しないといけない。これら一連の過程がすべて完結したときに,初めて医薬品の適正使用が可能となる。
本書は病態についてまず説明して,その病態に対して医薬品がどのように作用して効果を発揮するのかを54種類の医薬品について,大変わかりやすいカラーイラストにまとめている。各病態,各医薬品についての説明も2-3ページに簡潔にまとめてある。薬学生や薬剤師が自分の知識のまとめや確認などのために座右の書とするといいだろう。
一方,本書の応用についてであるが,薬剤師が患者に医薬品の薬効や副作用について説明する場合には,業界言葉でなく,患者のわかる言葉で説明しないといけない。人口の高齢化で老年患者が急増し,複数診療科にかかっている患者が多く,処方される医薬品の数も多く,わかりやすい言葉で話しても,基礎知識のない患者にはなかなか理解できない。本書は医薬品の効果について大変わかりやすいカラーイラストにまとめている。「百聞は一見に如かず」というが本書を使い,薬局のカウンターやベッドサイドで病態のこと,医薬品の作用点や作用機序を説明することにより,患者の理解が容易になるものと思われる。
しかし上述したように複数の医薬品を処方されると,どの医薬品がどうだったのかあいまいになる。各医薬品について本書のイラストを患者に見せることができるようになると,医薬品に対する理解が向上するものと思われる。そうすればadherenceが向上し,医薬品の適正使用に繋がると思われる。
本書には医薬品に関連した興味深い話題が20のコラムとして挿入されている。薬学生や薬剤師にとっては,これらコラムを読むことは息抜きになると思われる。またこのコラムから得た知識は患者に服薬指導する場合のコミュニケーションツールとして使えると思われるので,どんどん使っていただきたい。
B5・頁184 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00235-6


精神障害のある救急患者対応マニュアル
必須薬10と治療パターン40
宮岡 等 監修
上條 吉人 執筆
《評 者》大野 博司(洛和会音羽病院ICU/CCU,感染症科,腎臓内科,総合診療科)
急性期身体疾患と精神障害 救急医と精神科医を結ぶ良書
 この本は本当にすばらしい。
この本は本当にすばらしい。
私は医師になってからずっと地域の救急病院で勤務してきました。その救急医療の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
