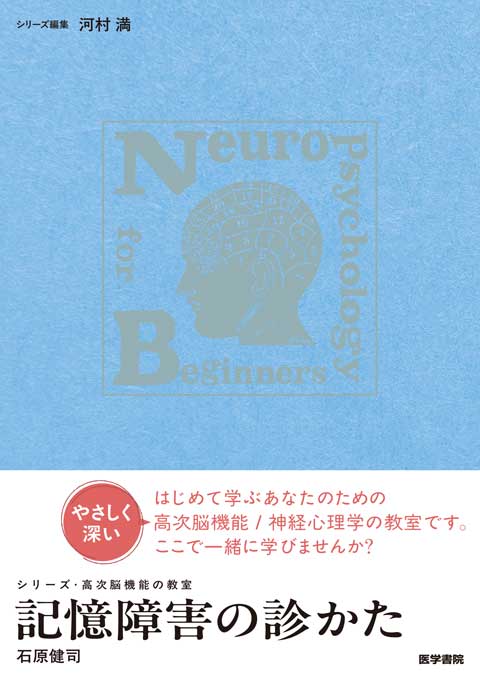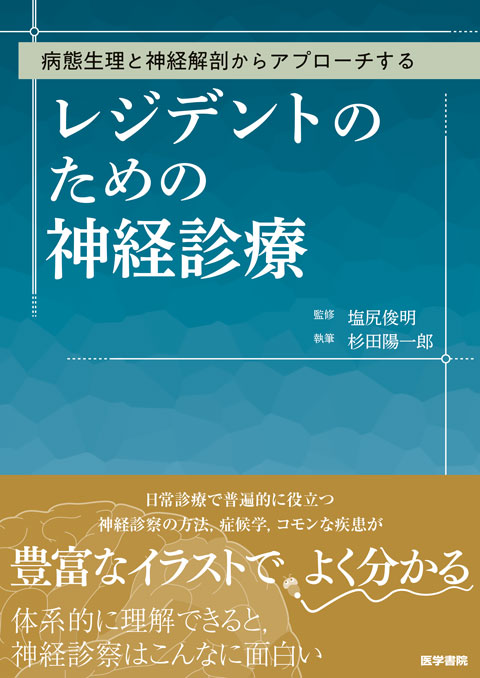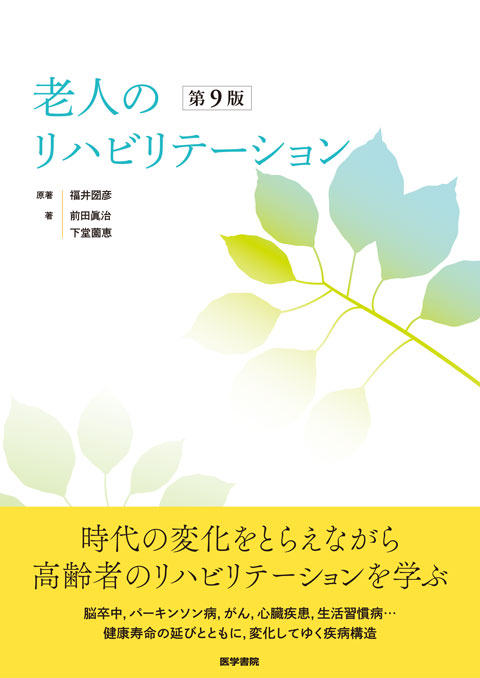失行の診かた
「動きとは何か」から始める、これまでにない失行の入門書!
もっと見る
高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。この複雑なテーマをエキスパートがトコトンわかりやすく解き明かす。「なぜ失行は理解しにくいのか?」。その問いに向き合い、まずは前提となる「動き」のしくみから丁寧に解説。そして失行を「発見」したLiepmannを軸に、彼以前以後まで広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。カラーイラストも豊富に収載。
| シリーズ | シリーズ・高次脳機能の教室 |
|---|---|
| シリーズ編集 | 河村 満 |
| 著 | 近藤 正樹 |
| 発行 | 2025年11月判型:A5頁:200 |
| ISBN | 978-4-260-06272-5 |
| 定価 | 3,850円 (本体3,500円+税) |
更新情報
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
シリーズ編集者のことば/まえがき
シリーズ編集者のことば
本書を手にとっていただき,誠にありがとうございます。
本書を手にとられたということは,高次脳機能や神経心理学に興味はあるけれど「どうもよくわからない」という気持ちをお持ちなのではないでしょうか。私は40年間以上神経心理学を専門として臨床・研究を続けてまいりましたが,残念ながらいまだに皆さんと同じ気持ちです。それでも長く続けてこられた理由は,高次脳機能の不思議さ,またそれを探求する神経心理学の奥深さの一端に触れずっと魅了され続けてきたからなのです。いまだに,高次脳機能/神経心理学の臨床は日々驚きの連続で,興味が尽きません。
その立場から申し上げますと,高次脳機能/神経心理学に興味を持ち,本書を手にとったあなたは非常にお目が高いと思います。実際こんなに探求しがいがあり,臨床に役に立つ領域を,私はほかに知りません。
高次脳機能や神経心理学を学ぶということは,記憶,行動,言語,認知,注意,情動,時間認知といった人間を人間たらしめている能力と私たちの脳がどのように結びついているのかを探求するということにほかなりません。つまり,医学の枠を越えて人間とは何かを追究できるのです。
また,高次脳機能の診かたがわかると,現在患者数が急増している認知症の症状を具体的に理解することができるようになります。何となくのイメージで症状名をレッテルのように貼り付けるのではなく,どの脳部位が侵されているかを想定し,何ができないのか(そして何ができるのか)を見立て,患者さんや家族が何に困っているか,どうすれば満足のいく生活をすることができるかまで考えられるようにもなるのです。世界中で加速度的に増加している認知症を診ることができる能力は,これからの社会において医療者に求められる必須のスキルと言えるでしょう。
そして,これはここだけの話ですが,この領域に対して苦手意識を持つ人が多いので競争が少なく,勉強すればすぐに頭一つ抜けることができます。もう少し頑張ることができれば,専門家として周りから頼られる存在になることも難しくありません。
どうでしょうか。なんだか少しやる気が湧いてきませんか。
本シリーズは,これから高次脳機能という大海原に漕ぎ出そうとしている未来の仲間たちに向けて,私の現在の仲間たちと一緒につくりました。読み進めていただけるとわかりますが,できるだけ平易な文章で楽しく高次脳機能/神経心理学の基本がわかるようにしてあります。かといって内容のレベルを下げることはしていません。
最初に読んでわかること,もう一度読んだときにわかること,さまざまな経験を経た後でようやくわかること,いくつかのレイヤーが積み重なって本シリーズはできています。ぜひお手元において何度も読み返していただければ,編者としてこれほどうれしいことはありません。
さあ私たちの教室で一緒に学び,一緒に楽しみましょう!
河村 満
まえがき
本書は,「わかりやすい」「役に立つ」「深掘りできる」を目標に執筆しました。「わかりやすい」を達成するために,失行というわかりにくい概念をどのように表現するかを考えました。第1章は,「動き」と「道具」から理解する方法でまとめました。この章は失行とは何かを考える手がかりになると思います。第2章は,「失行の考え方がどのようにできてきたのか」を理解することで,失行を理解できるのではないかと考え,失行の考えかたの成立から現在までの経緯をまとめました。
第3章は失行に関係する脳病巣と疾患(病気),第4章は失行の評価からリハビリテーションについてまとめています。ともに臨床に「役立つ」内容をめざしました。第5章は脳神経内科をローテートしている研修医を中心としたダイアローグ形式の中で臨場感を持って失行を理解していく構成になっています。
この本の読みかたは自由です。どの章から読んでも構いません。各章は単独でもある程度完結していますので,知りたいことが関係している章だけ読んでも構いません。例えば第5章だけ読んでも読み物として成立していますが,関連した内容が書かれている章やページがわかるようになっていますので,そちらも参照していただくと理解が深まります。また,関連した事項についてのcolumnを挿入していますので,「深掘り」したい方は併せて読んでください。第1章から第4章の章末には,まとめやQ&Aもありますので知識の整理,確認にお役立てください。もちろん最初から最後まで通読いただいても,理解しやすい構成になっています。
本書を読んで,失行症状がどのようなものなのかを見て確かめたいと思われる読者もいらっしゃると思います。そのような方には『≪神経心理学コレクション≫失行』がお勧めです。2008年に医学書院から発刊された書籍です。河村満先生,山鳥重先生,田邉敬貴先生の鼎談で構成されていて,失行の典型症候を動画に収めたDVDが付録として付いています。本書の中でも,『失行』のDVDのどの収録動画が関連しているかがわかるように記載しています。
私事ですが,私は2007年から2008年にかけて半年間,当時の昭和大学の神経内科の教授であった河村先生のもとに国内留学していました。そのときに臨床心理士の小早川睦貴先生の手伝いをして,録音の書き起こし原稿や鼎談時に供覧したビデオの整理などをしました。付録のDVDはそのときのビデオが編集されたものです。ぜひ本書と併読していただけるとさらに理解が深まると思います。
2025年9月
近藤正樹
目次
開く
第1章 どうして,失行は難しいのか──「動き」と「道具」を手がかりに
イントロダクション
なぜ「動き」と「道具」が重要なのか?
■ 失行の定義は難しい
■ とっかかりとしての「動き」と「道具」
「動き」の話
■ 「動き」とは何か
■ 「動き」はどのように調節されるのか
■ 「動き」はイメージからつくり出される
■ 「動き」のしくみ
・ 運動を支配しているのはどこか?
・ 運動の指令はどこを通って伝わるのか?
■ 「動き」の障害メカニズム
■ 「動き」を表現する言葉
・ 運動,動作,行為・行動
・ 運動,動作,行為,行動が名前に入った症候
・ ジェスチャーとパントマイム
「道具」の話
■ 道具とは何か
■ 道具を使うための2つの機能
■ 人類の進化,発達からみる道具使用
■ 道具はどのようにしてつくられ,使われるようになったのか
■ ヒトの発達過程と道具使用
確認のためのQ&A
第2章 失行の「始まり」から「現在地」まで──失行の本質を理解する
イントロダクション
本章のあらすじ
Liepmann以前の「失行」
■ 動作はどのようにつくり出されるのか
■ 動作がうまくできなくなるのはなぜか
・ ①精神麻痺(Seelenlähmung 独, mind palsy 英)
・ ②失象徴(Asymbolie 独, asymbolia 英)
■ Liepmann登場
Liepmannの失行理論/失行モデル
■ Liepmannの一例報告
・ ①予測された温存領域
・ ②予測された損傷部位
・ ③病理所見
■ Liepmannの失行理論の特徴
・ ①除外的な定義
・ ②左大脳半球に優位性がある
・ ③左側失行における脳梁損傷の役割
・ ④左頭頂葉の重要性
・ ⑤失行を3つに分類
■ Liepmannの失行モデルと分類
■ 動作を生み出す過程のモデル
■ 3つの失行分類の病変部位のモデル
Liepmannとは異なる失行理論
■ 失行中枢(Kleist)
■ 全体論からみた失行の理解(Marrie)
■ 大脳生理学からみた失行の解釈(Jackson, von Monakow, Brun)
Liepmannの失行理論から現在の失行理論へ
■ 構成失行,着衣失行の独立
■ 観念性失行の解釈の変遷
■ Liepmannの失行モデルの改訂
・ ①行為産生過程モデル
・ ②行為概念系・行為産生系のモデル
・ ③道具使用のモデル
確認のためのQ&A
章末付録 もう少し掘り下げたい人のための失行研究史
Pick(1851~1924)/道具使用の障害
Grünbaum(1885~1932)/失行失認
Morlaas(1895~1981)/使用の失認
Denny-Brown(1901~1981)/磁性失行と反発性失行
De Renzi(1924~2014)/使用の健忘
Geschwind(1926~1984)/離断症候群と失行
Signoret(1933~1991)/身振り素,運動素
Goldenberg(1949~)/失行の症候病巣関連研究
Osiurak(1981~)/道具使用モデル
第3章 失行の原因──病変部位と関連疾患を理解する
イントロダクション
失行に関係する病巣
■ 第2章のおさらい
■ 失行症状と脳病巣──Liepmann以後の報告から
・ 肢節運動失行と中心前回・中心後回
・ 観念性失行と左頭頂葉
失行をきたす疾患
■ 脳梗塞で起こる失行と神経変性疾患で起こる失行の違い
・ ①病巣の広がりの違い
・ ②症候の複雑性の違い
■ 脳梗塞
■ 神経変性疾患
・ 大脳皮質基底核変性症(CBD)
・ アルツハイマー病(Alzheimer disease:AD)
・ ピック病〔前頭側頭葉変性症(FTLD)〕
・ 原発性進行性失行症(primary progressive apraxia)
■ 局所損傷を伴う疾患
・ 脳出血
・ 脳腫瘍
・ 感染性・自己免疫性の炎症性疾患
確認のためのQ&A
第4章 失行の評価と支援──診察・検査法と介入を理解する
失行の評価
■ 神経学的診察
・ ①運動麻痺
・ ②筋緊張異常,不随意運動
・ ③運動失調
・ ④感覚障害
・ ⑤理解障害
・ ⑥視覚性失認と意味記憶障害
■ 失行のための診察
■ 失行のための診察に用いる検査バッテリー
・ ①WAB失語症検査,下位項目(行為)
・ ②標準高次動作性検査(Standard Performance Test for Apraxia:SPTA)
■ どのように誤るのか(誤反応分析)
■ 評価の後に失行の特徴を考える
・ ①観念性失行
・ ②肢節運動失行
・ ③観念運動性失行
・ ④その他の“失行”
失行評価の実際の流れ
・ ①初回面接
・ ②スクリーニング
・ ③総合的検査
・ ④検査結果をリハビリテーションに活かす
・ ⑤実生活での能力評価
失行のリハビリテーション
■ 失行にはどのようなリハビリテーションを行ったらよいのか
・ コクランデータベースにおける介入方法
・ Heilmanグループのテキストブックでのリハビリテーション
・ リハビリテーション私論
■ 失行症例のリハビリテーションの複雑さ
■ 今後の展開
確認のためのQ&A
第5章 失行の教室──症例から失行を理解する
イントロダクション
Lesson1 「左頭頂葉病変の失行」を学ぶ
幕間小話 頭頂葉はスクランブル?
Lesson2 「失語と失行」を学ぶ
幕間小話 左利きの失行
Lesson3 「脳梁病変の失行」を学ぶ
幕間小話 脳梁の毀誉褒貶
Lesson4 「CBDの失行」を学ぶ
幕間小話 原著にみられるCBDの特異な症状
Lesson5 「意味記憶障害と失行」を学ぶ
幕間小話 認知症患者とその家族
column
固有感覚と固有感覚受容器
他人の手徴候
動きに関係した英語表現
「木器時代」はなぜないのか
失行研究黎明期の時代背景:局在論(連合主義)vs.全体論
Hugo Karl Liepmann
記憶の痕跡(engram)
プラキシコン(praxicon)
秋元波留夫先生(1906~2007)の功績
「失行」という訳語はいつから使われているのか
日本国内の失行研究の動向
感覚鈍麻と失行の関係
脳梁と拮抗性失行
大脳皮質基底核症候群(CBS)
パーキンソン病と失行
ミラーニューロンと模倣
WAB失語症検査日本語版
身体物品化現象(body part as object:BPO)
新しい機器をどう考える?
あとがき
索引
書評
開く
わかりやすさと体系的な理解の「絶妙な按配」
書評者:中川 賀嗣(北海道医療大教授・リハビリテーション科学)
本書は高次脳機能障害に携わり始めて間もない方々が,失行を基礎から学び,理解することをめざした書である。失行の概念,症状は難解であり,そのため読者にとって説明が詳しすぎると整理しづらいものとなり,逆に簡潔すぎると言葉足らずで,文脈を理論的に追跡できなくなる可能性がある。本書は平易さを保ちながらも,体系的に理解できる説明がなされているため,絶妙な按配の入門書というのが私の印象である。
失行を理解するには,「運動機構」(ボトムアップ的な理解)とその「制御方法」(トップダウン的な理解)の両方の理解が求められるが,本書は,この2つをわかりやすく解説し,網羅してくれている。特に図を豊富に用い,コラム(補足説明)を活用することで,用語や概念の難しさを解消している。本書のわかりやすさ,面白さは各章の見出しからも垣間見ることができる。例えば第1章は「どうして,失行は難しいのか―『動き』と『道具』を手がかりに」である。こうしたわかりやすい表現,魅惑的な表現での解説が,「運動・感覚を支える生理学的知見」「古典的失行論から現在までの主な失行論」「評価の実践的な方法」「リハビリテーションの意義」についてなされている。
また本書は,最近の研究も考慮している。例えば失行型の一つに道具の使用動作が障害されるタイプがあることは以前より知られていたが,その使用動作の可否を評価する課題内容の違いには,ほとんど注目されてこなかった。それが最近では,道具を手にせずにパントマイムで再現させるのか,手にして再現させるのか,あるいは道具の使用対象も視覚提示しているのかどうかなど,具体的に条件を規定して成否を評価するようになっている。それは同じ使用動作でも,これらの条件が異なることが,動作の成否に影響することが知られるようになっためである。
本書はこうした最近の失行研究の動向をも踏まえた,失行の本質にも迫る書といえる。
近藤正樹氏とめぐる失行ガイドツアー
書評者:平山 和美(仙台青葉学院大教授・脳神経内科学)
本書は,失行の診療と研究に,いくつもの重要な貢献を続けてこられた近藤正樹氏による待望の解説書です。
「失行」は,高次脳機能障害の一つです。言葉を話したり理解したりすることが難しくなる「失語」や,出来事を覚えられなくなる「健忘」などに比べて,なじみの少ない言葉かもしれません。失行では脳の損傷によって,習熟しているはずの道具が使えなくなったり,手指を細やかに動かすことができなくなったり,習熟しているはずの身ぶりが行えなくなったりします。行為ができなくなるのですから,生活上の重大な問題となります。失行でこれらの問題が生じるのは,力が弱い(運動麻痺),持続的な筋収縮の程度が正しくない(筋緊張異常),勝手に動いてしまう(不随意運動),協調して動かすことができない(運動失調)などのためではありません。また,見たものが何かわからない(視覚性失認)ためや,ものの意味についての知識がなくなってしまった(意味記憶障害)ためでもありません。このような条件を満たす「失行」が起こり得ることからは,脳の中に上記の諸病態で損なわれている機構とは別に,行為そのものにかかわる仕組みのあることがうかがわれます。
失行の研究に最大の貢献をしたLiepmann(1863-1925)をはじめとして,現在まで多くの人々がその仕組みを明らかにしようと努力してきました。また近年は,脳梗塞などの局所病変によるものだけでなく,アルツハイマー病などの変性疾患に伴って生じる失行も注目されています。不思議で,難しそうな症状ですね。
しかし,心配は要りません。本書には,この症状を理解し,他の症状でないことをチェックし,生じている問題を抽出し,症状のある患者さんを支援していくために必要な事柄が,漏れなく,大変わかりやすく,丁寧に記されています。それは,各章のタイトルからもうかがえます。第1章「どうして,失行は難しいのか――『動き』と『道具』を手がかりに」,第2章「失行の『始まり』から『現在地』まで――失行の本質を理解する」,第3章「失行の原因――病変部位と関連疾患を理解する」,第4章「失行の評価と支援――診察・検査法と介入を理解する」,第5章「失行の教室――症例から失行を理解する」。
私は特に,第2章に記された,Liepmannの研究の道筋に心を動かされました。一人の患者さんと出会い症状をよく調べて仕組みについての仮説を立て,その後の複数の患者さんでの経験に従って仮説を修正,重要な点については(いまから100年以上前に!)多数例での検討を行ったという科学的な姿勢。第5章は,二人の研修医が指導医と会話し,さらに言語聴覚士や作業療法士,臨床心理士のもとへも訪れて,失行について学んでいく設定になっています。脳画像も豊富に示され,臨在感に満ちています。そこには,著者である近藤氏や氏の周囲の人たちの,温かなチーム医療の姿が反映されているように思われます。
皆さまも本書を手に,近藤氏の案内で失行を探る営みに参加しませんか?
二重の“やさしさ”で学ぶ失行
書評者:早川 裕子(横浜市立脳卒中・神経脊椎センターリハビリテーション部)
書店の棚でもひときわ存在感を放つ,柔らかなピンク色の表紙。第1弾の石原健司先生による『記憶障害の診かた』がパステルブルーだったので,2冊並ぶとシリーズとしての世界観が立ち上がる。医学書は手に取りにくい印象があるが,本シリーズは思わず触れてみたくなる可愛さがある。シルバーであしらわれた“Neuropsychology for Beginners”の文字や,ガルの骨相学を思わせるイラストもシリーズ編集者である河村満先生の美意識が感じられる。第3弾の「失語」の色調も楽しみになる。
本書の魅力は,近藤正樹先生の語り口に集約されると思う。近藤先生といえば,学会で鋭い質問を投げかける姿が印象的だ。発表者が見落としがちな視点をすくい上げるその問いは,知識の深さと臨床経験の厚みに裏打ちされている。その思考は,1章から3章に丁寧に示されている。一方で,近藤先生の人柄をより強く感じるのは4章以降だ。長年,患者さんと向き合い,若い医師やコメディカルを育ててきた医療者としての温かさと誠実さが,語り口に自然とにじんでいる。まるで同じ教室で,先生のお話を聞いているようだ。
そして本書には,二重の“やさしさ”がある。語り口の“優しさ”と,失行を初めて学ぶ読者にも寄り添う“易しさ”だ。失行はしばしば「ややこしい」と敬遠されがちな領域だが,近藤先生は「確かに複雑さはあるけれど,こんなふうに整理してみるとわかりやすいよ」と語りかけてくれる。若手にも,そして私のような昭和セラピストにも等しく届く,稀有な入門書だと感じた。
細部の親切さにも触れたい。例えば,海外の研究者名にカタカナのルビが振ってある点だ。お恥ずかしい話だが,私はずっとDe Renziを「初めの読みはデ?ド?」と迷っていたし,Poeckの読みも曖昧だった。そんな悩みを軽くしてくれる,嬉しい工夫である。また,関連項目として〈神経心理学コレクション〉やシリーズ第1弾への参照が随所にあり,学びが立体的に深まる点もありがたい。
興味深かったのは,失行を発達や進化から捉える視点だ。失行という現象の背景にある人間の営みの歴史を考えさせられた。一方で,ケースの深掘りをもっと読みたいという思いも残ったが,これは同じ医学書院から刊行された『ひもとく・理解する・支援する 失行のリハビリテーション』を併読することで,補完されると感じた。
読後,失行の概念が大きく変わったわけではないが,むしろ,もっと臨床がしたくなった。机上の理論だけではない実際の失行の世界を,今いちど丁寧に見つめたいという気持ちが強くなった。本書は,若手にもベテランにも,そして「失行って苦手だな」と思ってきた人にも道標となる。シリーズの第3弾を手に取る日が楽しみになる,そんな温度のある一冊だ。
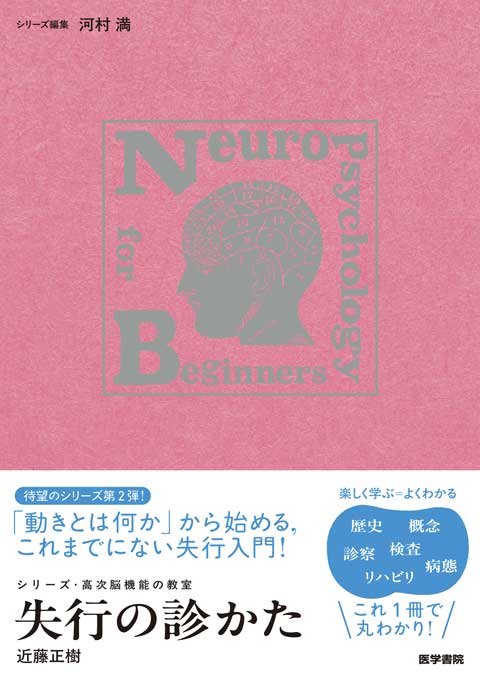
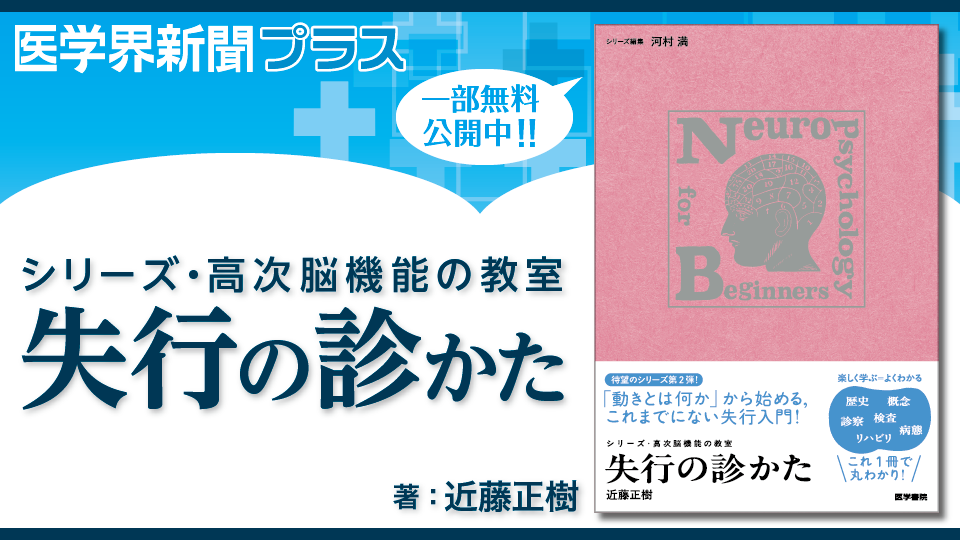
![失行[DVD付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2016/0457/5816/5662.jpg)