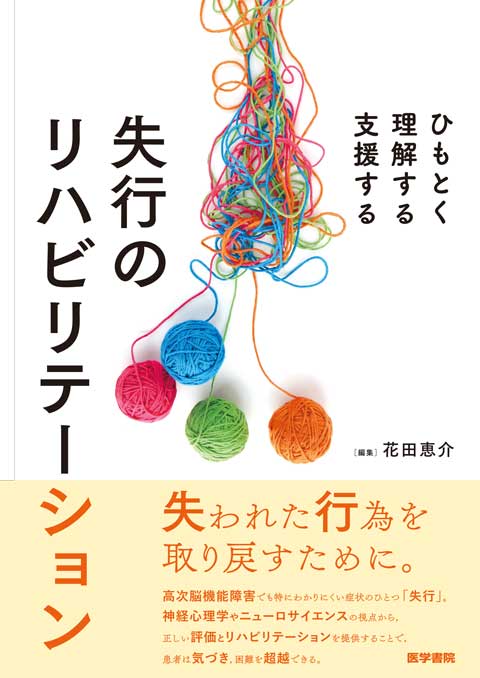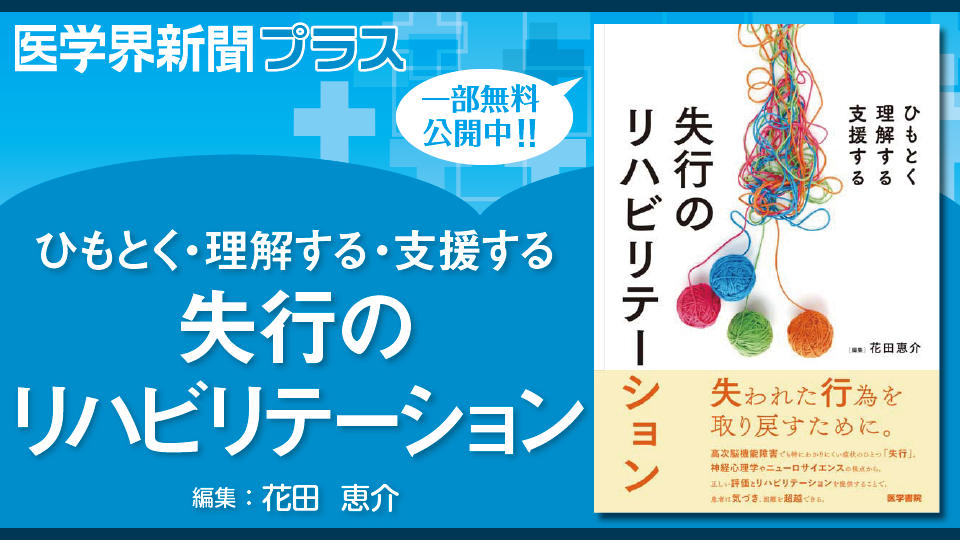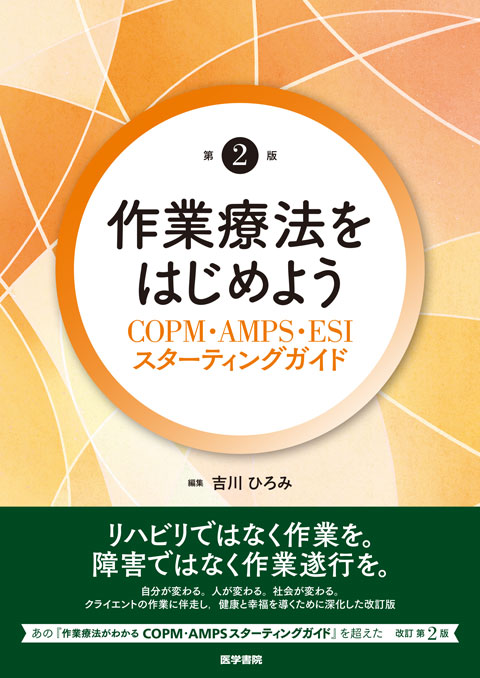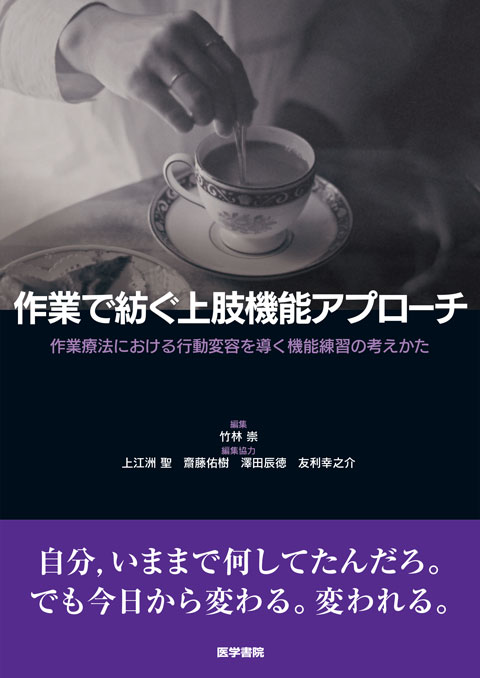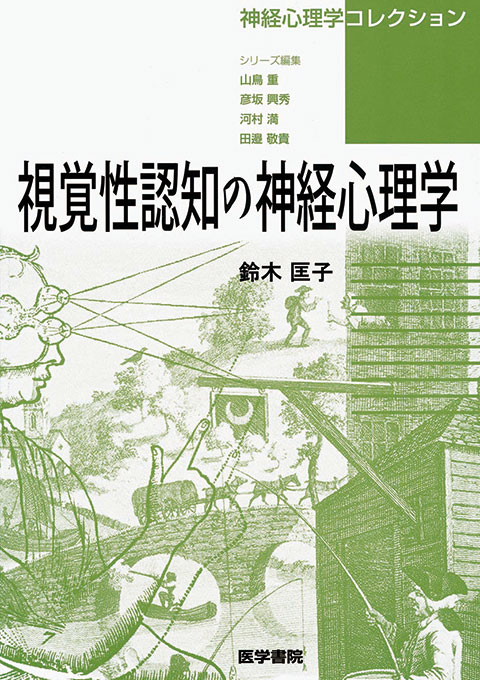ひもとく・理解する・支援する
失行のリハビリテーション
失われた動作や行為の本質をひもとき、学び、支援に活かす
もっと見る
高次脳機能障害は身体障害に比べると目に見えにくく、療法士にとって、患者への対応に難渋することも少なくない。本書は、その代表的な障害である「失行」に焦点を当て、神経心理学やニューロサイエンスの視点から症状の本質を探っていく。リハビリテーションや用いられるアウトカム尺度の現況をバランスよく示すとともに、臨床での支援例も多数収載。複雑にからみあった症状をひもとくことで、患者に「気づき」をもたらす1冊。
| 編集 | 花田 恵介 |
|---|---|
| 発行 | 2025年11月判型:B5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-05585-7 |
| 定価 | 4,950円 (本体4,500円+税) |
更新情報
- 序文
- 目次
序文
開く
序──症状を「ひもとく」ことの意味
手を動かす力はあるのに,なぜか動作がちぐはぐになる.道具は手に取れるのに,どう使えばよいのかわからない──.
失行は,高次脳機能障害のなかでも,特にわかりにくい症状の1つかもしれません.そんな患者さんの姿を前に,私たちセラピストは問いを立てます.
どうしてこのようなことが起きているのだろう?
何がこの方の「できなさ」を生んでいるのだろう?
どうすれば,この方が「またできる」ようになるのだろう?
この問いを持ち続け,1つひとつの症状に丁寧に向き合うこと.それこそが,本書のタイトルにある「ひもとく」営みであり,私たちセラピストに与えられた大切な役割だと感じています.セラピストは,日々決まった時間のなかで,患者さん一人ひとりの症状や生活に寄り添い,注意深い観察と対話を重ねながらかかわることができます.そのなかで見えてくる「小さな変化」や「意外なつまずき」こそが,絡み合った症状の本質を浮かび上がらせてくれる貴重なヒントになるのです.
とはいえ,そのヒントを私たちだけで完結してしまっては意味がありません.
ひもといた内容を,できる限り丁寧に,わかりやすく患者さんに説明する.すると,「そうだったのか」と気づきを言葉にしてくださる方がいらっしゃいます.なかには,ご自身で工夫し,私たちが想像もしなかった方法で困難を乗り越えていく方もいらっしゃいます.
そうした姿に私たちが学び,また次の支援へと活かしていく──.これこそが,「理解する」,そして「支援する」という営みの本質であると私は考えています.
本書が読者の皆様にとって,実臨床に役立つ視点や知識を深める機会となれば幸いです.
本書の刊行には,5年以上の歳月を要しました.
編著者である私自身,今わかっていることを,できるだけ正確に,そして誤解なく伝えることの難しさ──それを痛感し続けた5年間でした.
そのようななか,医学書院の北條立人氏には,変わらぬ姿勢で辛抱強く伴走していただきました.幾度となく励まし,支えてくださったことに,心より感謝申し上げます.
畿央大学の信迫悟志先生をはじめ,共著者の先生方には,それぞれの専門性と臨床経験をもとに,渾身の原稿をご執筆いただきました.いずれの章も,実践的でありながら深い洞察に満ちた,大変読み応えのある内容です.執筆者のご尽力なくして,この書籍は完成し得ませんでした.心からの敬意と感謝を申し上げます.
また,本書の執筆を「やってみないか」と最初にお声がけくださったのは,大阪公立大学の竹林崇先生でした.あのときの何気ないひと言が,私にとって大きな一歩となりました.さらに,仙台青葉学院大学の平山和美先生には,神経心理学的症状の解説をはじめ,全体構成にわたり多くのご助言を賜りました.内容面のみならず,構成や表現においても,たびたび的確なご指摘をいただき,大きな支えとなりました.
本書にかかわってくださったすべての皆様に,深く御礼申し上げます.
2025年9月
花田恵介
目次
開く
第I章 動作・行為にかかわる神経心理学
1 神経心理学とはなにか──障害名や症候名にとらわれず症状をみる
2 同名性視野欠損
3 視覚性失認
4 観念性失行
5 観念運動性失行
6 肢節運動失行(拙劣症)
7 把握の障害
8 道具の把握の障害
9 物品の意味記憶障害
10 精神性注視麻痺(眼球運動失行)
11 視覚性注意障害
12 視覚性運動失調
13 半側空間無視
14 半身無視
15 着衣失行
16 把握反射
17 本能性把握反応
18 使用行動と道具の強迫的使用
19 運動無視
第II章 動作・行為の障害にかかわるニューロサイエンス
1 行為処理モデルを参考に介入の指針を定める
2 視覚の3つの経路──背背側路,腹背側路,腹側路
3 体性感覚の2つの経路──背側路,腹側路
4 言語の2つの経路──背側路,腹側路
5 行為のオンライン制御機構
6 アフォーダンスの神経機構
7 ジェスチャーエングラムの神経機構
8 シミュレーションの神経機構
9 エラー検出の神経機構
10 道具関連動作に必要な2つの知識──道具の操作の知識,道具の機能の(意味的)知識
11 機械的問題解決──技術的推論の神経機構
12 道具使用パントマイム(他動詞ジェスチャー)と自動詞ジェスチャーの神経機構
13 模倣の神経機構
14 行為の系列化,行為の抑制の神経機構
第III章 動作・行為の障害に対するリハビリテーション
1 動作・行為の障害に対するリハビリテーションの原則
2 戦略的訓練(Strategy training)と直接的訓練(Direct training)
3 ジェスチャートレーニング(Gesture training)
4 Naturalistic Action Therapy(NAT)
5 Cognitive Orientation to daily Occupational Performance(CO-OP)
6 工学機器を用いた介入
7 着衣障害に対するリハビリテーション
8 非侵襲的脳刺激法(NIBS)──rTMS,tDCS
第IV章 動作・行為の障害に対する評価
1 臨床で評価する前に知っておきたいこと
2 症候分析のはじめかた──収集した情報と臨床面接を統合する
3 認知機能のスクリーニング検査の意味
4 言語的な問題の評価
5 視力・視野・眼球運動の評価
6 視覚認知の評価
7 視覚-運動協調の評価
8 道具使用(行為)の評価
9 標準化された上肢機能検査
10 無視症候群の検査
11 標準化されたADL,IADL評価
12 A-ONE
13 介護負担
第V章 動作・行為の障害のある症例への評価とその対応
1 症例報告のまとめかた
Case.1 大脳皮質基底核症候群により重度の書字障害をきたした症例──ICTによる介入
Case.2 視覚性失認による電子機器の操作障害例
Case.3 視覚性注意障害による電子機器の使用障害例
Case.4 多彩な視空間認知障害によって行為の問題が生じた症例
Case.5 視覚性運動失調(ataxie optique)をきたした症例の介入経験
Case.6 道具の使用方法に合わせて適切な把握ができなかった症例
Case.7 道具を使用する向きに主な問題が生じた症例
Case.8 道具とそれに適した対象物との対応関係を誤る症例
Case.9 習得された動作の解放現象と意図的な行為とのconflict
Case.10 日常生活に支障をきたすほど action slipが多発した外傷性脳損傷例
Case.11 就寝時の病的把握現象に対し手袋装着が有効だった症例
Case.12 「してしまう」行為障害を認めた前頭葉損傷の症例
Case.13 ADSによって道具の使用障害が生じた症例
Case.14 左上肢の運動無視を呈した症例に対する修正CI療法の試み
Case.15 衣服に目印をつけることで着衣が可能になった着衣障害の症例
Case.16 観念運動性失行によるジェスチャー障害例に対する感覚情報変換練習
Case.17 観念運動性失行によるジェスチャー障害に対する介入
索引