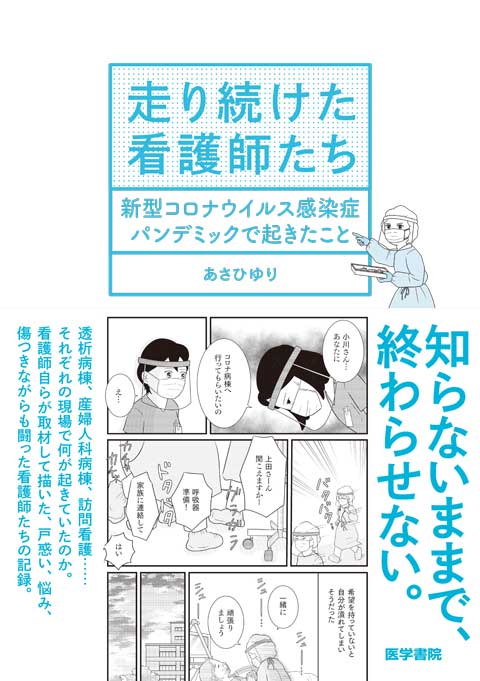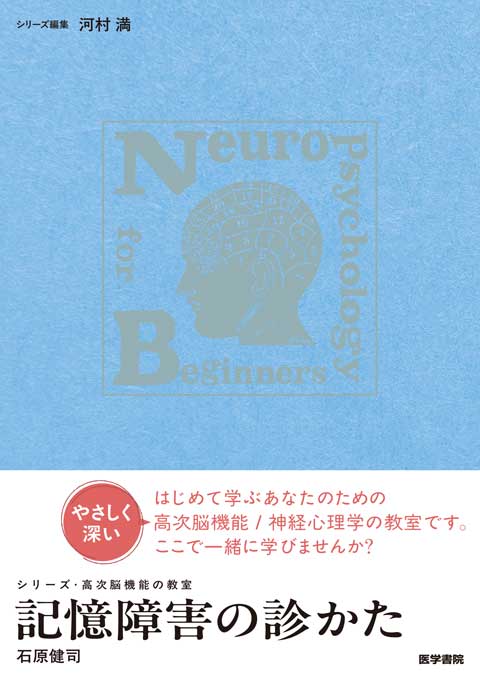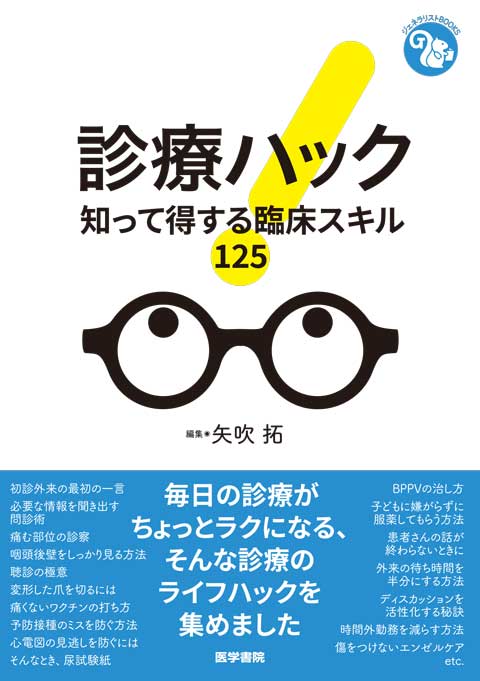MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.07.08 医学界新聞:第3575号より
《評者》 坂本 史衣 板橋中央総合病院院長補佐 / QIMSセンター副センター長
名もなき看護師たちの物語が静かに問いかけるもの
『走り続けた看護師たち』で紹介されるエピソードの多くは,新型コロナウイルス感染症(以下,コロナ)の流行が国内で本格化した2020年春の医療現場を舞台としています。ワクチンはまだ存在せず,確立された治療法もなく,個人防護具,検査,病床,人員と,あらゆるものが不足していた時期でした。新興感染症のパンデミックに対応できる医療体制が整っていない中で,コロナ診療とそれまでの日常診療を両立させるというミッションをにわかに担うことになった医療現場は,それでも,いつものように,静かに回っていました。ベッドサイドには,ガウン,手袋,N95マスク,ゴーグルを身につけた看護師がいました。回復を促し,合併症や事故を防ぎながら,少しでも快適に,前向きな気持ちで過ごせるように,患者とその家族に伴走する専門職たちです。
プロフェッショナルは,どのようなときも淡々と業務を遂行します。しかし,未知の感染症が流行している状況で,心配事がないはずはありません。当時,感染管理に従事していた私は,コロナ対応に当たる看護師たちとコロナについて何でも質問できるQ&Aセッションを頻繁に開催していました。何が自身や家族の感染につながるのか,また,どのように防ぐことができるのか。さまざまな制約がある中で,患者や家族のニーズをどうすれば満たせるのか。患者に最も近い存在であるが故に看護師たちが抱える心配事を一つずつ解消していくことが,当時の私の最も大切な仕事でした。
本書は,戦車に竹やりで立ち向かうような看護師の自己犠牲を美化したフィクションではありません。パンデミックに対応するための医療体制を理論的に語る政策提言書でもありません。看護師と漫画家という二つのスペシャリティをもつ作者・あさひゆりさんは,コロナの現場にいた複数の看護師へのインタビューを通じて,早くも忘れられつつある「あのときの日常」を本書の中で見事に再現しています。読者は,コロナ専門病棟,透析病棟,産婦人科病棟,そして,訪問看護の現場を巡りながら,当時の空気を肌で感じ,あのときを再び生きるような感覚を味わうでしょう。そこに登場する看護師たちは,何かを声高に訴えることはありません。ただ,抑えた語り口で綴られる出来事や思いを通じて,私たちは何を学んだのだろうか,次に備えるには何が必要だろうかと読者にさりげなく問いかけてきます。あのとき,走り続けた名もない看護師たちの物語を,本書を通して共有することの意味は,その問いに耳を傾けることにあると私は考えています。過ぎ去った日々がよみがえることで,私たちは立ち止まり,考え,次に備えることができるのです。
《評者》 前島 伸一郎 国立長寿医療研究センター 長寿医療研修センター長
高次脳機能が苦手でもわかる! 記憶障害の最良テキスト
本書は,河村満氏が編集する《シリーズ・高次脳機能の教室》の1冊として刊行されました。著者は,長年にわたり高次脳機能障害の診療と研究の最前線に立ち続けてきた石原健司医師(旭神経内科リハビリテーション病院)です。
石原氏は1995年に千葉大医学部を卒業後,昭和大,亀田総合病院,汐田総合病院などの神経内科で研鑽を重ね,2006年に昭和大神経内科講師に就任,16年より現在の旭神経内科リハビリテーション病院に勤務されています。神経症候の精緻な観察,神経病理に基づいた深い理解,そして画像診断における卓越した読影力を兼ね備えた,まさに現場と理論を融合する第一級の臨床家です。
その豊かな経験と知識は,本書にも余すところなく反映されており,「高次脳機能障害は苦手」と感じる臨床家にとって,まさに福音ともいえる内容となっています。専門的でありながらも丁寧で平易な記述が貫かれ,これほどまでにわかりやすく記憶障害を解説した書籍は,これまでほとんど例がありません。
構成は第1章「記憶の分類」から始まり,第2章「記憶障害の分類」,第3章「記憶障害を生じる脳病変部位と疾患」,第4章「記憶の検査方法」,そして第5章「症例検討」へと続きます。特に第3章では,疾患ごとの画像と詳細な模式図が豊富に掲載されており,視覚的理解を助けてくれます。第4章では,臨床現場で用いられる記憶検査が網羅的に紹介されており,読者が即座に実践へと結びつけられるよう工夫されています。
第5章の症例検討は,先生と生徒によるQ&A形式で進行し,記憶障害の評価から画像診断,診断確定に至るプロセスが臨場感あふれる筆致で描かれています。まるで診察室に同席しているかのような臨在感に満ちており,若手医師や学生にとって実に貴重な学びとなるはずです。
また,各章末には要点の整理と確認のためのQ&Aが付されており,知識の定着にも配慮されています。医学生や若手療法士はもちろん,日本神経心理学会と日本高次脳機能障害学会が共同で認定する「臨床神経心理士」資格の受験対策にも有用です。
加えて,コラム欄には“Squire”や“Tulving”といった記憶研究の大家の紹介や,「自伝的記憶の分類」「蛋白質異常症」の解説など,関連分野に関する知識が広がる工夫も随所に見られ,読み物としても飽きさせません。
《シリーズ・高次脳機能の教室》というシリーズ名にふさわしく,記憶障害の全体像を系統的かつ親しみやすく学べる本書は,医療関係者のみならず,心理学や脳科学に関心のある教養人にも広く薦めたい1冊です。
高次脳機能障害の臨床に携わる全ての人が座右に置くべき,まさに現場のための決定版といえるでしょう。
《評者》 山中 克郎 諏訪中央病院
臨床現場に「気づき」と「応用力」をもたらす本
本書を読み地元の公共温泉につかりながら,こんなことを考えた。初診外来で最初に「具合が悪いのはいつからですか」と聞き,いつまで元気だったかを確認して急性発症なのか慢性疾患なのかを判断することは重要である。「映像化」ができるくらい詳細に病歴を聴取することが大切だということも以前,指導医から聞き実践しようと心掛けている。これら「知っていると便利な臨床の智慧」を教えてもらうと診療がアップグレードする。
しかしながら,医療はサイエンス(知識や技術)だけでなく,アート(他人への優しさ)が大切である。印象的なのは,本書の「診察前のスキル」で取り上げられた,「名前を呼ぶ」という行為である。患者だけでなく,同僚スタッフに対しても名前を呼ぶという行動が,医療チーム全体の信頼関係を構築し,結果として診療の質を高めるという主張は,アートとしての医療の視点をわれわれに投げかける。
さらに本書は,身体診察においても「気づき」を与えてくれる。例えば殿部痛を訴える高齢者に対しては胸腰椎移行部の圧迫骨折を疑うべきであること,若年者の多発転移がんではAFPとhCGを測定し予後良好ながんを見逃...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。