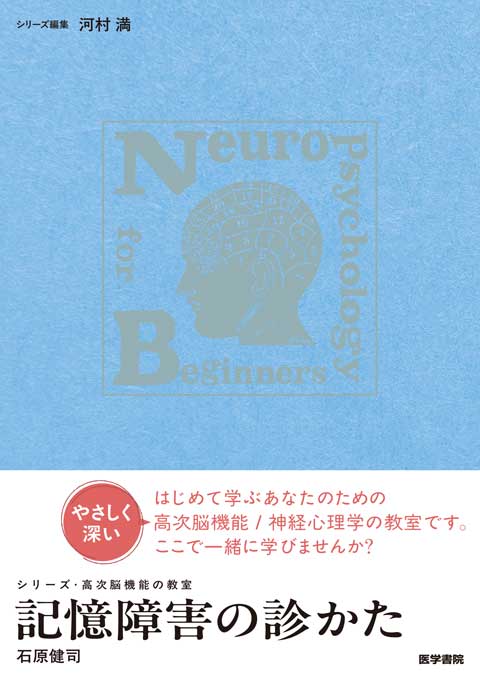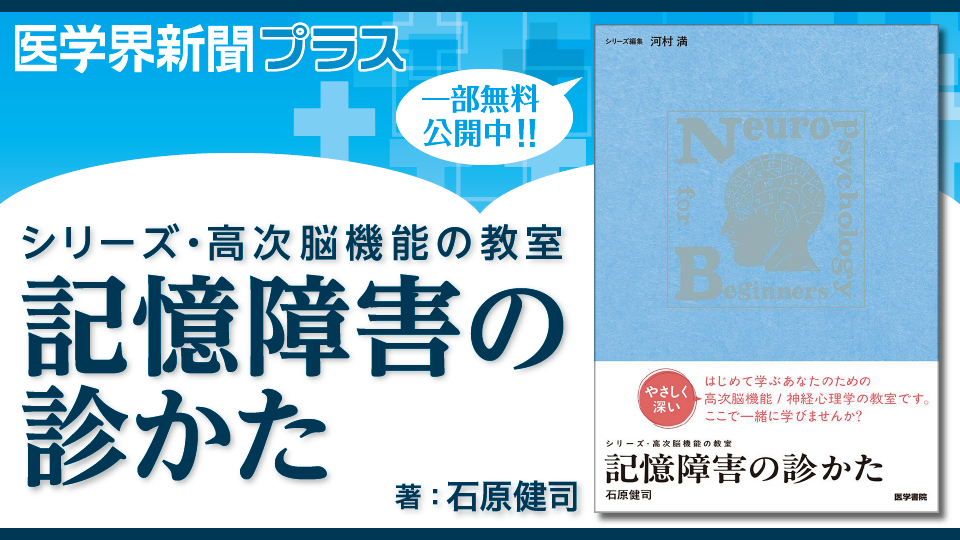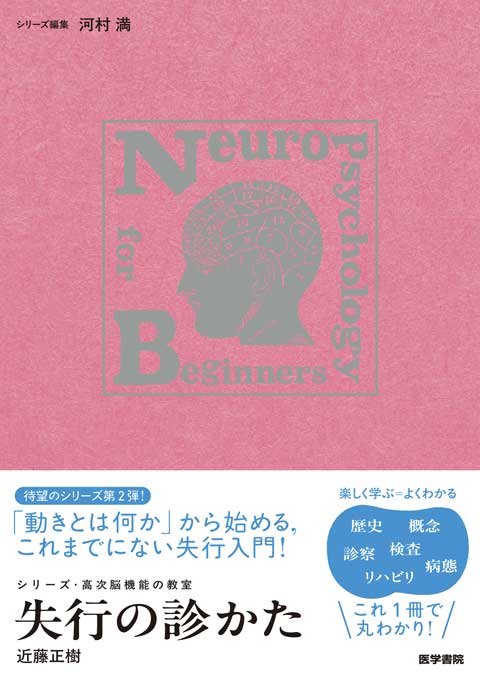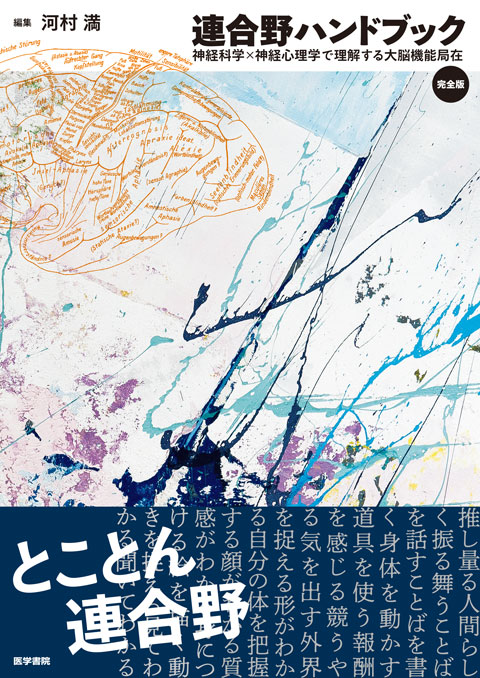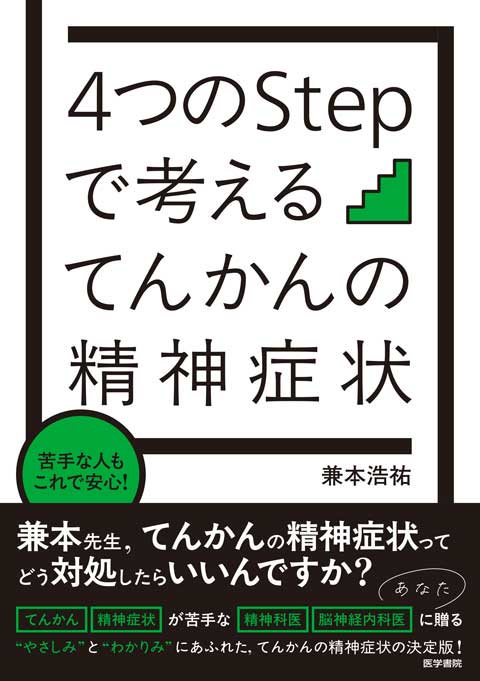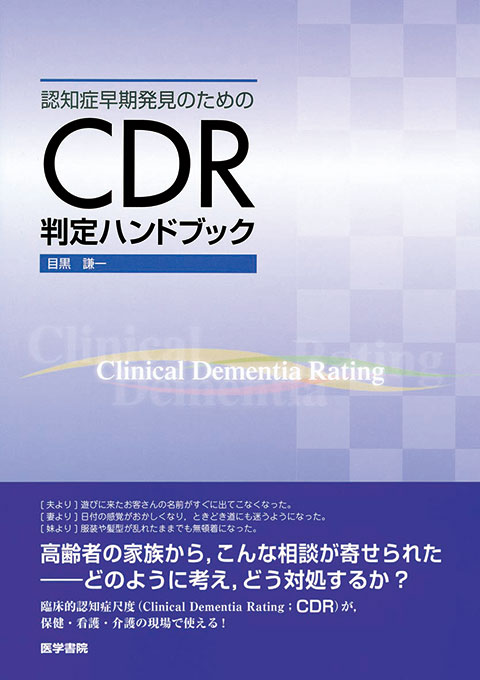記憶障害の診かた
記憶障害をどう診るか、記憶のしくみから検査法まで、やさしく深く丁寧に解説!
もっと見る
《シリーズ・高次脳機能の教室》第1弾! 認知症をはじめとするさまざまな疾患で生じる記憶障害=健忘を、誰にでもわかる言葉で丁寧に解説した最良の入門書。記憶にはどんな種類があり、それが障害されると何が起こるのか? 脳のどの部位が損傷すると記憶が失われるのか? 診断や検査の方法は? 臨床に必要な知識を網羅しながらも、やさしく深く楽しく解説。記憶の仕組みと記憶障害のメカニズムを学びたいすべての人へ。
| シリーズ | シリーズ・高次脳機能の教室 |
|---|---|
| シリーズ編集 | 河村 満 |
| 著 | 石原 健司 |
| 発行 | 2025年05月判型:A5頁:192 |
| ISBN | 978-4-260-06030-1 |
| 定価 | 3,850円 (本体3,500円+税) |
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2025.05.07
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
シリーズ編集者のことば/まえがき
シリーズ編集者のことば
本書を手にとっていただき,誠にありがとうございます。
本書を手にとられたということは,高次脳機能や神経心理学に興味はあるけれど「どうもよくわからない」という気持ちをお持ちなのではないでしょうか。私は40年間以上神経心理学を専門として臨床・研究を続けてまいりましたが,残念ながらいまだに皆さんと同じ気持ちです。それでも長く続けてこられた理由は,高次脳機能の不思議さ,またそれを探求する神経心理学の奥深さの一端に触れずっと魅了され続けてきたからなのです。いまだに,高次脳機能/神経心理学の臨床は日々驚きの連続で,興味が尽きません。
その立場から申し上げますと,高次脳機能/神経心理学に興味を持ち,本書を手にとったあなたは非常にお目が高いと思います。実際こんなに探求しがいがあり,臨床に役に立つ領域を,私はほかに知りません。
高次脳機能や神経心理学を学ぶということは,記憶,行動,言語,認知,注意,情動,時間認知といった人間を人間たらしめている能力と私たちの脳がどのように結びついているのかを探求するということにほかなりません。つまり,医学の枠を越えて人間とは何かを追究できるのです。
また,高次脳機能の診かたがわかると,現在患者数が急増している認知症の症状を具体的に理解することができるようになります。何となくのイメージで症状名をレッテルのように貼り付けるのではなく,どの脳部位が侵されているかを想定し,何ができないのか(そして何ができるのか)を見立て,患者さんや家族が何に困っているか,どうすれば満足のいく生活をすることができるかまで考えられるようにもなるのです。世界中で加速度的に増加している認知症を診ることができる能力は,これからの社会において医療者に求められる必須のスキルと言えるでしょう。
そして,これはここだけの話ですが,この領域に対して苦手意識を持つ人が多いので競争が少なく,勉強すればすぐに頭一つ抜けることができます。もう少し頑張ることができれば,専門家として周りから頼られる存在になることも難しくありません。
どうでしょうか。なんだか少しやる気が湧いてきませんか。
本シリーズは,これから高次脳機能という大海原に漕ぎ出そうとしている未来の仲間たちに向けて,私の現在の仲間たちと一緒につくりました。読み進めていただけるとわかりますが,できるだけ平易な文章で楽しく高次脳機能/神経心理学の基本がわかるようにしてあります。かといって内容のレベルを下げることはしていません。
最初に読んでわかること,もう一度読んだときにわかること,さまざまな経験を経た後でようやくわかること,いくつかのレイヤーが積み重なって本シリーズはできています。ぜひお手元において何度も読み返していただければ,編者としてこれほどうれしいことはありません。
さあ私たちの教室で一緒に学び,一緒に楽しみましょう!
2025年2月
河村 満
まえがき
本書は日本神経学会学術大会で開催されているハンズオンセミナー「高次脳機能の評価と解釈」の講義内容をベースに,セミナーでは伝えきれない内容,高次脳機能や神経心理を学ぶうえで知っておいていただきたい事柄を加筆し,作成したものです。初学者の方でも理解できるよう,基本的な内容から始め,読み進めるに従って臨床場面でも応用できるような内容の構成にしました。それぞれの章に,目標,まとめ,確認のためのQ&Aをつけてありますので,知識の整理にご活用ください。
読者の皆さんが「記憶」についての理解を深められ,記憶障害の臨床に興味をお持ちいただければ,筆者にとって無上の喜びです。
2025年2月
石原健司
目次
開く
第1章 記憶の分類
イントロダクション
記憶する内容に基づく分類
▪ 宣言的記憶(陳述記憶)
・ エピソード記憶
・ 意味記憶
▪ 手続き記憶
・ 技能
・ プライミング
記憶情報を保持する時間に基づく分類
▪ 即時記憶
▪ 近時記憶と遠隔記憶
確認のためのQ&A
第2章 記憶障害の分類
イントロダクション
エピソード記憶の障害
意味記憶の障害
手続き記憶の障害
特殊な記憶障害
▪ 一過性全健忘(TGA)
▪ てんかん性健忘
記憶障害と鑑別を要する病態:失語と失認
記憶障害の周辺:作話と見当識障害
▪ 作話
▪ 記憶錯誤
▪ 妄想
▪ 見当識障害
確認のためのQ&A
第3章 記憶障害を生じる脳病変部位と疾患
イントロダクション:記憶と関係する脳のシステム
エピソード記憶の形成と想起に関係する脳部位と疾患
▪ 側頭葉内側性健忘
▪ 間脳性健忘
▪ 前脳基底部性健忘
▪ 頭頂葉内側性健忘(脳梁膨大後域健忘)
意味記憶の貯蔵に関係する脳部位と疾患
手続き記憶の形成に関係する脳部位と疾患
確認のためのQ&A
第4章 記憶の検査方法
イントロダクション:記憶の検査を始める前に
エピソード記憶の検査方法
▪ 前向性健忘の検査
・ 言語性記憶の検査
・ 視覚性記憶の検査
・ 全般的な記憶検査
・ 行動記憶の検査
▪ 逆向性健忘(遠隔記憶)の検査
・ 自伝的記憶の検査
・ 社会的出来事記憶の検査
意味記憶の検査方法
手続き記憶の検査方法
確認のためのQ&A
第5章 症例検討
症例1 パペッツの回路の損傷により記憶障害は生じうるか?──単純ヘルペス脳炎例
症例2 Treatable amnesia──脳弓病変による前向性健忘例
症例3 遠隔記憶が単独で障害される──孤立性逆向性健忘例
症例4 突然発症する記憶・見当識の障害──一過性全健忘例
症例5 頭部外傷の後遺症──外傷後健忘例
症例6 てんかんと記憶障害──てんかん性健忘例
〈column〉
Larry Ryan Squire(1941~)
Endel Tulving(1927~2023)
エピソード記憶と意味記憶は完全に分けられるか?
語義失語と意味記憶障害,意味性認知症
マジカルナンバー
失行と手続き記憶の障害
自伝的記憶の分類
逆向性健忘の時間勾配
人生の時間軸とエピソード記憶
大脳辺縁系
パペッツの回路は情動と関係していると考えられていた
情動と記憶──アルツハイマー病患者さんの震災体験
アルツハイマー病とコリンエステラーゼ阻害薬
エピソード記憶の想起──なぜ記憶形成と記憶想起を分けて考えるのか?
蛋白質異常症(プロテイノパチー)
ワーキングメモリと言語性記憶,視覚性記憶
長谷川式認知症スケール(HDS-R)
意味性認知症と進行性失語
あとがき
索引
書評
開く
あなたも神経心理学の専門家に近づく診療ができる
書評者:川勝 忍(福島医大会津医療センター教授・精神医学)
今回,石原健司先生による「記憶障害の診かた」が発刊されました。本書は,河村満先生による≪シリーズ・高次脳機能の教室≫の先陣を切るものです。本書の表紙には,「Neuropsychology for Beginners」と書かれているとおり,初学者の方でも理解しやすいように意識された本です。章末には各章のまとめと確認のためのQ&Aが短い形で設けられていて,ここをみて読み返すことで知識の確認をすることができます。第1章では記憶の分類について,これを踏まえて第2章では記憶障害の分類,第3章では記憶障害を生じる脳病変部位と疾患,第4章で記憶の検査方法が概説されています。これを応用して,第5章で種々の原因による記憶障害の症例検討を生徒と先生が登場して議論するという構成になっています。
通常の神経心理学の教科書では,脳機能解剖や難しい用語の説明から入ることが多いためとっつきにくいと感じる方も多いようです。本書は臨床に必要な記憶障害を診るということに主眼があり,症状の捉え方が重視されています。第1章のイントロダクションから,例として意味性認知症の話が出てきます。意味性認知症は語の意味記憶が選択的に障害される疾患で,左側頭葉前部の限局性脳萎縮をきたしますが,知らなければアルツハイマー病としばしば誤診されます。意味性認知症は変性疾患による進行性失語としても代表的な疾患ですが,その評価方法がわからなければ診断ができません。一過性全健忘もまた,意味性認知症と同様に多くの神経心理学の専門家の興味を引きつけてきた疾患で,急激に発症し,数時間から半日程度で改善することが多いため,よほど準備しておかないと記憶検査をすることも難しいことが述べられています。普段から知識を整理して,次の患者さんを見たときに役立てるようにすることは臨床の醍醐味でもあります。本書では,その他にも記憶障害の理解に役立つ興味深い症例が紹介されています。
神経心理学と神経病理学は,どちらも難しくて敷居が高いと思われがちな領域で,この分野に関連する脳神経内科医,精神科医はともに必要だとは認識しながらなかなか勉強する機会が少ないのが現状です。高次脳機能/神経心理学は,従来ドイツを中心に大脳病理学Gehirnpathologieとして発展してきましたが,1960年代に米国を中心に神経心理学という名称が用いられるようになりました。元の大脳病理学の名称が示すように神経心理学と神経病理学は密接に関連する領域ですが,近年,臨床医が病理までみることが少なくなっています。画像診断があるから病理までは必要ないだろうと誤解されていることは残念な傾向です。石原先生は神経心理学と神経病理学の両方を専門とする数少ない脳神経内科医です。本書では,単純ヘルペス脳炎後例の記憶障害についての神経心理学的評価,画像診断による評価に加えて,病理所見まで呈示されています。右側頭葉内側から外側が主病変ですが,右の海馬だけでなく,右の脳弓,乳頭体,視床前核のパペッツの回路の病変がみられ,健側の左側との対比が見事に示されています。著者の長年の神経心理学と神経病理学の経験の蓄積を感じさせる内容です。
記憶障害は,認知症のみならずよく遭遇する症状です。本書があれば,誰でも神経心理学の専門家に近い診療が可能になるのではないかと思われます。また,ポケットマニュアル的にも使用して復習することができますので,初学者のみならず,多くの臨床医にお薦めの書です。
認知症の理解にも役立つ,記憶障害を楽しく学べる1冊
書評者:池田 学(阪大大学院教授・精神医学)
本書は《シリーズ・高次脳機能の教室》のトップバッターとして出版された。本シリーズはこれから高次脳機能/神経心理学を学ぼうとする人たちを対象としているので,記憶・記憶障害のエッセンスが,この分野のエキスパートである著者のわかりやすい文章と美しい図表で優しく語られている。しかし,内容は深い。経験豊富な認知症にかかわる多くの職種の皆さんにも,手元に置いて繰り返し読んでいただきたい内容である。
私が神経心理学を学び始めた1990年前後は,神経心理学の研究対象が失語,失行,失認などから記憶,情動,いわゆる前頭葉症状へと拡大しつつあった時期であった。エピソード記憶の障害を学ぼうとすれば,自然に目の前のアルツハイマー病の患者さんに引きつけられた。本書でも紹介されている語義失語を意味記憶障害,意味性認知症の視点から再評価した師匠の田邉敬貴先生の仕事にもかかわることができた。そして,認知症の人の生活支援を考えると,保たれている手続き記憶の活用が欠かせなかった。当時は,まだまだ神経心理学をベースにした認知症の研究者は少なかったが,自然に認知症の研究や診療に進むことができたのは,本書のテーマである記憶障害の診かたをある程度身につけていたおかげであると思っている。本シリーズの編集者である河村満先生が冒頭で述べられているように,高次脳機能の診かたがわかると,認知症の症状を具体的に理解することができるようになり,患者さんや家族が何に困っているのか,どうすれば満足のいく生活をすることができるかまで考えられるようになると思われる。
当時は,本書で紹介されているSquireによる記憶の分類やTulvingの記憶の分類の原著を懸命に読みあさる毎日で,Squireの『Memory and Brain』という単行本の日本語訳『記憶と脳』が河内十郎先生の訳で医学書院から出版された時のうれしさは今でもはっきり覚えている(情動を伴うエピソード記憶かもしれない)。その後のさまざまな研究成果を加えた上で,症例検討では学んだ記憶障害の評価と解釈,実臨床での活用が体験できるように工夫し,各章の目標とまとめ,確認のためのQ&Aまで懇切丁寧にわれわれが楽しく学べる本書を出版してくださった著者に感謝したい。
正確さとわかりやすさを両立した新しい入門書
書評者:小林 俊輔(帝京大主任教授・脳神経内科学)
本書は神経心理のモノグラフの第一弾として刊行されました。神経心理のモノグラフといえば,同じく医学書院から,河村満先生がシリーズ編集を務めた《神経心理学コレクション》が既に存在します。そのため,新シリーズがいかに既存シリーズと差別化を図るのかが注目されるところです。シリーズ第一弾のテーマに選ばれたのは「記憶障害」。まさに神経心理学の中心ともいうべき症候であり,先行する「コレクション」シリーズには,神経心理学の巨匠・山鳥重先生による名著『記憶の神経心理学』があります。新シリーズで記憶障害を担当する著者のプレッシャーは想像に難くありません。
そう思いながら,本書を手にとってみると,医学書院と河村先生の巧みな戦略が見えてきます。既存の「コレクション」は神経心理学を科学として深く掘り下げ,臨床家への啓蒙を意図していたのに対し,新シリーズは初学者が神経心理学をわかりやすく学び,「面白い」と感じてもらうことを目標にしているのが伝わってきます。本書の「わかりやすさ」は,数ある神経心理学の教科書の中でも際立っています。まず,「です・ます」調で書かれていることに驚かされます。大きな活字,豊富なイラスト,まるで中学生向けの教科書のようです。専門家向けの内容でありながら,予備知識がほとんどなくても理解できるように工夫されています。
学術書は厳密さを優先するあまり,特に初学者には「わかりにくい」ものになりがちです。中には,難解な説明で本質を曖昧にして,煙に巻くような文章も散見されます。逆にいうと,「わかりやすく」書くことを突き詰めるとごまかしがききません。「中学生にもわかるように書く」というのは,わかりやすさをめざす際のベンチマークの1つです。池上彰さんの説明が多くの人に届くのも,この基準を徹底しているからでしょう。わかりやすさを優先するあまり,物事を単純化しすぎて正確を損なうという落とし穴もありますが,本書は学術的な正確さを妥協せず,わかりやすさを実現している点が特筆されます。
著者の石原健司先生は,私が研修医時代を過ごした亀田総合病院の同窓ですが,長年神経心理の現場で研さんを積み,この領域の第一人者です。本書の第5章の症例検討では,先生と生徒の対話形式で症例理解が深められるように構成されていますが,ここで解説する「先生」は真面目で優しい石原先生のお人柄をほうふつとさせます。
私自身,高校生のころ,「なぜヒトの脳はものを覚えておくことができるのだろう」と疑問に思い,時実俊彦先生の『脳の話』(岩波書店)を読みました。時実先生の本は名著ですが,当時本書のような本があったらどんなによかったかと思います。記憶について素朴な疑問を持つ中高生が本書を手に取れば,そこに広がる神経心理の世界に思わず引き込まれるでしょう。また,医学部や心理学,言語聴覚士過程の授業の参考図書としても適しています。さらに,脳神経内科,精神科,脳外科といった神経系の診療科で働く医師,看護師,リハビリテーション科スタッフが,肩肘張らずに勉強するのにも最適です。本書はこうした幅広い読者にぜひお薦めしたい一冊です。
高次脳機能が苦手でもわかる! 記憶障害の最良テキスト
書評者:前島 伸一郎(国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長)
本書は,河村満氏が編集する《シリーズ・高次脳機能の教室》の1冊として刊行されました。著者は,長年にわたり高次脳機能障害の診療と研究の最前線に立ち続けてきた石原健司医師(旭神経内科リハビリテーション病院)です。
石原氏は1995年に千葉大学医学部を卒業後,昭和大,亀田総合病院,汐田総合病院などの神経内科で研鑽を重ね,2006年に昭和大学神経内科講師に就任,2016年より現在の旭神経内科リハビリテーション病院に勤務されています。神経症候の精緻な観察,神経病理に基づいた深い理解,そして画像診断における卓越した読影力を兼ね備えた,まさに現場と理論を融合する第一級の臨床家です。
その豊かな経験と知識は,本書にも余すところなく反映されており,「高次脳機能障害は苦手」と感じる臨床家にとって,まさに福音ともいえる内容となっています。専門的でありながらも丁寧で平易な記述が貫かれ,これほどまでにわかりやすく記憶障害を解説した書籍は,これまでほとんど例がありません。
構成は第1章「記憶の分類」から始まり,第2章「記憶障害の分類」,第3章「記憶障害を生じる脳病変部位と疾患」,第4章「記憶の検査方法」,そして第5章「症例検討」へと続きます。特に第3章では,疾患ごとの画像と詳細な模式図が豊富に掲載されており,視覚的理解を助けてくれます。第4章では,臨床現場で用いられる記憶検査が網羅的に紹介されており,読者が即座に実践へと結びつけられるよう工夫されています。
中でも第5章の症例検討は,先生と生徒によるQ&A形式で進行し,記憶障害の評価から画像診断,診断確定に至るプロセスが臨場感あふれる筆致で描かれています。まるで診察室に同席しているかのような臨在感に満ちており,若手医師や学生にとって実に貴重な学びとなるはずです。
また,各章末には要点の整理と確認のためのQ&Aが付されており,知識の定着にも配慮されています。医学生や若手療法士はもちろん,日本神経心理学会と日本高次脳機能障害学会が共同で認定する「臨床神経心理士」資格の受験対策にも有用です。
加えて,コラム欄には“Squire”や“Tulving”といった記憶研究の大家の紹介や,「自伝的記憶の分類」「蛋白質異常症」の解説など,関連分野に関する知識が広がる工夫も随所に見られ,読み物としても飽きさせません。
《シリーズ・高次脳機能の教室》というシリーズ名にふさわしく,記憶障害の全体像を系統的かつ親しみやすく学べる本書は,医療関係者のみならず,心理学や脳科学に関心のある教養人にも広く薦めたい1冊です。
高次脳機能障害の臨床に携わる全ての人が座右に置くべき,まさに現場のための決定版といえるでしょう。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。