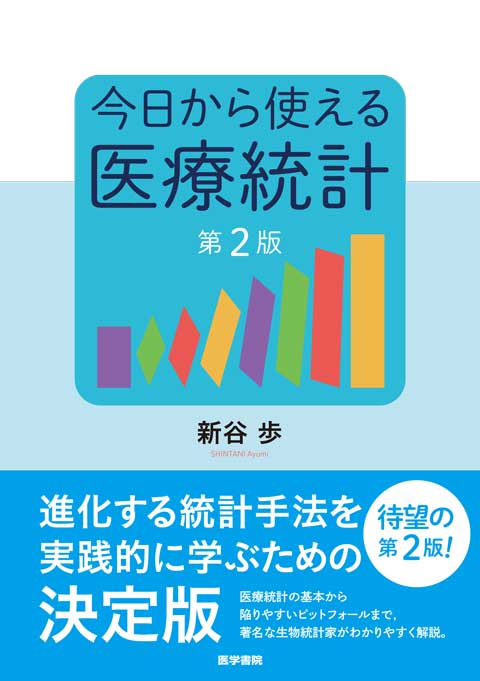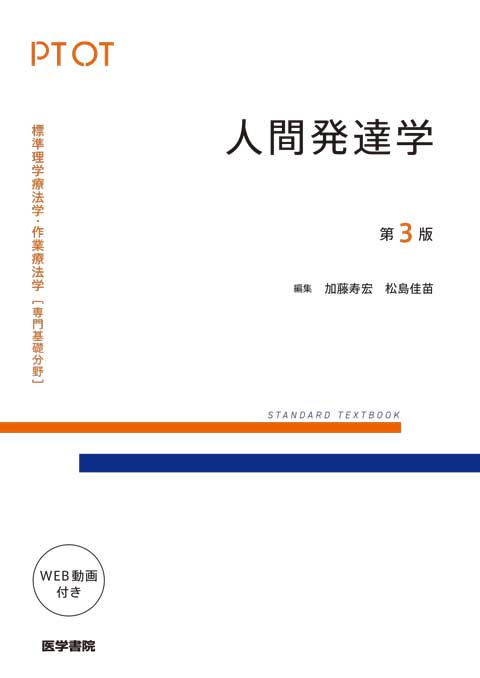MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.05.13 医学界新聞:第3573号より
《評者》 松浦 一登 国立がん研究センター東病院頭頸部外科科長
危険地帯を走り抜け,患者さんの笑顔を守ろう!
最初に本書を手に取った時に「きれいな本だな」といった印象がとても強かった。一見すると美術書のような雰囲気であるが,その表題は『Facial Danger Zones』!
本書は,もともとフェイスリフトを施行する際のリスク回避のために執筆されたものである。われわれ,耳鼻咽喉科・頭頸部外科医にとってはなじみのない手術手技であるが,顔面神経の走行やその保護,顔面の血管走行に重点を置いた記載がされており,その詳細な記載は顔面・頸部の手術をする者にとって新たな発見を与えてくれる。
本書の最大の特長は美しい絵図と手術写真,わかりやすい解説にある。解剖学的構造は精細なイラストと鮮明な術野写真を用いて示されており,視覚的に理解しやすい。また,各チャプターに二次元バーコードが付されており,動画を通じて手術手技や解剖のキモを確認できる点もありがたい。実際の術野での神経の位置関係や注意すべきポイントを動画で確認できることは,外科医にとって大きな学習効果をもたらすだろう。
頭頸部腫瘍の治療が柱である頭頸部外科においては,腫瘍切除後の機能温存が重要であり,特に顔面神経の損傷は患者のQOLに重大な影響を与える。本書では,第I章で顔面神経の各枝の解剖学的位置,危険領域(Danger Zones)の詳細な記載と共に,顔面の「層構造」を意識することで神経損傷のリスクを最小限に抑える戦略が解説されている。これは神経温存を考慮した手術計画の立案に大いに役立つ知識であり,形成外科医や美容外科医のみならず,頭頸部外科医にとっても極めて実践的なガイドとなる。
第II章では顔面の血管分布に関する詳細な記載があり,これが顔面皮膚切開を伴う手術において重要な示唆を与えている。動静脈の走行を正確に理解することで,皮膚切開時の血流阻害による壊死を防ぐことが可能となる。特に,頬部や口周囲の血流支配についての知識は,局所皮弁を用いる手術を行う際に有用であり,血行障害を回避するための戦略を立てる上で役に立つ。
最終章では「エネルギーデバイス」に関する解説がなされている。これらの機器は主に美容形成外科で使用されるものであり,われわれが直接使用する機会は少ないかもしれない。しかし,本章で述べられている「安全性を最大限に高める」というフィロソフィーは,頭頸部外科領域においても共通する概念である。
本書を貫いている優れた点は,Safety-IとSafety-IIの視点を自然に包含していることである。従来の「危険を回避する(Safety-I)」という観点にとどまらず,「いかに手術をより安全に,かつ効率的に進めるか(Safety-II)」という視点からの工夫が随所にみられる。術野の展開方法,組織の牽引や剥離の工夫,各種エネルギーデバイスを用いる場合の安全への配慮など,臨床の場で即座に役立つ情報が盛り込まれている。頭頸部外科領域において機能温存を重視する外科医にとって,本書は解剖学的知識を深めるための優れたリソースであり,手元に置いておく価値のある一冊である。
《評者》
重見 大介
株式会社Kids Public産婦人科オンライン代表
日医大女性診療科・産科
医療統計の基礎から実践まで体系的に学べるバイブル
本書は,生物統計家のエキスパートである新谷歩先生が2015年に刊行した初版を大幅にアップデートした第2版である。初版は「数式をできる限り避ける」という大きなコンセプトの下,基礎知識から実践編まで体系的にわかりやすくまとめられており,多くの医療者に愛読されてきた名著だ。約10年ぶりの新版ということで,期待が膨らむのは当然だろう。
第2版では,初版よりおよそ70頁増の248頁となり,内容が大幅に充実している。新たに追加された項目も多く,リスク比やオッズ比,回帰分析のメカニズム,欠損値の補完,繰り返し計測したデータの扱い方,さらにはベイズ法など実践的トピックがわかりやすく解説されている。
私自身,臨床研究を始めた当初は「リスク比とオッズ比の違い」を十分に理解できていなかったが,近年は「研究成果を示す際に最適な指標を選ぶこと」の重要性が高まっており,リスク比を示すのかオッズ比を示すのかなどしっかり検討する必要性をあらためて感じている。また,「P値の正しい理解と使い方」や「欠損値をどう取り扱うか」は,論文を読む上でも臨床研究を進める上でも避けては通れない問題である。まだ自信が持てていない方には本書の一読を強く勧めたい。さらに,近年の観察研究でよく用いられる「傾向スコア」や「混合効果モデル」についても丁寧に触れられており,臨床研究でのより広い応用が可能になるだろう。
全体を通して図表が豊富に使われている他,ビジュアル面もより洗練されている。初版よりも濃いブルーを配色に取り入れるなど,視覚的にもわかりやすく工夫されている上,サブタイトルを効果的に用いた構成が読みやすさを一層高めている。こうした細かな改善により,本書は内容のみならずレイアウトやデザイン面でも格段にわかりやすくなったと感じた。
加えて,第2版の巻末には,新谷先生がこれまでに公開してきた100本以上のYouTube動画の二次元バーコードが掲載されていて,スマホからすぐにアクセスできる。視覚と聴覚でも学べるコンテンツを提供できるのは,新谷先生ならではの強みだろう。ちなみに,日本語の動画で再生数トップ3は①「EZR使い方」,②「基礎科学のための統計チェックリスト」,③「傾向スコアの使い方とコンセプト」だった(閲覧時点)。本書を読んでいてわかりにくかったトピックがあれば,ぜひ動画をチェックしてみることをお勧めする。
本書が多くの医療者や研究者にとって,新たな“バイブル”となることを心から期待している。
《評者》 井上 和広 北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課
発達の基礎と臨床に役立つ実践的知識が得られる一冊!
医学書院から発刊された『人間発達学 第3版』は,理学療法士や作業療法士をめざす学生のみならず現職者にとっても,発達の基礎を学ぶ上で欠かせない一冊です。本書は,従来の発達学の枠を超え,運動機能,認知機能,心理社会的機能の三つの視点から,人間の発達を多角的に解説しています。特に,発達のメカニズムを理解することに重点が置かれており,臨床における応用力を高める内容となっています。
本書の大きな特徴の一つは,発達過程の詳細な記述とその構成の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![Facial Danger Zones日本語版 (フェイシャルデンジャーゾーン)[Web動画付] 手術・注入療法・非侵襲機器療法を安全に行うために](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6917/2974/8422/115172.jpg)