人間発達学 第3版
全面改訂。内容と完全リンクした動画を多数収載
もっと見る
理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行ううえで重要なポイントに絞って全面改訂。国家試験の出題基準はしっかりとおさえたうえで、臨床現場において必要な視点を凝縮。Web付録の動画は、その数なんと100以上。新生児期~学齢期の発達を、リアルな実感をもって理解することが可能です。
| シリーズ | 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 |
|---|---|
| 編集 | 加藤 寿宏 / 松島 佳苗 |
| 発行 | 2025年01月判型:B5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-05703-5 |
| 定価 | 4,950円 (本体4,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
第3版 序
人間発達学は,理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則において専門基礎分野に位置づけられている.専門基礎分野は,理学療法・作業療法の専門分野である評価学や治療学の基礎にあたるが,人間発達学はほかの専門基礎の科目(解剖学,生理学,運動学など)と比較し,その重要性が伝えられることは少ない.
その理由として,発達(小児)領域外の専門科目との関連がわかりにくいことがあげられる.一方で,人間発達学が発達領域の専門科目と関連することは,誰もが容易に理解できるが,身体や精神の領域,青年期以降から老年期においても人間発達学は重要な学問である.
理学療法・作業療法が対象とするのは人である.人は今(現在)を生きる存在であるが,昔のことを思い浮かべたり,未来のことを想像したりすることもできる.これを,心的時間旅行(mental time travel)というが,人は過去から未来までの時間の広がりが,ほかの動物と比較して大きいことが特徴である.人間発達学は,主に誕生してから亡くなるまでの人の変化(発達)を学ぶ学問である.人の時間の広がりを理解することは,発達という概念を理解することにもつながる.そして,理学療法士・作業療法士は,目の前の対象児・者が,①どのような経過をたどって(過去)現在の状態になったのか,②現在の状態が,時間経過に伴いどのように変化するのか(未来)を理解し治療・支援しなければならない.人間発達学を学ぶことで,どのような疾患・障害であれ,対象児・者が「どのような経過で現在の状態となっているのかを評価し,リハビリテーションを提供することで,今後どのような生活が可能となるのか(実施しなければ,10・20年後にはどのようになるのか)」といった発達的な視点をもち,リハビリテーションを実施することができる.
人間発達学の知識は,小児領域の理学療法・作業療法と関連づけて学んでも,その知識を治療や支援に活用することには難しい側面がある.先に述べたとおり,人間発達学は,時間軸に沿って人のさまざまな機能や能力の変化を学ぶ学問である.そのため,歴史年表(794年平安京遷都)のように「10か月でつかまり立ち」「1歳で歩行」などのマイルストーンを暗記する学問と認識されやすい.歴史年表を暗記するようにして得た知識で可能となる治療は,歩行ができない2歳児に,つかまり立ちや介助しての歩行を繰り返すことだけであろう.これは,適切な治療・支援といえるのであろうか.理学療法士・作業療法士は,発達のメカニズム(つかまり立ちから歩行を獲得する間,子どもは何をどのように経験し,どのような機能・能力を発達させることで歩行が可能となるのか)を考え,治療や支援に応用できなければならない.そして,なぜつかまり立ちから歩行ができるようになったのか,歩行ができるようになったことで,ほかの機能や能力(認知機能,心理社会的機能)にどのような発達的変化(影響)があるのかについても興味を広げ学ぶことが大切である.
本書は,発達のメカニズムに興味をもち,理解してもらうための人間発達学の書として作成している.特に,理学療法士・作業療法士にとって核となる誕生から歩行獲得までの乳児期の運動機能の発達については,詳細に解説している.運動機能の発達は,姿勢と粗大運動,巧緻運動,口腔運動のように身体部位に分けて解説されることが多いが,各々の発達は強い関連があるため月齢ごとにまとめている.また,本書では,運動機能の発達,認知機能の発達,心理社会的機能の発達の3つの機能を取りあげているが,これらの機能も単独で発達するものではなく,互いに関連しながら発達し,日常生活や遊びといった複合的な能力や活動・参加へとつながる.本書では,3つの機能が年齢に伴いどのように発達するのかという縦の関係だけでなく,各発達期において3つの機能がどのように関連するのかという横の関係にも着目して学んでもらえる章立てとしている.
さらに,今回の改訂では多くのWeb動画を加えていることも特徴である.理学療法士・作業療法士は,ある運動や行動ができているか否かだけでなく,その質を評価することが重要である.特に乳幼児の運動や行動は,成人とは異なるため文章や図では理解が難しい.動画を見て学習することにより,発達のメカニズムへの理解を深めてもらいたい.
最後に,本書のWeb動画にご協力いただいた,智景さんご一家,梅原恵茉さん,榎本大貴様ご一家,土屋左弥子様,小段美裕さん,優心さん,惣正さんに心より感謝いたします.
2025年1月
加藤寿宏
松島佳苗
目次
開く
I 総論
1 人間発達学総論
A 人間発達学とは
B 発達とは何か
C 発達段階と発達区分
D 身体の発達
II 各論
2 発達の基礎理論
A 発達理論とは
B 発達段階の理論──エリクソン,レヴィンソン,ハヴィガースト,ピアジェ
C 関係性の理論──ボウルビィをはじめとしたアタッチメント理論
D 社会・環境を基盤とする理論──ヴィゴツキー,ブロンフェンブレンナー
3 人間発達とリハビリテーション
1 リハビリテーションで重視される発達領域
2 運動機能の発達
A 理学療法士・作業療法士と運動機能の発達
B 人における運動機能の発達
C 発達期ごとの運動発達
D 原始反射・立ち直り反応・平衡反応
3 認知機能の発達
A 認知発達とは
B 知覚の発達
C 言語機能の発達
D 概念形成(カテゴリー化)の発達
E 注意の発達
F 実行機能の発達
4 心理社会的機能の発達
A 情動の発達
B 社会的認知の発達
5 発達検査
A 発達検査とは
B 発達検査の目的
C 発達検査の種類
4 各発達期の特徴
1 胎生期~老年期の特徴とは
2 胎生期
A 胎生期の特徴
B 中枢神経系の発達
C 循環器・呼吸器の発達
D 筋骨格系の発達
E 感覚機能の発達
F 運動機能の発達
G 睡眠の発達
3 乳児期
A 乳児期とは
B 乳児期の日常生活活動
C 乳児期の遊び
4 幼児期(前期:1~3歳)
A 幼児期(前期)とは
B 幼児期(前期)の日常生活活動
C 幼児期(前期)の遊び
5 幼児期(後期:3~5歳)
A 幼児期(後期)とは
B 幼児期(後期)の日常生活活動
C 幼児期(後期)の遊び
6 学齢期(前期:6~8歳,後期:9~15歳)
A 学齢期とは
B 学齢期の日常生活活動
C 学齢期の遊び
7 青年期
A 青年期の特徴と課題
B 心身機能の発達
C 認知機能の発達
D 心理社会的発達
8 成人期~老年期
A 身体構造の変化
B 運動機能の変化
C 感覚機能の変化
D 日常生活における機能制限
E 認知機能の変化
F 役割の変化(家族,就労,地域)
G 機能低下/喪失や死に対する受容/適応
H まとめ
索引
NOTE
第1章 人間発達学総論
1 胎児の母体外生存可能時期(生育限界)
2 AGA(appropriate for gestational age)児
第2章 発達の基礎理論
3 バルテスのSOC理論
第3章 人間発達とリハビリテーション
4 直立二足歩行の獲得
5 巧緻運動と微細運動
6 胸部の拡張と肋間筋
7 central pattern generator(CPG)
8 失立(astasia)期
9 中心窩
10 on elbows(puppy position)
11 肩甲骨・肩関節筋群による体幹の保持
12 融像
13 輻輳運動
14 手の感覚の発達
15 不安定な関節構造
16 骨盤の運動性と安定性
17 四つ這い位になるための下肢の屈曲とbottom lifting
18 座位が可能となる条件
19 骨盤の安定性
20 姿勢変換と保護伸展反応
21 収縮と関節運動の方向
22 舌の側方運動の見方
23 スキップの開始時期
24 バイオロジカルモーション
25 空間認知の発達
26 感覚モダリティ間での知覚
27 内受容感覚の発達
28 モノの永続性
29 因果関係の理解
30 随伴性と意図性
31 発話能力獲得と視聴覚情報:乳児の視線
32 オノマトペと言語学習
33 数の概念
34 社会的随伴性と静止顔パラダイム(stillface paradigm)
35 自己認識と自己鏡像認知
36 情動的共感に関連するミラーニューロンシステムと模倣の発達
37 ストレンジ・シチュエーション
38 他者の意図理解と合理的模倣
39 表情の認識
40 発達スクリーニング検査
41 同時処理,継次処理
第4章 各発達期の特徴
42 赤ちゃんの個性(気質:temperament)
43 「もの遊び」のバリエーションの発達的変化
44 自己概念・自己理解
45 社会的ルール・社会的規範の獲得
46 “ふり”に対する理解
47 社会的責任目標(social responsibility goals)
48 メタ認知
49 勤勉性と有能感
50 BMI(body mass index)
51 Timed Up and Go test(TUG)
52 5回立ち上がりテスト
53 対体重最大酸素摂取量
54 難聴
55 深部感覚と固有受容感覚
書評
開く
発達支援の第一歩に――多面的な理解をサポートする
書評者:仲間 知穂(YUIMAWARU株式会社代表取締役)
本書は,人間の発達を多角的に理解するための重要な書籍です。本書は,胎児期から青年期以降までの発達過程を解説し,発達のあらゆる側面を幅広く取り上げています。特に,発達の歴史的・文化的背景を考慮する視点が含まれており,子どもの発達を理解するための基本的な知識を提供している点が特徴です。
私は,巡回相談を通じて,保育園や学校で「学校作業療法」を行っています。その中で,子どもの現在の状態を,単独の視点ではなく,身体・認知・情緒・社会性といった複数の側面からとらえることを大切にしています。本書はまさに,多面的な理解をサポートするのに非常に役立つ一冊です。実際の臨床現場においては,まずは最初の手掛かりとなる情報が得られる本だと感じました。
例えば,学校現場で「学習に集中できない」「手先の動きが不器用」といった状況に直面したとき,どこからひもといて考えればよいのか戸惑うことがあります。本書は,そうしたときに多様な情報を提供し,ヒントをくれる書籍です。課題に対して,どのような観点から理解を深められるのかを考える手掛かりとなります。実際の支援には別の専門書や経験が必要になりますが,本書を読むことで,何に着目すればよいのかを整理する助けになります。
また,本書にはQRコードを利用した動画コンテンツが収録されており,理論だけでなく視覚的に学べる工夫がなされています。これにより,発達の各過程をより直感的に理解することができ,子どもの動作や発達の特徴をとらえる際に有益な資料となるでしょう。特に,臨床現場で子どもを評価する際に,どのような状態かを視覚的に把握できることは非常に役立ちます。以前は,写真で子どもの状態を学ぶことが主流でしたが,本書では実際に動いている動画を見ることができるため,発達の理解がより深まります。このような学習方法は,臨床家だけでなく,これから発達について学ぶ学生にとっても非常に重要です。学生のうちに子どもの発達の様子を映像で確認しておくことは,将来の臨床での評価力を養う上でも大きな助けになります。臨床に出たときに,どのような発達の特徴を観察すればよいのかを知る基礎づくりとしても,この動画コンテンツは非常に価値のあるものだと感じました。学ぶ機会がある方には,ぜひ本書の動画を活用してほしいと思います。
本書は,発達支援に携わる方にとって,重要な基礎知識を学ぶことができる書籍です。課題への直接的なアプローチ方法を示すものではありませんが,発達を考える上での基本的な視点を提供し,支援の方向性を検討するためのヒントを与えてくれる一冊です。今後も多くの臨床家や教育現場で活用されることを期待しています。
発達の基礎と臨床に役立つ実践的知識が得られる一冊!
書評者:井上 和広(北海道立子ども総合医療・療育センターリハビリテーション課)
医学書院から発刊された『人間発達学 第3版』は,理学療法士や作業療法士をめざす学生のみならず現職者にとっても,発達の基礎を学ぶ上で欠かせない一冊です。本書は,従来の発達学の枠を超え,運動機能,認知機能,心理社会的機能の三つの視点から,人間の発達を多角的に解説しています。特に,発達のメカニズムを理解することに重点が置かれており,臨床における応用力を高める内容となっています。
本書の大きな特徴の一つは,発達過程の詳細な記述とその構成のわかりやすさです。例えば,乳児期から学齢期にかけての運動発達に関する章では,つかまり立ちから歩行獲得に至るプロセスを段階的に説明しており,発達の流れを縦断的かつ横断的に理解できるよう工夫されています。さらに,発達段階ごとの重要なマイルストーンが明確に示されており,臨床現場での評価や介入に役立つ実践的な知識が得られる点も魅力的です。
また,本書の大きな特長として,130本ほどの動画コンテンツがWeb付録として収載されている点です。発達を学ぶ上で,文字や静止画像だけではとらえにくい動きの変化を,動画によって直感的に理解できるのは大きな利点です。特に,新生児の原始反射や乳児の姿勢制御の発達など,実際の臨床評価で求められる知識を,具体的な動画を通じて学べる点は,教育的価値が高く,現職者にとっても再確認できる内容となっています。
近年,小児リハビリテーションの対象となる子どもたちが有する疾患は,脳性麻痺のみならず,骨・関節疾患や神経・筋疾患,発達障害や染色体異常,先天異常,呼吸・循環器疾患など多種多様化しています。また,障がいを持つ子どもたちの支援の場も,家庭だけではなく,施設,病院,保育園,幼稚園,発達支援センターや児童デイサービス,学校などの教育機関など多岐にわたり,ライフサイクルに合わせて,かかわる職種も変化していきます。そのような現状からも,本書を通じて,発達の基礎を多角的,包括的にとらえることが重要であり,子どもへの直接的な支援だけではなく,家族指導や家族支援,多職種連携における情報共有や指導などにも効果的に使用できる内容だと考えています。
『人間発達学 第3版』は,発達の基礎を学ぶ全ての人にとって価値のある一冊であり,学生にとってはわかりやすく,臨床家にとっては実践に即した内容が豊富であり,専門職の知識を深めるための優れた参考書となり得ます。動画コンテンツを活用した学習効果の向上や発達のメカニズムへの深い理解,最新の研究成果の反映といった点において,本書がさまざまな形で,小児リハビリテーションの充実,発展,さらには障がいを持つ子どもたちや家族の健康と幸福に影響,貢献していくことを期待しています。
付録・特典
開く
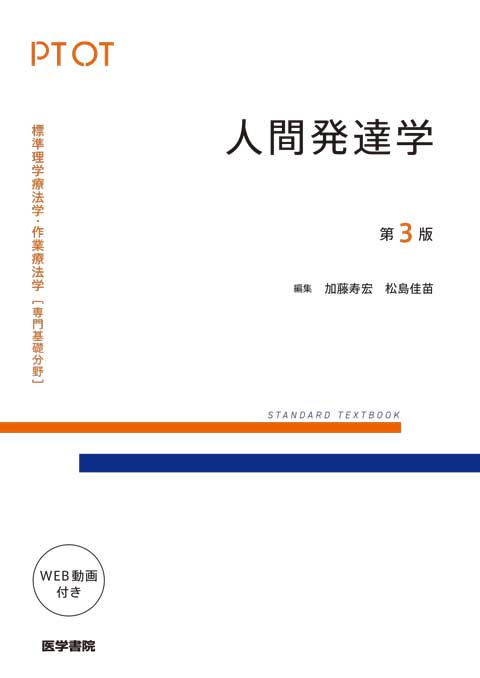
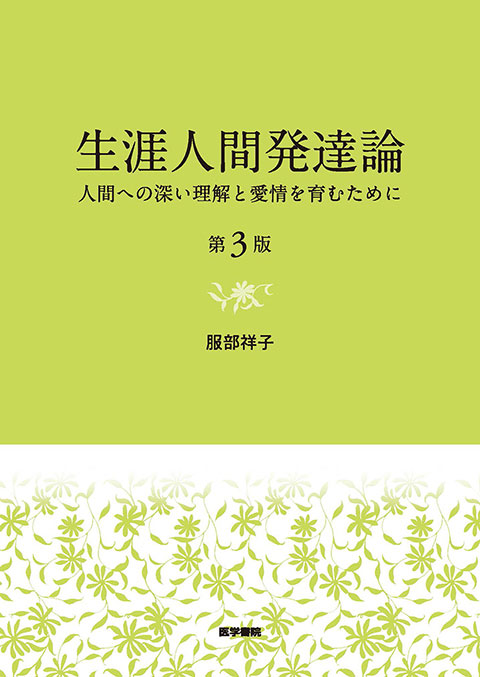
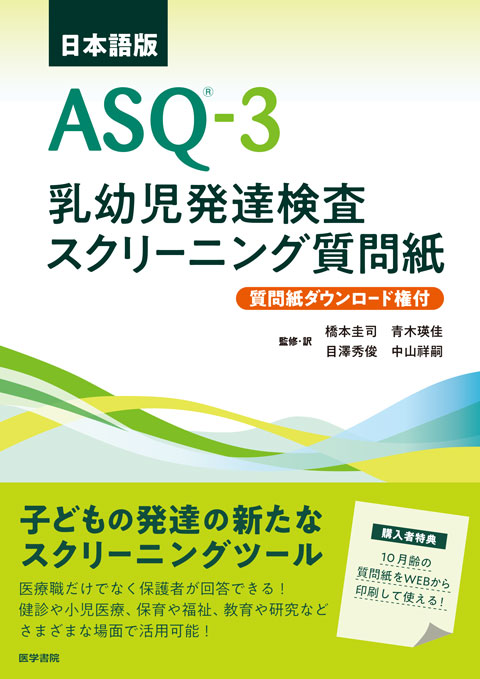
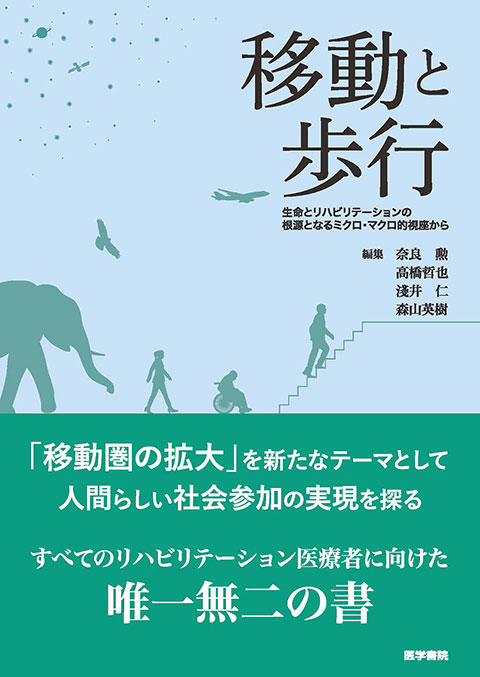
![文化人類学 [カレッジ版] 第4版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6516/0879/6737/107254.jpg)