Facial Danger Zones 日本語版(フェイシャルデンジャーゾーン)[Web動画付]
手術・注入療法・非侵襲機器療法を安全に行うために
顔面への安全な施術に必要不可欠な解剖と手技を豊富なイラストと写真でまとめた実用書
もっと見る
顔面の美容外科施術を安全に行うために必要不可欠な解剖と実際の手技を、豊富なイラストと写真でコンパクトにまとめた。美容外科医のみならず、美容皮膚科、審美歯科、形成外科、再建外科さらには顔面神経にかかわる耳鼻咽喉科や脳神経外科まで顔面にアプローチするすべての医師に役立つ実用書。
| 原書編集 | Rod J. Rohrich / James M. Stuzin / Erez Dayan / E. Victor Ross |
|---|---|
| 監訳 | 宮脇 剛司 / 石田 勝大 |
| 訳者代表 | 西村 礼司 |
| 発行 | 2024年11月判型:A4頁:160 |
| ISBN | 978-4-260-05739-4 |
| 定価 | 22,000円 (本体20,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
日本語版推薦の序/日本語版の序/序/献辞/謝辞
日本語版推薦の序
本書で述べられている顔貌の“若返り”のための治療法は,健康保険制度とはほぼ無縁で,医学部の教育でも取り扱われないが,このような願望や手法は古くから存在し,今日では健康であることと同様に人間のもつ根源的な欲求の1つに対応する医療分野である.
この本の原著をお読みになった東京慈恵会医科大学の宮脇剛司教授は,著者のRod J. Rohrichがその序文で述べているように,現在のように発展した顔貌の若返り法を安全に施行するには,相応の形成外科の経験と本書で記されているFacial Danger Zonesのことなどを熟知している必要があると思われ,そして,細かな解剖的表現は日本語に訳したほうが読みやすいと判断され,このたびの出版につながった.これはまさに英断で,今日の顔貌の若返り法を安全に施行する手引き書となることが期待される.
形成外科としての顔貌の若返り法は,この外科の開祖Gilliesが1930年代に完成させた皮弁法によるフェイスリフト手術に始まるとされる.このGillies法は,両頬に手のひらを置いて手を斜め上方向に引き上げたとき,加齢に伴って弛んだお肌が引き上がって,お顔が若いときの様子に一新するさまを手術に置き換えたような方法で,実際には,耳前部に置かれたフェイスリフト切開線から鼻唇溝に至る皮弁を剥離挙上し,引き上げ,余る皮弁を切開線上で切除して縫合する手法であった.
Gillies法は,Gilliesの弟子たちの間に受け継がれ,第二次世界大戦後,彼らがそれぞれの母国に帰国しこの方法でフェイスリフト手術を施行したので,当時のスタンダードとなった(筆者は1971年に,Gilliesの弟子のManchesterがなさるこの手術をニュージーランドで拝見したことがある).
その後,1970年頃までには,顔貌の老化に伴う変化は皮膚だけでなく,軟部組織や顔面骨の萎縮や変形なども加わった複合的な変形であるとの認識が広まるなか,さらなるリフト効果を求めて,Mario Gonzales-UlloaのEar Island法のようなトータルフェイスリフト手術時代へと向かった.
しかし,この時代までのフェイスリフト手術では,多少の工夫はあっても基本的には皮弁法なので,切開線から挙上された皮弁を強く引けばリフト効果は上がるが,このようにすれば,皮弁の血行が障害されて皮弁の部分壊死を招くといったジレンマがあった.
このようななか,Skoogは1970年頃から,耳前部の切開線から剥離挙上される皮弁を最小限にして,後にMitzらによってSMASと呼ばれることになるような皮下のこのシステムをリフトすることで,皮弁に緊張を与えることなく効果的な中顔面のフェイスリフトできる方法を模索し,1974年に自身の著書で示した.この手法はSkoog法あるいはSMAS法として世界中に広まった.
その後,SMAS法は数々の変法を生みながら発展し,より確実なフェイスリフト法を求めて1990年代にはこのSMASの裏側,すなわち顔面神経が走行する深さまで手術操作が及ぶようになった.
したがって,1990年以降の本格的フェイスリフト手術では,手術とかかわる顔面神経の解剖を正しく理解しながら行わないと患者の安全は守れなくなった.
2000年代頃からは,新鮮死体を用いた顔面の老化現象の研究が盛んになって,顔面の脂肪のコンポーネントや顔面の形態を保持している顔面保持靱帯の研究も進捗して,フェイスリフト手術はさらに進化し,かつてのSMASの存在を否定する意見も登場しながらさらに発展している.
1970年頃に探求の始まった老化に伴う顔面の軟部組織や骨の萎縮や変形に対しては,シリコーン注射やシリコーンプロテーゼの挿入などが用いられたが,これらが使用される機会は減って,次第に脂肪の注入移植法や各種のフィラーの注入法などが用いられるようになった.
これらの注入法は一見簡便に見えるが,誤って動脈に注入すれば塞栓を生じ,この結果,失明や鼻翼の壊死といった重大な合併症が生じることが,まれではあるが,知られているので,本書で解説されている脈学とフィラー注入の実際をマスターすることをお勧めする.
特にわが国では,終戦の混乱期にシリコーンオイルなる物質を注入する豊胸術や隆鼻術などが流行し,この結果があまりに酷く,社会問題化したこともあり,注入法には常に慎重であるべきである.今日では,厚生労働省が美容目的での使用を認めているフィラーが存在し,これに合わせて厚生労働省が承認するボトックス注射や各種レーザー機器も顔貌の若返り治療に利用することができる.
顔貌は,その“見た目”が機能で,社会生活のなかでは人の“自信”と関係するため,各種の若返り法は多くの方々の人生を豊かにするだろう.
2024年8月9日
元東京警察病院形成外科部長
日本美容外科学会名誉会員
銀座グランフォレクリニック院長
大森喜太郎
日本語版の序
“顔面の危険地帯”,人目を引く印象的なタイトルだ.危険地帯,すなわち重要な神経や血管の走行を知ることで,より安全に治療を提供することを目的に本書は出版された.初版のFacial Danger Zonesは1990年代初頭に流行したsub SMAS face liftに対する安全性への警鐘としてBrooke Seckelが20年以上前に出版した.2010年には次世代の形成外科医に向けて再版された.その後ヒアルロン酸に代表されるフィラーを用いた治療やボツリヌス毒素による表情筋の制御治療,さらにはLASER機器に代表されるエネルギーデバイスの発展など,低侵襲で新しい治療の選択肢が急速に普及してきた.その一方で,かつて経験したことのない失明などの重篤な合併症も散見されるようになった.本書はこれらの新しい医療技術に付随するリスクを補完するために,2020年にRod J. Rohrich,James M. Stuzin,Erez Dayan,E. Victor Rossがタイトルを変えずに内容を刷新して出版したものである.
外科医の仕事は人体の解剖を熟知しなければ成り立たない.外科医は手術の前に解剖書を読み,手術書を手にする.しかし実際の手術では,書物との違いに大いに戸惑い,時に手が止まってしまう.なぜなら,解剖書は解剖学者が書き記したもので,手術という航海の手順は示されていない.手術書は経験豊富な外科医が,手術で最も気を使う場面を中心に記述しているため,やはり目標地点までの到達方法が不十分となる.手術は皮膚の切開から目的部位までの剥離において幾度となく重要な構造体に直面し,その都度立ち止まり判断し決意して前進する.そのアプローチが特に難しいのが顔面であり,まさに本書の存在価値がここにある.本書は外科医の目線から顔面の神経と血管の走行について過去の論文や実際の解剖所見を交えて細やかに記述している.特に耳下腺を出た後の顔面神経が走行する深さについて,顔面の層構造との関係をもとに解説している.そして何度も解説が繰り返されて読者の頭に焼きついていく.まさに手術の実践書にふさわしい内容であり,読者の見たい場面は動画で確認できるようにも仕掛けられている.フィラーの注入操作においても血管内への注入を防ぐ手法が示されているが,危険部位を知り危険回避できる手技を習得することが安全への近道である.
さて,SMAS(superficial muscular and aponeurotic system)は本書の中で最も多用される用語で,SMASをどのように扱うかが本書の大きなテーマでもある.しかし,SMASの解剖学的構造には否定的な意見もある.この日本語版の序文の執筆と前後して,face lifterとして有名なMendelsonのチームから「SMASは実在するのか」と題された論文がPlastic and Reconstructive Surgery誌にpublishされ,2本の続報も掲載された.1976年のVladimir Mitzに端を発するSMASは,その後多くのface liftの論文で取り上げられ,50年近く経った今,その存在が議論されている.この議論によってSMASの定義がより明確になったが,しかし,本書の役割が薄れることはない.顔面の危険地帯である顔面神経,三叉神経,血管などの走行は解剖学的に不変であり,SMASという用語の外科的意義も変わらず,むしろSMAS議論によって組織の剥離方法や術式のコンセプトがより明確化されたからである.次の改訂の際にはSMASの明確な定義が追加されることであろう.
本書の想定読者は美容外科医であるが,美容皮膚科,審美歯科,形成外科,再建外科さらには顔面神経にかかわる耳鼻咽喉科や脳神経外科の医師にとっても,安全に手術や非手術療法を提供するうえで大いに役立つものと確信している.本書を通して顔面のさまざまな医療が普及すれば訳者一同これに勝る喜びはない.
謝辞
本書の翻訳にあたり著者であるRod J. Rohrichに橋渡しいただいたNorthwestern University Feinberg School of Medicine外科(形成外科専門)の山田朗教授,翻訳と用語に関して的確なアドバイスをいただいた銀座グランフォレクリニックの大森喜太郎先生に感謝申し上げます,また,翻訳を快く引き受けてくれた東京慈恵会医科大学形成外科学講座の医局員と同窓の先生方,耳鼻咽喉科学講座の山本裕教授,そして膨大な事務作業を捌いていただいた形成外科学講座秘書の内藤恩さん,蒲生原光代さんに感謝申し上げます.
表紙の薔薇の絵は,著名な現代画家である井上文太氏によるものです.“美しい薔薇には棘がある”──まさに本書の意図するところです.素晴らしい作品のご提供に心より感謝申し上げます.
2024年パリオリンピック,そして未曾有の酷暑の夏に
監訳者 宮脇剛司,石田勝大
訳者代表 西村礼司
序
なぜ『FACIAL DANGER ZONES』を刷新したのか? それはこのトピックに関する新たな文献を今まさに共有したいと感じたからです.
原点となる教科書は,20年以上前に神経学と美容外科という2つの専門医資格をもつDr. Brooke Seckelによって書かれました(Quality Medical Publishing,1994).Dr. Seckelが初版を執筆するきっかけは,1990年代初めに報告されたより積極的なSub-SMASフェイスリフトによって起こりうる顔面神経損傷への懸念でした.彼の教科書は,その時代に再建手術および顔面美容外科手術を行う外科医にとっての参考書となり,次世代の形成外科医のために2010年に再出版されました.
この10年間に美容外科手術と美容医療の世界は大きく変化しました.美容手技の世界的な需要は急速に増加し,それに伴って患者の安全性確保の必要性も高まっています.美容手術は今や外科的および非外科的な技術の両方を含み,さまざまな分野の医師によって実施されています.そして,この需要の増加に伴い,今までにないより深刻な合併症が増加していることにわれわれは気づいています.Dr. Seckelが『FACIAL DANGER ZONES』を執筆した頃には,フィラーの注入による失明について耳にすることはありませんでしたが,今では残念ながら頻繁に報告されています.形成外科研修では一般的に再建手術が重視される一方で,顔面解剖学の教育は表面的であり,顔面美容外科手術の微妙なニュアンスにはあまり時間が割かれていません.われわれの施設のレジデントはフェイスリフトよりも複雑な微細血管吻合による再建手術のほうが快適に行えるようですが,開業医になると研修期間に十分な教育を受けていない治療を患者に提供するのはよくあることです.本書の初版から20年が経った今も,患者の安全確保は依然として最優先事項であり,われわれの思いは『FACIAL DANGER ZONES』の最新情報を再定義することにあります.
多くの分野で専門家が美容施術を行うなかで,技術は変化し,治療の提供方法も進化しましたが,解剖学は不変です.われわれの視点からは,顔面の軟部組織解剖と血管解剖の3次元的な知識が,運動神経損傷,失明,組織虚血などの合併症回避の鍵と考えています.非侵襲機器やレーザーの普及も,これらの機器を使用する際の安全性の配慮と制約の理解が必要となります.
この本の目標は次の3つです.
▪ 顔面解剖の最適な知識は,顔面美容外科手術において最良かつ安全な結果を得るために不可欠です.これは特にフェイスリフト手術における顔面神経の複雑な解剖の際に必要となるもので,Dr. James Stuzinが解説します.
▪ 失明や皮膚欠損を含む重篤な合併症を予防しつつ,安全にフィラー注入を行うためには顔の血管の解剖学に関する知識を洗練し,明確にすることが重要です.ここはDr. Rod Rohrichが解説します.
▪ レーザーや超音波技術,radiofrequencyの最小侵襲技術による治療の限界や安全領域を明確にし,顔面頚部領域における治療を最適化することと,最大限の安全性の確保について,Dr. Erez Dayan とDr. Victor Rossが解説します.
『FACIAL DANGER ZONES』の執筆にあたっては,提示した解剖が正確であるか,顔面軟部組織の複雑な解剖がわかりやすく伝えられているかを確認するために解剖実習室に立ち戻りました.文章による説明ではわかりにくい複雑な内容については読者が簡単に理解できるように,解剖写真やイラストと短編動画を組み合わせて示しました.本の書式は知識を効率化するためのもので,動画や電子書籍とともに,本書で得た知識をもとに手術室や治療室の現場で,自信をもって安全に美容手技が実施できるように心から願っています(訳注:日本語版では電子書籍は付けていない).
美容医療手術を行う医師の責任は,結果の精度を高めることと患者の安全を確保することにあります.美容医学の芸術性は視覚的で直感的ですが,一貫した分析基盤は基本的かつ徹底的な解剖知識と,解剖と顔面形態の関係性の理解です.本書を通して読者が顔面軟部組織解剖を3次元的に理解し,手技の際にデンジャーゾーンに気づくように心から願っています.そして患者と医師の両者にとって,安全で満足のいく結果が得られるように心から願っています.
Rod J. Rohrich, MD
James M. Stuzin, MD
Erez Dayan, MD
E. Victor Ross, MD
献辞/謝辞
われわれはすべての患者の安全のためにこの本を捧げます.われわれのこの仕事によって臨床医が安全に目を向けるようになることを願っています.読者にとって本書は,本書が示した手技により最高の治療を提供できる最高の形成外科,皮膚科,顔面形成外科,眼形成外科の専門医になるための手引きとなるでしょう.
美容外科はあなたの患者と,彼らの安全および治療結果を最優先事項としています.本書はこの必要性に注目し,医師として有害事象を起こさない「Do No Harm(訳注:ヒポクラテスの誓いより)」という責任をもつことを使命としています.
日常診療において医療の実践を通じて,われわれがより優れた,より思いやりのある医師にとなる手助けをしてくれたすべての患者に,謝意と敬意を表します.
特に,本書の完成を手伝ってくれたスタッフ,われわれの長期的なアシスタント兼管理者であるDiane Sinn,われわれの偉大なThiemeのスタッフであるJudith Tomatと出版社のSue Hodgson,そしてこの素晴らしい本の各ページに専門知識を活かしたイラストを描いてくれたAmanda Tomasikiewiczに感謝します.
Rod J. Rohrich, MD
James M. Stuzin, MD
Erez Dayan, MD
E. Victor Ross, MD
目次
開く
日本語版推薦の序
日本語版の序
序
献辞/謝辞
Video Contents
執筆者一覧
I 顔面神経
1 顔面組織解剖の概要
2 顔面脂肪のコンパートメント
3 概要:顔面神経のデンジャーゾーン
4 顔面神経側頭枝
5 頬骨枝と頬筋枝
6 顔面神経下顎縁枝と頚枝の保護
7 大耳介神経
8 手技上の配慮:拡大SMAS剥離と外側SMAS切除/広頚筋開窓
II フィラーと神経調節因子
9 はじめに
10 デンジャーゾーン1──眉間領域
11 デンジャーゾーン2──側頭部領域
12 デンジャーゾーン3──口唇領域
13 デンジャーゾーン4──鼻唇溝領域
14 デンジャーゾーン5──外鼻領域
15 デンジャーゾーン6──眼窩下部領域
III エネルギーデバイス
16 アブレイティブレーザーの安全性を最大限に高める
17 ノンアブレイティブレーザーの安全性を最大限に高める
18 トリクロロ酢酸とジェスナー液を併用したケミカルピーリングの安全性
19 ラジオ波(RF)機器の安全性を最大限に高める
20 低温脂肪溶解法の安全性を最大限に高める
21 マイクロニードル法の安全性を最大限に高める
索引
書評
開く
知識は転ばぬ先の杖 正しい知識でQOLを守る!
書評者:外木 守雄(亀田総合病院顎変形症治療センターセンター長)
医学書院から発刊された『Facial Danger Zones日本語版(フェイシャルデンジャーゾーン)[Web動画付]』は,口腔顎顔面解剖学の複雑さを臨床場面に即した形で明確に解説した,極めて実用的な良書です。特に口腔顎顔面領域の手術に携わる形成外科,皮膚科,美容外科,耳鼻咽喉科,頭頚部外科,さらには口腔外科の医師,歯科医師にとっても,本書は不可欠な名書となるでしょう。
ご存じのように,顎顔面には,外傷や腫瘍の手術中に損傷を避けるべき重要な神経,血管,筋肉が網の目のように存在しています。これらを熟知しないと,患者の顔面機能や審美性に深刻な影響を及ぼすリスクが高まります。本書は,このようなリスクを回避するための指針として,専門医はもとより,研修医にとっても極めて優れた役割を果たします。
本書の最大の魅力は,解剖学的な基礎を詳細かつ視覚的に解説している点です。豊富なイラストや解剖写真,症例写真,Web動画が掲載されており,視覚的な理解が大変容易です。また,顔面神経の走行や枝分かれ,血管網の配置などが具体的に示されているため,理論的な知識としてだけでなく,実際の臨床現場での即応的な知識として活用できます。
また,術後合併症を防ぐためのポイントも数多く挙げられており,術中だけでなくリハビリを含めた術後管理にも役立つ情報が満載です。特に,腫瘍切除や再建手術など,美容的および機能的な側面を考慮した計画立案の方法が丁寧に解説されています。
さらに,最新の技術や手法についても触れています。例えば,神経モニタリング技術を用いた手術の安全性向上に関する具体例や,リスクを最小化するための標準的なアプローチが解説されており,これらは全ての外科医にとって大いに役立つでしょう。
また,本書は,外科医としての倫理的観点や患者への配慮についても踏み込んでいます。顔面は患者の生活の質(QOL)に直結する領域であるため,美容的・機能的な側面を総合的に考慮する必要があります。本書では,これらを反映した治療計画の立て方についてもアドバイスがなされており,単なる技術書にとどまらない包括的な内容となっています。
今回,監訳された宮脇剛司先生と石田勝大先生は,日本を代表する優れた形成外科医であり,本書の勘所を日本語でうまく誘導してさまざまなレベルの読者に適した内容となっています。また,翻訳の任に当たられた,訳者代表の西村礼司先生,慈恵医大耳鼻咽喉科学講座の山本裕先生,同・形成外科学講座同門の先生方の適切な訳,特に日本の医学事情に即した対応が素晴らしく,本書の内容をより高めているといっても過言ではありません。
本書は,口腔顎顔面領域の手術に携わる医師のみならず,多くの医療関係者にとって,その負うべきリスクを最小化し,安全かつ効果的な治療を実現するための貴重な一冊です。この本を手に取ることで,口腔・顎顔面外科の奥深さに触れ,患者の生命と生活の質を守る医療の本質を再確認することができるでしょう。
危険地帯を走り抜け,患者さんの笑顔を守ろう!
書評者:松浦 一登(国立がん研究センター東病院頭頸部外科科長)
最初に本書を手に取った時に「きれいな本だな」といった印象がとても強かった。一見すると美術書のような雰囲気であるが,その表題は『Facial Danger Zones』!
本書は,もともとフェイスリフトを施行する際のリスク回避のために執筆されたものである。我々,耳鼻咽喉科・頭頸部外科医にとってはなじみのない手術手技であるが,顔面神経の走行やその保護,顔面の血管走行に重点を置いた記載がされており,その詳細な記載は顔面・頸部の手術をする者にとって新たな発見を与えてくれる。
本書の最大の特長は美しい絵図と手術写真,わかりやすい解説にある。解剖学的構造は精細なイラストと鮮明な術野写真を用いて示されており,視覚的に理解しやすい。また,各チャプターに二次元バーコードが付されており,動画を通じて手術手技や解剖のキモを確認できる点もありがたい。実際の術野での神経の位置関係や注意すべきポイントを動画で確認できることは,外科医にとって大きな学習効果をもたらすだろう。
頭頸部腫瘍の治療が柱である頭頸部外科においては,腫瘍切除後の機能温存が重要であり,特に顔面神経の損傷は患者のQOLに重大な影響を与える。本書では,第I章で顔面神経の各枝の解剖学的位置,危険領域(Danger Zones)の詳細な記載と共に,顔面の「層構造」を意識することで神経損傷のリスクを最小限に抑える戦略が解説されている。これは神経温存を考慮した手術計画の立案に大いに役立つ知識であり,形成外科医や美容外科医のみならず,頭頸部外科医にとっても極めて実践的なガイドとなる。
第II章では顔面の血管分布に関する詳細な記載があり,これが顔面皮膚切開を伴う手術において重要な示唆を与えている。動静脈の走行を正確に理解することで,皮膚切開時の血流阻害による壊死を防ぐことが可能となる。特に,頬部や口周囲の血流支配についての知識は,局所皮弁を用いる手術を行う際に有用であり,血行障害を回避するための戦略を立てる上で役に立つ。
最終章では「エネルギーデバイス」に関する解説がなされている。これらの機器は主に美容形成外科で使用されるものであり,我々が直接使用する機会は少ないかもしれない。しかし,本章で述べられている「安全性を最大限に高める」というフィロソフィーは,頭頸部外科領域においても共通する概念である。
本書を貫いている優れた点は,Safety-IとSafety-IIの視点を自然に包含していることである。従来の「危険を回避する(Safety-I)」という観点にとどまらず,「いかに手術をより安全に,かつ効率的に進めるか(Safety-II)」という視点からの工夫が随所にみられる。術野の展開方法,組織の牽引や剥離の工夫,各種エネルギーデバイスを用いる場合の安全への配慮など,臨床の場で即座に役立つ情報が盛り込まれている。頭頸部外科領域において機能温存を重視する外科医にとって,本書は解剖学的知識を深めるための優れたリソースであり,手元に置いておく価値のある一冊である。
実践的表在性の顔面解剖書が必要な医療従事者へ
書評者:山田 秀和(近畿大アンチエイジングセンター)
本書は,形成外科や美容医療,あるいは顔面外科に携わる医師にとって必携の一冊だ。原著はRod J. Rohrichらが編集し,日本語版は慈恵医大の宮脇剛司主任教授と石田勝大教授の監修により出版された。本書の出版により,日本の医療従事者にとって,より実践的で信頼できるリソースが提供されることになった。
原書は,1994年の発刊当時から顔面を扱う医師にとって待望の書籍だった。評者自身,海外の学会展示で初めて手に取った時の喜びを今でも鮮明に記憶している。基礎的でありながら実践的な内容が詰まっており,「助かった」と直感的に感じた瞬間が思い出される。初版から30年経って,Facial Danger Zonesの最新情報を再定義してもらったことはありがたい。本書は,顔面の「危険領域」に焦点を当て,手術,フィラー注入,非侵襲デバイスの使用における安全確保のための具体的なアプローチを解説している。研修医にとっての基礎教材としてはもちろん,表在の顔面解剖を必要とする,幅広い診療科で活用できる内容である。
解剖学的なリスクやSMAS(顔面の筋膜系:表情筋と皮膚の間に存在する支持組織)の詳細な解説を通じて,施術の安全性と効果を最大化する方法を学ぶことができる。特にフィラーやボトックス治療においては,注入部位周辺の血管や神経の走行を理解することが,合併症予防の観点から極めて重要となる。豊富な図解や写真による説明は,顔面の解剖学的変異の理解を深める上で大きな助けとなる。本書の最大の特徴は,解剖学的リスクに基づいた安全な施術ガイドの提示と,充実したWeb動画コンテンツの提供だ。二次元バーコードを介して閲覧できる動画は,顔面の構造的な危険領域の理解を深める上で非常に効果的だ。静止画では伝えきれない立体的な解剖学的構造や,実際の手術手技における注意点を,動画を通じて具体的に学ぶことができる。これにより,初心者からベテランの医師まで,それぞれのレベルに応じた学習が可能となろう。
現代の美容医療は,従来の手術療法に加え,ヒアルロン酸注入やレーザー治療,高密度焦点式超音波(HIFU)など,多様な手法が採用される時代に突入した。患者の安全を守るためには,解剖学的変異や血管・神経走行の理解が不可欠だ。本書は,形成外科医や美容外科医だけでなく,皮膚科医,美容皮膚科医にも強く推奨される一冊だ。また,研修医にとっては,顔面外科や美容医療を学ぶための基礎教材として最適だ。特に顔面の立体構造や血管・神経走行に関する知識を深めたい医師にとって,重要なリソースとなるだろう。『Facial Danger Zones』は,手術や非侵襲的治療を行う全ての医師にとって,施術の安全性を高めるための必須書籍だ。初版が顔面外科に革命をもたらしたように,日本語版はより多くの医療従事者に安全な施術を提供するためのガイドラインとなるだろう。顔面医療がますます多様化する中,医療現場での必携書として強く推奨される。
<
>顔面手術の必携バイブル,動画で学ぶ安全術!
書評者:鈴木 芳郎(ドクタースパ・クリニック 院長/日本美容医療協会理事長)
私自身,過去約30年にわたりフェイスリフト手術にかかわってきましたが,この『Facial Danger Zones』は,フェイスリフトを行うドクターにとっては必ず持つべきバイブル的な書であると感じさせられました。本書の最大の特徴は,これまでに類を見ないほど詳細な顔面神経の走行の解説と,それに基づいた危険回避の具体的な方法の提示です。これにより,術中および術後の合併症リスクを大幅に低減するための実践的な知識を得ることができます。
フェイスリフトを含む顔面手術では,顔面神経や主要な血管の解剖学的理解が安全性の要です。しかし,顔面神経の詳細な走行とその周囲でのリスク管理に関する文献は,これまで一部の断片的な情報に限られていました。本書では,これらの情報が精緻な図解とともに網羅されており,特に以下の点が際立っていると感じました。
1.顔面神経の詳細な走行の解説
顔面各部位での顔面神経の走行や,危険領域の解剖学的特徴が細部に至るまで記載されています。これにより,例えばSMAS層を扱う際にどの深さで剥離すべきか,どの方向に牽引すべきかといった具体的なガイドラインが得られます。また,術中に注意が必要な領域が明確に示されており,実際の手術手技に直結する情報が充実しています。
2.術中の危険回避に向けた実践的アドバイス
危険領域における神経・血管損傷を防ぐための具体的な手法が解説されています。例えば,深部組織への侵襲を最小限に抑えるためのアプローチや,出血リスクを抑えつつ解剖学的境界を確認するための実践的なポイントが示されています。
3.注入療法や非侵襲的機器療法への応用
本書はフェイスリフト手術にとどまらず,注入療法や非侵襲的機器療法を行う美容外科医師にとっても極めて有用です。ヒアルロン酸やボツリヌス毒素の注入を行う際,顔面神経や主要血管の走行を正確に把握することは合併症を回避する上で不可欠です。本書では,これらの治療における具体的な注意点や推奨される手技が詳述されています。また,非侵襲的機器を用いた治療では,エネルギーデバイスが神経や血管に与える潜在的な影響を考慮した安全な方法についての示唆も得られます。
4.付録のWeb動画による理解の促進
本書には付録のWeb動画があり,これが内容理解をさらに助ける大きな役割を果たしています。図解やテキストだけではとらえにくい顔面神経や血管の立体的な配置が動画内のキャダバー(献体)を用いた説明から可視化され,解剖学的構造をリアルな視点で学ぶことができます。これにより理解が飛躍的に深まり,手術に応用できる具体例として非常に参考になります。このように静的な情報にとどまらず,動的な視点から解剖学的知識を学べる点は本書の大きな魅力です。
総じて,本書は,顔面の美容外科手術を日常的に行うドクターにとってこれまでにないほど有用なリソースです。特に,顔面神経の詳細な走行を明示し,その知識を基に危険を回避する手法を提示している点は,他の解剖学書や手術ガイドにはない独自性を有しています。また,注入療法や非侵襲的機器療法を行うドクターにとっても,神経や血管への配慮を深めるための強力なサポートとなるとともに,付録のWeb動画が実際の施術方法も示してくれており,その習得をさらに容易にしてくれるものと期待しています。初心者から熟練医まで幅広い層にとって価値ある内容だと確信しております。
![Facial Danger Zones 日本語版(フェイシャルデンジャーゾーン)[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6917/2974/8422/115172.jpg)
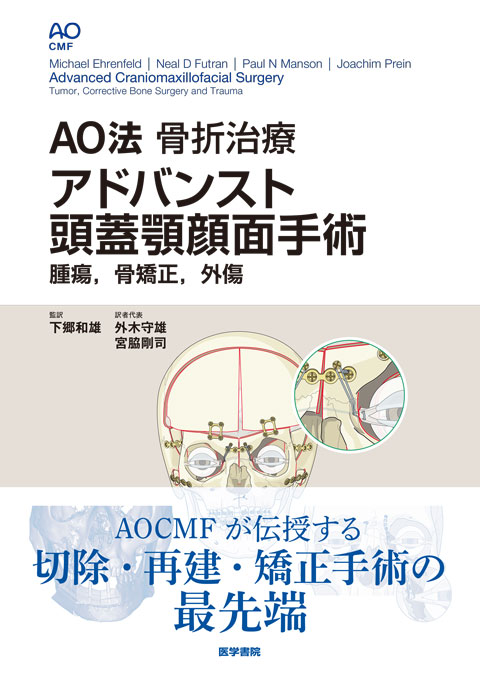
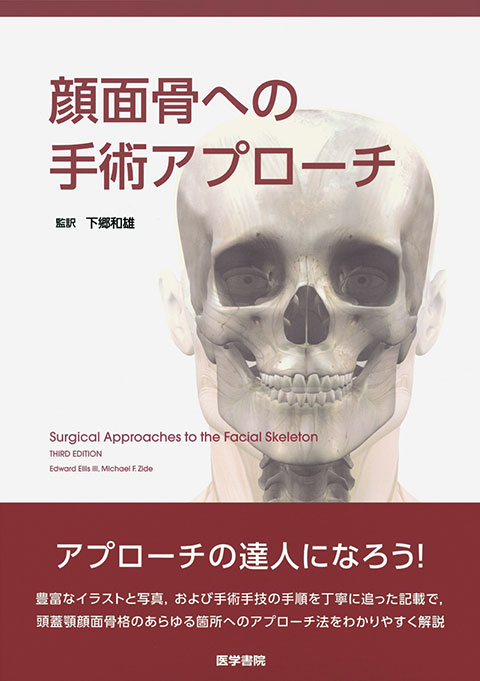
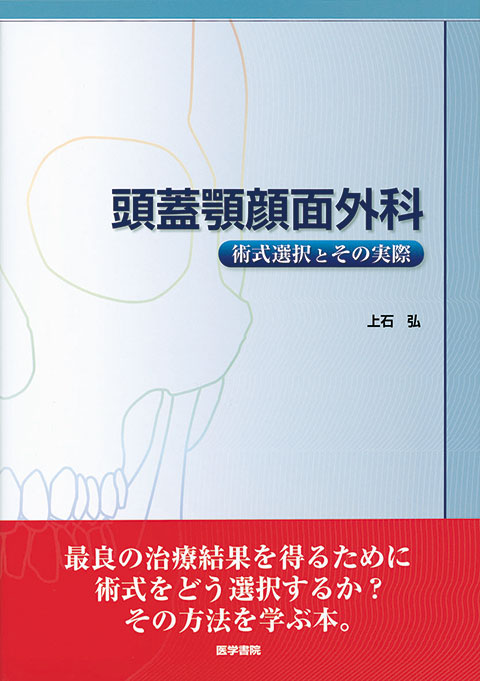
![皮膚科手技大全[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6817/1688/3829/05483_w480.jpg)