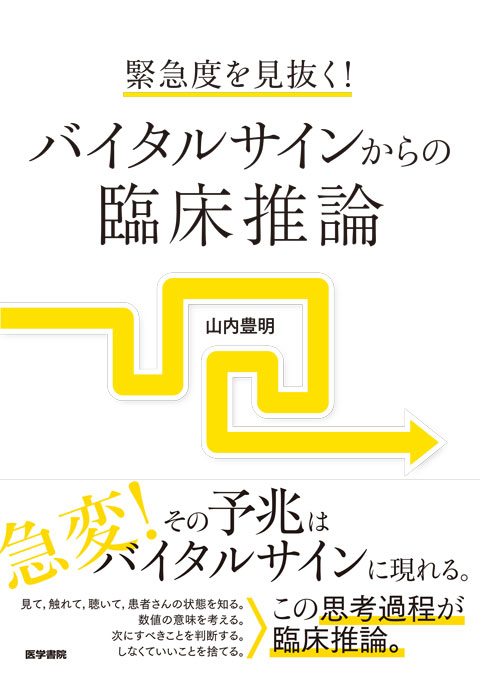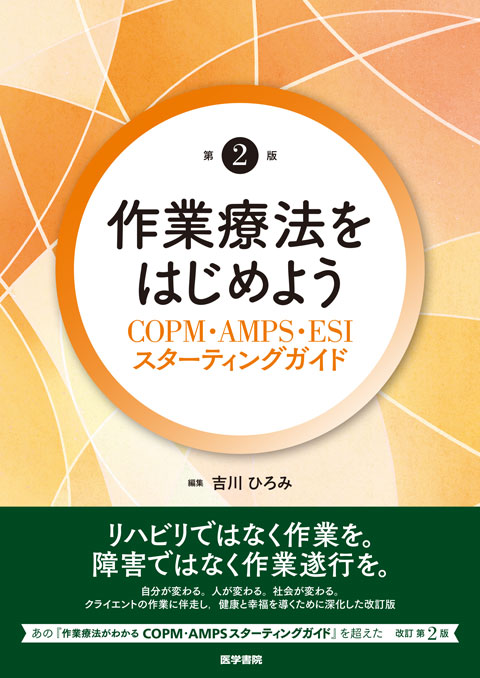MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2025.02.11 医学界新聞:第3570号より
《評者》 安達 洋祐 原看護専門学校学校長
できるナースは,バイタルサインを感じて,考える
◆生命徴候:呼吸を数え,脈拍を触れる
著者の山内さんが本書で伝えたいのは,「呼吸と循環を感じて考えること」である。本のタイトルは「緊急度を見抜く」,キャッチコピーは「この思考過程が臨床推論」とあるが,本文を読んで感じたのは,「みんな,もっとバイタルサインを感じよう!」という呼びかけである。
バイタルサインは「生命徴候」と訳されるが,アメリカのロックバンドGreen Dayの歌にあるように(Check my vital signs to know I'm still alive),「生命の信号,生存の合図」であり,自分が生きていることを周囲の人に気付いてもらう「無言のメッセージ」である。
ナースは,患者の最も身近な存在であり,患者の変化に最初に接する立場にある。著者は医療の現場を支えるナースに期待し,ナースこそバイタルサインに精通してほしいと願い,「患者のメッセージを感じてほしい」「身体の変化を読み取ってほしい」と祈っている。
◆病態把握:身体の変化を理解する
バイタルサインの変化は緊急事態であり,的確な判断と迅速な対応が求められる。例えば呼吸数であれば,「人間は酸素なしでは生きられない→酸素が不足すると呼吸数が増える→呼吸数が増えると死腔が増える→換気効率が悪化して酸素摂取は不十分→酸素投与が必要」となる。
慢性呼吸不全の患者は,脳幹のセンサーが高濃度の二酸化炭素に慣れており,「酸素不足で酸素分圧低下→呼吸数増加と酸素投与で順応→脳幹は酸素過剰と判断して呼吸を抑制→二酸化炭素の蓄積で昏睡」となり,このような病態を理解しないままの機械的な対応は患者を危険にさらす。
パルスオキシメーターが普及し,バイタルサインはすべて器械による測定になり,医師は「ナースが測定するもの」,ナースは「測定して記録するもの」ととらえるようになった。著者はナースのために,「数値を見て記録するだけのロボットになるな」と言っている。
◆臨床推論:病状を考え,対応を決める
著者は20年前に『フィジカルアセスメント ガイドブック』,10年前に『フィジカルアセスメント ワークブック』(ともに医学書院)を上梓している。「バイタルサインは五感で把握」「信用できるのは器械より五感」という神経内科医(身体診察が上手)の言葉は説得力がある。
さらに,著者は米国で診療看護師の資格も取得しており,「患者を観察し判断して対処に結びつける」というアセスメントのスキルを熟知している。医師が臨床検査に頼って身体診察を怠る昨今,ナースのアセスメント技法を易しく惜しみなく伝授しているのが,本書の魅力であろう。
私は外科医として,11の市中病院と大学病院で勤務したが,どの病院にも「賢いナース」(知識が豊富),「できるナース」(技能が秀逸)がいて,私を助けてくれた。著者とは経歴がまったく異なるが,看護教育に従事して思うことは不思議と同じであり,随所に共感を覚えた。全国のナースが本書で学び,「賢いナース」「できるナース」になって活躍してほしいと願う。
《評者》 仲間 知穂 YUIMAWARU株式会社代表取締役
クライエント中心の実践の意義がわかる作業療法入門書
作業療法における基本的な概念として「クライエント中心の実践」があります。本書『作業療法をはじめよう 第2版――COPM・AMPS・ESIスターティングガイド』は,その実践を支える知識と技術を網羅した一冊です。COPM,AMPS(Assessment of Motor and Process Skills),そしてESI(Evaluation of Social Interaction)という三つの評価ツールを中心に,作業療法士にとって重要な基礎と実践的な知見が検討されています。
◆COPMとクライエント中心の実践
COPMは,クライエントが自分にとって重要な「作業」を探究し,その実行に向けて主体的に関与していくプロセスを支援するツールです。私自身も臨床現場でCOPMを活用し,生活を変えていくことに受け身であったクライエントが,自らの課題に取り組む姿勢に変わる瞬間に立ち会ってきました。クライエントと協働的に「作業ができること(作業の可能化)」の実現に向けアプローチする作業療法において,クライエントの作業を理解することは最も重要なプロセスといえるでしょう。
本書の特筆すべき点は,面接という難しい実践について,事例を...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。