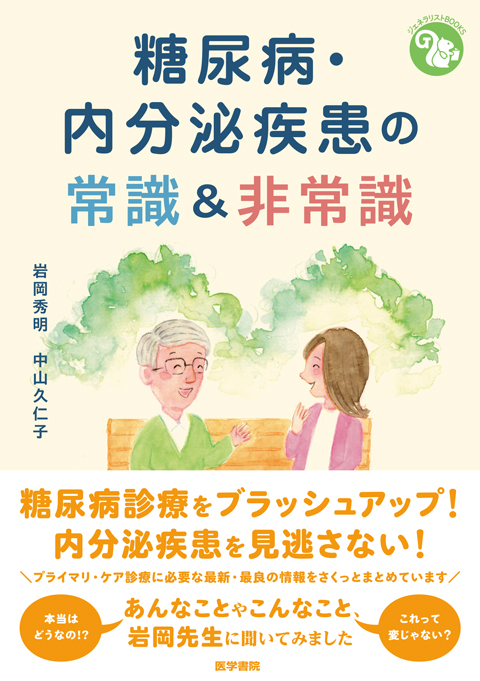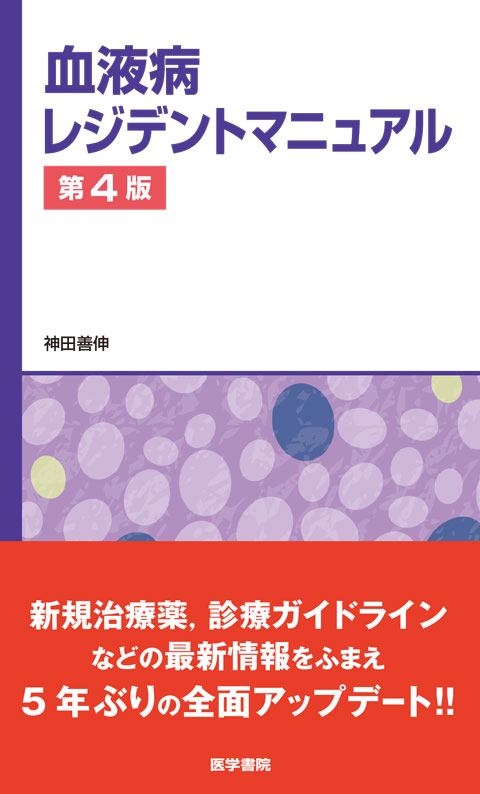MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.08.13 医学界新聞(通常号):第3564号より
《評者》 三澤 美和 大阪医薬大病院総合診療科
初心者には最良の基礎学習となり,上級者には最高の復習の時間となる本
前半の糖尿病の食事療法を読み始めると,岩岡秀明先生が普段患者さんと笑顔で話している診察室の会話が見えてくるような気分になる。「果物は1日に握りこぶし1個分」「(コーヒーは)無糖にしないとだめだよ」「時々は記念日を作ろう」。患者さんの気持ちをおもんぱかりながら,丁寧にアドバイスする様子が目に浮かぶ。そこに中山久仁子先生が誰でも抱くような素朴な疑問を投げかけ,また丁寧な解説が続く。対話形式の内容を読み進めると,いつしか自分の診療を一番底のほうからいったんすくいあげて見直しているような気持ちになった。
「あ~そうそう,そうだった」と思わせられる重要なエビデンスしかり,「最近はそうなってたんだ」という新しい発見しかり。糖尿病の薬物療法には多くのページが割かれ,丁寧に疑問に答えてくれる。意外とあいまいにしてしまいがちな高尿酸血症についても言及されている。しかもこの本は糖尿病だけにとどまらず,日常でよく出合う内分泌疾患の素朴な疑問にも答えてくれている。甲状腺や副腎,日常的に出合う頻度が非常に高い骨粗鬆症。内分泌だけを特集した分厚い教科書と格闘するよりずっと,知識としてすんなり入ってくる。また会話から中山先生が普段どのような診療をされているかも垣間見え,プライマリ・ケア医としてどこまでが必要とされているのかを確認できる。プライマリ・ケアの良き理解者である岩岡先生と,現場の家庭医である中山先生が繰り広げる言葉のキャッチボールは,まるで自分が小さなカンファレンスにお邪魔したような気持ちにさせられた。
ページのところどころに指差しサインで「非常識」と書かれている。自分の診療に知らないうちに非常識が紛れ込んでないか,ドキッとする。私たちはいつも自分の診療を振り返り,updateし続けないといけない。かといって,自分一人で全てのエビデンスやガイドラインの進歩を根こそぎ見つけにいくのは難しい。この本をすらすらと読み通すと,糖尿病や内分泌疾患の「今の常識」がしっかり確認できる。そして今日からさっそく自分の診療に生かせるような内容ばかりだ。初心者は最良の基礎知識が得られ,上級者には診療の質を振り返る最高の機会をくれる。
個人的には,数多ある糖尿病治療薬の一般名と製品名,さらには先発品と後発品に分けての3割負担の場合の薬価負担額が一覧となっているところに心を打たれた。エビデンスは大事だが,糖尿病薬は高価なものも多い。この表を見ると目の前の患者さんが本当に無理をしない最適な治療を選ぶことができているのか,と自分に問いたくなる。診察室でこの表を見ながら患者さんと治療法を一緒に決めていくのもいいだろう。読み終えたあとも,まだ二度も三度もおいしい本である。表紙には,公園で笑顔で話すお二人のイラストがある。私もその会話に入り込んで糖尿病や内分泌の話題をもっと話してみたくなった。
《評者》 國松 淳和 南多摩病院総合内科・膠原病内科部長
なぜこのような専門外の本を私が必要とするのか
素晴らしい書籍がまた改訂された。私は総合内科,あるいは地域医療としてのリウマチ・膠原病診療をしているのであって,血液内科の専門治療をしているわけではない。が,じつは初版から今回まで毎版購入している。いってしまえば熱心な本書の読者である。
さて,専修医でも専門医でもない私がなぜこのような専門外の本を必要とするのか。当たり前だが,知識をアップデートするためである。そこで,本書を読むなどして最近の血液学の臨床について気付いたことが2つあってそれについて述べる。
1つは,新規治療が増えたということはもちろんだが,血液病の治療として「内服薬」が明らかに増えたという点である。血液病の治療といえばとにかく入院して何本かの点滴を次々にやっていくイメージを持ってしまうが,非常にスマートな治療薬が増えてきた。外来で治療をすることの重要性,必要性はおそらく確実に高まってきていて,この点内科医にとって外来力のビルドは急務になってきている。私の場合は不明熱診療がそうで,病名なしに「とりあえず入院精査」のようにはしにくい医療制度になってきている。できる限り入院せずに解決するような外来力が望まれていることを日々感じる。
もう1つは,“地域医療 in hematology”とでもいおうか,すなわち,血液病の治療を高次機関で厳密に完璧にやるという考えとは対比的に,無治療で緩和のみというのではないものの,無理して完全寛解をめざすのではなく,生存がそれなりに延び,遠くの高次機関に通院するのではなく自宅近くの相対的に小さく機能の低い医療機関でも実施できるような治療選択肢が増えてきた印象を抱いた点である。内服薬があるという点で1つ目と重複はするが,例えば骨髄異形成症候群,慢性骨髄性白血病,慢性リンパ性白血病,真性多血症など,専門的な診断・評価・ステージングが最初は必要でも,観察や治療などは地域の病院でも可能な場面が増えてきたように思う。低リスク骨髄異形成症候群へのアザシチジンなどは,化学療法をやっていて緊急採血ができるような医療機関ならば,常勤専門医が不在でも(サポートを受けながらであれば)外来で実施可能だし,例えば慢性骨髄性白血病や慢性リンパ性白血病などは,診断も治療も外来でできる。慢性リンパ性白血病なら骨髄穿刺なしでも診断できる。データの推移,血算のパターン,細胞表面マーカー解析を見ることは通常の血液検査で実施可能である。治療に用いられるBTK阻害薬も経口薬である。また,本書にはホス...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。