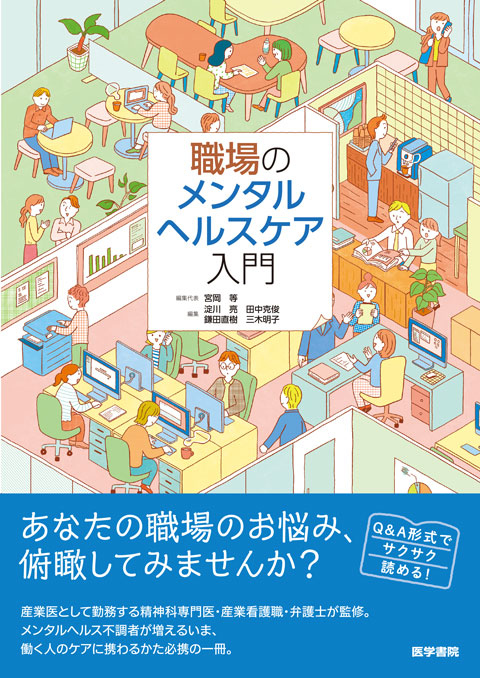健康と自殺から考える予防的介入
対談・座談会 玉手慎太郎,末木新
2024.08.13 医学界新聞(通常号):第3564号より

平常時からの「予防的なかかわり」が前提とされる点で共通する,公衆衛生と自殺。個人の自由の尊重を基本的な価値とみなす現代社会において,予防的介入が無制限に許容されることはない。本紙では,公衆衛生倫理を専門とする倫理学者の玉手氏,自殺や自殺予防を専門に研究する心理学者の末木氏による対談を企画。ヘルスケアや自殺を考える際に生じる葛藤やもやもや感について,広く議論した。
末木 私は臨床心理学を専門に,自殺や自殺予防を中心とした研究を行っています。主軸は自殺予防におけるインターネット関連技術の活用にあり,NPO法人OVA(オーヴァ)の行っているインターネット・ゲートキーパーという検索連動型広告1)を用いた自殺の危機介入にかかわっています。そうした研究・実践を通して,より良い危機介入の在り方を模索しているところです。
玉手 私はもともとは経済思想や政治思想を勉強していて,博士号を取得した後,縁があって7年ほど東京大学の医療倫理学教室でお世話になりました。その頃から公衆衛生倫理の領域に携わるようになり,22年の末に『公衆衛生の倫理学――国家は健康にどこまで介入すべきか』(筑摩書房)2)を上梓したことから,その内容について医学界新聞でインタビュー3)を受けました。自殺も公衆衛生倫理も比較的ニッチな領域ではありますが,両者をクロスさせて考えることで,新たな展望を得られればと思います。
時代や地域によって変わる自殺への価値観
末木 自殺の研究は心理学のフィールドであまりメジャーではありません。1998年の自殺者数急増,2006年の自殺対策基本法成立を受けて自殺に関する研究に関心が集まったことは確かですが,研究・実践の面で中心的な役割を担ってきたのは心理学者ではなく,地域精神保健に携わる方々でした。
玉手 そうした研究・実践において,自殺予防はどう扱われてきたのでしょうか。
末木 基本的には自殺を防ぐことを念頭に置いてあらゆる研究・実践が行われてきたと言っても過言ではないと思います。自殺を予防するにはどうすればいいのか,との観点が常にベースにあるのです。先に述べた自殺対策基本法は,国および地方公共団体が自殺対策を策定・実施する責務を有することを定めていますし,国民に対しては「生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする」としています。しかし,自殺は予防すべきだ・予防しなければならないとの考え方は人類の歴史において普遍的なものではなく,地域や時代によって大きく異なります。
玉手 自殺予防は所与の前提,自明の正義ではないということですね。
末木 はい。世界的に自殺対策への関心が高まったのは1990年代で,自殺対策国家戦略モデル作成のためのWHO専門家会議が開催されたのは96年です。予防の対象とされる以前のキリスト教圏では,自殺は犯罪同然の罪深い行為とされていましたし,日本では江戸時代に近松門左衛門による浄瑠璃『曽根崎心中』の影響で恋愛心中が増加した際に心中禁止令が出され,心中既遂者の遺体や未遂者に対して処罰が行われました。しかし,さらにさかのぼると,ローマ帝国の国教とされる以前の初期キリスト教においては,自殺を罪とし罰を与えることはありませんでした。こうして簡単に過去を振り返るだけでも,自殺予防に対する考え方に時間的・地域的普遍性がないことはおわかりいただけると思います。数百年~数千年後の人類社会においても自殺が予防すべきものと考えられている保証は全くないわけです。こうしたことから,「自殺はそもそも予防すべきなのか?」との問いを,常に持ち続けています。
生命の公共化と,拭いきれない違和感
玉手 ちょうど今,担当するゼミでジョン・ロック(註1)の著作を読んでいるのですが,古典的リベラリズムにおいては個人の領域と国家の領域がはっきりと分けて考えられていたことがよくわかります。ロックは個人が不幸になることに待ったをかけるのは国家の役割ではないと明言しているのです。いわゆる公私二分論で,現代にもつながる考え方のはずですが,歴史上どこかの段階で公私を二分できない部分が生じたのだと思われます。自殺が私的問題から公的問題とされるようになったことに見られるように,われわれの生命がいわば公共化していると言っていいかもしれません。
末木 生命の公共化ですか。言われてみると,そうなのかもしれません。
玉手 昔であれば,たばこを吸って結果的に肺がんになろうがそれはその人の勝手であり,他人の知るところではなかったわけです。それがいつの間にか,予防可能ながんによる経済的負担を減らすために適切な予防策を……といった方向で,公共の問題として扱われるようになりました。その基底にあるのは,われわれの身体は国家の資産,資源であり,労働力および生殖を行う再生産力として国家管理の対象とするという,フーコーの指摘した近代社会の在り方です。もちろん私的領域には外部から口出しできない,という状況はある種の抑圧の温床としての側面を持つため,公共化が総じて問題かと言うとそうではありません。例えば家庭内における女性の抑圧を公共の問題としたフェミニズムによる公私二元論批判(註2)は,適切な指摘であったと考えます。
末木 自殺に関しても,予防を促進するためのロジックを構築してきた歴史があります。自殺直前の人間の心理状況を異常/病的なものとして,合理的な判断を下せる状態ではないから予防するといった方向の議論は随分昔から存在します。最近では,自殺者は社会的な構造によって追い込まれているのだから予防の必要があるといったロジックも目につきます。予防が大切だということ自体に異論はないものの,本当にそれでいいのか,予防に傾きすぎているのではとのもやもやを抱えています。
玉手 ヘルスプロモーションの基本もやはり予防です。しかし,国家による健康への予防的な介入が無制限に許されると考える人はほとんどいないでしょう。本人の利益になることを相手の同意なしに強制することをパターナリズムと呼びますが,無制限のパターナリズムは許容されません。日本国憲法には国民が基本的人権を有することが記されており,個々人の感覚としても個人の自由が尊重されるべきだとの考えを多くの人が持っているものと思われます。リベラリズムが基本OSとしてインストールされているような状態です。だからこそ,個人の自由を制限する予防的な介入に対して,どこか引っ掛かる感覚や気持ち悪さを抱くのではないでしょうか。
致命的な局面ではクリシェでしゃべれなくなる
末木 気持ち悪さに関連した話題なのですが,最近は生成AIを相談事業にどこまで活用して良いのかについて考えることが増えました。「いのちの電話」の類の相談...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

玉手 慎太郎(たまて・しんたろう)氏 学習院大学法学部政治学科 教授
2014年東北大大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。東大大学院医学系研究科生命医療倫理教育研究センター特任研究員等を経て,21年より現職。近著に『公衆衛生の倫理学――国家は健康にどこまで介入すべきか』(筑摩書房),『ジョン・ロールズ――誰もが「生きづらくない社会」へ』(講談社)。

末木 新(すえき・はじめ)氏 和光大学現代人間学部心理教育学科 教授
2012年東大大学院教育学研究科臨床心理学コース博士課程修了。博士(教育学)。12年和光大現代人間学部心理教育学科講師等を経て,21年より現職。公認心理師,臨床心理士。主著に『自殺学入門――幸せな生と死とは何か』(金剛出版),『「死にたい」と言われたら――自殺の心理学』(筑摩書房)など。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。