失敗しない臨床留学の進め方
対談・座談会 筒泉貴彦,山田悠史
2024.06.11 医学界新聞(通常号):第3562号より
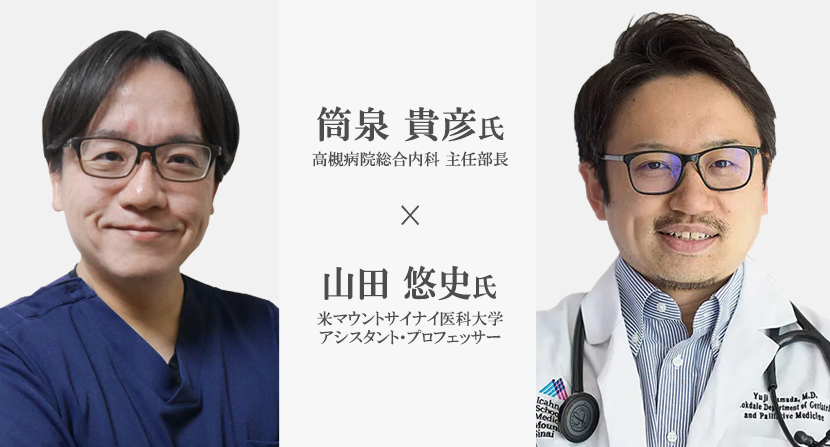
臨床留学は医師としてのキャリアだけでなく,人としての成長にもつながります。一方で,留学先での働き方や,現地での生活になじめず挫折してしまう人も少なくありません。臨床留学を実りあるものにできる人とそうでない人の違いはどこにあるのでしょうか。
多くの留学生を輩出し自らも米ハワイ大学に留学した経験を持つ筒泉氏と,米ニューヨーク市・マウントサイナイ医科大学で臨床に従事する山田氏の対談を通じて,臨床留学を検討する際に求められる心構えを考えました。
筒泉 大学6年生のときに神戸大学が設けていた1か月間の短期留学プログラムでハワイを訪れたことが臨床留学を志したきっかけです。ニューヨークやタイも留学先の候補としてありましたが,ミーハーだった私はハワイを選びました。そこで医学教育や臨床で行われる医療の質の高さを目の当たりにして,ここで内科医としての研鑽を積みたいとの思いを抱きました。その短期留学プログラムを終えた後,USMLE(米国の医師国家試験)の勉強と,日本の研修医としての努力を並行して行い,卒後6年目からハワイ大学の内科研修プログラム(UHIMRP)のレジデントとして臨床留学することができました(写真1)。
山田 私は医学部に入学してから,医師になること以外で何かをやり遂げたいと考え,USMLEの対策本と『六法全書』を買って,米国の医師免許か,弁護士資格のどちらかにチャレンジしようとしていました。勉強を進めていたところ,自分は医学が好きだと改めて自覚したことから米国医師免許の取得に舵を切りました。
臨床留学は成長するための一つの選択肢
筒泉 山田先生は大学在学時からUSMLEの勉強をされていましたが,渡米したのは卒後7年目でしたね。
山田 とんとん拍子で行けば卒後2,3年目から臨床留学できそうですが,研修医としての生活自体が楽しく充実していたので留学への興味がいったん薄れました。臨床留学を再び考えるようになったのは後期研修中です。それまで面白いように医師としての飛躍的な成長を感じて充実感を抱いていたものの,徐々に陰りが見えてきました。そうした時に大学院へ進学し博士号を取得する人もいますが,私は学生時代にUSMLEのステップ1を取得していたこともあり,初心に帰って臨床留学について考えるようになりました。ちょうどそのタイミングで藤谷茂樹先生(聖マリアンナ医大)に出会い,「USMLEを取っているのに渡米しないなんてもったいない」と情熱を持って声を掛けられ,背中を押される形で,当時練馬光が丘病院総合内科のプログラムディレクターを務められていた筒泉先生の下で2年間トレーニングを積んで留学に至りました。タイミングや人との出会いが私を米国に導いたのです。
筒泉 私と出会う前から山田先生は総合診療に軸足を置かれていました。総合診療を学ぶことも米国留学のモチベーションだったのでしょうか。
山田 はい。今でこそ多くの病院に総合診療科が立ち上げられましたが,私が初期研修医の頃はほとんどありませんでした。総合診療のスキルを伸ばしながら自らのキャリアパスを歩もうと思ったときに,総合診療が分野として成り立っている米国で学ぶことは自分のビジョンと合致していました。
筒泉 山田先生は臨床留学を自らの成長に生かせていると思います。もちろん日本国内だけでも成長できる機会はたくさんあります。一概に米国と日本どちらが良いかという話ではありませんが,自分のやりたいことと,それを提供してくれる環境とのマッチングが重要なのであり,それが国内であっても,どこの国でも良いと思います。私の友人である心臓血管外科医のうち何人かは,オーストラリアやタイに武者修行として留学しています。加えて,医学部に入学してすぐに米国医師免許や弁護士資格のための勉強をしようなんて普通は思わない中でプラスアルファを求めてきた山田先生にとっては,努力している人のほうがより報われる環境も向いていたのだと思います。日本の組織はどうしても年功序列や平等性を意識するところがあるので,高みをめざして何かスペシャルなことをしたい人には,海外の環境は合っています。山田先生は今も米国で過ごされていて,環境としてはどうですか。
山田 診療科や働く地域によっても変わりますので,全てを反映した言葉にはならないものの,異動したり帰国したりする理由が何も見つけられないほど今の病院に満足しています(写真2)。日本では2024年から始動した働き方改革の面でも米国は先進的で,医師が守られている点が大きな違いかと思います。

筒泉 私も留学によって20~30年前に米国の働き方改革を見ていて,日本の働き方改革を考えるに当たっての道標をいただきました。また,日本と米国それぞれの研修医を経験して,井の中の蛙とならず世界という大海を知ることができたように思います。同じ病気を見ているはずなのに重症度分類も,治療指針とそこに至った根拠の考え方も全部がとにかく違って,それを直に学べたことで医師としての視野が広がりました。昨今はインターネットで日本との違いは調べられますが,実際に体験するのとでは理解度が異なります。
留学による成長は生活面でも実感しました。自分と肌の色,国籍,宗教,言語が違う人たちとかかわるというのは,日本語ネイティブで容姿も似通った人が大半を占める日本での生活と全く異なります。家族とも異なる環境での生活をお互いに頑張っていこうとラポールも深まりましたし,自分の人生の中でスペシャルな期間となりました。
山田 私も医師としての成長と,人間としての成長の両方を感じています。ニューヨークは世界でも有数の多言語・多国籍の都市なので,時に英語ですら使いものにならないこともありました。診療では6言語の通訳を使う日もあり,時間もかかるため大変ですが,学びもすごく大きいです。これまでの人生でいろんなことを知った気になっていましたが,何も知らなかったのだと日...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

筒泉 貴彦(つつみ・たかひこ)氏 高槻病院総合内科 主任部長
2004年神戸大医学部卒,同大病院にて初期研修。淀川キリスト教病院,神戸大病院での後期研修を経て,09年より米ハワイ大内科レジデントプログラムで留学。12年に帰国後,練馬光が丘病院にてプログラムディレクターとして総合診療科の立ち上げ,15年には明石医療センターの総合内科の立ち上げに従事する。17年より現職。総合内科専門医,米国内科専門医,米国内科学会上級委員。編著に『THE内科専門医問題集』シリーズ(医学書院)ほか。
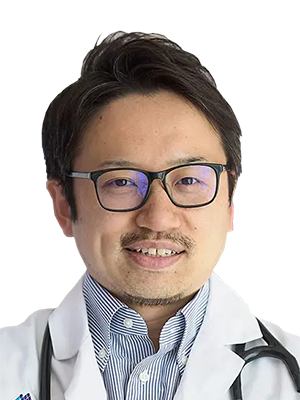
山田 悠史(やまだ・ゆうじ)氏 米マウントサイナイ医科大学 アシスタント・プロフェッサー
2008年慶大医学部卒。東京医歯大病院にて初期研修修了。川崎市立川崎病院総合内科,練馬光が丘病院総合診療科を経て15年に渡米。米マウントサイナイベスイスラエル病院にて内科レジデントとして勤務する。18年埼玉医大病院総合診療内科の助教として帰国した後,20年に再度渡米し現職。総合内科専門医,米国内科専門医。編著に『THE内科専門医問題集』シリーズ(医学書院)ほか。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![THE内科専門医問題集(Ver.2)1 [WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/5017/0840/2038/111559.jpg)
![THE内科専門医問題集(Ver.2)2 [WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6217/0850/1235/111560.jpg)
![THE内科専門医問題集(Ver.2)3[WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2717/0979/5964/111561.jpg)
![最強の医学英語学習メソッド[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/7716/0458/9929/107485.jpg)