MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.05.14 医学界新聞(通常号):第3561号より
《評者》
草場 鉄周
北海道家庭医療学センター理事長
日本プライマリ・ケア連合学会理事長
薬剤処方の危険を見抜くための感度を高める
本書は好評だった初版から10年を経て,紙幅も大幅に増して掲載薬剤数も充実して刊行された待望の改訂版である。
2008年に米国のBeers博士との共同研究で今井博久先生らが発表した「日本版ビアーズ基準」をベースに,高齢者に避けるべき薬剤の紹介とそれに対する代替薬の提示,その使用法を解説するのが初版の大きな特徴であった。今回はさらに,有用な情報が追加で盛り込まれている。まず,高齢者のコモンディジーズである心不全,腎不全,認知症,転倒などを持つ患者に対して避けるべき薬剤が新たに提示された。加えて,多疾患合併が一般的な高齢者に,相互作用を惹起しやすい薬剤についての情報も掲載された。
評者のようにプライマリ・ケア医として外来診療,在宅診療に取り組む際に遭遇する一番の課題は,診療時間の多忙さである。例えば,高血圧,糖尿病,脂質異常症,脳梗塞後遺症,高尿酸血症,神経因性膀胱にて受診する高齢患者がいたとする。7種類ほどの薬剤が投薬されており,その中でシロスタゾールが脳梗塞の再発抑制目的で処方されていたとしよう。診察の中で糖尿病の検査データを確認し,内服状況をチェック。さらには,脳梗塞後遺症による神経因性膀胱の影響で夜間の頻尿が目立ち,歩行の不安定性もあって転倒する機会が増えていることを踏まえ,介護保険を利用した手すりの設置や段差の解消をケアマネジャーに依頼する。10分程度の診療でこうしたマルチタスクを行うわけだが,この患者が下腿浮腫と労作時の呼吸苦を訴えて心エコーで心不全が指摘されたとしたらどうするか。この際に,避けるべき薬剤があると速やかに認識するのは簡単なことではない。
本書では高齢者の心不全でシロスタゾールがもたらす頻脈や催不整脈作用を踏まえると,中止が望ましいことが紹介されている。そして,代替薬としては少量アスピリンやクロピドグレルが提示されている。既に処方されている薬が,新たな健康問題によって避けるべき位置付けとなった場合に気付くのは難しい。本書ではそうした気付きのきっかけとなる知識がわかりやすく整理されている点が実にありがたい。
同じく,相互作用についても日本のように多くの診療科でさまざまな投薬がなされているのが一般的な環境では,他科から新規に処方された薬を確認した時点で相互作用にすぐに気付くことも容易ではない。本書を活用することで,新規処方による変化に対応できるメリットも大きいだろう。
このように,疾患とリンクした避けるべき薬剤一覧,さらには相互作用を起こしやすい薬剤の一覧が頭に入っていることは,多忙な診療の中で効率良く薬剤を選択する大きな武器になる。現場の第一線で活躍する臨床医の皆さんには,ぜひ本書を手に取って,危険を見抜くベースラインと感度を高めていただきたい。まさに「使える」テキストである。
《評者》 真田 弘美 石川県立看護大学長
デジタルツールが苦手な人から熟達者まで,まず映像から見て学べる良書
「教育のDX化はもう耳にタコができるほど聞いているが,いまだにパワーポイントの録画から進化せず,自身の講義に満足できない教員がいかに多いことか!」 今回の評は,まさに今でも講義室で80人以上の学生の前で画一的な授業をしている自身への自責の念を込めて書いています。
COVID-19の流行により,われわれはICTを活用した教育を余儀なくされ,知識もデバイスもそろわない中で大きな課題に直面しながら授業を実践しました。しかし第5類感染症に分類されたことをきっかけに,ほとんどが対面授業に戻っていきました。それはなぜでしょうか? われわれのような熟練教師は,根本的にデジタルツールに弱いからでしょうか。あるいは,「対面教育こそが学生の反応を確認でき,個々に最適な教育を提供できる」と神話のように信じているからでしょうか……。
私自身,デジタル教育と対面教育の違いは,その臨場感にあると信じてきましたが,本書はその思い込みを覆してくれました。紹介されたデジタルツールの有効性もさることながら,チュートリアル教育のように傍らに寄り添ってくれるという感覚,そしてさまざまな動画などの媒体を使って情報を獲得していく合理的かつ自律的な手法が本書には満ちていて,満足度は事前の想像を超えました。
COVID-19流行時,学内演習しかできなかった学生たちのために,当時はオンライン教育の未経験者でありながら,急ピッチで対応を迫られ,試行錯誤しながらデジタルツールを使った教育方法を蓄積してくれたのが,この著者です。本書は,彼だけでなく,学生のために右往左往しながら教材づくりに尽力してくださった若手教育者全体の英知が統合された新教材作成テキストとして,痒いところに手が届くようにノウハウがわかりやすくまとめられています。
本書においては,まずは紙面を先に読むのでなく,それぞれのテーマの映像から見ることをお勧めします。書籍を開いてみると,Zoomやパワーポイントはともかく,それ以外に聞き慣れない方法や機器の名前が出てきます。ですから,実際に説明,活用している動画を先に見て,それから,なぜこれらが教育に効果的なのかをより理解するために紙面を読むと良いでしょう。これを私は繰り返しました。そこで感じたのは,デジタルツールの活用方法や注意点の解説と同時に看護教育の方法論までにも言及した非常に実践的な書籍であるということです。ですから本書は,初心者から上級者まで幅広い層に対応しますが,特にデジタルツールが苦手な人にもお薦めです。
各章内もレベル別になっていますが,第1章から第6章に進むにしたがって,さらにどんどんレベルが上がっていきます。私は第5章までは自力で使えそうだと思いましたが,読者の中には第6章まで使いこなせる方も出てくるでしょう。学生に貢献できる機器がここまで開発されたことに驚くとともに,この新しい教育に対応するスピード感は,必ずや学生を満足...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

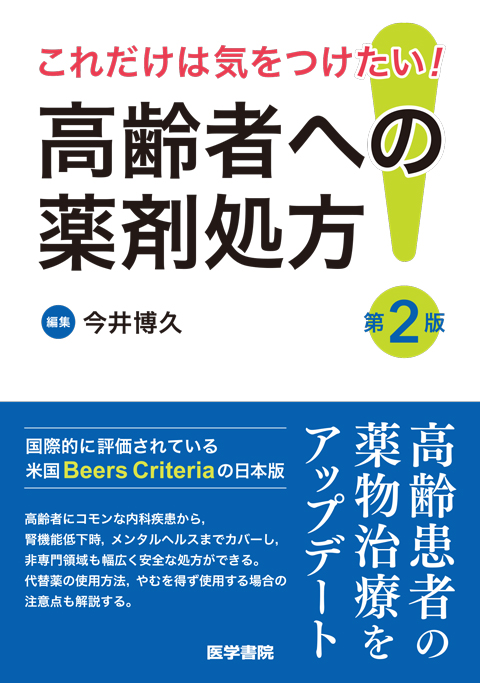
![看護教員のためのデジタルツール活用法[Web動画付] 動画で学んでオンライン授業の質向上!](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1617/0839/4453/113627.jpg)