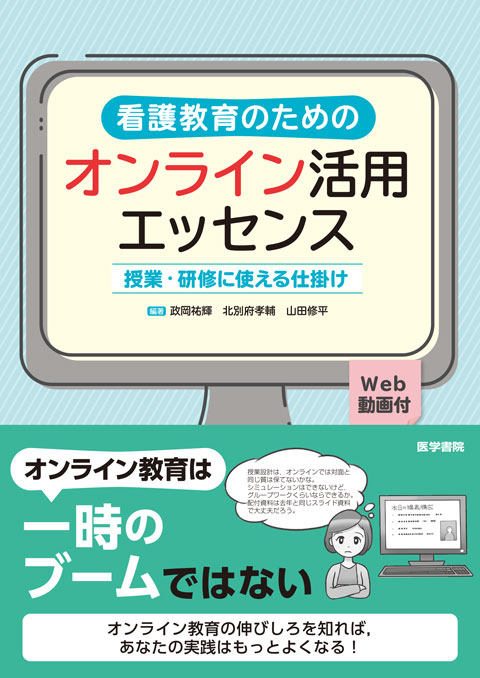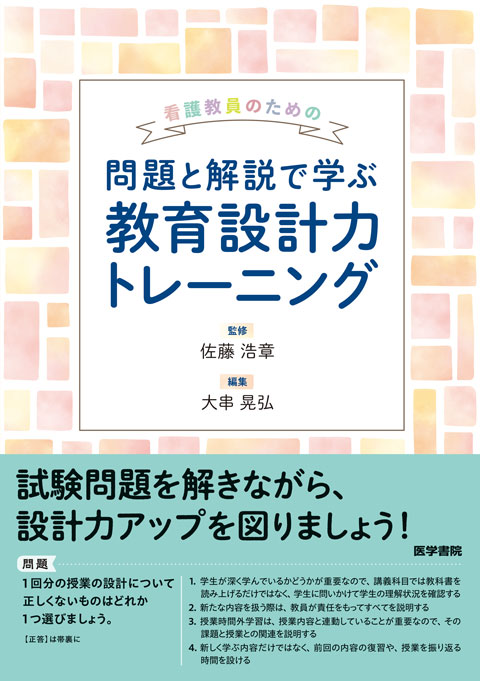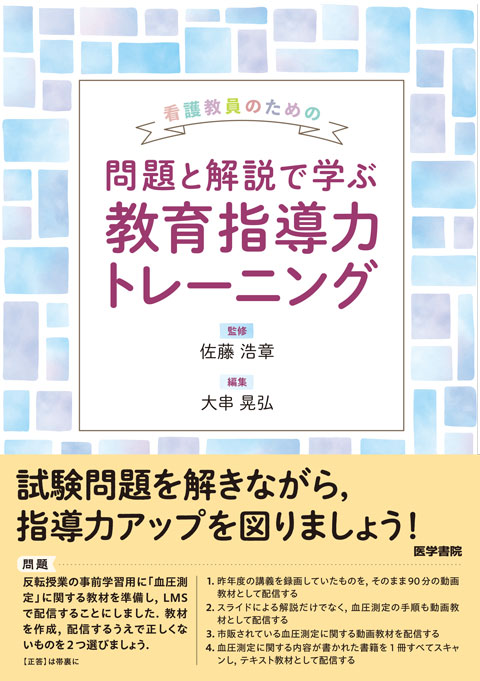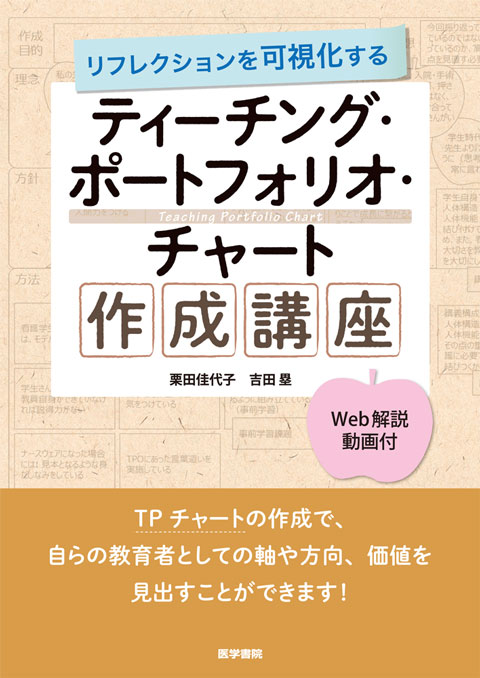看護教員のためのデジタルツール活用法[Web動画付]
動画で学んでオンライン授業の質向上!
オンライン教育に役立つデジタルツールの活用法を映像とテキストで丁寧に解説!
もっと見る
現在、ほとんどの教育機関で何らかのオンライン教育が行われており、そのためのさまざまなデジタルツールが登場しています。ただ、教育方法は多岐に渡り、状況に応じてどのようなツールを適正に組み合わせればよいか、悩みは多いことでしょう。本書は、著者が実際に活用しているデジタルツールについて、その効果と使い方を映像とテキストで解説したものです。映像とテキストを行き来しながら活用法を身につけてみてください。
| 著 | 板谷 智也 |
|---|---|
| 発行 | 2024年02月判型:B5頁:136 |
| ISBN | 978-4-260-05379-2 |
| 定価 | 2,860円 (本体2,600円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 著者による本書の紹介
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
著者による本書の紹介
開く
序文
開く
はじめに──デジタルツールで授業の質向上
■オンライン教育はデジタルツールでもっとよくなる
2020年の新型コロナウイルス感染症流行後,教育機関は大混乱に陥りました。ほとんどの教員は「オンライン授業」なるものを経験したことはなく,知識もツールも揃わない状態で,それでも急ピッチでオンライン教育の対応をせざるを得ませんでした。私自身も何から手を付けていいかわからず,右往左往しながら取り組んでいた記憶があります。「次の授業からオンラインで」と突然言われ「そんな無茶な」と思ったことは何度もありました。しかしながら,「できません」というわけにもいきませんので,四苦八苦しながらなんとかオンライン授業の準備を進めていきましたが,教育機関で働く多くの人が同じような経験をしたのではないでしょうか。
一方で教育機関の底力はあなどれないとも感じました。「激変」と言っていいほど大きな改変に,内容の差はあれども,いずれの教育機関も対応し,日本の教育は最初の新型コロナウイルス感染症の流行を破綻することなく乗り越えました。これはすごいことだと思います。
最近では,ほぼすべての教育機関で何らかのオンライン教育が行われていると思います。コロナ禍になって数年が経ち,オンライン教育は業界にも浸透してきました。コロナ禍後の教育が1つの形になってきたように思います。その一方で,教育機関で教えている先生のなかにも,未だにオンラインを使った授業などに慣れていない方も多いのではないでしょうか(何を隠そう私もその1人です)。なぜなら,オンライン教育の方法は多岐にわたり,状況に応じてどのような方法をとるか随時選択する必要があるからです。とにかく選択肢が多いと思います。方法が1つに絞られるのであれば,回数をこなすことで慣れていきますが,授業ごとに方法が変わるオンライン教育においては,状況とツールを適正に組み合わせて教材を提供する必要があり,そこが難しい点だと思います。
看護教育について言及しますと,看護学は実践的技術を習得する側面が強い学問です。したがって,座学と同時に演習(ここでは「実践を想定した身体活動を伴う能動的な学習」としておきます)が大変重視されます。看護の教育機関における教員は,「演習」をどのようにオンラインで実施するかに頭を悩ませているのではないでしょうか。オンラインで演習はなかなか難しく,注射や点滴など手技の習得を行うのは困難かもしれません。しかし,コミュニケーションや資料の作成など,情報交換を主とする演習であればデジタルツールを活用することで十分可能です。こうしたオンライン演習の方法を設定するヒントになる内容も本書では含んでいます。
■本書の構成──前半はやさしく,後にいくほどレベルアップ
本書ではさまざまなオンライン教育の方法を整理し,それぞれに用いるデジタルツールと使い方を具体的に示していきます。紹介するデジタルツールにはさまざまな種類があり,最も基本的でよく使われるハードとしてのパソコンに始まり,操作の難易度の高いものとしてはオーディオミキサーやビデオスイッチャーなどが登場します。ソフトウェアについても,われわれにはなじみ深いPower-Pointから始まり,動画配信に用いるOpen Broadcast Software(OBS)の説明まで進みます。また,それぞれの章において「まずはここから」「次はこうする」「ここまで行こう」「どうせだったら」というようにレベル分けをして,レベル1から数字が大きくなるほど難易度が上がります。さらに,書籍全体についても,基本的には前半はやさしく,後半になるほど難易度が上がるようになっています。登場するデジタルツールについても,後半にいくほど使い方が難しいものが登場します。
具体的な内容について少し触れておきますと,第1章のレベルでは,普段の講義で使っているPowerPointのスライドからオンデマンド教材をつくる方法を説明します。使用するのはパソコンとPowerPointだけです。操作自体は難しくはありませんが,学習効果に言及しながらテキストと動画で説明をしていきます。章の後半では,学生を引きつける教材をつくるための「編集」の方法まで説明していきます。本章の説明では実際の方法をなるべく具体的にイメージができるように,私が実際に使っている教材を提示しながら説明していきます。第2章ではWeb会議システムを使った授業について説明します。単に操作方法を説明するのではなく,それぞれの教育効果に言及しながら通常のWeb会議システム,ウェビナー,ハイブリッド形式について説明します。
第3章では,オンライン授業などにおける学生とのコミュニケーション方法について説明します。オンライン教育ではコミュニケーションがとりにくいと思われがちですが,Web会議システムに備わっているツールや,外部ツールを使ってコミュニケーションをとることができます。第4章では,オンライン授業での,学生間の対話を促す方法について説明します。この章はデジタルツールそのものの使い方というよりは,デジタルツールを使ったアクティブラーニングについて説明する内容になります。
第5章は対面とオンラインを混ぜて実施する方法について説明します。最近では感染対策の規制が緩和されつつも,引き続きオンラインを使った対策も並行して行われる場面が多くなっています。ただ,対面とオンラインを混ぜた教育はデジタルツールの使い方がとても複雑になります。この章では,ツールのセッティング方法から丁寧に説明をしていきます。章の後半では,学術大会でも使えるようなハイレベルな使い方についても説明していきます。第6章はライブ配信を説明します。レベル1ではスマートフォンを使って簡単に配信する方法を説明しますが,章の後半ではOBSを使った配信方法を説明します。OBSを使った方法は技術的な難易度は上がりますが,非常にダイナミックで,学生を引きつけ集中力を高めた授業ができます。
最後の7章ではトラブルシューティングを用意しました。デジタルツールを使ったオンライン教育にはトラブルがつきものです。ネットワークの接続問題,パソコンの操作トラブル,学生のデバイスに関する問題など,よくあるトラブルを取り上げて対処法を列挙しましたので,困ったときはここを開いてみてください。
なお,私は在宅看護が専門なので,事例の多くは在宅看護関係ですが,他の科目で活用できるのはいうまでもありません。
■幅広い読者に対応するため2種類の動画を提供
デジタルツールを使うメリットとしては2つあり,1つは教員側の教育業務の作業効率が上がるということ。もう1つは学生の学習効果が高まるということです。この書籍のねらいとしては,まずは簡単なデジタルツールを活用して,手軽に授業教材を作成し,教育業務の負担をできるだけ抑えるような解説をしていこうと思います。各章のレベル1では,そのようなツールの説明を行っていきます。そして,レベルが上がるごとに「教育効果の向上」をねらったツールとその使い方を説明していきます。詳細は本編をご覧いただきたいですが,「デジタルツールなんて苦手!」という方から,「対面とオンラインを混ぜたハイブリッド形式の学会をしたい!」という方まで幅広い内容を扱っていきます。
デジタルツールの使い方や注意点は,テキストで読んでいてもわかりにくい部分があります。いえ,テキストの説明だけですっきり理解できることはほぼないように思います。そこで,本書では動画での説明も用意しました。なかでも,2つの解説動画を用意したものがあります。1つはパソコンの画面を使って説明しているもの。もう1つは,実際にデモンストレーターとして「デジタルツール初心者」が登場するものです。具体的には5章レベル4と6章レベル4の操作の部分です。この動画内で初心者が説明を受けながらパソコンなどを操作する様子が見えます。実際にパソコンを操作する「人」が登場することで,この本を手に取った方が自分自身を置き換えてイメージしやすいのではないか,という発想でつくった動画です。どちらも内容は同じですので,わかりやすいほうを選んでご視聴ください。まずはテキストで知識を整理しながら,動画で使い方を確認することをお勧めします。
先に述べたように本書はデジタルツール初心者からハイブリッド形式の学会を主催したい人まで幅広く対応します。本書を活用することで,教育業務が少しでも楽しくなり,そして少しでも看護学教育における教育効果が向上することを願っています。これからはウィズコロナ社会として,デジタルツールを使った教育が定着していくと思います。本書がその一助となれば幸いです。
2024年1月
板谷智也
目次
開く
はじめに──デジタルツールで授業の質向上
第1章 オンデマンド授業や自習で使う教材を作成する
▪ まずはここから(LEVEL 1)
普段の講義で使っているPowerPointのスライドに講義音声と気持ちを吹き込もう!
──無味乾燥な「成人看護学」のスライドを,潤いのある動画に
TIPS スライドをわざわざ「音声付き動画」にするのはなぜ?
TIPS 動画撮影の際のちょっとしたコツ!
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
Windows標準装備のアプリでデスクトップ画面を録画して,動画をつくろう!
──パソコンを使った演習の準備として操作方法を動画で説明,反転授業にも使える!
TIPS 「動画作成」のメリットは授業教材に限らない!
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
書き出した動画を編集して,学生を魅了するクリエイティブな教材をつくろう!
──カット編集とテロップ&画像を使って動画をテンポアップ
TIPS 動画編集がプレゼンスキルを向上させる!
第2章 Web会議システムを使ったライブ授業をする
▪ まずはここから(LEVEL 1)
いつもの授業をZoomミーティングでやってみよう!
──「在宅看護論」の授業で学生が自主的に学ぶ姿が見てみたい
TIPS Zoomを使った授業がうまくいくポイント
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
教員(主催者)が操作を行う安定感のある授業をWebexウェビナーでやってみよう!
──「在宅ケアと看取りの研修会」で,複雑な内容をわかりやすく伝える
TIPS 研修の在り方を激変させたウェビナー
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
対面授業に,オンラインからでも違和感なく参加してもらう「ハイブリッド(ハイフレックス)形式」の授業に挑戦しよう!
──「在宅看護論」の対面授業にオンラインでも参加できるようにすると対面の臨場感とWebの利便性の両立が可能に
TIPS ハイフレックス授業では「ボディランゲージ」が活用できる
第3章 ライブ授業で参加者とコミュニケーションをとる
▪ まずはここから(LEVEL 1)
スタンプを使って学生のリアクションを受け取ろう!
──スタンプだったら恥ずかしがり屋も問いかけに反応が
TIPS 実務的に大変有効なスタンプ活用
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
チャット機能を使って意見集約しよう!
──単純なスタンプより具体的で細かな反応が見える
TIPS 実務的なチャット活用法,出席確認
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
オンラインアンケートツールを使って「匿名で」意見集約! リアルタイム表示で結果を共有しよう!
──slidoを使って「あなたは人生の最期をどこで迎えると思いますか?」と問いかけてみると
TIPS slidoを活用するメリット
第4章 ライブ授業でスモールグループに分けて対話させる
▪ まずはここから(LEVEL 1)
Zoomのブレイクアウトルームを使って議論を活性化しよう!
──ブレイクアウトルームを使えば,対面よりグループワークがスムーズに
TIPS オンラインのアクティブラーニングにブレイクアウトは必須である
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
ブレイクアウトルームのなかで資料(記録)も作成しよう!
──グループワーク中にGoogleドキュメントで資料が作成できる
TIPS 授業だけじゃない! あらゆる場面で作業を効率化するクラウド型ツール
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
ブレイクアウトルームを任意参加設定にしてジグソー法をやってみよう!
──オンラインでのアクティブラーニングで,グループダイナミクスを活かした学習効果が得られる
TIPS 難しい面もある! ファシリテーションが重要なオンラインのグループワーク
第5章 対面とオンライン参加者のコミュニケーションを違和感なく促す
▪ まずはここから(LEVEL 1)
対面とオンラインをミックスし,あたかも「みんなそこにいる」かのようなディスカッションの場をつくろう!
──研究室のゼミで,その場にいない参加者とも自然に話せるようになる
TIPS とっても便利なスピーカーフォン
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
講義室にいる参加者に向けてオンラインでプレゼンテーションしてもらおう!
──オンライン参加のプレゼンテーターに話してもらうためのセッティング
TIPS 音質と機能性に優れたオーディオインターフェース
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
ビデオスイッチャーを使ってサクサク画面切り替え! テレビ放送のような配信をしよう!
──パネルディスカッションが,カメラを切り替えながらの配信でまるでテレビ番組に
TIPS ビデオスイッチャーをオンライン会議で使うメリットは?
▪ どうせだったら(LEVEL 4)
対面とオンライン参加をミックスしたハイブリッド形式の学会を開催しよう!
──会議や発表をオフライン,オンライン関係なく共有すれば,学会運営もこわくない
TIPS オンライン学会を自前でできれば費用は10分の1??
第6章 YouTube を使って授業や演習をライブ配信する
第1章で作成した動画教材をYouTubeで配信してみよう!
▪ まずはここから(LEVEL 1)
スマートフォンを使って,手軽に簡単にさくっと授業を配信しよう!
──「保健統計学」を題材に,全身を映して講師の細かい訴えを可視化する
TIPS とにかく簡単! スマホを使ったライブ配信
▪ 次はこうする(LEVEL 2)
外部カメラ,外部マイクによる高品質な音と映像を配信して,学生の心をつかもう!
──「保健統計学」を題材に,映像と音声の高品質化で見取り聞き取りできる情報量がアップ
一眼レフやダイナミックマイクを使用する場合に必要な機材の例
TIPS ガジェット沼に気をつけよう
▪ ここまで行こう(LEVEL 3)
ちょっと変わった配信方法! 「Zoomを使った対話」をライブ配信しよう!
──「市民公開講座」を題材に,「Zoomでの打ち合わせの様子」配信で会議をトークショー化
TIPS Zoomミーティングをライブ配信するさまざまなメリット
▪ どうせだったら(LEVEL 4)
Open Broadcaster Software(OBS)を使って,授業をライブ配信しよう!
──「保健統計学」のスライドを題材に,配信テクニックの活用で授業がみるみるダイナミックに
TIPS OBSの価値を高めるのは教員の技量?
第7章 トラブルシューティング
インターネット接続の問題
映像や音声の問題
共有機能や画面共有の問題
ミーティングにおける設定や接続方法の問題
参加者のトラブル対応など
おわりに
索引
動画一覧
VIDEO 1 第1章 レベル 1 PowerPointに音声を吹き込む
VIDEO 2 第1章 レベル 2 デスクトップ画面を録画して説明動画を作成する
VIDEO 3 第1章 レベル 3 PowerDirectorを使って「Excelの使い方」の動画を編集する
VIDEO 4 第2章 レベル 1 Zoomを使ったオンライン授業の方法
VIDEO 5 第2章 レベル 2 Webexウェビナーの設定から開始まで
VIDEO 6 第2章 レベル 3 最も簡単なハイフレックス授業2つの方法
VIDEO 7 第3章 レベル 1 Zoomのスタンプでリアクションを受け取る
VIDEO 8 第3章 レベル 2 Zoomのチャット機能で意見集約
VIDEO 9 第3章 レベル 3 Zoomを使いながらslidoで意見集約
VIDEO 10 第4章 レベル 1 Zoomでブレイクアウトセッションをやってみる
VIDEO 11 第4章 レベル 2 Zoomミーティング中にGoogleドキュメントで資料作成
VIDEO 12 第4章 レベル 3 ブレイクアウトルームを活用してジグソー法実施
VIDEO 13 第5章 レベル 1 スピーカーフォンとWebカメラ,大型モニターを使ったハイブリッド会議
VIDEO 14 第5章 レベル 2 オーディオインターフェースで対面会場とオンラインの音をつなぐ
VIDEO 15 第5章 レベル 3 ビデオスイッチャーで画面切り替えしてテレビのような配信
VIDEO 16 第5章 レベル 4 ハイブリッド形式の学会設営を自前で済ます
VIDEO 17 第5章 レベル 4 補足──ハイブリッド形式に用いる機材のセッティングをしてみよう
VIDEO 18 第6章 レベル 1 スマホを使ってYouTubeでライブ配信
VIDEO 19 第6章 レベル 2 パソコンと外部カメラ,外部マイクを使ってライブ配信
VIDEO 20 第6章 レベル 3 ZoomミーティングをYouTubeでライブ配信
VIDEO 21 第6章 レベル 4 Open Broadcaster Software(OBS)を使ってライブ配信
VIDEO 22 第6章 レベル 4 補足──外付けマイクとカメラをOBSにセットしてみよう
書評
開く
デジタルツールの活用で、オンラインと対面は相補的になる!
書評者:大村 裕佳子(金城大学看護学部)
COVID-19の流行は教育機関にも大きな混乱をもたらした。本書には、著者がその流行を機に試行錯誤して得た、質の高いオンライン教育のための実践知が集約されている。デジタルツール初心者からハイブリッド形式の学会を主催したい人まで幅広く対応した内容で、テキストは簡潔にまとめられ、各章ごとに説明動画が収録されている。使用機材も丁寧に説明されていることから、手技や環境の再現も比較的容易だろう。
私から見た著者は、山岳に心酔して世界各国のトレイル・ランニングを制覇するスーパーアスリートでありながら、そのGPSのログを解析して健康増進に寄与できないかと論文化してしまう、保健統計学のエキスパートでもある人物だ。故郷で災害が起きた際には、その健脚を活かして孤立した集落に到達し、支援活動を行っていた。そして、大学教員系YouTuberとして看護師国家試験対策動画を配信するなど、まさに越境人材・進化系教員として心から尊敬している。
私は「いしかわ多職種連携教育プロジェクトあいまいぴー」という、学校でも職場でもないサードプレイスでの多職種連携教育/学習(Interprofessional Education/Learning:IPE/IPL)の運営に携わっている。保健医療福祉などの学生、実践者、教員を中心に、参加者がゲームや自職種の紹介、「ごちゃまぜカンファ」という多職種でのグループワークを通してお互いから学び合い、より良い連携・協働の在り方について考える営みだ。COVID-19の流行前は多様な人々が一堂に会することに価値を置き、運営メンバーと対面で密なコミュニケーションを図りながら、IPEイベントを計画してきた。
IPE/IPLは、いかにインタラクティブ(相互作用)であるかが重要である。オンラインでは再現が難しいのではないかと絶望していたが、Google Jamboardを用いれば、遠隔でもブレインストーミングができ、また、文書の共同編集、データの共有、ミーティングのログとしての録画の活用などができた。本書の中でも紹介されているSlidoは、タイムリーに匿名でコメントを集約・共有することができ、オンラインIPEイベントにおいてとても役立った。
このように、今やオンラインは単なる対面の代替ではなく、相補的なものとなった。デジタルツールの活用により、人々は距離を超えて集うことが可能になり、工夫次第では双方向での学びも可能である。あいまいぴーの仲間にはデジタルツールの最適化の達人がおり、共にオンラインでさまざまな作業に取り組むうちに、いくつものツールを使いこなせるようになった。さらに、本書を読んだことで目的に合わせた各ツールの設定の詳細がわかり、より自信を持って円滑に操作できるようになったと感じている。看護教員はもちろん、幅広い分野の方に本書をご活用いただきたい。
(「看護教育」 Vol.65 No.3 掲載)
デジタルツールが苦手な人から熟達者まで,まず映像から見て学べる良書
書評者:真田 弘美(石川県立看護大学長)
「教育のDX化はもう耳にタコができるほど聞いているが,いまだにパワーポイントの録画から進化せず,自身の講義に満足できない教員がいかに多いことか!」 今回の評は,まさに今でも講義室で80人以上の学生の前で画一的な授業をしている自身への自責の念を込めて書いています。
COVID-19の流行により,われわれはICTを活用した教育を余儀なくされ,知識もデバイスもそろわない中で大きな課題に直面しながら授業を実践しました。しかし第5類感染症に分類されたことをきっかけに,ほとんどが対面授業に戻っていきました。それはなぜでしょうか? われわれのような熟練教師は,根本的にデジタルツールに弱いからでしょうか。あるいは,「対面教育こそが学生の反応を確認でき,個々に最適な教育を提供できる」と神話のように信じているからでしょうか……。
私自身,デジタル教育と対面教育の違いは,その臨場感にあると信じてきましたが,本書はその思い込みを覆してくれました。紹介されたデジタルツールの有効性もさることながら,チュートリアル教育のように傍らに寄り添ってくれるという感覚,そしてさまざまな動画などの媒体を使って情報を獲得していく合理的かつ自律的な手法が本書には満ちていて,満足度は事前の想像を超えました。
COVID-19流行時,学内演習しかできなかった学生たちのために,当時はオンライン教育の未経験者でありながら,急ピッチで対応を迫られ,試行錯誤しながらデジタルツールを使った教育方法を蓄積してくれたのが,この著者です。本書は,彼だけでなく,学生のために右往左往しながら教材づくりに尽力してくださった若手教育者全体の英知が統合された新教材作成テキストとして,痒いところに手が届くようにノウハウがわかりやすくまとめられています。
本書においては,まずは紙面を先に読むのでなく,それぞれのテーマの映像から見ることをお勧めします。書籍を開いてみると,Zoomやパワーポイントはともかく,それ以外に聞き慣れない方法や機器の名前が出てきます。ですから,実際に説明,活用している動画を先に見て,それから,なぜこれらが教育に効果的なのかをより理解するために紙面を読むとよいでしょう。これを私は繰り返しました。そこで感じたのは,デジタルツールの活用方法や注意点の解説と同時に看護教育の方法論までにも言及した非常に実践的な書籍であるということです。ですから本書は,初心者から上級者まで幅広い層に対応しますが,特にデジタルツールが苦手な人にもお勧めです。
各章内もレベル別になっていますが,第1章から第6章に進むにしたがって,さらにどんどんレベルが上がっていきます。私は第5章までは自力で使えそうだと思いましたが,読者の中には第6章まで使いこなせる方も出てくるでしょう。学生に貢献できる機器がここまで開発されたことに驚くとともに,この新しい教育に対応するスピード感は,必ずや学生を満足させるに違いないと確信します。そして,われわれ熟練者が心配しなくても,本書で用いられているようなデジタルツールは,学生が自ら作成し,自立・自律的に学習するのに用いることになるでしょう。これがきっと,著者の考える教育の将来像なのではないかと感じざるを得ません。
![看護教員のためのデジタルツール活用法[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1617/0839/4453/113627.jpg)