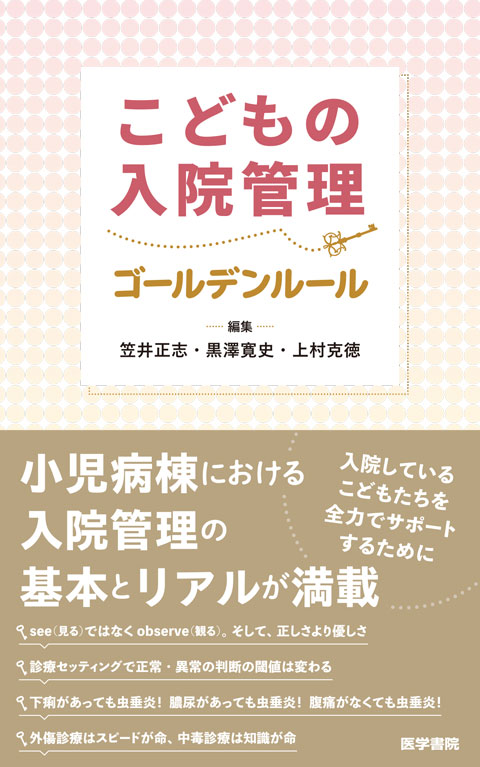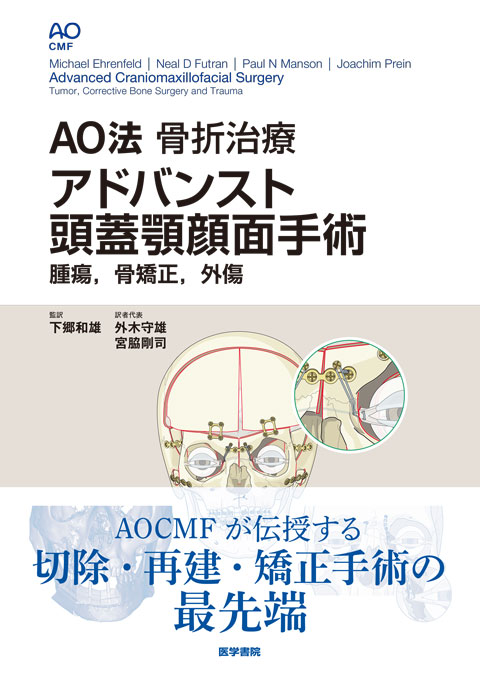MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.03.18 週刊医学界新聞(通常号):第3558号より
《評者》 伊藤 健太 あいち小児保健医療総合センター 総合診療科医長
こどもたちのために,光り輝くルールを知ろう!
笠井正志先生から「ロックな書評を」と依頼され,(何を言っているのかよくわからなかったが)ロックな書評を試みてみようと手に取った本の書名が『こどもの入院管理ゴールデンルール』である。反抗の音楽の代表格ともいえるロケンロールな書評の対象が「ルール」とは……。ルールを破ってこそが,ロックじゃないのか。
*
気を取り直して,「ルール」とは何か,考えてみた。ルールは,よくある「マニュアル」や「トリセツ」と何が異なるのだろうか? そんな思いを抱えながら,この本を読み進めていった。すると本書がルールとしているものがおぼろげながら見えてきた。
本書では,各病態や疾患ごとのページの頭に「ゴールデンルール」と称したクリニカルパールのような一文がある。例えば,細気管支炎の項では「余計なことをせず,安寧・安心が最大の治療」とか,栄養の項には「絶飲食にするなら,その理由と,どうなったら経腸栄養を開始するのかを説明できなければいけない」というふうに。なるほど,これらの一文たちを読むだけでも,とても現実的で実践的な臨床現場のリアルを感じる。数多のマニュアル本ではその疾患・病態の定義に始まり,Aという状況にはBとか,Xという数値を超えたらYとか,懇切丁寧に一対一対応を教えてくれるが,このゴールデンルールはそんな知識やガイドよりもっと「知恵」に近い。そしてこの知恵は,笠井先生をはじめ上村克徳先生,黒澤寛史先生,そして兵庫県立こども病院の面々が日々のこどもの入院診療の中で絞り出し厳選し,その中から浮かんできた不文律を言語化したモノ,つまりルールなのだ。
その実,各医療施設にもおのおのの不文律が多いことを私は知っている。入院3日目には採血とか,CRP 2 mg/dL以上は抗菌薬とか,解熱しないと退院できないとか……ね。
さて,皆さんにはそれらの不文律をルールとして言語化して書式化する勇気はあるだろうか? その不文律は,どうして生まれたのか? 疑問を呈しても変わらないのはなぜか? 何より誰のためなのか? これらの問いに胸を張って答えることはできるだろうか?
翻って,本書におけるルールには,一本しっかりとした芯がスゥっと通っている。それは「こどものためになっているか?」である。この信念があるからこそ,不文律は胸を張って言語化され,ルールとして日の目を見たのだ。
*
さて,最後に本書で白眉ともいえる部分をもう一つ紹介する。重症なこどもの入院管理の先,つまり各病態の集中治療管理におけるルールも教えてくれているのである。小児科医は手前味噌で集中治療をやりすぎるきらいがあるが,本当にこどものためを考えるなら,集中治療の専門家に診療を任せたほうが良い瞬間が実はたくさんあることを,本書から学んでほしい。
本書を通読中,私はずっと深くうなずき続けていた。傍から見たその姿は,ロックに心酔しヘッドバンキングしているようだったろう。皆さんも珠玉なルールたちにロックを感じてください。ロックな書評,オシマイ!
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。