MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2024.01.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3548号より
-
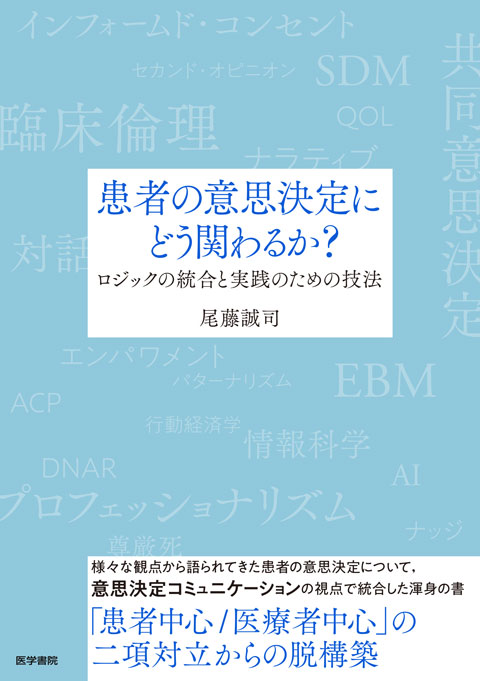
患者の意思決定にどう関わるか? ロジックの統合と実践のための技法
- 尾藤 誠司 著
-
A5・頁248
定価:4,180円(本体3,800円+税10%) 医学書院
ISBN978-4-260-05330-3
《評者》 秋山 美紀 慶大教授・環境情報学部/医学部大学院健康マネジメント研究科
最良の意思決定に関与するための羅針盤
「膵臓のがんが,肝臓のあちこちに転移してます」。今年7月,都内のがん専門病院で,母が宣告を受けた。説明を聞いた母の口から最初に出てきた言葉は,「先生,今年パスポートを10年更新したばかりなんですけど……」だった。説明した医師も,隣にいた私も意表を突かれ,しばしの沈黙となった。
著者の尾藤誠司氏は,ロック魂を持った総合診療医であり,臨床現場の疑問に挑戦し続けるソリッドな研究者でもある。諸科学横断的な視座から探求し続けてきた研究テーマは,臨床における意思決定(注:医師決定ではなく意思決定)である。尾藤氏は約15年前に『医師アタマ――医師と患者はなぜすれ違うのか?』(医学書院,2007)を出版し,誤ったエビデンス至上主義がはびこりつつあった医学界へ一石を投じた。その数年後には一般向けに『「医師アタマ」との付き合い方――患者と医者はわかりあえるか』(中公新書クラレ,2010)という新書を出した。帯に「医師の取扱説明書」とあるとおり,患者・市民が医師の思考パターンを理解し,良好な関係を築けるような知恵が詰まったわかりやすい書籍だった。
さて,今回出版された『患者の意思決定にどう関わるか?――ロジックの統合と実践のための技法』は,氏のこれまでの集大成となる渾身の学術書であり,実践への指南書でもある。今日まで蓄積されてきた,臨床の意思決定を考える上で不可欠な理論や領域(例えば,プロフェッショナリズム,臨床倫理,さまざまな行動科学理論,EBM,ナラティブ,さらには生成AIに至るまで)を網羅するだけでなく,そこに経験を積んだ臨床家ならではの深い考察と分析が加えられている。思弁的な部分と実践的な部分が交差する本書は,実用的でありながらも,経験知やハウツーを伝える医学書とは明らかに一線を画している。
医師と患者の関係は,医師が主導権を持つパターナリズム,サービス消費者ととらえられる患者が力を持つコンシューマリズムを行き来し,SDM(shared decision making:共同意思決定)の時代に入ったといわれている。PubMedで論文を検索すると,2010年代半ばからは,SDMの論文刊行数がインフォームド・コンセント(IC)を抜いて急上昇し続けている。しかし,ICもSDMもEBMも全て,欧米から輸入された概念である。それらが登場した文脈や,めざす理念は理解できたとしても,実際の診療現場にそれらをやみくもに落とし込もうとすると大きな困難と混乱にぶつかる。日々の診療は,「決める」という行為の連続である。時間に追われる中,目の前の患者の訴えは置き去り,EBMもICも形骸化し,医療者にとっての正解を押し付けてしまうことも多いだろう。
例えば,医療者は知識やエビデンスなどを,患者は自身の価値観や病の体験などを持ち寄り,共同で意思決定を行うことは可能なのだろうか。そもそも両者は何をシェアすべきなのか。両者の信頼とはどのようなことを言っているのか。本書では,そうした疑問を持つ医療者が思考を深め納得できるよう議論が展開されていく。本書は,患者の意思決定の「支援」ではなく,意思決定への「関与」が大事だと強調している。支援と関与はどのように異なるのか,なぜ支援より関与が大事なのか,ぜひ臨床家の皆さんに本書を手に取って確認していただきたい。
冒頭で紹介した母は,告知の2か月半後に彼岸へ旅立った。パスポートは使えなかったが国内旅行を2回楽しみ,自宅で家族に手を握られながら息を引き取った。母にとって最良の意思決定ができたのか,本書を読みながら考え続けている。
《評者》
伊東 直哉
愛知県がんセンター感染症内科部
感染対策室長
感染管理の実務担当者の新たなバイブル本
坂本史衣先生といえば,言わずと知れた「感染管理のプロフェッショナル」です。感染症業界の人ならば,まずその名を知らない人はいないのではないでしょうか? 知らなかったらモグリです。「感染管理ならば,感染症内科医もやっているでしょ? 専門でしょ?」と,思われるかもしれませんが,チッチッチ,それは違うのです。あくまでもわれわれ感染症内科医は,感染症「診療」の専門家であって,「感染管理」の専門家ではないのです(一部に両方に深い見識と経験を持つ稀有な存在もいますが)。坂本先生は,学会活動や多くの著書を通じて,長きにわたって日本の感染管理を牽引されてきました。私自身も,実際に坂本先生の講演や著書で感染管理を学んできた熱心なファンの一人です。そのような師匠的存在の坂本先生の著書の書評を書かせていただくことはとても光栄なことで,とてもとてもうれしいことなのです。
さて,『感染対策60のQ&A』ですが,『感染対策40の鉄則』(医学書院,2016)よりもさらに読みやすく進化しており,感染管理の実務担当者の新たなバイブル本の一つになると確信しています。
本書は各テーマが数ページにコンパクトにまとまっており,忙しい業務の合間にもさっと読むことができます。内容は網羅的に記載されているので,臨床現場で直面する可能性がある頻度の高い疑問に対してはきっと答えを見つけられると思います。...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

