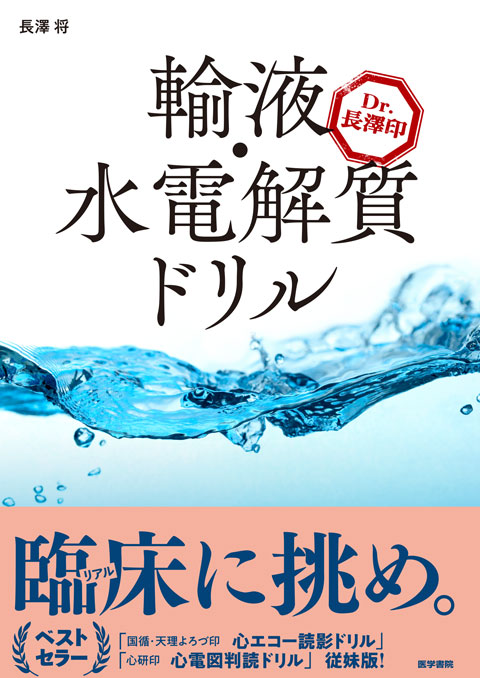輸液・水電解質のもやもやを考える
対談・座談会 長澤将,木附大晴,笠原千晶
2023.11.13 週刊医学界新聞(レジデント号):第3541号より

輸液・水電解質の知識は重要ではあるものの,原因が明快にわからずもやもやするケースや検査値がグレーゾーンで判断に迷うケースが多く,苦手意識を持つ研修医は少なくないだろう。このたび長澤将氏が上梓した『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』(医学書院)は,そんな悩み多き輸液・水電解質にまつわる問題を,厳選した20症例を通じて解説しており,臨床での考え方をわかりやすく学ぶことができる。
そこで本紙では長澤氏と腎臓内科医をめざす卒後2年目の笠原氏,総合診療科の専攻医で卒後3年目の木附氏による座談会を企画。笠原氏,木附氏が臨床で感じた率直な疑問を長澤氏に投げかけた。
長澤 本題に入る前に一つお伺いしたいのですが,先生方は学生時代に輸液・水電解質をどれくらい勉強してきましたか?
笠原 正直に言うとまとまった勉強をしたことはなく,研修医になる直前に教科書を1冊読んだ程度です。内科ローテーションの最初の1か月は何がわからないかもわからず,メインとなる輸液の選択一つとっても不安から過度に考え込むことがありました。卒後2年目とまだ経験を積んでいる最中なので,現在は電解質異常の患者に出会うたびに,あんちょこ本とにらめっこしながらどうにか対処している状態です。
木附 私も笠原先生と同じく,学生時代はほとんど輸液の勉強はしてきませんでした。恥ずかしながら輸液には1号液から6号液,リンガー液,生理食塩水があり,それぞれNa濃度が異なることくらいしか知らなかったです。臨床に出て,知識が必要になるたびにその場で調べ,学んできました。
長澤 やはりそういうものですよね。ですが,勉強をしていなくとも困ったケースはあまりなかったのではないでしょうか? 腎臓は輸液に応じて臨機応変に対応してくれるため,輸液をそれなりに行っても大抵は何とかなりますし,経験の浅いうちはそれでも良いと私は思っています。
木附 たしかに臨床に出たばかりのころは,先輩のまねをして安直に生理食塩水をつなげているだけで解決することも多く,特に困らなかったです。ですが,日を経るにしたがって付け焼き刃では対処できない悩ましいケースに当たる機会が多くなり,もやもやすることもどんどん増えてきました。今日は長澤先生にお話を伺い,この疑問を解決できればと思います。
体液量は患者のエピソードも併せて多角的に評価する
笠原 まずお聞きしたいのは体液量評価についてです。低Na血症を鑑別する際などに体液量評価は重要だと思うのですが,例えばエコーで下大静脈(IVC)が12 mm/8 mmで少し浮腫んでいるように見える,心不全のグレーゾーンにいる患者をどう評価すべきか毎回悩んでいます。
長澤 何か一つの指標で簡単に判断できることが理想ですが,複雑な実臨床でそれは難しいです。私が一番妥当だと思う方法は,カルテを見て患者の話を聞き,病歴やエピソードから多角的視点で患者を評価することです。例えば,食事が摂れていなければ脱水の可能性が高く,多量の輸液をされていた場合は溢水が疑われます。嘔吐や下痢がある患者の体液量が過剰になることも通常はあり得ません。熱中症で溢水に陥るケースもそうないでしょう。ケースごとに細かく分析し,常識にのっとって評価することで,おのずと予測が立てられます。
木附 身体所見についてはどう考えれば良いでしょうか?
長澤 体液量を示唆する身体所見として,口の粘膜の乾燥や目のくぼみ,ツルゴールなどがありますが,救急外来で初めて診る患者に対しては活用が難しいことも多いです。また臨床経験がまだ浅いと,典型的な身体所見でも経験したことがないものもあるのではないでしょうか? 例えば重度の溢水で結膜まで浮腫んだ患者を実際に診たことはありますか?
木附 教科書には記載されていても,それほど重度の浮腫みを実際に見たことはないです。
長澤 そうですよね。ですが検査値や病歴など,身体所見以外のさまざまな情報を合わせれば判断できますから,実際に目にした経験がなくても大丈夫です。教科書的な知識は知識として理解しておけば良いと思います。
さらに考えてほしいのは,今すぐに結論を出す必要があるのかということです。臨床上,すぐに出さなくて良い答えは数多く存在します。ですから最初は,「○○なのでおそらくこれは脱水だと思います。なので,まず輸液を入れます。◇◇時間後にフィードバックします」のように判断できればOKです。フィードバックの結果も情報の一つになります。採血・尿検査などの結果やエコーなどのさまざまな情報を統合すれば,最終的に正しい治療につなげられるでしょう。
木附 なるほど。さまざまな手段を使って多角的に判断し,治療の方向性を修正していくというのは非常に納得がいきました。
笠原 多角的に判断するには総合的な判断力が必要だと思いますが,その判断力はどう身に付けていけば良いでしょうか?
長澤 教科書と臨床経験の両輪でバランス良く学ぶことです。教科書に関しては,自分と相性の良いものを探し,繰り返し読むことを勧めます。読むたびに成長度に応じた新たな知識や気づきが得られるでしょう。
一方で,迅速な臨床方針の決定方法,複数の患者を診る際の優先順位の考え方は現場での経験からでなければ絶対に身に付けられません。臨床で先輩の動き方を見たり,患者を診たりしながら学んでいくしかないです。また臨床では教科書通りにならないことも多くあります。そうした経験がその後の研究活動,ひいては領域の発展にもつながるので,教科書通りでない事例に巡り合った時は論文や本に当てはめようとせず,自分の所見を信じて行動してみてください。
数学的に割り切れそうで割り切れない輸液・水電解質
木附 次は,臨床でよく出合うNa,K異常に関してお聞きします。教科書的に鑑別はついたものの異常の原因がはっきりせず,治療によって患者の体調は良くなりましたが,もやもやすることがよくありました。
笠原 そのような事例は頻繁にあります。以前,低Na血症で抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)パターンの患者を診た際,好発する高齢者でなく,原因となりそうな薬剤の使用もなく,肺炎や中枢神経感染症もない事例がありました。その患者にはNa補正を行ったところ症状は改善したのですが,結局原因はわからずじまいでした。
長澤 臨床では原因不明のNa,K異常は度々起こります。例えば抗利尿ホルモン(ADH)は,高張や脱水以外にも採血の痛みや尿道カテーテルの留置による内圧上昇でも分泌されることが実はあります。そうした刺激で一過性の低Na血症になり,検査で引っかかるのです。
笠原 そうしたストレスによる低Na血症になりやすい人はいるのでしょうか。
長澤 間違いなく存在します。ですから患者が退院される際には「のどが渇いていない時は,あまりたくさん水を飲まなくてもいい」とアドバイスしておくと良いかもしれません。再吸収できる水分が減るので,ストレスがあった場合でも低Na血症になる可能性が低くなります。
木附 そのような患者には,何に主眼を置いて対応すれば良いですか。
長澤 大事にするべき基準は,患者の症状が改善しているか,患者が困っていないかということです。将来的には原因が明らかになるかもしれませんが,現時点ではわからないことは数多くあります。その時の処置によって体調が良くなったのなら,原因を過度に気にする必要はありません。もし原因が深刻なものならば,電解質異常を繰り返し訴える可能性が高いので,その時に適切に対処しましょう。
笠原 長澤先生のお話を聞いて,輸液や電解質で感じる難しさやもやもやは,輸液や電解質が一見すると数学的に明快に割り切れそうな雰囲気のある分野だからこそ生じるのかもしれないと感じました。数学的に見えるのにそうではないというところが,輸液・水電解質の難しさであり,奥深い面白さなのかもしれません。
長澤 「輸液・水電解質分野はもやもやするものだ」と認識し,もう少し気楽に診療できるようになれば,この分野が得意でない方も少し苦手意識が薄れるかもしれませんね。
検査も輸液も結果を予想しながら行う
長澤 原因のわからない電解質異常は多々あるとの話が出ましたが,例えば症状のない低Na血症に当たった時,先生方はどのように考えて処置を行っていますか? 例えば,ルーチンで検査をした際,患者さんは元気だったもののNa=121 mEq/Lだった場合です。実際現場でこういった事例はよくあると思います。
笠原 その数値は基準値から離れすぎていて怖いです。125 mEq/Lを下回ると心配になります。初診で高齢でない方が121 mEq/Lであれば焦って入院してもらうかもしれないです。
長澤 じゃあ126 mEq/Lまでならセーフ?
笠原 その時の状況次第ですが……。
長澤 ちょっと意地悪な質問でしたね。そういった場合は尿の比重や尿電解質で判断すると良いでしょう。比重が低かったり低浸透圧だったりする時は,腎臓が調整している最中なので,何も行わなくとも良くなります。むしろそこで輸液をしてしまうと,さらに低Na血症が進みます。ラーメンの味が薄いのにさらにスープを追加するようなものです。
そもそも患者も困っていない,自分も疑っていない項目をルーチンで検査するのは,果たして患者のためになっているのかをよく考えてください。今の病態にその検査は本当に必要ですか? 何かを明確に疑ったり,検査後の方針を考えたりしていないなら測定しないほうが良いです。
木附 1,2年目の時はとりあえず電解質を検査してしまうことも多く,異常を見つけたらもうけものくらいに考えていたのですが,検査項目一つであっても費用はかかり,患者の負担になります。必要性を考えてから行動に移すべきでした。
長澤 将来の自分に「自分はなぜこの選択をしたのか」を説明できるよう,根拠を意識し,結果を予想しながら検査や輸液をオーダーしてください。きちんと考えて行動すると,力がついてきます。覚えることが日々たくさんあり忙しいと思いますが,時間に余裕がある時は一つひとつの「なぜ」を追究する作業を大事にしてほしいです。
こだわりを突き詰めることで力をつける
笠原 卒後1年目の6月ごろに,細かい輸液の種類などを私が思っていたほど上級医が気にしていないと感じ,驚いた記憶があります。今日お話を伺い,あのころの上級医は一つひとつの数字の帳尻を合わせることではなく,「最終的に患者の体調が良くなること」をゴールに設定していたのだなと感じました。
長澤 冒頭で輸液はそれなりに対応すればどうにかなると言いましたが,慣れてくるとみんなそこまで神経質には考えていないのが真実ですよね。実際,なんとなく輸液を選んでも腎臓が帳尻を合わせてくれるため,8~9割のケースはそのまま解決します。ただし肝に銘じておいてほしいのは,医療は8~9割の患者が良ければOKではないということ。残りの1~2割の患者も問題なく診られるように,日ごろから予測と答え合わせを繰り返して学んでいってほしいです。根拠を持って輸液や検査を選ぶのと,とりあえずで選ぶのとでは成長の度合いが大きく変わります。多忙な中,全ての行動において予測とフィードバックを行うと疲れてしまうかもしれないので,まずは自分のこだわりポイントを見つけてそこから始めてみてください。
木附 「こだわりを持つ」「将来の自分に説明できるように診療する」という言葉は,今専攻医という多少責任ある立場になったからこそ重要性を強く実感します。現在専攻している総合診療は浅く広くのイメージが強いですが,自分は何かしら一つ,得意分野を極めていきたいと思っています。例えば,侵襲なく情報を収集できるエコーは非常に有用だと考えており,脱水を疑った場合の多角的評価の一助として頻繁に活用しています。自分にとっての得意分野を突き詰めていくためにも,一つひとつこだわって日々診療していきたいです。
長澤 良いと思いますよ。木附先生がエコーが得意なら,エコーを極めることをめざしてください。慣れてくると心臓の動きを見て,「心臓の動きやIVCの動きが少し速いから,脱水気味かもしれない」のような感覚がつかめてきます。そしてさらに経験を積むと,エコー画像には描出されないものの違和感を覚えるケースが出てくるでしょう。大抵その感覚は当たりますから,経験を積んで,“何かいつもとは違う”という感覚を身に付けるのは大事です。自分の得意な方法を見つけ,技術を磨くと,もっと診療がスムーズに行えるようになると思います。
笠原 私は腎臓内科医志望なので,本日のお話は非常にためになりました。日ごろもやもやしながら診療することが多かったので,この分野はもやもやするものなのだとわかったこと自体が大きな収穫です。主体的に,こだわりを持って患者の対応に当たり,成長していきたいと思います。今日はありがとうございました。
長澤 こだわりは,「リンは原因を明確に疑うまで検査しないぞ!」のような些細なポイントでも構いません。そうしたこだわりを大事にしながら診療していけばどんどん力がつくと思います。頑張ってください。
(了)

長澤 将(ながさわ・たすく)氏 東北大学病院腎臓・高血圧内科 講師
2003年東北大卒。12年同大大学院修了。14年石巻赤十字病院腎臓内科部長などを経て, 19年より現職。著書に『カニでもわかる水・電解質』(中外医学社),『Dr. 長澤印 輸液・水電解質ドリル』(医学書院)など。

木附 大晴(きつき・たいせい)氏 順天堂大学総合診療科
福岡県出身。2021年愛知医大を卒業後,順大附属順天堂医院で初期臨床研修を実施。その後,同院の総合診療専門医の研修プログラムに進む。現在は筑波記念病院救急科に勤務。

笠原 千晶(かさはら・ちあき)氏 東京都立墨東病院
石川県金沢市出身。2022年東大医学部医学科を卒業後,現在は東京都立墨東病院で初期臨床研修を行っている。患者や上級医とのかかわりの中で体液や腎臓の面白さに気づき,腎臓内科医を志望する。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。