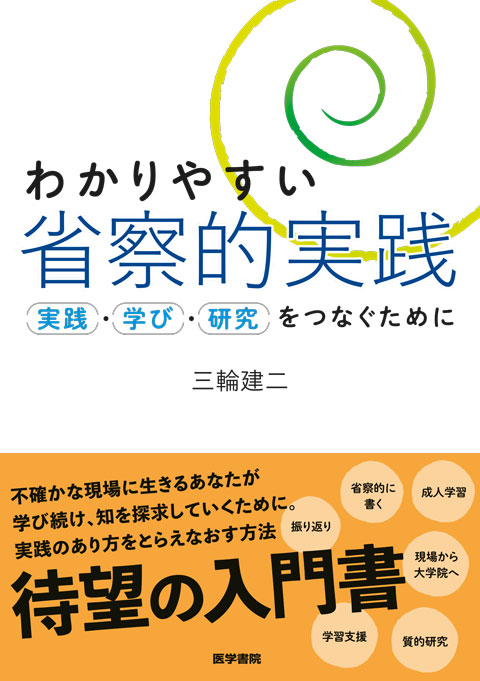省察的実践で看護師の「わざ」を磨く
三輪 建二氏に聞く
インタビュー 三輪建二
2023.03.27 週刊医学界新聞(看護号):第3511号より

ドナルド・A・ショーンが提唱した「省察的実践者」(Reflective Practitioner)の考え方は,現在の専門職の学びに大きな影響を及ぼしている。看護学生,看護師の教育においても,自らの経験から学ぶ省察(リフレクション)の重要性が認められ,多くの教育実践が報告されている。
省察的実践や成人学習に関連した書籍の翻訳を手掛けてきた三輪建二氏が,この度『わかりやすい省察的実践――実践・学び・研究をつなぐために』(医学書院)を上梓した。書籍のねらいと看護師に適した省察的実践の活用法を聞いた。
――先生は,ドナルド・A・ショーン著『省察的実践とは何か――プロフェッショナルの行為と思考』(鳳書房)の監訳をはじめとし,省察的実践や成人教育に関連する書籍の翻訳や執筆に数多く取り組んでこられました。今回発行された書籍について執筆の経緯を教えてください。
三輪 勤務先の大学院で,小・中・高等学校の教員のみならず,多くの看護師,社会福祉の専門職の方々が,対人支援の場での教育的なかかわりに悩んでいることに気づきました。いわばそうした“対人関係専門職”の在り方に,省察的実践の考え方はマッチしているのだと考えています。一方でショーンをはじめ,これまで手掛けてきた翻訳書は非常に分厚く,また日本の文化に合わない記述もあります。省察的実践や成人学習について初めて学ぶ方でも,ご自身の実践と結びつけながら理解できる内容をめざし,筆を執りました。
――省察的実践の考え方が“対人関係専門職”にとってなぜ重要なのでしょうか。
三輪 例えば看護師は,同じ疾患の患者でも,その人の背景や個別性をとらえたケアが求められます。看護師自身と患者の関係性にも大きく左右されるでしょう。つまり教科書的な正解を目の前の患者にそのまま当てはめればよいわけではありません。これらの実践では,暗黙知や「わざ」と表現される言語化されていない専門性が駆使されています。しかし,この専門性は科学的でないという理由から歴史的にも低く評価され,対人関係専門職は「専門家」としての扱いを十分には受けてきませんでした。そこでショーンが新しい専門家像として提唱したのが,「省察的実践者」です。私は,対人関係専門職は省察的実践者としての側面があると考えています。
――省察的実践者の特徴はどのようなものですか。
三輪 学びに焦点を当てると,全ての学びを「自分事」として受け止め,日々の自らの実践を振り返り,そこから学びを得る(リフレクション/省察)ことです。リフレクションの1つの方法は,「物語る」こと。自分自身の実践・経験を誰かに向けて語り,コメントや語り合いを通して,暗黙知やわざ,また自身の信念や価値観に気づいていく必要があります。
わざを育てる本来のリフレクションを実践するために
――看護実習後に振り返りの時間が設けられるなど,看護学生や看護師の教育において積極的にリフレクションが活用されていると感じます。
三輪 そうですね。私が勤める大学院の社会人院生には看護師が特に多く,自己成長への熱意や吸収力には目を見張るものがあります。一方で院生の話を聞くと,リフレクションが知識・技術を得るための手段になっており,本来の考え方とは異なる方法で用いられているのではないかと疑問を抱きました。
――どういうことでしょう。
三輪 ショーンは省察的実践者を,「技術的熟達者」との対...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
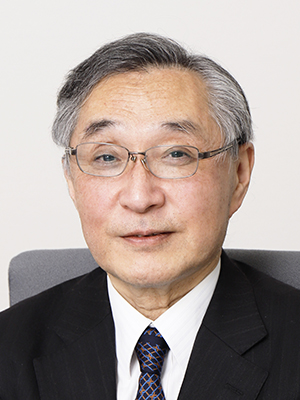
三輪 建二(みわ・けんじ)氏 星槎大学大学院教育実践研究科 教授
1981年東大法学部卒。同大大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。東海大,上智大,お茶の水女子大での勤務を経て,2018年より現職。専門は成人教育論,省察的学習論。監訳本に『省察的実践とは何か――プロフェッショナルの行為と思考』『教師の省察的実践――学校教育と生涯学習』(いずれも鳳書房)など。著書に『おとなの学びとは何か――学び合いの共生社会』(鳳書房),『わかりやすい省察的実践――実践・学び・研究をつなぐために』(医学書院)などがある。日本の成人教育学の啓発・研究に長年取り組み,教員研修,看護研修など多分野で活躍している。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。