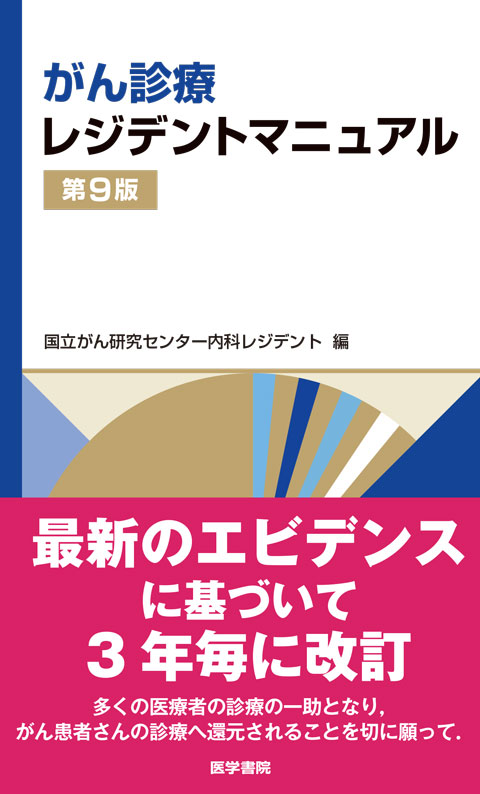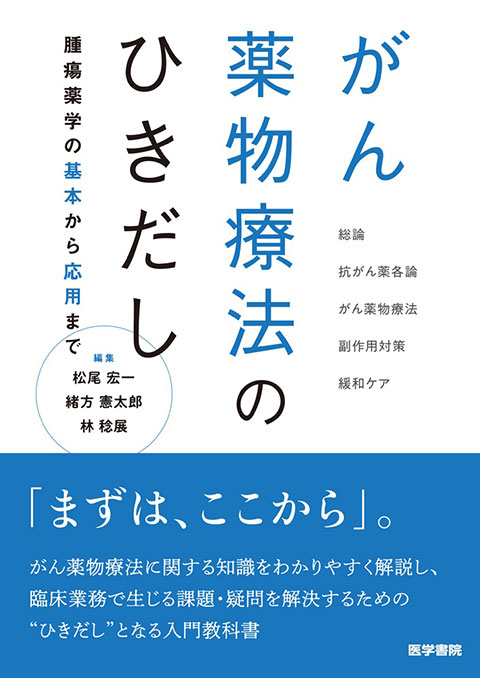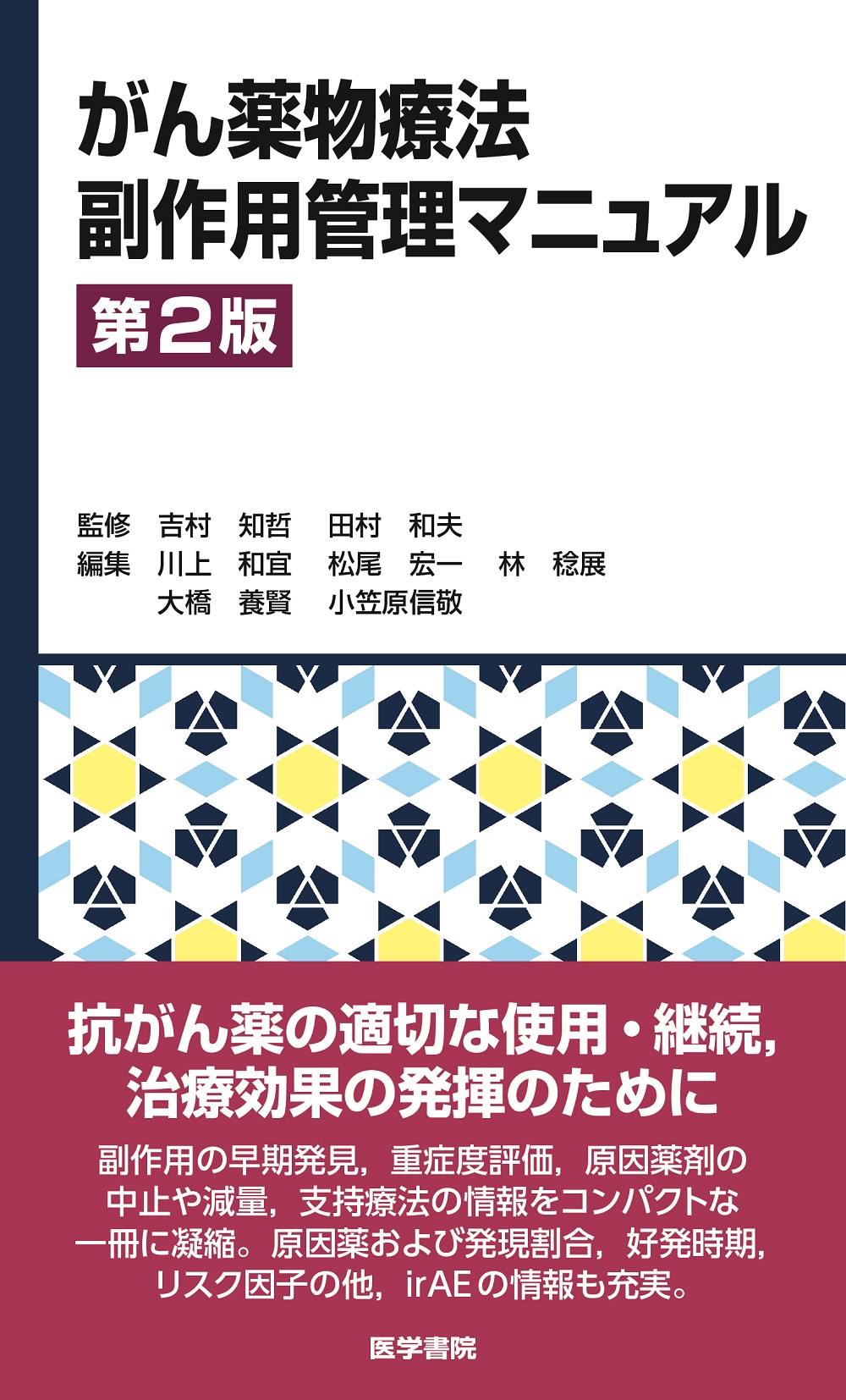外来がん薬物療法看護における患者発信力・トリアージ向上の取り組み
寄稿 磯貝佐知子
2022.12.12 週刊医学界新聞(看護号):第3497号より
がん薬物療法は,がんに対して薬物を使用する全身治療のことを指し,使用薬の種類によって,細胞障害性抗がん薬治療(化学療法),分子標的療法,内分泌療法,免疫療法と呼び分けられることもある。がん種や特定の遺伝子異常の有無によって使用可能な薬剤は限定されるものの,これらから1種類または複数の薬剤を使い,がんの治癒や進行抑制,症状の緩和をめざす。手術療法や放射線療法と併用されることもある。
がん薬物療法の場は入院から外来にシフト
従来がん薬物療法は,入院が主な治療の場であった。しかし2002年度の診療報酬改定で初めて外来化学療法加算が設定され,翌年に入院を対象とした包括支払い制度が導入されたことが,がん薬物療法の場を入院から外来へ移行するインセンティブとして作用した。さらに近年,分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの新薬が数多く上市され,新たなレジメンの開発やがんゲノム医療による個別化医療の進歩が患者の生存率向上と治療期間の長期化をもたらしている。厚労省の調査では,①がん治療患者は50代以上に多いこと,②がん治療患者において,2005~08年の間に外来患者が入院患者の総数を上回っていること,③外来患者はがん治療の副作用や症状をコントロールしつつ,治療を受けながら仕事を続けている場合が多いことが報告された1)。
2018年に制定された第3期がん対策推進基本計画では,外来がん薬物療法に関する多職種での検討の場の設置と,専門医や薬剤師,看護師,がん相談支援センターの相談員等の人材育成と適正配置に努める他,専門職が連携し患者に適切な説明を行うための体制整備に努めるよう医療者に求めている。これを受けて,無菌製剤処理料(2008年度改定),がん患者指導管理料(2014年度改定),連携充実加算(2020年度改定)が新設され2),2022年度は外来でがん薬物療法を実施する患者の緊急時の相談・対応に対して,外来腫瘍化学療法診療料が設置された。
これら医療情勢の変化と治療法・支持療法の進歩に加え,社会生活重視の考え方などにより,現在がん薬物療法の場はさらに外来へと移行している。がん薬物療法を受ける患者は今後も増加が予測されるため,緊急時の相談・対応の体制整備とともに,病院だけでなく地域を含めた多職種連携の強化が求められている。
外来でがん薬物療法を実施する看護師の役割とは
外来でがん薬物療法を安全に実施するには,看護師・医師・薬剤師などの多職種が連携した治療体制の構築が重要である2)。そうした治療体制の中で看護師に求められるのは,副作用の管理や緊急時の対応・体制整備などになる。以下に当院での取り組みを紹介する。
◆副作用症状のマネジメント
細胞障害性抗がん薬や分子標的薬,免疫チェックポイント阻害薬など,薬剤により副作用の機序や発症時期は異なる。近年はこれらを組み合わせた複合がん免疫療法が初期治療として行われ,副作用マネジメントがより複雑化している。また,がん患者の生存率向上によるがん薬物療法期間の延長に加えて高齢化,就労,AYA(Adolescent and Young Adult)世代,心血管系など合併症を持つ患者の増加など患者背景も多種多様になっている。そのため患者ががん薬物療法と社会生活を両立できるように,多角的な視点でアセスメントし,支援を進めていくことが重要となる...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

磯貝 佐知子(いそがい・さちこ)氏 新潟県立がんセンター新潟病院 副看護師長 / がん化学療法看護認定看護師
1996年新潟県病院局に入職。2002年より新潟県立がんセンター新潟病院の化学療法病棟に勤務。09年に聖路加看護大(当時)看護実践開発研究センターにて,がん化学療法看護認定看護師の教育課程を受講し,10年に同資格を取得。同年より新潟県立がんセンター新潟病院外来化学療法室に勤務し,14年より現職。日本がん看護学会,日本臨床腫瘍学会,日本緩和医療学会に所属。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。