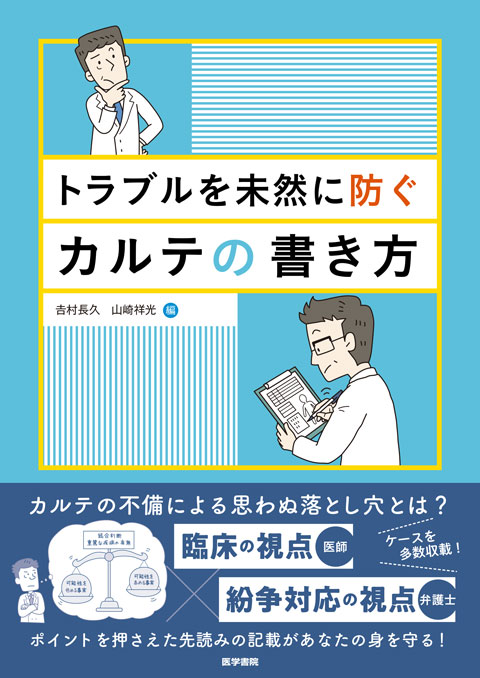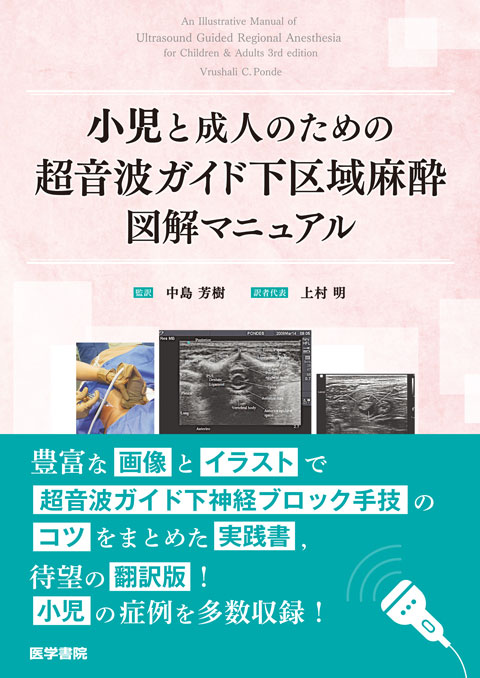MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.10.24 週刊医学界新聞(通常号):第3490号より
《評者》 園部 俊晴 コンディション・ラボ所長
新たな発見で臨床の奥深さに気付かせてくれる一冊
近年,「筋膜(myofascia)」や「膜(fascia)」という用語は,医療だけでなく一般にも認知され,コンビニに並ぶ雑誌にすら「筋膜」という言葉を目にするようになりました。そして,これまでわからなかった筋膜や膜に由来する病態が徐々に明らかになり,整形外科医を含め,運動器にかかわる医療者が,筋膜や膜の臨床的意義を認識するようになってきました。本書『アナトミー・トレイン』は,その先駆け的存在であったと,多くの医療者が認めるところです。
臨床の世界は,どれだけ経験を重ねても,学べば学ぶほど奥が深く,発見の連続であるといえます。筋膜や膜が関与する病態については,最近になってわかってきたことが多く,その顕著な例といえるでしょう。これまで,腰部の障害や病態が原因と思われていた下肢の痺れや痛みも,筋膜へのアプローチによって改善することを,臨床では多く経験します。つまり,実は筋膜の病態であったと確認できることが多くあるのです。その他,筋や腱,靭帯,滑膜,脂肪体が原因と思われた病態が,実は筋膜や膜の病態であることも珍しくありません。こうした発見は,本書に書かれている身体の膜の構造と機能を理解することでひもとけることでしょう。
本書の原著者であるトーマス・W・マイヤース氏は,運動器を連続体としてとらえ,筋膜や膜が姿勢制御や運動連鎖に深く関連していると考えています。これまでの運動器治療は,局所に着目しすぎてきたと私は感じています。だからこそ,この考えにはとても共感できますし,多くの医療者に「身体が連続体である」という考え方を知ってほしいと思っています。今回の第4版で追記された「ピラティス的な考え方」や「ボディリーディング®」の概念も,こうしたトーマス・W・マイヤース氏の考えを理解するのに役立つため,ぜひ一読してほしい項目です。
今後,筋膜や膜に関する病態,ネットワークシステム,運動の連動,さらには皮神経の機能解剖との関連性など,さまざまなことが解明されていくことは疑いありません。そして,それに基づいた運動器治療の変革があるはずです。
私たちが臨床と真摯に向き合い,素直な気持ちで,筋膜や膜の視点も含め,運動器疾患の治療に取り組んでいくことが大切であると,この一冊が気付かせてくれるはずです。
最後に,訳者の板場英行先生と石井慎一郎先生の強い思いとご尽力により,本書がわが国に広まったことに感謝します。
《評者》 川崎 誠治 三井記念病院院長
正確なカルテ記載が身を守る
本書は,北野病院の吉村長久院長と山崎祥光弁護士の編集で上梓されたものである。適切なカルテ記載の重要性を認識し,もともと関心を持っていらっしゃった吉村院長が,医師の資格もあり臨床経験もお持ちの山崎弁護士にカルテ記載に関する講演を数多く依頼してきた。その講演の内容が土台となったのが本書である。このお二人の組み合わせこそが,独特の視点を持つ本書の出版を可能にしたといえる。北野病院医療安全管理室の先生方と山崎弁護士が中心になり著述されているが,本書を読むと,「カルテ記載のない事柄はなかったことになる」ということがあらためて強く認識される。その他に,何となくそうではないか,あるいはぼんやりとどうなのだろう,と思っていたいくつかのことが明瞭に説明・記述されており,大変参考になる。以下に例を挙げる。
・カルテと異なり,忌憚のない意見交換の場であるカンファレンスや医療安全事例検討会などの議事録は開示の義務はない(むしろ開示すべきではない)。それと関連して開示・非開示の書類の区別を医療機関内できちんと定めておくべきである。
・カルテ改ざんと追記訂正は別である(改ざんと思われるのをいたずらに恐れて誤った記載をそのままにするのは問題である)。ただし追記訂正で望まれるのは,初めの記載から1~2日以内,トラブル発生以前である。
・暴言を繰り返したり大声を出したりする患者・家族と病院職員とのやりとりを録音する際には患者・家族の同意を得る必要はなく,同意を得なくても証拠として役立つ。
・救急受診患者の帰宅を認めるときには,重篤な疾病である可能性を低める事実・所見も意識してカルテに記載する。
きちんとカルテに記載するということは基本的に時間を要する作業になるが,医師および診療に携わるスタッフの時間とエネルギーはできるだけ実際の患者診療に向けられるべきであるということが本書では強調され,チェックリストを利用するなどの具体的で簡便なカルテ記載方法も示されており,現場に寄り添った視点が貫かれていることに感銘を受けた。
《評者》 鈴木 玄一 日本小児麻
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![アナトミー・トレイン[Web動画付] 第4版 徒手運動療法のための筋膜経線](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/4216/6071/0392/110492.jpg)