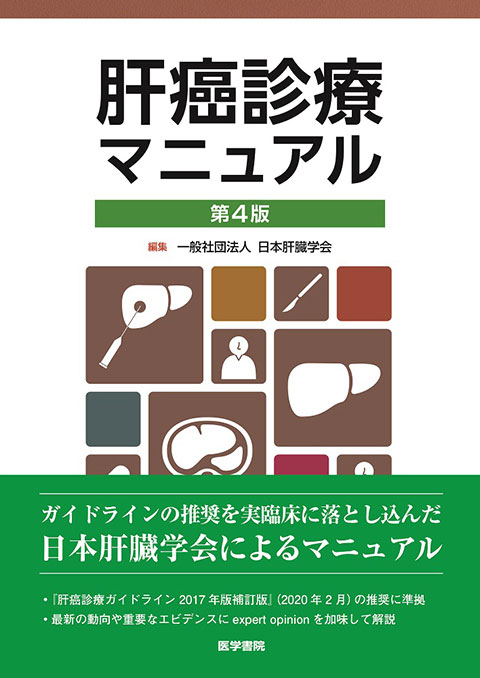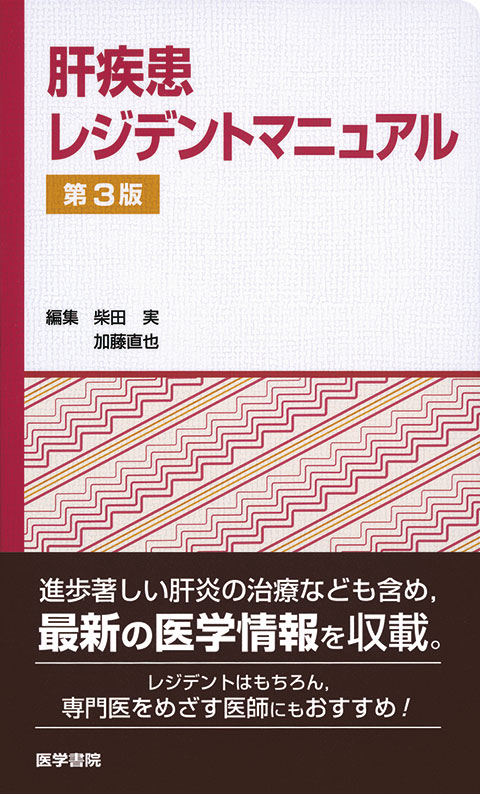かかりつけ医に期待がかかるNAFLD線維化症例のスクリーニング
寄稿 玉城信治
2022.08.22 週刊医学界新聞(通常号):第3482号より
臨床において,肥満や糖尿病の患者が増加していることは多くの先生方が実感していると思われる。これに伴い,それらの疾患を背景とした非アルコール性脂肪性肝疾患(Nonalcoholic Fatty Liver Disease:NAFLD)患者が増加し,またNAFLDを背景とした肝癌の発生も増加している。
増加を続けるNAFLDに適切なスクリーニングを
肝癌の原因を調べたわが国における全国調査では,いわゆる非ウイルス性(non-B,non-C)肝癌が1991年に10.0%であったのに対して,2015年には32.5%まで増加していた1)。非ウイルス性肝癌の中にはさまざまな病態が含まれるが,NAFLDを背景とした肝癌の増加が,全体の増加に寄与していることは間違いない。2019年の1年間に武蔵野赤十字病院で健康診断を受診した2021人の調査では,実に797人(39.4%)が脂肪肝を有しており2),脂肪肝,すなわちNAFLDから肝硬変,肝癌,肝不全へと進展する患者は今後さらに増加することが予測される。進展ハイリスク症例の同定は重要な課題である。
近年の技術の進歩によって,肝線維化,肝脂肪化に対する超音波やMRIを用いた非侵襲的な定量評価が可能となっている3)。具体的には,MRIを用いて肝臓の硬さを測定し,肝線維化を予測できるMRエラストグラフィ,また肝脂肪化の超音波減衰を用いた定量化が可能な減衰測定法が一例となる。これらが2022年度の診療報酬改定において保険収載されたことも,本邦においてNAFLDが重要な臨床課題となっていることの裏付けであると言える。
NAFLDの予後や肝関連合併症発生の予測について,従来は肝生検によって病理組織のバルーニングや炎症所見を検討し,非アルコール性脂肪性肝炎(Nonalcoholic Steatohepatitis:NASH)の有無を診断することが重要とされてきた。しかし近年の研究においては,NASHの有無よりも肝線維化ステージが予後と最も相関することが明らかとなっている4)。すなわち高度線維化・肝硬変症例がNAFLDにおける肝癌・肝不全進展のハイリスク症例であり,肝線維化の程度(高度線維化や肝硬変の有無)を適切に診断することが求められる。
ただし,NAFLDは日本人の中で数千万人が罹患していると考えられる。そこで,NAFLDのハイリスク症例の同定には大規模な集団から効率よく囲い込むことが必要であり,そのためには特にかかりつけ医によるスクリーニングが極めて重要と言える。
ハイリスクNAFLDスクリーニングの実際
2020年に刊行された日本消化器病学会・日本肝臓学会による『NAFLD/NASH診療ガイドライン』5)にて,肝線維化進展例の絞り込みフローチャートが新たに推奨されている。かかりつけ医において,健康診断や人間ドックで脂肪肝を指摘された場合,また糖尿病や脂質異常症,肥満など代謝性の危険因子を有し,肝機能異常や腹部超音波で脂肪肝などの異常を指摘された場合は,肝線維化のスクリーニングが必要となる。
かかりつけ医でのスクリーニングは,大規模な集団からのハイリスク症例の絞り込みが求められるため,簡便に幅広い患者に適応可能な血清線維化マーカーが,一次スクリーニング法として推奨されている(表)。その他,日常臨床で簡便に利用可能なマーカー...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

玉城 信治(たまき・のぶはる)氏 武蔵野赤十字病院消化器科 副部長/肝疾患相談センター 副センター長
2006年日医大卒,20年山梨大大学院総合研究部医学域修了。博士(医学)。初期臨床研修修了後,08年から武蔵野赤十字病院に勤務。20~22年1月まで米カリフォルニア大サンディエゴ校に留学。留学中は,主にNAFLDの診断と治療に対する臨床研究に従事し,帰国後も継続する。22年7月より現職。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。