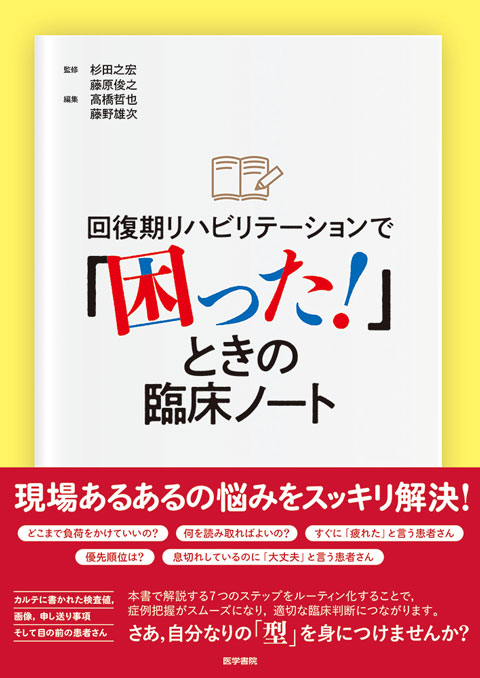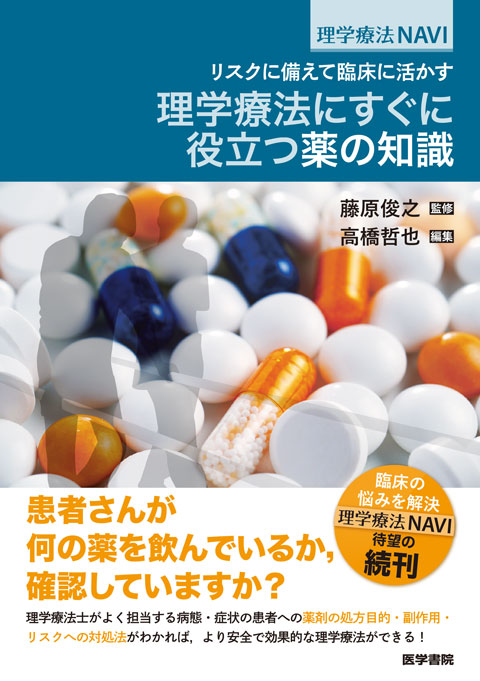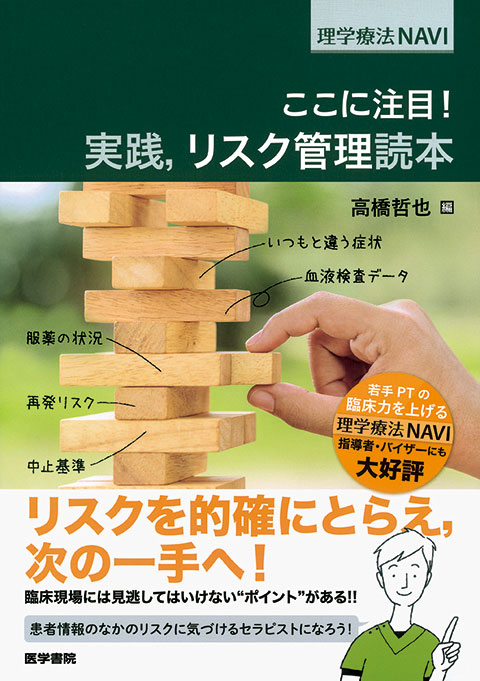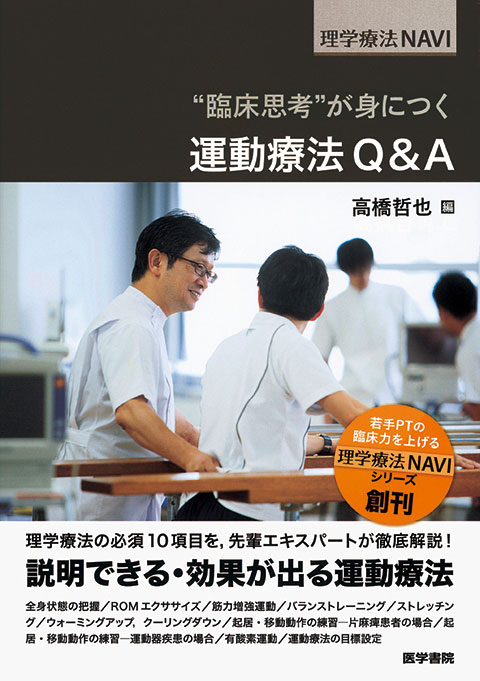患者の全体像を把握し,最適なリハビリテーションを届ける
インタビュー 高橋 哲也
2022.06.20 週刊医学界新聞(通常号):第3474号より
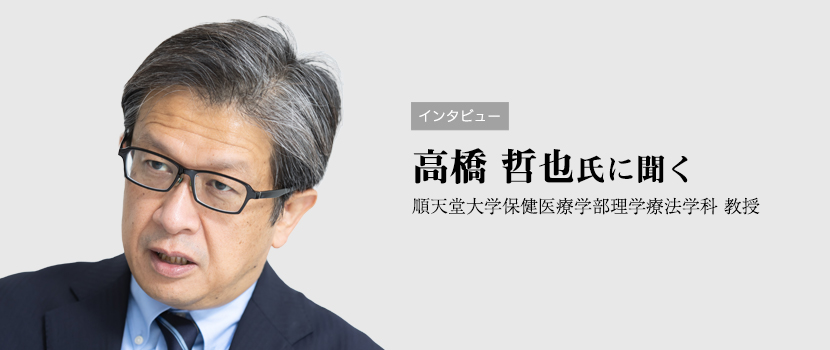
2022年度診療報酬改定では,回復期リハビリテーション病棟入院料に関して,重症患者割合の引き上げ,心大血管疾患リハビリテーションの対象追加を含む見直しが行われた。重症患者,心疾患患者への対応増加が見込まれる中,リハビリテーション職種の患者対応能力の向上は差し迫った課題となっている。
課題の解決策として,上梓された『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』(医学書院)では,一定の「型」を用いた症例の全体像の把握を推奨している。その重要性について,同書の編者を務めた高橋氏に話を聞いた。
――2022年度の診療報酬改定では,回復期リハビリテーション病棟入院料に関して見直しが行われました。その内容についてどうお考えですか。
高橋 今回の見直し内容は,突然出てきたわけではありません。2014年度の診療報酬改定の際,病床の形をどのように変えていくのかというグランドデザインが示され,入院早期からリハビリテーションを推進する方向性が明記されました。これは急性期病棟の入院期間短縮を意味していましたし,発症から回復期リハビリテーション病棟入院までの期間のさらなる短縮を示唆していました(後者は2020年に「発症からの期間を問わない」と緩和)。
続く2016年度の診療報酬改定では,より質の高い医療を提供する目的で,“リハビリテーションの効果”を測定する実績指数の指標であるFIM(Functional Independence Measure)が導入されました。アウトカムが厳格に評価される流れは,今後も続いていくと思われます。
――結果の評価という意味では,特に重症患者割合の引き上げは,臨床への影響も大きいのではないでしょうか。
高橋 そう思います。急性期病棟の入院期間が短縮されたため,回復期リハビリテーション病棟に入院してきたタイミングでも発症早期で病態が不安定なことに加えて,重症とみなされる状態では運動機能や認知機能がかなり低く,そうした患者さんを安全に管理するのは簡単ではありません。これまで重症度の高い患者さんを担当した経験が少ないセラピストは,運動負荷をかけることに及び腰になりがちです。重症患者への対応能力の向上やマンパワーの強化は,課題として目前に迫っています。
回復期リハビリテーション病棟で心疾患をみるということ
――今回の改定では「回復期リハビリテーションを要する状態」に「急性心筋梗塞,狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」が追加されたことも,大きなポイントだと思います。この変更には,どのような背景があるのでしょうか。
高橋 どの疾患群でもそうですが,高齢化に伴い,運動療法をする以前に,立てない,歩けない患者さんが増えています。また,心疾患治療の急性期は安静が重要であるものの,高齢患者ではわずか数日間安静にしているだけで立てない状況に陥り,自宅に帰れないケースがあまりにも増えました。「心疾患のリハビリテーション」というと,運動負荷試験を行い,その結果に応じた強度の自転車エルゴメータやトレッドミルなどの運動療法によって機能を回復するという流れをイメージすると思います。しかし,実際にそうした運動療法を実践できる高齢患者さんは少ないと言えます。そのため,上記に示した一般的な運動療法以外にも,運動機能が低下した患者さんに適したリハビリテーションをしていく必要が...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

高橋 哲也(たかはし・てつや)氏 順天堂大学保健医療学部理学療法学科 教授
1989年国立仙台病院附属リハビリテーション学院理学療法学科卒。01年豪カーティン大大学院理学療法研究科修士課程,04年広島大大学院医学系研究科博士課程修了。07年兵庫医療大教授,12年東京工科大教授を経て,18年より現職。日本理学療法士協会理事。編書に『理学療法NAVI』シリーズ,『回復期リハビリテーションで「困った!」ときの臨床ノート』(いずれも医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。