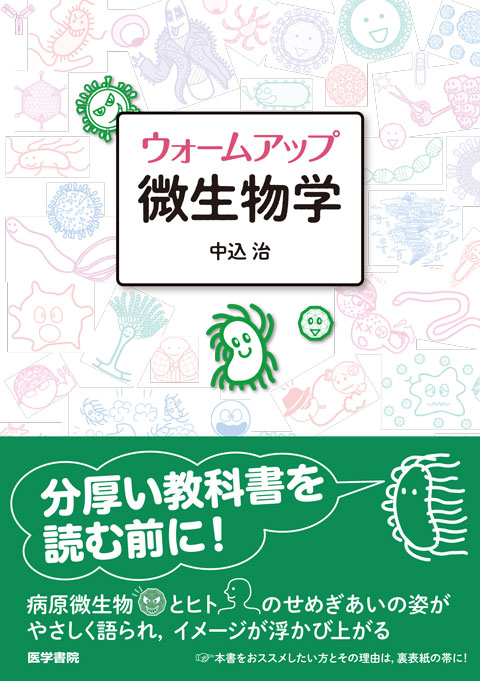野口英世と黄熱の歴史から100年を経た教訓
寄稿 中込 治
2022.04.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3465号より
レジデントになると,経験した症例を通して知識を蓄積していきます。症例を報告するときにないがしろにできないのが,症状や身体所見がどうであったのかわかるように記述することです。この点で気になる例を挙げると,「インフルエンザ様の症状で発症し……」という表現が,いつの間にか多く使われるようになったことです。おそらく,突然の発熱,悪寒,全身倦怠感,頭痛,筋肉痛,食思不振といった症状を指しているのでしょう。微生物学的にみるとこれらの症状は,病原体の侵入に対して宿主が炎症性サイトカインを放出したことに起因するものです。インフルエンザ様の症状といっても,咳などの呼吸器症状の有無はわかりませんので,病歴を書いたり読んだりするときには注意が必要です。
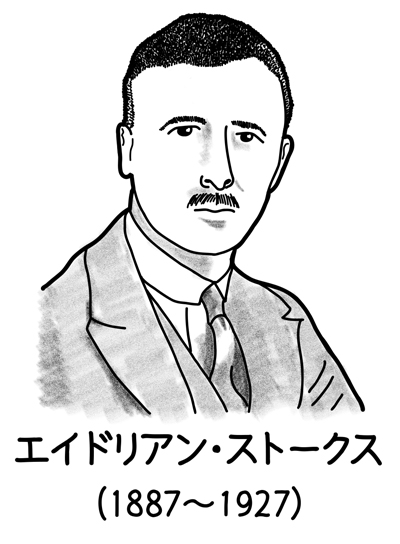
ワクチンのもとになった西アフリカの黄熱症例
“インフルエンザ様の症状”で始まる病気の一つに黄熱があります。黄熱ウイルスは,西アフリカで研究していた英国人のストークス(1887-1927)たちが分離に成功した,初めてのヒトのウイルス病の病原体です。ストークス自身はこの研究中に黄熱にかかり殉職していますので,論文の発刊は彼の死後になりました。ストークスの論文1)をみると,2例の黄熱患者で分離が試みられ,1例だけが成功しています。黄熱ウイルスが分離された症例を見てみましょう。
患者はアシビという28歳のアフリカ人男性で,ストークスの同僚の医師が黄熱と診断しました。アシビは突然の悪寒で発症し,発熱と激しい頭痛に見舞われましたが,嘔気や嘔吐はありませんでした。黄疸はなく,尿蛋白は陰性でした。翌日には体温が下がり始め,発症から6日で仕事に復帰したと書かれています。“インフルエンザ様の症状”で発症したようですが,この論文からは,黄熱の特徴である黄疸,黒い吐血,蛋白尿が一つもありませんので,アシビが黄熱だったと確診できる臨床症状は何もないようにみえます。しかし,アシビは歴史上もっとも重要な黄熱患者だったのです。なぜなら,アシビから分離された黄熱ウイルスそのものが弱毒化され,黄熱ワクチンとして今も世界中で使われているからです。今日の目で見ると,アシビは黄熱症例の大部分を占める非黄疸型の軽症例だったのです。
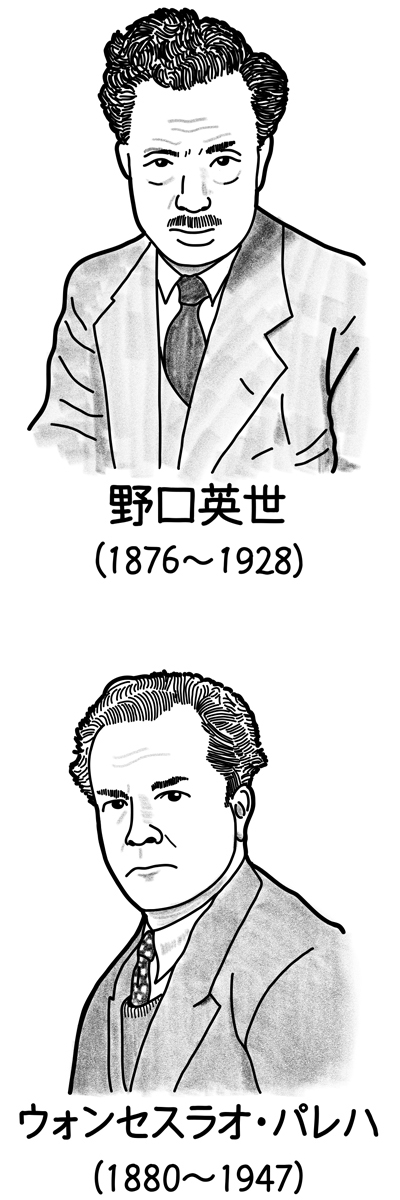
野口英世と黄熱
黄熱と聞くと,西アフリカ(現・ガーナ)にわたり黄熱の病因を探究中に感染して殉職した野口英世(1876-1928)のことを思い浮かべる日本人が多いでしょう。野口と黄熱との関係の始まりは,ストークスたちによる黄熱ウイルス発見の10年前である1918年にさかのぼります。
この年に南米のエクアドルで黄熱が流行し,その調査に行った野口は,彼がレプトスピラと命名したスピロヘータに似た新しい病原体の一つが黄熱の原因であると発表しました2)。黄熱と診断した患者の血液を野口に提供したのは,エクアドルのグアヤキル大学のパレハ教授(1880-1947)でした。黄熱の病原体の分離・同定に成功した野口は,黄熱レプトスピラに対する抗血清やワクチンをつくり,それらはエクアドルでの黄熱患者に一定の効果を示しました。
このように野口は,黄熱の病因はもう10年も前に解決済みと思っていたので,「黄熱の病原体が西アフリカで新たに分離されたけれども,それはレプトスピラではなかった」と聞いたとき,信じられませんでした。そこで,自分自身が西アフリカに行って決着をつけることにしたのでした。
エクアドルでの黄熱症例と野口の誤りの原因
黄熱の病因がレプトスピラであることに野口自身は自信満々だったのですが,しばらくすると野口のレプトスピラとワイル病の原因となるレプトスピラが同じではないかと言う研究者が現れました。ワイル病とは,黄疸,出血傾向,腎障害が起こる重症型レプトスピラ症のことです。野口は野生のネズミからワイル病レプトスピラを発見するなど,この分野での第一人者でしたので,激しい論争になりました。しかし,野口の死後に,黄熱レプトスピラとワイル病レプトスピラは同一菌種であると確定されました。そこで現在は,野口がレプトスピラを分離した患者は黄熱ではなくワイル病だったとされ,そのために,黄熱の病原体を誤って同定したという評価を受けています。
黄熱ではなくワイル病の患者の検体を使って研究したことが野口の犯した過ちの原因だとすれば,症例を提供したパレハ教授が誤診したのでしょうか。そうではありません。野口の論文をみると,野口はパレハ教授の診た黄熱患者172例の臨床的特徴を詳しく分析し,エクアドルの黄熱症例には今まで報告されてきた黄熱の特徴と異なるものがないことを確認しています3)。
試みに,野口が最初に黄熱レプトスピラを分離したA.A.という17歳の女性の症例を見てみましょう2)。彼女は頭痛,悪寒,発熱,全身の激しい痛みで発症し,翌日には黄熱の特徴であるチョコレート色の吐物がありました。発病して5日目に入院したときにも暗黒色の吐血があり,全身の皮膚に黄疸,結...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
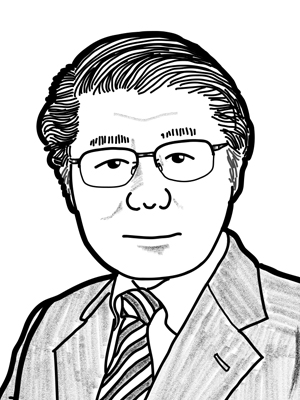
中込 治(なかごみ・おさむ)氏 秋田大学名誉教授/ 長崎大学名誉教授
1977年秋田大医学部卒。81年東北大大学院修了(医学博士)。秋田大微生物学講座教授などを経て,2003年から長崎大大学院感染免疫学講座教授。この間,同大の熱帯医学修士課程専攻長,分子標的医学研究センター長,英リバプール大大学院感染症グローバルヘルス研究科客員教授を歴任。18年に定年退職。編集および共著書として『標準微生物学』(執筆:第6~14版,編集:第9~13版,医学書院),新著に『ウォームアップ微生物学』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。