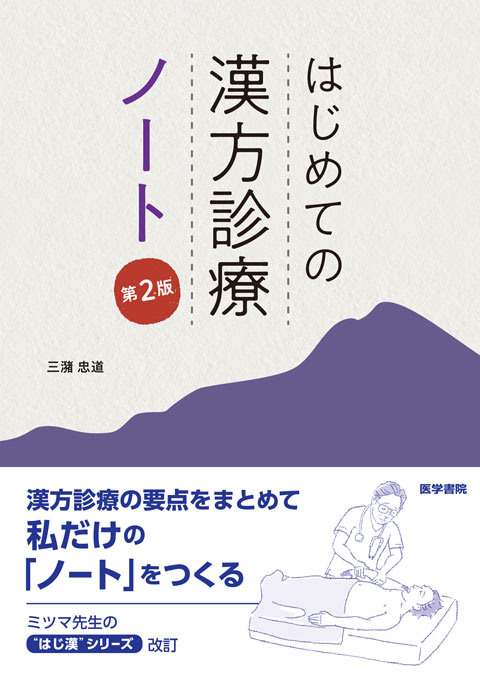漢方医学教育SYMPOSIUM開催
取材記事
2022.03.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3461号より
漢方医学教育の発展・充実をめざして2017年に設立された日本漢方医学教育振興財団による「漢方医学教育SYMPOSIUM 2022」が2月11日,Web配信形式で開催された。同財団による2018年度漢方医学教育研究助成対象となった7研究の最終報告の他,2021年度漢方医学教育奨励賞・功労賞受賞者の講演,総合討論などが行われた。
わが国の漢方医学教育のさらなる充実化のために必要な取り組みは
奨励賞を受賞した近畿大東洋医学研究所の武田卓氏は,更年期障害や月経関連疾患に漢方薬が多く処方されている現状を紹介し,女性のヘルスケアにおける漢方の重要性を強調した。氏も作成委員を務めた日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会監修による「産婦人科診療ガイドライン――婦人科外来編2011」では,漢方の内容を多く盛り込み,若手医師の漢方診療教育に寄与したという。今後の展望として,「漢方医学教育を研修医に実施し,全診療科の医師が女性ヘルスケア疾患の初期対応をよりスムーズに担えることをめざしたい」との見解を示した。
続いて「漢方医学教育には,漢方薬を用いて患者中心の医療を提供できる臨床医の育成が重要」と主張したのは,功労賞を受賞した松田隆秀氏(聖マリアンナ医大)。漢方薬を用いた臨床医の育成には,学修者が①漢方医学の知識と技能,②医療倫理をはじめとする漢方医学の「作法」を修得する必要性があると訴えた。また大学間で漢方医学教育資源の格差が大きい現状を問題視し,解決に向けて全国82の大学医学部が参加する日...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![はじめての漢方診療 十五話[WEB動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8416/2788/8744/110303.jpg)