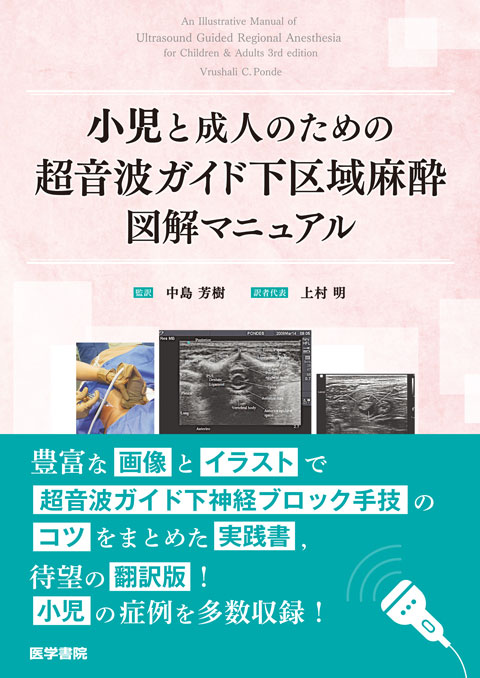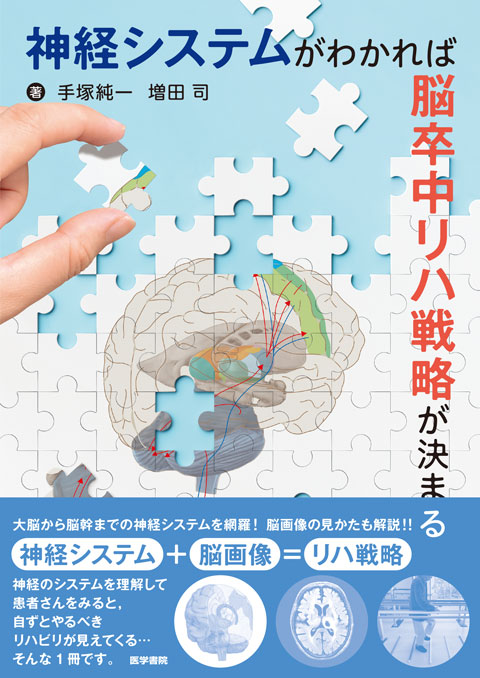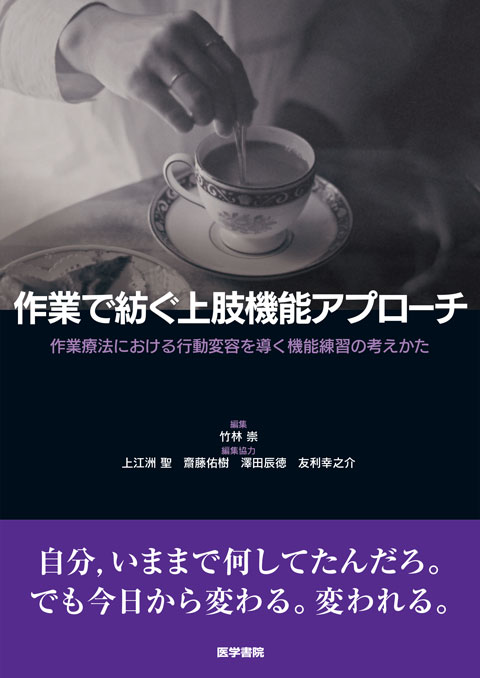MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.01.31 週刊医学界新聞(通常号):第3455号より
《評者》 鈴木 昭広 自治医大病院教授・麻酔科学・集中治療医学
小児が成人より大きく取り上げられているのが特徴だ!
『小児と成人のための超音波ガイド下区域麻酔図解マニュアル』。書籍のタイトル自体で,「小児」が「成人」より大きく書かれていることがまずユニークだ。平置きで「映える」こと請け合いである。麻酔科領域において,確かに小児の鎮痛は長いことおざなりにされてきた。そもそも暴れて泣き叫ぶ小児に,区域麻酔など危なくてできやしない。術中もおとなしくしているはずもない。手術の大小にかかわらず,何か必要があればすぐに全身麻酔。大人なら併用するはずの硬膜外麻酔もなく,戦う武器はせいぜい仙骨ブロックのみ。起きた患児は,創は痛いわ足は動かないわでパニック状態。手術をした後もやっぱり手がつけられない。「母親が1番の薬だよ」と全ては母親に丸投げ……。私自身,恥ずかしながらこういうプラクティスを繰り返し,古くからの悪習を後輩に伝える悪い先輩だったことだろう。しかし,前職の東京慈恵会医科大学で小児麻酔への考えを改めさせられた。JPOPS(Jikei Post-Operative acute Pain Service)という術後疼痛管理チームが術後痛のプロトコールを決め,小児でも胸部や腰部の硬膜外を実施し,区域麻酔の補助のあるなしにかかわらず,薬をタイトレーションして覚醒させ,抜管後にスヤスヤと過ごすわが子を母親がそばの椅子に座って見守る風景が当たり前の術場回復室(PACU:Post-Anesthesia Care Unit)。もし子どもが泣いていようものなら「なんで泣いてんだ!?」とU主任教授が怒り心頭でやってくる。それ以来,小児事例が当たると,わが子の麻酔と思って他のスタッフと同じような穏やかな目覚めを提供できないかを考えるようになった。
現在,鏡視下手術全盛期を迎え,硬膜外に代わり,超音波ガイド下区域麻酔がシェアを拡大している。私は成人で行う程度で小児に関してはまだまだ未熟者だが,そもそも小児の体は水分に富み,しかも深度が浅いので成人と比べても超音波の通りがよく,画質もはるかによいので,神経ブロックのよい適応のはずである。なるほど,本書内に盛り込まれた成人と小児の超音波図譜,カラフルな解剖解説や実施体位を見ると,「ね,あなたも小児でやってみない?」と誘われる気分になる。これまで,小児の神経ブロックを解説した書籍はほとんど皆無である。第3版になるまでインドで眠っていたこの書籍を日本に知らしめた中島芳樹先生,上村明先生のご慧眼に感服する。さらには,小児の鎮痛のことは成人よりも大きく取り上げられてしかるべきだと考えてか,原書ではChildren&Adultsという同じ文字サイズのタイトルを訳すに当たり,小児の文字サイズをあえて大きくした医学書院の英断にも敬意を表したい(次回は背表紙の文字も……)。なお,書籍の最後には近年流行りの気道・肺・胃といった麻酔科医に関連深いpoint of care ultrasoundの掲載もある。手元に置いておきたい相棒といえる一冊である。
《評者》 吉尾 雅春 千里リハビリテーション病院副院長
「戦うことを略して勝つ」リハ戦略を知ることができる
本稿執筆時点で,本書が出版されて半年が経ちました。本来ならば,出版後まもなく書評を書かせていただくべきところですが,ここまで延びてしまったことをお詫びしなければならないと思います。本書『神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる』は,著者である手塚純一先生と増田司先生のこれまでの学びが臨床にどのように反映されているかが,見事に表現されている一冊です。甚だ失礼な言い方ではありますが,「〇〇大学教授」というような重々しい肩書きのないお二人の真摯な取り組みがここに集約されており,しかもこの後の展開が期待できるような一冊になっています。これに感動を覚えない,痺れないセラピストはいないでしょう。そのためにも早く皆様に紹介しなければならなかったのですが,本書の価格とは不釣り合いなほどその内容が重厚であり,一瞬,筆が止まってしまったことを覚えています。
2014年9月に理化学研究所を研究拠点に「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」が立ち上がりました。多くの方は,脳を局所機能解剖的に学んでこられたのではないかと思います。それはそれで重要なことですが,現在では脳は局所的というよりもいろいろなネットワークを組みながら,システムとして機能していると受け止められています。その全容解明が世界的取り組みとして進められており,これまで多くのシステムが報告されてきました。
本書では,それらの中からリハビリテーション医療に即生かせそうなものを取り上げて解説しています。ただシステムを理解するだけではなく,その障害が見られたとき,どのような戦略が考えられるかを具体的に提案しています。「戦略」とは,「戦いに勝つための策略・企て」という意味を持ちます。しかし,本書では「戦うことを略して勝つ」という意味の「戦略」を優先して考えていこうとしています。セラピストが無用な戦いを挑んでいる臨床場面をよく見かけます。そうしてしまう原因は,その病態が生じた理由,すなわち脳の中で何が起こっているのかということを理解せず,また活用できそうな残された部分に気付かないまま,患者に挑んでいるからだと思います。
脳のシステム障害に関して,これほどまでに多くの知識とリハ戦略のヒントをまとめた書籍はありません。日々の臨床の傍らに携えておきたい一冊です。
《評者》 中村 春基 一般社団法人日本作業療法士協会会長
作業療法の「質と量」が見える化された良書
竹林崇氏らによる『作業で紡ぐ上肢機能アプローチ――作業療法における行動変容を導く機能練習の考えかた』が上梓された。竹林氏や本書編集協力の澤田辰徳氏とは,某紙の対談において作業療法(OT)の「質と量」について議論したが,本書はまさにそれに応える内容であり,臨床家,教育者,学生に多くの示唆を与えてくれると確信している。また,OTの歴史的課題について,「機能に焦点を当てた練習」と「作業に焦点を当てた練習」の二つの信念対立の構造から,利用者中心のEBPに基づく複合的なアプローチを紹介している。
以下に各章の内容を紹介するが,あらためて,学ぶことの楽しさやその必要性を強く再認識させてくれる良書である。
「1.作業療法におけるエビデンスと上肢機能に対するEBP」では,基本的なevidence-based practice(EBP)について解説し,また上肢機能アプローチを網羅的に整理している。加えて,対象者中心のコミュニケーション,shared decision making(SDM)model,予後予測などについて論述している。「エビデンスの圧政」についての記述はまさしくその通りと思う...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。