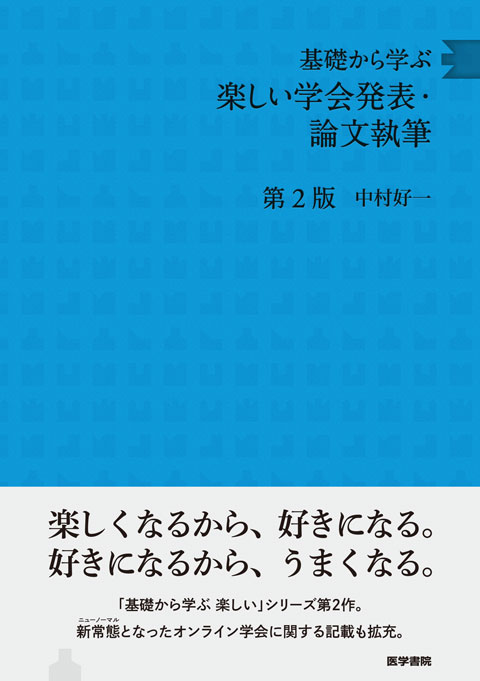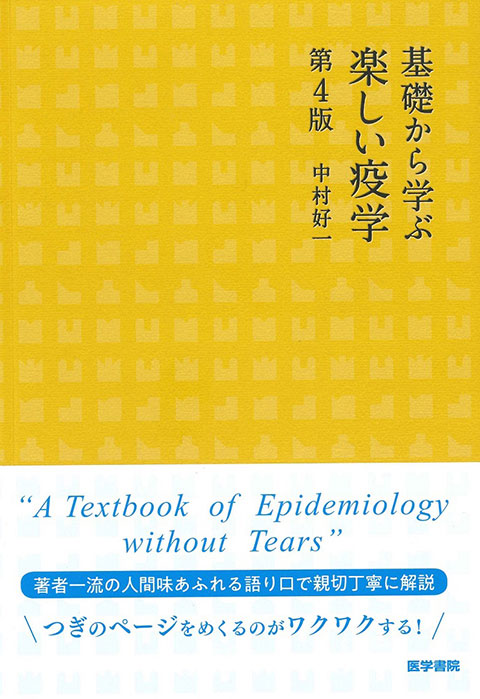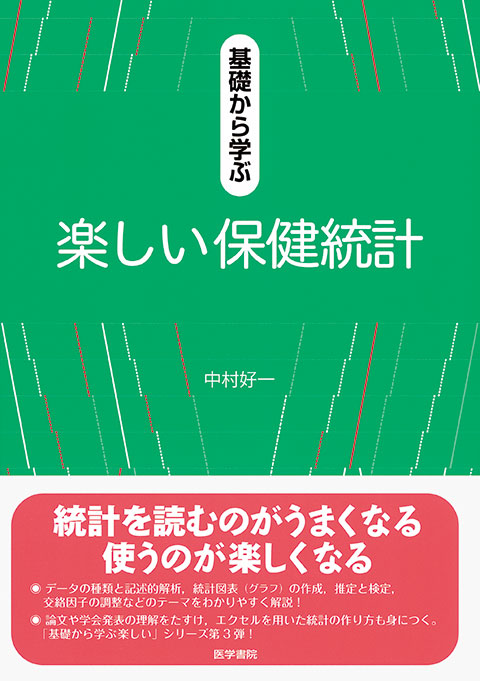川崎病疫学のこれまでとこれから
寄稿 中村 好一
2022.01.17 週刊医学界新聞(通常号):第3453号より
2020年6月に川崎富作先生が亡くなった。川崎先生が,当時概念が確立していなかった50例の川崎病症例をまとめて論文(註1)として報告1)したのが1967年。それから半世紀以上が経過した。川崎病は「Kawasaki Disease」として海外でも知られる疾患であり,これまでにわが国では40万人以上の患者2)が発生している(註2)。しかしいまだに原因は解明されていない。
病態と治療方法
川崎病は主として4歳以下の乳幼児が罹患する発熱性の疾患であり,本態は全身の血管炎である。特に中型血管(その中でも冠動脈)の中膜や内弾性板が障害され,一部の患者では動脈の拡大や瘤が発生する。急性期の治療方法は免疫グロブリン大量静注(IVIG)療法(2 g/kg/日の単回投与)である。この治療法の普及により,冠動脈瘤を中心とする後遺症を残す患者の割合は,1997~98年頃の20.1%から著明に減少し,最新の調査では2.5%になった2)。一方で20.4%の患者がIVIG不応であるとも報告2)されており,その場合はステロイド治療などの追加療法を検討しなければならない。原因が不明であるために確定診断はなく,日本川崎病学会らによる「川崎病診断の手引き(改訂第6版)」にしたがって診断する。また急性期の治療に対しては,日本小児循環器学会による「日本小児循環器学会川崎病急性期治療のガイドライン(2020年改訂版)」(以下,ガイドライン)がある。
川崎先生は当初この疾患を「予後良好の疾患」としていたが,1970年の第1回川崎病全国調査で10例の突然死が報告され3),心障害・後遺症の存在が明らかになった。以降,急性期の川崎病患者を診療する小児科医の最大の目標は「後遺症を残さない」であり,ガイドラインでは「第7病日までにIVIGを投与することが望ましい」とされている。後遺症が残った患者の予後には,明らかでない点が多い。少なくとも後遺症を持つ者の一定期間中の死亡率は一般人と比較して高いと追跡調査で明らかにされており4),循環器専門医による管理が必要である。また後遺症が残らなかった既往者の予後も同様に不明点があるが,川崎病既往者は後遺症を持たなくても一般の人と同様に適正体重の維持,血圧や血清脂質の管理,防煙/禁煙など循環器疾患の一次予防が欠かせないのは言うまでもない。
全国調査を通じて見えてきた疫学像は
川崎病全国調査は,1970年の第1回から,おおむね2年に1回の頻度で実施されている(註3)。小児科を標榜する100床以上の病院および100床未満の小児専門病院に郵送または電子メールで調査票を送付し,回答を得ている。 2021年には2019~20年の2年間の患者を対象とした第26回全国調査を実施し,先日結果がまとまった(1345/1745機関=回収率77.1%)2)。
これまでの調査から見えた川崎病の患者数や罹患率の推移について図に示す。1979年・82年・86年と過去3回,3~4年スパンでの全国的な流行があったものの,その後全国的な流行は起こらなかった。しかし1990年代半ばから患者数が増え続けている。また罹患率計算の分母となる小児人口(註4
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

中村 好一(なかむら・よしかず)氏 自治医科大学公衆衛生学部門 教授
1982年自治医大卒。同年より福岡県職員として県庁・保健所に勤務,89年同大公衆衛生学教室教員,99年より現職。92年米テキサス大公衆衛生学部,98年慶大法学部卒。第16回川崎病全国調査より研究責任者を務める。著書に『基礎から学ぶ 楽しい保健統計』『基礎から学ぶ 楽しい疫学(第4版)』『基礎から学ぶ 楽しい学会発表・論文執筆(第2版)』(いずれも医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。