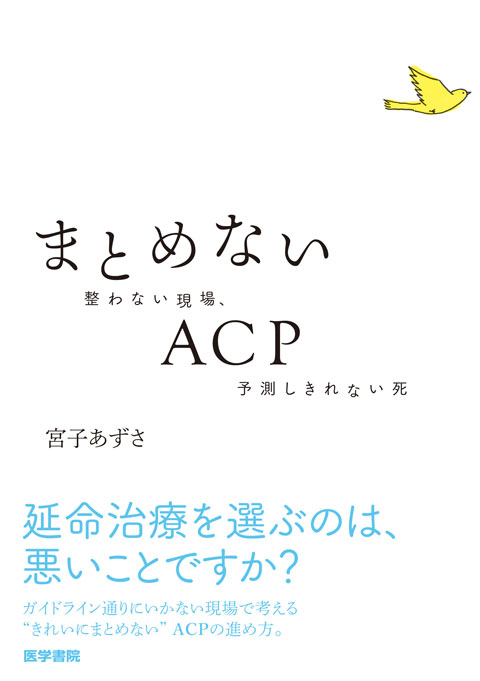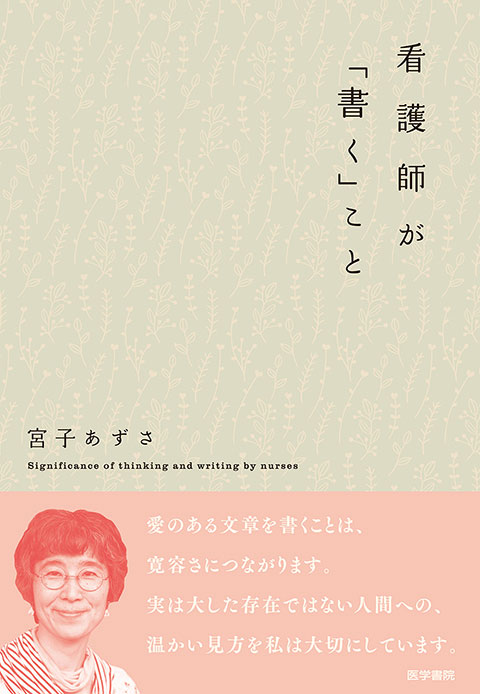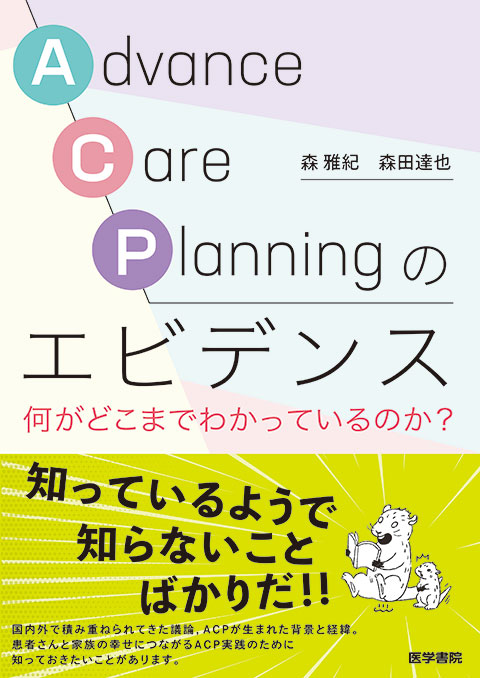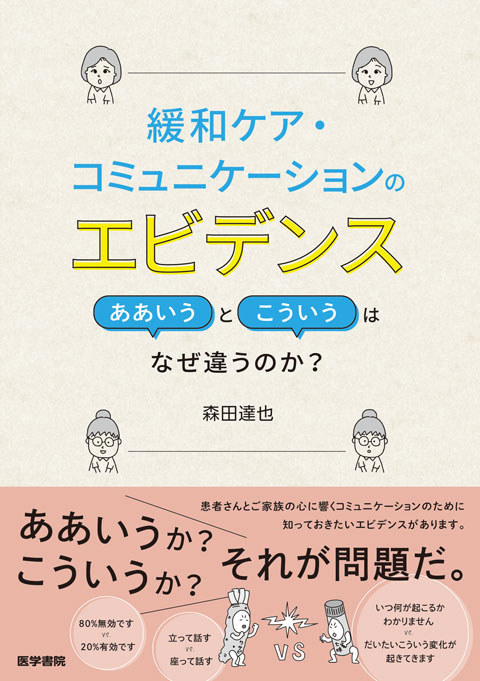きれいにまとめないACPの進め方
「整わない現場」で何を考えるのか
インタビュー 宮子 あずさ
2021.11.22 週刊医学界新聞(看護号):第3446号より
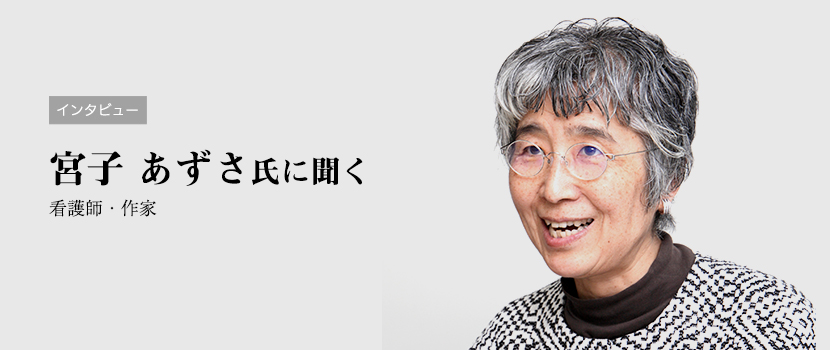
「ACPを取り入れ事前にさまざまな準備をしていても,いざ死を目の前にして予想できない反応を見せたり,本人の思い通りにならなかったりする,『整わない現場』をたくさん見てきました」。こう語ったのは,書籍『まとめないACP――整わない現場,予測しきれない死』(医学書院)を上梓した,看護師で作家の宮子あずさ氏だ。国を挙げてACP(Advance Care Planning)が推進される中で,氏が抱いた違和感とは何か。書籍刊行に当たっての想いを聞いた。
生きることを諦めさせる手段としてACPを用いていないか?
――書籍『まとめないACP――整わない現場,予測しきれない死』(以下,本書)が出版されました。これまで数十年にわたって看護師として勤務する中で,多くの患者の看取りの現場に立ち会ってきた経験があるからこそのテーマだと思います。まずは執筆に至った経緯を教えていただけますか。
宮子 近年ACPが推進される中で,積極的治療を求めないことばかりが推進される感じがあると,かねて考えていました。直接のきっかけは,2019年に厚労省が配布した「人生会議」に関するPRポスターの騒動です。不謹慎な表現かもしれませんが,私にはあのポスターのめざす先が,生きることを諦めさせる“シネシネ会議”に見えてしまったのです。
――とてもセンセーショナルな言葉ですね。
宮子 こう表現してしまうほどに,患者・利用者の自己決定を迫る手段として用いられるケースが増加し,積極的治療を求めず亡くなることが是とされてしまうのではないかとの不安がありました。また最近世間では,事前に決めておかないと余計な医療を施されてしまうのではとの漠然とした恐怖から,「より良く死なねば」という気持ちが強まっているようにも感じます。こうした風潮が,これまで何百人と看取ってきた私の経験からくる現場の印象と何か合いませんでした。
――違和感を覚えたと。
宮子 ええ。ACPを取り入れ事前にさまざまな準備をしていても,いざ死を目の前にして予想できない反応を見せたり,本人の思い通りにならなかったりする,「整わない現場」をたくさん見てきました。だからこそ,ポスターが意図した「早くから意思決定をしておくべき」というメッセージは,「整わない現場」を無理に整えようとする,聞きようによっては暴力的なメッセージなのではと感じてしまったのです。
――いま実践されているACPが,意図しない方向に進んでしまうことを危惧されたのですね。
宮子 その通りです。ですから私がこれまでに経験し学んできたさまざまな事例をまとめることで,人が病み,亡くなる経過を追体験していただき,ACPの実践に生かしてほしいと考えました。ACPに取り組まなければならないけれども,実際にどうすればいいのかわからないと戸惑う医療職の方々にぜひ読んでもらいたいですし,看取りの経験が少ない方にこそ参考にしていただきたいと考えています。
――なぜ看取りの経験が少ない方を読者対象として強調されるのでしょう。
宮子 医療者には人の生き死にを左右する力があるからです。人の死にかかわる機会がなかった人にいきなりACPを,と言っても無理な話でしょう。まずは人がどう亡くなっていくのかをイメージできるようになってほしい。その一助になればと思い,執筆しました。ACPの議論は抜きにしても,死というもののイメージを持つためには役立つはずです。
ガイドラインを改めて読み解く
――本書の執筆に当たってACPを改めて学び直すために,「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

宮子 あずさ(みやこ・あずさ)氏 看護師・作家
1987年東京厚生年金看護専門学校卒。東京厚生年金病院(現JCHO東京新宿メディカルセンター)に22年間勤務し,内科・精神科・緩和ケア病棟などを経験。2009年から精神科病院で訪問看護に従事する傍ら,文筆活動や講演,大学・大学院での学習支援を行っている。13年東京女子医大大学院看護学研究科博士後期課程修了。博士(看護学)。『まとめないACP』『看護師が「書く」こと』(いずれも医学書院)など著書多数。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。