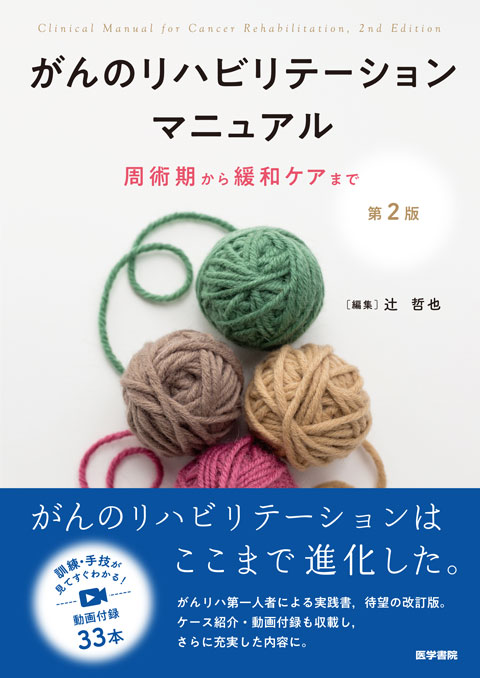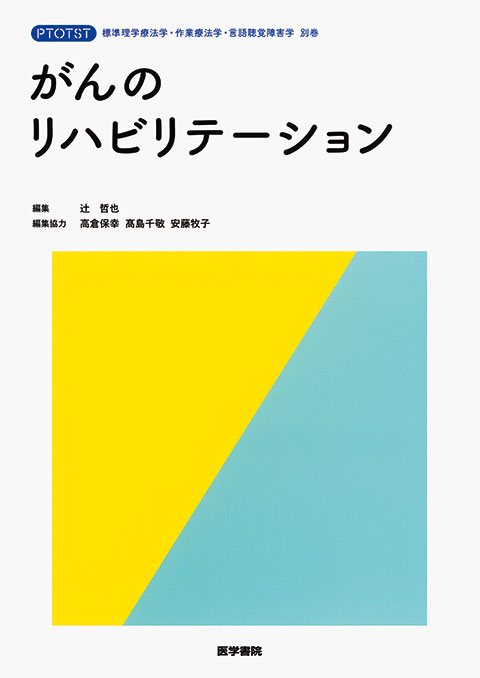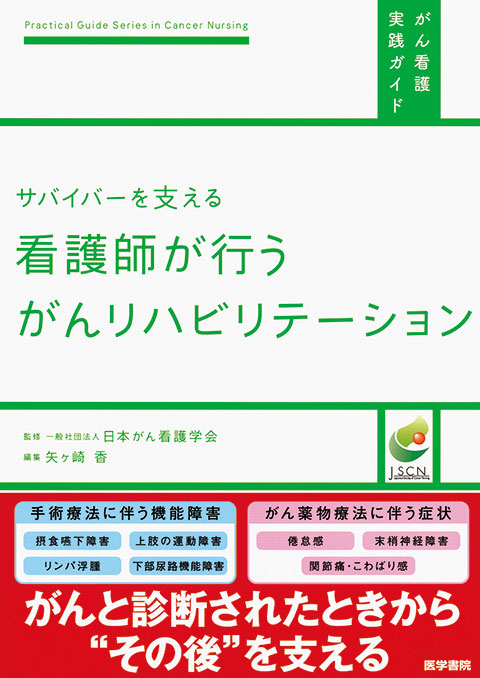がんリハが挑む新たなステージ
対談・座談会 辻 哲也,渡邊 清高,上野 順也
2021.09.20 週刊医学界新聞(通常号):第3437号より

「リハ関連の学協会や大学でのがんリハに関する一層の取り組みを期待したい」。日本におけるがんのリハビリテーション(以下,がんリハ)分野の第一人者として,10年前に本紙インタビュー(第2933号)でこう展望を語った辻哲也氏。実際,2010年度診療報酬改定において「がん患者リハビリテーション料」(以下,がんリハ料)が保険収載されたことが転機となり,大規模研究を基にしたエビデンスの創出,関連学会によるガイドラインの整備など,がんリハの普及・啓発活動が進み,次なるステージへと足を踏み出そうとしている。
本座談会では腫瘍内科医の渡邊清高氏,理学療法士の上野順也氏を迎え,これまでの10年でがんリハ分野に起きた変化を振り返りつつ,これからのがんリハに寄せる期待を語った。
辻 がん医療の世界は,直近10年だけを見ても状況が大きく変化しています。免疫チェックポイント阻害薬の登場をはじめ,医療技術の発達によって早期診断・早期治療がより一層実践されるようになりました。がん種によっては5年生存率が9割を超える場合もあるなど,「がんとの共生」を意識する時代となっています。
渡邊 全がんを対象としたがん年齢調整死亡率の年次推移を見ると,1980年代から徐々に低下しはじめ,その傾向は現在も続いています1)。つまり,がんを患いながらも長く存命される方が増加しているのです。その影響を受け,がん罹患者の3分の2が65歳以上1)という「がん患者の高齢化」が,がん医療の中では一大トピックとなっています。
辻 高齢がん患者にはどのような特徴があるのでしょう。
渡邊 認知症,高血圧,糖尿病など何らかの疾患を併存した方や,加齢によるフレイル,サルコペニア状態の方が多いことです。がんとの共生を考えられる状況になってきたからこそ,がん治療に専念するだけでなく,その後の生活を見据えたゴール設定が求められています。実際,全国のがん診療連携拠点病院を対象に行った患者体験調査2)では,多くの患者さんが「納得いく治療選択ができた」「治療前に病気や療養生活について相談できた」と,治療に関して概ね十分な対応をしてもらえたと回答した一方,体や心のつらさに関して「相談できた」と回答した方は半数以下でした。すなわち,身体的・精神的・社会的サポートについては,まだまだ改善の余地があるということです。
身体活動とがんの関係性
辻 いま指摘いただいた点は,がん患者さんの機能や生活能力の維持・改善を図るために,まさしくがんリハが介入すべきポイントと言え,最近では,特に運動療法の効果に関するRCTやメタアナリシスが発表されるなど,エビデンスの集積が進んでいます。
理学療法士としてがんリハを実践する上野先生から,運動とがんの関係性が明らかになったエビデンスを紹介いただけますか。
上野 がんの発症リスク低減のために身体活動が効果的との報告は以前からなされています3)。また,がん患者さんに限った話でも,日常においてどの程度の身体活動に取り組むべきかに関するガイドラインも発表されるようになりました4)。さらに昨今,筋肉量が多いほうが免疫チェックポイント阻害薬の効果は高まるとの論文も発表されています5)。
身体機能と生命予後の関連についても,高いレベルで身体機能を維持できた方のほうが全生存期間(OS)が延長されるとの報告も出てきました6, 7)。がんリハの存在が直接的な因子か,間接的な因子かは議論の余地があるものの,一つの可能性として,身体活動によって全身状態(PS)が向上し,抗がん薬の投与期間を延長できたことでOSが延長したとも考えられるでしょう。
渡邊 がん治療後,いわゆるがんサバイバーの方にとっても運動は推奨されていますよね。
上野 不活動の時期を避け,できる限り早期から通常の身体活動に復帰することが求められています。こうした結果から,「どの病期のがん患者さんであっても運動が必要だろう」との実感を持っていただけるのではないでしょうか。
辻 しかし漠然と「運動をしてください」と伝えても,どのように取り組めばよいかがわからず,運動習慣が続かない方も多いはずです。
上野 その通りです。患者さんはさまざまな理由をつけて運動をしなくなってしまいます8)。この点は海外でもよく指摘されており,米国がん協会によるガイドラインでは,がんサバイバーの健康維持のために必要な運動量の目安として「少なくとも週150分以上の中等度,または週75分以上の高強度の有酸素運動を行うとともに,週2回以上の筋力増強訓練を行うこと」を示しています9)。けれども日本では高齢世帯の増加に加え,孤立化も進行しているために,上記のような強度の身体活動に取り組むことはなかなかハードルが高く,専門知識を有した医療者のかかわりが求められています。
がんリハのさらなる認知度向上に向けて
辻 そうした専門家を育成するため,2007年よりがんのリハビリテーション研修(CAREER研修)を実施してきました。本研修の受講は,2010年に保険収載されたがんリハ料の算定要件である上,医師,看護師,療法士のチームによる参加が義務付けられているために,医療者内でのがんリハの認知度向上にも一役買っています。これまで延べ4万人余りが受講し,がん診療連携拠点病院に対して行われたアンケート調査では,入院中のがんリハの実施率は97.4%となりました10)。
上野 実施率が高い背景には,2020年にがんリハ料の算定要件が緩和されたこともあると考えています。
辻 そうですね。入院中という縛りはあるものの,保険収載当初に限定されていたがん種の制限がなくなりました。また終末期のがん患者さんにも算定できるようになったことは大きな前進です。以前は少なかったがん診療科からリハビリテーション科へのがん患者さんの紹介数も増えているようですね。
上野 おかげさまで,当院はわれわれ療法士が困るほどに患者さんを紹介いただけるようになりました。その一方で,講師としてCAREER研修に参加した際,数は少ないながらも受講する医師から「がんリハって本当に必要なの?」と質問されることが依然としてあり,気掛かりです。
渡邊 恐らく多くの医師にとってリハに初めて接するタイミングは,長期臥床に起因する拘縮の予防や,肺の術後合併症の予防を目的としたリハの時だと思います。これらは後遺症予防や術後の成績向上など,改善後の姿がある程度イメージできます。対してがんリハを受ける患者さんは,PSは保持されていて普段の生活も大きな問題なく過ごせている方が多く...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

辻 哲也(つじ・てつや)氏 慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 教授
1990年慶大医学部卒。2002年静岡県立静岡がんセンターリハビリテーション科部長時代にがんリハと出合い,現場のニーズを実感。05年慶大リハビリテーション医学教室へと戻り,がんリハ全般のエビデンス構築に励む。20年より現職。『がんのリハビリテーションマニュアル 第2版』『がんのリハビリテーション』(いずれも医学書院)など編著書多数。

渡邊 清高(わたなべ・きよたか)氏 帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 病院教授
1996年東大医学部卒。初期研修終了後,同大病院消化器内科。2008年より国立がん研究センターがん対策情報センター室長。科学的根拠に基づくがん情報を発信。14年帝京大医学部,20年より現職。腫瘍内科医として臨床・教育・研究に取り組む。

上野 順也(うえの・じゅんや)氏 国立がん研究センター東病院 リハビリテーション室 室長
2002年理学療法士免許取得。総合病院で臨床経験を積み,05年関西電力病院にてがんリハ部門の立ち上げを行う。12年国立がん研究センター東病院リハビリテーション科の立ち上げに従事し,18年より現職。呼吸療法認定士。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。