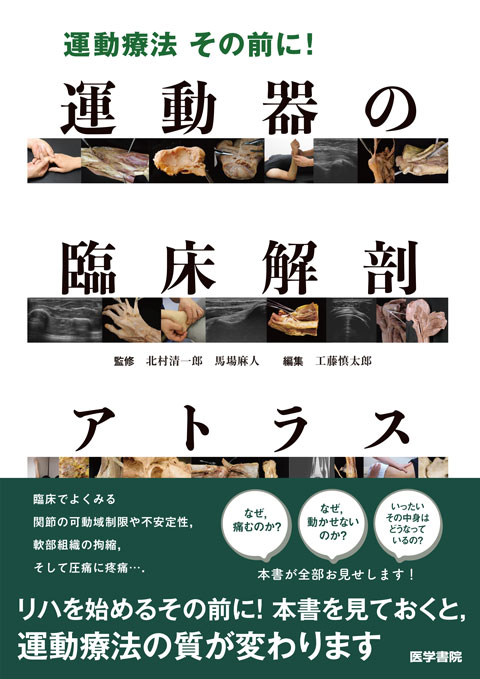MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.08.23 週刊医学界新聞(通常号):第3433号より
《評者》 秋田 恵一 東京医歯大大学院教授・臨床解剖学
読者の観察力が,価値を高める一冊
「解剖学は本当に重要ですよね」。
多くの外科医や理学療法士をはじめとするセラピストに,こう言っていただくことが多い。
このことは,本当に喜ばしいことだと思う。やはり,しっかりとした解剖学的基盤の上に,診断法や治療法が構築されることが重要であるし,そのための解剖学であることは言うまでもない。
その一方で,解剖学(この場合は肉眼解剖学に限定)においては,他の学問分野ではありえないようなことが起きているということも理解しておかなくてはならない。もし機会があれば1800年代から1900年代初頭に出版された欧米の解剖学書の「絵」と,現代の教科書の「絵」を比較していただきたい。現代の解剖学の教科書のほうが,臨床的な重要性をさまざまな角度から示唆する「絵」が描かれていることがわかる。しかし同時に,実に多くの省略もなされているのである。解剖学的記述にしても同様である。重要なところを強調し,学習の効率化を図るための省略は,臨床的関連事項を強調するためにも合理的なことであり,重要なことではある。一方で,「絵」から見えているはずのさまざまな細かな線が消えてしまい,詳細な観察的記述も割愛されることにもなっており,それが常識であり,真実として受け入れられているところもあるのである。生理学的・運動学的な臨床研究が日々進化する中で,合理的につくられた教科書的知識が基盤となっているのであれば,ともすると学問的な障害にもなり得るのではないだろうか。
「人体の構造は単純ではなく,複雑なのである」という当たり前のことを理解するために,解剖学実習はある。本物に触れ,観察を通して,機能的理解を深め,さらなる応用を考えるための礎をつくることができる。ただ,多くのセラピストにとって,そのような機会を得ることは難しい。特に,本当に知りたい,理解したいと切望したとき,つまり臨床の場で悩みが生じたときに,すぐにアクセスすることはできない。
本書には,臨床で必要となるとき,いつでも本物に触れることができる多くの写真が収められている。課題となり得ることがすでに目次に示されており,課題に従ってさまざまな写真が示されている。一つひとつの写真をくまなく見ていただきたい。近年の解剖学書では省略されている,さまざまな筋束や構造を見いだすことができるはずである。本文の説明の行間を,写真の中に見いだしていくこと,それが,本書の醍醐味であると考える。
本書を手に取ることによって読者の想像力が喚起され,深い洞察を呼び覚まし,実診療をさらに高めていくことにつながると期待される。本書の構成および解剖写真は,その目的に十分にかなったものであると感じる。読者の観察力が,本書の価値をさらに素晴らしいものとするはずである。その意味で,読み手も試されていると言える一冊である。
-
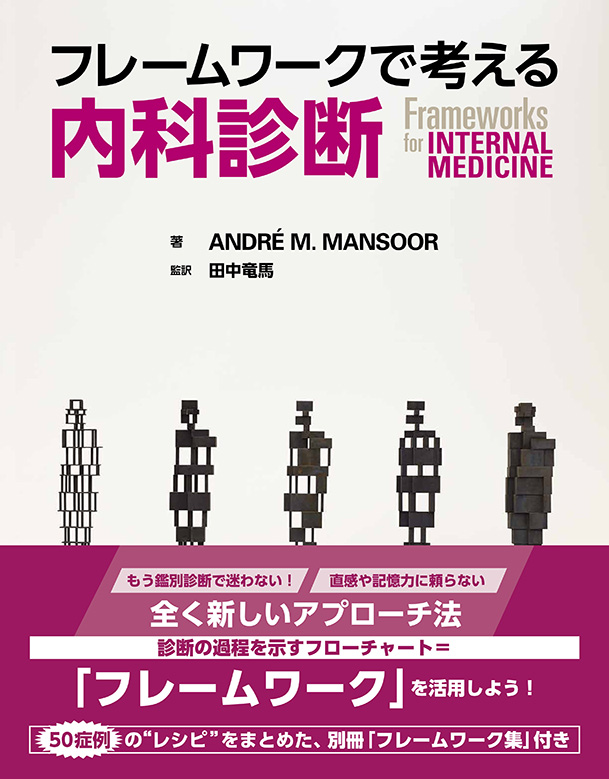
フレームワークで考える内科診断
-
André M. Mansoor 原著
田中 竜馬 監訳 -
A4変型・頁676
定価:9,130円(本体8,300円+税10%) MEDSi
https://www.medsi.co.jp
-
André M. Mansoor 原著
《評者》 岩田 健太郎 神戸大大学院教授・感染治療学
フレームワークで考え「ろ」,内科診断
世の中には2種類の人間がいる。何でも「2種類」に分類したがる人間と,そうでない人間だ。
ぼくは前者である。「胸痛」患者がいれば,「心原性」と「非心原性」に分けずにはいられない。消化管出血なら「上部」と「下部」に分けずにはいられない。まあ,貧血のように「大」「中」「小」と3つに分けることもあるけれども,とにかく問題をざっくり大きくくくらなければ済まないタイプである。
理由は簡単だ。記憶力が悪いからである。50を過ぎて「天命を知る」どころか,ますます記憶力も理解力も落ちていく一方である。不明熱の原因を何百もリストアップできるかよ,とついつい考えてしまう方である。
だから,ぼくの頭の中はフレームワークでできており,診療は「こっちか? そっちか?」を常に患者に問いながらアプローチしている。よって,本書『フレームワークで考える内科診断』は大好物だ。そうそう,こうやって患者にアプローチしていけばいいんだよ,っとふに落ちる構成,展開になっている。
ぼくのように記憶力が日々退化していなくても,網羅的に鑑別診断を検討する医師は多くない。勉強してないから,忙しいから,疲れちゃったから。理由は多々あろうが,「貧血」で止まってしまい,鉄剤を出したり,「低カリウム」で止まってしまい,カリウムを投与したり,「発熱」で抗菌薬をGo! となったりする。もちろん,ぼくらの多くは勉強不足で,忙しくて,疲れているので同情はするけれども,そこで止まってはならない。行き着くところまで行かねば「診断」ではない。
だから,フレームワークだ。診療現場で多く遭遇するような問題を「ざっくり」2つに大別する。その後,さらに分けていく。そうやってバッサリ,バッサリ切っていくうちに,最終診断に行き着くというわけだ。全ての訴えに対する全ての鑑別診断を網羅的に記憶しておく必要はない。
だから,本書は,極言を恐れずに言えば,「流し読む」本だ。もちろん,著者や訳者は「一字一句,こぼさず,丁寧に読み込まんかい」と思うに決まっているのだが,まずはざっくり診断に行き着く道具と割り切ったってよい。そうやって何度も何度も行きつ戻りつ道具として使いこなしたら,例えば医学教育に応用したっていいだろう。そのとき,611ページ以降の「チョークトーク」のセクションを精読するチャンスにもなるだろう。本書はもともと,効果的な医学教育がきっかけとなって生まれたのだから。
それにしても,本書の守備範囲は非常に広い。守備範囲狭めな大学病院に身を置いていると,クラクラするような幅広さだ。よって,本書はそこそこ,大きく,重い。こういうコンテンツ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。