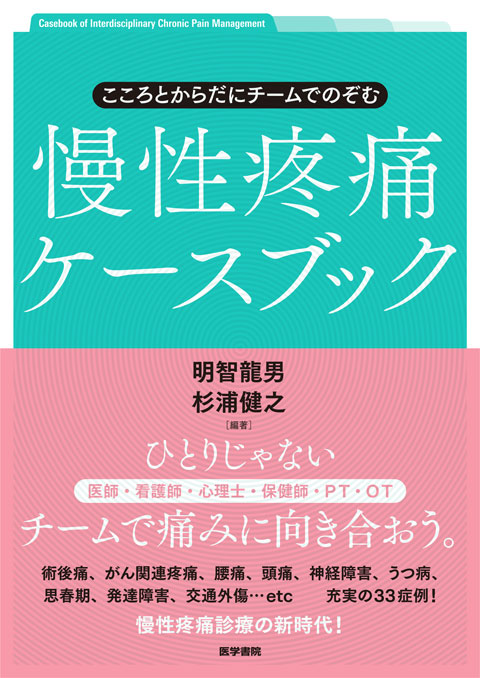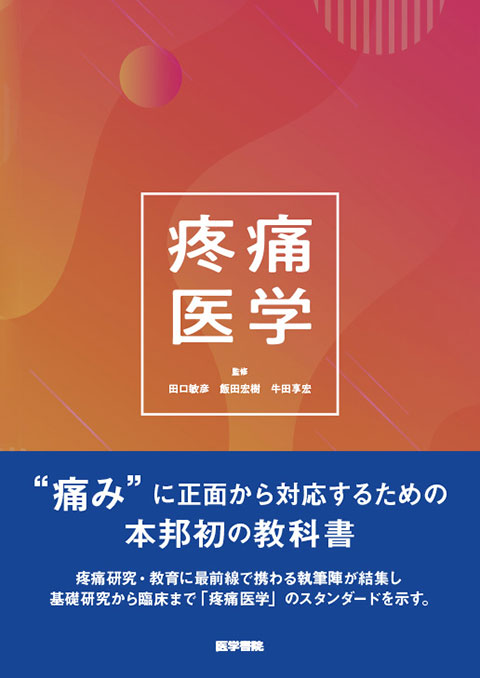慢性痛対策に多職種介入が必要な理由
寄稿 杉浦 健之
2021.08.23 週刊医学界新聞(通常号):第3433号より
さまざまな要因によって修飾される痛み
興味深いことに,社会学・人類学的に痛みの閾値には民族的な差異があるとされている。この事実を裏付けるかのように,痛みの受容器(Transient Receptor Potential Vanilloid 1:TRPV1)やオピオイド受容体(Opioid Receptor,Delta 1:OPRD1)の遺伝子多型には民族的な差が見つかっており1),痛みの感受性の民族間における違いの説明に十分な生物学的証拠を与えているかもしれない。
もちろんわれわれの体験する痛みの本質が,単なる侵害受容神経の興奮だけで規定されるほど単純でないことはご存じの通りだろう。ニューロ・マトリクス理論2)としてよく知られた概念で一部説明されるように,痛み認知機構は性別・個人の遺伝的構成に加え,現在の身体状況,これまでの経験,事前学習,期待・気分など多くの生物学的・心理学的要因によって大いに修飾される。
さらに痛み認知は,社会文化的環境にも大きな影響を受ける。ヒトは社会生活やその成長過程で痛みについて学んでいく。例えば「男の子なんだから痛くても辛抱しなさい」と親に言われ続け,痛みを感じた時の対応(辛抱・忍耐)を学んできた日本人は多い。その結果,痛みに対する忍耐力が身につき,日本には「痛みの表現を辛抱する文化」が作り上げられてきたと思われる。痛みに関するインターネット調査でも,自身の長引く痛みに対して,「痛みがあってもある程度,我慢するべきである」と考えている人が66.6%もいたことが報告されている3)。
40年ぶりに更新された痛みの定義4)では,痛みのさまざまな特徴(=多面性)を付記することで,感覚かつ情動の不快な体験である痛みの本質を端的にとらえている。定義の中では,痛みを感じた患者の訴え自体を重視することが強く求められ,痛みは極めて個人的な体験であること,思っている以上に生物学的,心理的,社会的要因によってさまざまな程度で影響を受けること,言葉だけでなく他の疼痛行動としても表出することが明記されている。もともと痛みは適応反応の役割を担っているわけであるが,その一方で身体・精神面の健康に悪影響を及ぼすこともあり,積極的な治療の対象となる。
標準的治療では歯が立たない慢性痛も一定数存在
痛み診療を専門とするペインクリニックでは,薬物療法,神経ブロック,脊髄刺激や手術療法などの専門的手技による治療が行われている。休職を余儀なくさせる腰痛,電撃痛を誘発するため会話や食事が全くできなかった三叉神経痛,長年ADLを低下させていた頭痛,これらの痛みから解放されQOLの改善につながった患者は多い。しかし,治療法が進歩してきた今の時代ですら,標準的治療に反応しない患者が一定の割合で存在する。こうした患者に出会い,「生物学的モデル」による治療の限界を感じている医療者も少なくないだろう。重篤な神経障害性疼痛,精神疾患,全身痛の代表である線維筋痛症,非特異的腰痛症,舌痛症など,いまだ病態解明が困難なものから画像検査などでは評価できないストレスや不安要因により増悪している機能的疾患の痛...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

杉浦 健之(すぎうら・たけし)氏 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野 疼痛医学部門 教授
1993年名市大医学部卒。同大病院で研修を開始し,麻酔・集中治療・ペインクリニックに従事。米アイオワ大への留学を経験後,名市大医学部講師,准教授を経て2018年より現職。同大病院いたみセンター長を兼務。専門分野は麻酔科学,疼痛医学。編著に『慢性疼痛ケースブック』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。