「プロの内科医」になる準備をしよう
日米の内科専門研修の対比から見えてきたこと
対談・座談会 筒泉 貴彦,山田 悠史
2021.04.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3416号より
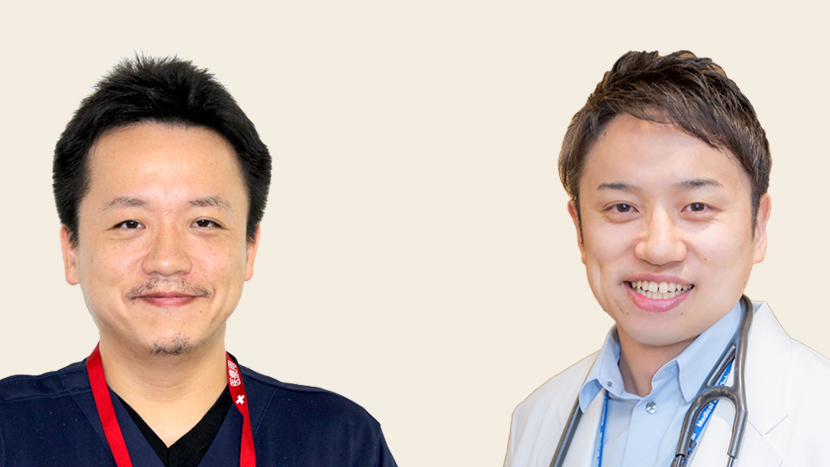
2018年の新内科専門医制度のスタートから3年。今年7月,ついに第1回内科専門医資格認定試験が実施される。「プロの内科医」をめざすために試験突破が重要なのはもちろんだが,その準備過程である内科専門研修では何を意識し日々の研鑽に励めばよいのだろうか。先ごろ,全国のトップ指導医を執筆陣に迎えた『THE内科専門医問題集1【WEB版付】』『THE内科専門医問題集2【WEB版付】』(いずれも医学書院)が上梓された。日米双方の内科専門医資格を有し,同書のチーフエディターを務めた筒泉氏,山田氏との対話を通じてその答えを探っていきたい。
筒泉 近年,内科志望の医師が徐々に減少していることを肌で感じます。理由の1つには見通しが定まらない新専門医制度の影響もあるのかもしれません。良かれと思い新制度が開始されたものの,その理念や具体的な方策が若い世代に十分に伝わっていないのではないかと考えます。
山田 おっしゃる通りです。今年7月には新しい内科専門医試験が実施されることもあり,これを内科医を育成する体制の見直しのチャンスととらえるべきです。
筒泉 日本の内科は今まさに岐路に立っていますよね。新内科専門医制度が理念として掲げる,「標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な知識と技能を習得する」ための具体的な取り組みを考えなければならないでしょう。
日本の内科専門研修の強みとは
山田 筒泉先生は,日本での臨床研修後,米ハワイ大学で内科レジデントとして研修されています。2012年に帰国後は練馬光が丘病院にて内科レジデントプログラムディレクターを務めるなど,現在は専攻医に教育を提供する立場としてご活躍中です。日米で内科専門研修を受けた経験からわかる,「日本の強み」を教えてください。
筒泉 良い意味で臨床教育システムが緩やかなことですかね。米国ほど厳密な教育体制が整えられているわけではなく,若いlearnerが追い詰められにくい環境だと感じます。
山田先生も,米国の教育病院であるマウントサイナイベスイスラエル病院にて内科レジデントとして臨床留学をされていたと思います。日米での教育内容の違いをどのようにとらえていますか。
山田 米国ではカルテ記載や,プレゼンテーションの教育に力点が置かれている印象です。これらの技術は大きく上達する一方,ベッドサイドで患者を診る時間が限られてしまうのは難点と言えます。日本にいた頃のほうが,ベッドサイドで過ごす時間は長かったです。
筒泉 ベッドサイドでの教育は,患者との対話を通して,医学知識にとどまらないマナーやプロフェッショナリズム等を学ぶ機会の創出となるため,可能な限り取り入れたいポイントですよね。
山田 ええ。それに米国の内科専門研修はどこか分断されたイメージがあります。例えば研修体制で言えば,6週間入院病棟で研修し,その後2週間外来研修に励むという「6+2」と呼ばれるシステムがスタンダードです。外来研修であれば外来のみ,病棟研修であれば病棟のみと,セクションごとでの研修が行われます。それに伴い指導医も頻回に変更となります。
日本の場合は,単一施設で比較的長期にわたる研修を受けます。担当患者を外来でフォローし,入院した際には自分で受け持てるために,患者に施される医療の流れを追うことができます。指導医の変更もほとんどなく,二人三脚で成長していくのが特徴です。診療・教育の継続性は日本の良さと言えるかもしれません。
筒泉 そうですね。ただ最近の日本の研修体制は,米国式に近づいている向きがあります。
山田 どのような点からそう感じるのでしょうか。
筒泉 冒頭に言及した新内科専門医制度です。同制度では広範な分野を横断的に研修し,さまざまな疾患の経験を積むことが求められています。内科医としての見識を広げるためには有用な取り組みだとは考えますが,例えば血液疾患などは容易に経験しづらい施設もあり,到達目標にある疾患のリストを埋める目的で複数の診療科をわたり歩く専攻医が現れ始めました。結果,初期研修のスーパーローテーションに似た研修生活を再度送る事態が発生しているのです。
山田 つまり,これまで日本の良さとして考えられてきた,自分の希望の診療科で師と共に成長していくスタイルの研修方法が変化しつつあるわけですね。
筒泉 その通りです。日米どちらの研修スタイルにも一長一短があるため優劣を付けることは一概にできませんが,今後,あらためての評価が必要な部分となるでしょう。
個々の施設や人材に教育が委ねられることのリスク
山田 では実際,臨床留学からの帰国後に教育者として指導に当たる中で,気付いた課題はありましたか。
筒泉 特に感じたのは,米国における研修体制がいかに恵まれていたかという点です。研修プログラム通りカンファレンスに出席しプレゼンテーションを行う日常を過ごせば,一定水準までは自然と成長できる体制ができあがっていました。もちろん,山田先生が指摘した「分断」というマイナス面はあるものの,アウトカムを重視した効率的な教育体制には見習うべきポイントが数多く存在します。
山田 米国卒後医学教育認定評議会(ACGME)を中心に進められる教育内容の標準化は,目を見張るものがあります。現在,さまざまな州の施設で研修を経てきた医師と共に勤務をしていますが,プロフェッショナリズムやタイムマネジメントなど必要最低限のスキルセットを全...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

筒泉 貴彦(つつみ・たかひこ)氏 高槻病院総合内科 主任部長
2004年神戸大医学部卒,同大病院にて初期研修。淀川キリスト教病院,神戸大病院での後期研修を経て,09年より米ハワイ大内科レジデントプログラムに留学。12年に帰国後,練馬光が丘病院にてプログラムディレクターとして総合診療科の立ち上げ,15年には明石医療センターの総合内科の立ち上げに従事する。17年より現職。総合内科専門医,米国内科専門医,米国内科学会上級委員。編著に『総合内科病棟マニュアル』(MEDSi),『THE内科専門医問題集1【WEB版付】』『THE内科専門医問題集2【WEB版付】』(いずれも医学書院)。
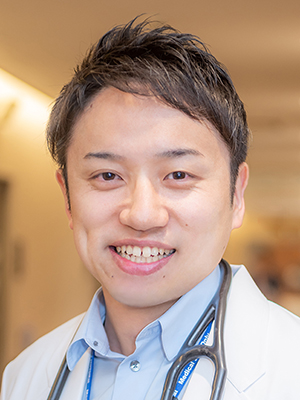
山田 悠史(やまだ・ゆうじ)氏 マウントサイナイ医科大学 老年医学科フェロー
2008年慶大医学部卒。東京医歯大病院にて初期研修修了。川崎市立川崎病院総合内科,練馬光が丘病院総合診療科を経て15年に渡米。米マウントサイナイベスイスラエル病院にて内科レジデントとして勤務する。18年埼玉医大病院総合診療内科の助教として帰国した後,20年に再度渡米し現職。総合内科専門医,米国内科専門医。編著に『総合内科病棟マニュアル』(MEDSi),『THE内科専門医問題集1【WEB版付】』『THE内科専門医問題集2【WEB版付】』(いずれも医学書院)。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![THE総合内科ドリル [WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2216/1526/4200/108324.jpg)
![THE内科専門医問題集1 [WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8316/1760/9929/108322.jpg)
![THE内科専門医問題集2[WEB版付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1616/1760/9930/108323.jpg)