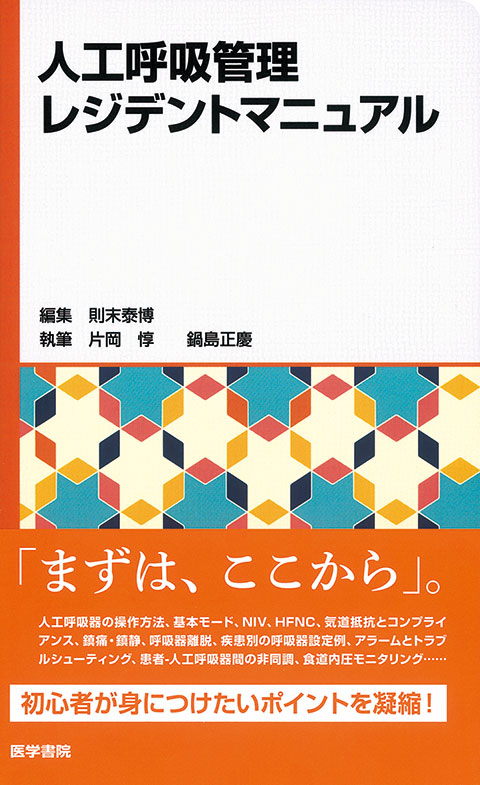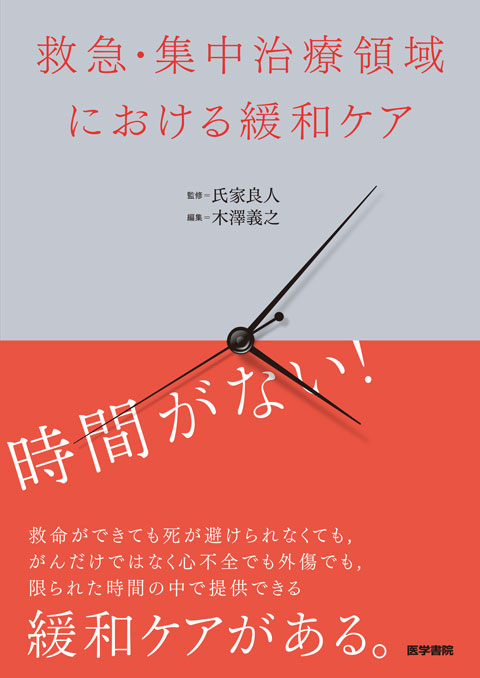救命に必要な医療資源が枯渇した場合の対応
現場任せではない,客観性と透明性のある指針の策定に向けて
寄稿 則末 泰博
2021.02.15 週刊医学界新聞(通常号):第3408号より
現在,国内で新型コロナウイルス感染症(以下,コロナ)が猛威を振るっており,本稿を執筆している2021年1月時点において,収束の兆しは全く見えていない。人工呼吸器が必要な患者を受け入れられる集中治療室の病床数は不足し,例えば高齢者施設からの重症患者の入院依頼を断らざるを得ない状況が各地の施設で発生している。いわゆる「命の選別」が現実的に行われ始めているのが現状である。
救命に必要な医療資源が枯渇した場合の判断
人工呼吸器,集中治療室の病床,重症患者を治療する人員など,救命に必要な医療資源が枯渇した場合に,現場の医療従事者はどのような判断をすればよいのか。マスコミでよく使用される「命の選別」という言葉は,その言葉自体に「患者に優先順位を付けることは悪である」というニュアンスが含まれているように感じる。しかし私たち医療従事者は,患者の優先順位付けを完全に放棄できるのであろうか。
現場で治療に当たっていればすぐに気が付くことであるが,医療現場では「判断をしないこと」自体が1つの判断となる。例えばコロナにかかわらず何らかの理由で呼吸不全となった,人工呼吸器なしでは死亡してしまう18歳の患者を考えてみる。隣のベッドに,人工呼吸器を継続しているものの救命できる可能性が極めて低い85歳の患者がいた場合,人工呼吸器が枯渇した状況であったらどうするか。「命は誰にとっても平等」,さらには「人工呼吸器を止めることは殺人である」という価値観の下に85歳の患者の人工呼吸器を止める判断をしないことは,「先着順」という優先順位に基づいた配分原則に従って18歳の患者を救命しない判断をすることであり,その結果には責任が伴う。すなわち医療資源が枯渇した医療現場では,その善悪にかかわらず患者の優先順位付けを放棄できないと言える。
現場の個人に決断させることの弊害
この決断を現場の個人に任せた場合に起こり得る弊害の一部を考えてみたい。第一に判断の客観性の問題である。現場の医師が「高齢者は優先順位が低い」という価値基準をたまたま持ち合わせていたとする。その場合,若者と同様に人生を元気に楽しんでいた70歳代の高齢者よりも,救命できないか,救命できたとしても生命予後が1年未満であることが予想される50歳代の末期心不全患者が優先されるかもしれない。次に透明性の問題である。著名人の患者,政治的に力を持つ患者,裕福な患者,院内でパワーバランス的に強い主治医や主科の患者などが秘密裏に優先されることがあるかもしれない。
最後は現場の医療従事者の倫理的苦悩の問題である。「ある患者の命を救うためにもう一人の患者の命を諦める」という過酷な意思決定と,その決定の家族への伝達を完全に現場に任せた場合,ただでさえパンデミックにおける治療によって疲弊している医療従事者は,倫理的苦悩によりバーンアウト症候群を起こす可能性がある。実際,コロナ第一波のイタリアでは,優先順位が低い患者の人工呼吸器を止める判断をした医師が泣いている様子が報道され,世界的に問題の深刻さが伝えられた1)。
これらにより,現場の医療従事者が判断のよりどころにできる客観性および透明性のある指針の重要性が国際的に認識されている2~4)。
患者の優先順位付けのためのいくつかの原則
それでは,「先着順」以外に患者の優先順位を決定する原則には何があるのだろうか。この問題について日本のはるか先を走るのが米国である。米国では2009年に大流行した鳥インフルエンザ(H1N1)の教訓から,国民...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
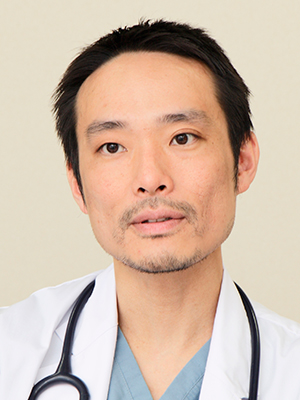
則末 泰博(のりすえ・やすひろ)氏 東京ベイ・浦安市川医療センター救急・集中治療科/集中治療部門部長・呼吸器内科部長/センター長補佐
1996年慶大文学部心理学科卒後,東邦大医学部へ進学。2004年沖縄県立中部病院にて初期研修,06年より米ハワイ大内科レジデント,09年米セントルイス大にて呼吸器内科・集中治療科フェロー。12年に帰国し現職。著書に『人工呼吸管理レジデントマニュアル』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。