患者の語りから医療者は何を学ぶのか
「健康と病いの語りデータベース」を,対話を通じた意思決定支援に生かす
寄稿 佐藤(佐久間) りか
2021.02.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3407号より
2021年は,G. Guyatt氏が「エビデンス・ベイスト・メディスン(EBM) 」という概念を,米国内科学会(ACP)が発行する『ACP Journal Club』に発表してから30周年に当たります。さらにEBMを補完する概念として「ナラティブ・ベイスト・メディスン(NBM)」がT. Greenhalgh氏らによって提唱されてから23年目を迎えました1)。
「EBMとNBMは車の両輪」としばしばいわれてきましたが,新型コロナウイルス感染症の到来により,その両輪のバランスが崩れそうになっています。数理モデル(その有用性を否定するものではありません)によって統計的に処理され脱人格化された患者さんの声は,マスクや防護服にも隔てられ,医療者により一層届きにくくなっています。このような時代だからこそ,あらためて医療者にとっての「ナラティブ」の意味を考えてみたいと思います。
病いや障害の当事者の語りをデータベース化
認定NPO法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」は,英オックスフォード大で厳格な質的調査手法を用いて健康体験を収集・分析する研究グループ,Health Experience Research Group(HERG)が開発した,患者体験のデータベースであるDatabase of Individual Patient Experiences (DIPEx)をモデルに日本版を構築し,社会資源として活用していくことを目的に2007年に発足しました。
以来,乳がん,前立腺がん,認知症,慢性の痛み,クローン病といった病いの当事者や家族,あるいは大腸がん検診,臨床試験・治験などの医療的介入の経験者,さらには障害がありながら高等教育機関で学んだ方々など,約350人にお話を伺ってきました。インタビューを通じて集められた,500時間超の「語り」は全て文字起こしされ,ご本人のチェックを経てアーカイブに収められています。
その一部を,疾患あるいは医療や障害の体験ごとに質的な分析を行ってデータベース化し,インターネット上に公開したものが「健康と病いの語りデータベース」です(写真)。誰でも自由にアクセスできるこのウェブサイトでは,映像(一部は音声・テキストのみ)を通して当事者の語りに触れることができます。診断の受け止め,治療の選択,日常生活の工夫,周囲に理解を求め合理的配慮を得る方法など,体験した方にしか語れないこと,体験したからこそ伝えたいことを知ることができるようになっています。
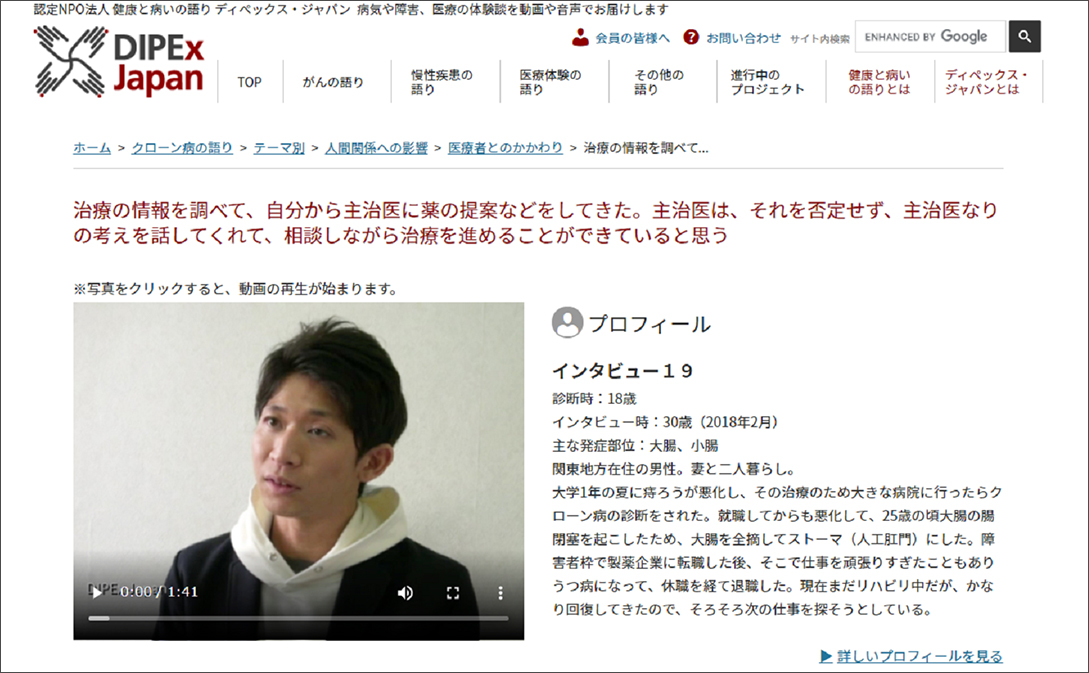
ウェブサイトでは,患者の診断時の思いや治療法の選択,副作用の経験などが,映像や音声,テキストを通じて語られる。
このウェブサイトの主たる目的は,語り手と同じ立場にある患者さんや,障害を持つ方とその家族が直面するであろう不安や苦痛,生活上の困難,社会的障壁と向き合うための知恵と勇気を提供することにあります。最新医療に関する専門知ではなく,生活者の経験知を社会的な資源として共有することが,私たちのめざすところです。当事者の経験知をデータベース化してウェブサイト上に公開すれば,同じ立場の当事者たちがそこから...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

佐藤(佐久間) りか〔さとう(さくま)・りか〕氏 認定NPO法人 健康と病いの語りディペックス・ジャパン事務局長
1982年東大文学部心理学科卒。91年米ニューヨーク大大学院アメリカ文化科修士号,2008年米プリンストン大大学院社会学科修士号取得。07年4月より現職。「健康と病いの語りデータベース」を活用した書籍『患者の語りと医療者教育――“映像と言葉”が伝える当事者の経験』(日本看護協会出版会)の刊行,教育プログラムの開発を行う。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
