MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.05.25
Medical Library 書評・新刊案内
安永 悟 著
《評者》栗林 好子(東京医療保健大助教・看護学)
協同学習やLTDのポイントが端的にまとまった実践書
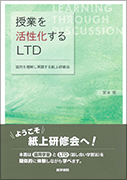 本書はLTD(Learning Through Discussion:話し合い学習法)に長年取り組んでおられる安永悟先生の著書です。協同学習に依拠したLTDの理解のため,本書前半は基本的な協同学習の活動(内容や手順),後半はLTDの活動について書かれています。特徴的なのは,紙上で研修会を再現して構成されていることです。
本書はLTD(Learning Through Discussion:話し合い学習法)に長年取り組んでおられる安永悟先生の著書です。協同学習に依拠したLTDの理解のため,本書前半は基本的な協同学習の活動(内容や手順),後半はLTDの活動について書かれています。特徴的なのは,紙上で研修会を再現して構成されていることです。
本書を読みながら,以前に著者が講師をお務めになった研修会(協同学習ワークショップ〈ベーシック〉)に参加したことを思い出しました。その研修会が私の協同学習にかかわるきっかけになったのですが,正直に言うとその時の研修会はやや不消化に終わっていました。これは著者自身も本書の中で語っていますが,研修会では対象の人数やレディネスを考慮し,内容や方法も吟味した上で,限られた時間の中で伝える内容を絞っていくため,伝えたいことを全て盛り込むことはできず,研修会はきっかけにすぎないと割り切ることもあると。このような研修会の持つ時間的制約と物理的制約が,研修会で私が感じた不消化の要因になっていたのだと思います。
しかし,本書においては著者の協同学習・LTDに関して伝えたい内容が,存分に盛り込まれていると感じますし,それらが体系的かつ系統的にまとめられて大変わかりやすくなっています。あの時,本書があったなら……と少々悔しい思いさえする内容でした。また,本書の約半分を占めるLTDについては,私自身の実践経験がなくこれまで理解不十分な点が多かったのですが,本書を読み進めながら紙上のLTD研修に参加する中で,協同学習の技法とのつながりとともに,LTDを支える理論(ブルームの教育理論)とLTDの実践のつながりを容易に理解できました。
これは,読者を研修参加者に見立てて紙上で研修会を再現するという一見突拍子もない“紙上研修会”の構成が,実際の研修会で行われている研修方法と同様に,実践と理論の関係が理解しやすい画期的な研修受講方法(実際は読書なのですが……)になっている結果だと思います。さらに,研修会などで理解に時間を要する内容について「もう一度説明してほしい」「聞き逃した」ということはよくあります。そのような場合でも,本書の“紙上研修会”では「読み返す」という行為で簡単に解決でき,内容の理解を深めていけるのではないかと思います。
協同学習やLTDの学習をする人にとって,端的にポイントをまとめている本書が理解を容易にすることは間違いないと思います。また,協同学習・LTDの理論や技法だけでなく,著者の授業づくりにおける秘訣など,参考になる内容がColumn(コラム)や脚注に書かれており授業運営にも大いに活用できると思います。
ただ,協同学習やLTDを実践するにあたり,「知っている」と「できる」は違うということを日々実感している私としては,紙上ではないリアルな研修会への参加が,より本書の理解を促すのだろうなとあらためて思っています。
B5・頁168 定価:本体2,400円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03941-3


片田 範子 編
《評者》濱田 米紀(兵庫県立こども病院看護部・小児看護専門看護師)
こどものセルフケアをとらえる拠りどころとなる書
 「こどもは生きる力(生きている力と生きていく力)を持っている」「こどもは,自らを発達させることができる」――こどもセルフケア看護理論の根底に流れるこどもの力を信じる強い思いは大変魅力的である。この理論は,オレムのセルフケア看護理論を基盤とし,「こどもを主体とする看護実践」をめざして構築されている。従来,こどもは発達途上にあるがゆえに,その未熟性に焦点が当てられ,「何かをしてあげる」対象として見られる傾向があった。しかし,日々こどもの力を目の当たりにしている看護師としては,こどもをセルフケアという視点でとらえることの重要性を感じている。
「こどもは生きる力(生きている力と生きていく力)を持っている」「こどもは,自らを発達させることができる」――こどもセルフケア看護理論の根底に流れるこどもの力を信じる強い思いは大変魅力的である。この理論は,オレムのセルフケア看護理論を基盤とし,「こどもを主体とする看護実践」をめざして構築されている。従来,こどもは発達途上にあるがゆえに,その未熟性に焦点が当てられ,「何かをしてあげる」対象として見られる傾向があった。しかし,日々こどもの力を目の当たりにしている看護師としては,こどもをセルフケアという視点でとらえることの重要性を感じている。
本書は,「第1章 こどもの力を引き出す看護を創り出すために」「第2章 こどものセルフケア」「第3章 こどものセルフケア不足」「第4章 こどもへの看護支援」「第5章 こどもと家族」と展開される。どの章においても,日本文化や社会に適した表現に工夫され,用語や概念が整理されている。また,具体的な場面や事例を挙げ丁寧に説明されているため,理解しやすく,活用につながる。「第6章 こどもセルフケア看護理論の活用事例」では,発達段階ごとに,この理論を実際に活用した事例が掲載されており,より具体的に身近なものとして理解できる。さらに,「付章 こどもセルフケア看護理論の構築に向けた取り組み」には,理論構築のプロセスが詳細に示されており,その道筋を知れることはとても興味深い。
子どものセルフケアは,親の影響が強く,どのようにとらえるとよいのか難しいところがあったが,この理論では,セルフケアを「卵の図」で表現してあり,複雑なこどもと親のセルフケアの状況を容易にイメージできる。また,「こどもセルフケア看護のアセスメントと計画策定の枠組み」がシート(表)として示されていることで,情報収集からアセスメント,看護デザイン・計画策定,評価までを整理し共有しやすくなっている。
この理論は,さまざまな臨床の場で...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2025.12.09
-
寄稿 2026.01.13
-
2026.01.13
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
