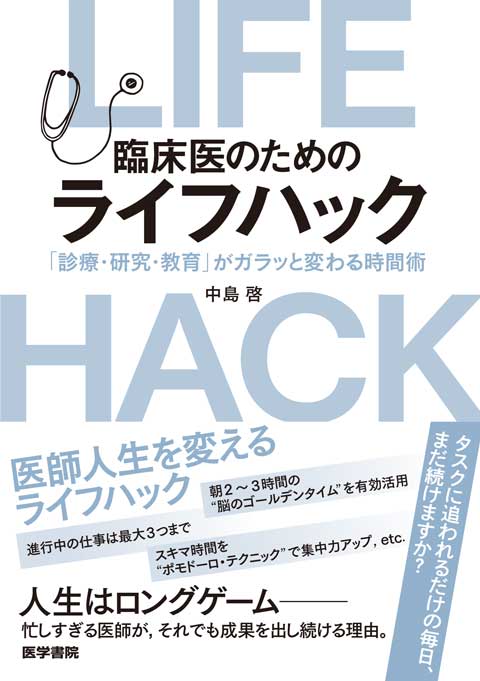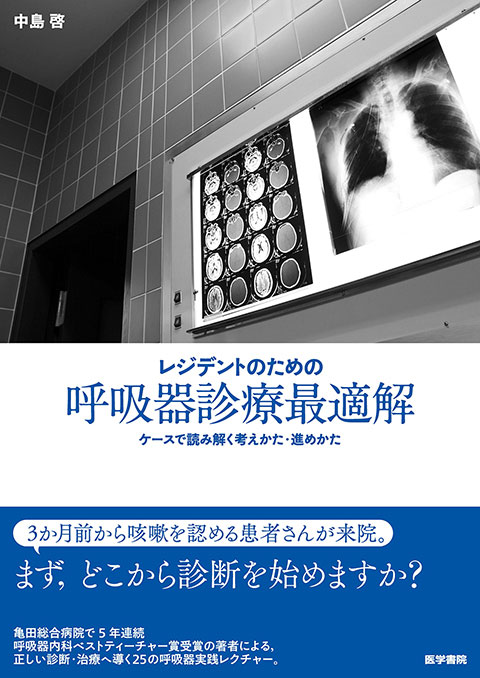三位一体で考える臨床×研究×教育
対談・座談会 宮本 篤,中島 啓
2020.04.13
【対談】三位一体で考える臨床×研究×教育 | |
|
| |
|
臨床,研究,教育。それぞれの分野でスペシャリストとして活躍する医師は数多く存在します。では,「この3つの要素をジェネラルに実践できていますか?」と問われたらどうでしょう。業務の忙しさなどを理由に,いずれかをおろそかにしてしまっていることもあるかもしれません。
「よき臨床から,よき教育と研究が生まれます。よき研究から,よき臨床や教育も生まれます」。臨床,研究,教育の3要素を意識して診療に励む呼吸器内科医の中島氏は,近著『レジデントのための呼吸器診療最適解――ケースで読み解く考えかた・進めかた』(医学書院)の中でこう述べています。三位一体の取り組みを進めるにはどのような考え方が必要なのでしょうか。中島氏と同じ志を持つ宮本氏が,臨床・研究・教育全てに臨床医が携わることの意義を議論しました。
中島 宮本先生が初めて研究発表をしたのは医師になってどのくらいの時期でしたか。
宮本 研修医1年目の秋です。循環器内科で研修をしていた頃でした。寝る間を惜しんで作った発表スライドは,「宮本篤」と書いた名前以外の全てにおいて指導医の添削が入っていましたね(笑)。こうした体験は多くの医師に心当たりがあるでしょう。でも,それは一度チャレンジしてみないとわからないことですよね。
中島 まさにその通り。まずは何事も型を覚えることから始めなければなりません。私は,医師3年目に栄養剤に関する研究を発表したものの,緊張で発表内容が飛んでしまい,大恥をかいた苦い思い出があります。もちろん,フロアの誰からも質問は出ませんでした。
宮本 初めての経験は何も若手だけに訪れるというわけではありません。私自身,医師12年目で国際学会のシンポジストを任され,英語による発表を20分間行った際は,久しぶりにとてつもない緊張感を味わいました。誰しも新しい挑戦に失敗は付き物です。
臨床医が研究する強みとは
宮本 そもそも臨床医が研究を行う意義はどこにあると考えますか。
中島 自身が行ってきた日常診療における取り組みを,エビデンスとして世の中に発信することにあると思っています。昔から医学は,実診療から出た疑問を検証する形で進歩を繰り返してきました。そうした流れの中に身を置くことは臨床医として大きな意味を持ちます。また,臨床研究に取り組むことで,自身が普段行う診療が正しいかどうかを再評価するきっかけにもなります。
宮本 同感です。自分一人が対応できる患者数には限界があります。そこで,多くの患者さんにより良い医療を提供するために臨床研究を行い,その結果を発信していくことが重要になると思います。ただし,臨床研究を始めることと同じくらい論文を「正しく」読めるようになることも大切だと考えます。
中島 「正しく」とは,研究を行う背景まで読み解くということでしょうか。
宮本 その通りです。例えば「ある集団にAという介入をしたら,Bという新しい知見が生まれた」との論文があったとします。ここで「ふーん,そうなんだ」と,文字通りに解釈するだけで終わってしまっては,論文を正しく読めたとは言えません。さらに一歩踏み込んで,この論文が臨床現場に対してどのようなメッセージを持って発信されたのかを読み解く必要があるのです。その点,患者さんをたくさん診ている臨床医は,現場をイメージしながら論文を読み進められ,患者さんとのかかわりの中で論文の結果を確認できるので,読解力を高めやすい立場にあると言えるでしょう。
中島 臨床現場を知っていることは研究をする上で大きな強みになりますよね。それに加え,論文を読むことでまれな疾患を疑似体験できるのもメリットとして挙げられます。例えば,私が研究テーマの一つとするニューモシスチス肺炎を例に考えてみます。当院で本症を診療するのは年間10例程度。その中でも主治医となれるのはたった1~2例です。しかし,本症を後ろ向きに10年さかのぼってみると,70例程度の症例がピックアップでき,なおかつ詳細なカルテ記録から個々の症例を疑似体験できます。この貴重な経験は診断能力の向上に加え,治療方針の立て方にも影響を与えますし,クリニカルクエスチョンを生み出すきっかけになりやすい。
宮本 そうですね。臨床経験に基づく臨床研究が行えれば,たとえトップジャーナルに掲載されるような大規模な前向き研究でなかったとしても,「このアイデアなら世の中に必要とする読者がいる!」と,自信を持って研究に取り組むことができます。
1日の業務の中でアカデミアの時間をどう生み出すか
中島 では実際,じっくりと読み込む論文はどのように選んでいますか。われわれが専門とする呼吸器領域に絞っても,肺癌やCOPD,間質性肺炎,感染症などの多分野に分かれており,各分野で数え切れないほどの論文が日々発表されています。
宮本 おっしゃる通りです。恐らく多くの呼吸器内科医は全分野の論文に目を通せていないでしょう。もちろん私もその内の一人ですし,呼吸器領域に限った話でもないはずです。そのため最近は,個々人に特化した情報だけを追うなど,ある種の割り切りが必要だと考えるようになりました。私は,主な研究領域であるびまん性肺疾患の情報だけは院内の誰にも負けないよう,漏れなくチェックすることを心掛けています。
その一方で,学問的な視野を広げるためにも若手の頃はそこまで情報を選別する必要はないとも考えます。
中島 例えば専門医の取得に手が届きそうな5年目ぐらいまでの医師には,オールラウンダーとして一通りの知識は押さえていてほしいですよね。その上で,アドバンストな知識を有する分野を一つ持てれば,他はある程度知識量に差があっても構わないと思っています。
ちなみに宮本先生は1日の業務の中で論文をどのタイミングで読むことが多いですか。
宮本 専ら始業前の時間です。出勤して一度電子カルテを見てしまうと,患者さんのことが気になってしまうので,メリハリをつけるために朝8時までは電子カルテを開かないと決めています。
中島 なるほど。ですが,臨床をしているとどうしてもイレギュラーにイベントが入ってしまい,なかなか論文を読む時間を作れないこともありますよね。
宮本 ええ。アカデミアに充てる時間がなく1日が過ぎてしまうととても悔しい気分になります。ですので,その時間を何とか生み出そうと常に考え,読む時間ができた時には少しでも情報を得られるよう必死に読み込みます。その際に心掛けているのは,今後の研究に役立ちそうな結果や興味深い解析手法などがあれば,こまめにまとめておくことです。
中島 確かに論文を読むことで自分が研究する際の手法を学ぶこともできますよね。私も役立つ論文を見つけた時は,①論文の要約をEvernoteにメモ,②科内のジャーナルクラブで共有,③SNSを通じて情報発信,のいずれかをするように努めています。これらの作業をすると,自身の記憶にも残りやすく,他者の意見も取り入れられるので有意義です。 ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。