MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.02.10
Medical Library 書評・新刊案内
Edward Ellis III,Michael F. Zide 原著
下郷 和雄 監訳
《評者》飯村 慈朗(東京歯大市川総合病院准教授・耳鼻咽喉科学)
頭蓋顎顔面領域の手術アプローチ法に特化した良書
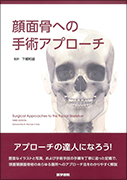 『Surgical Approaches to the Facial Skeleton』は,1995年の初版刊行以来,米国で頭蓋顎顔面外科を修める医師にとって教科書的な本となっている。本書は,その第3版(Wolters Kluwer, 2018)の日本語版である。本書の特徴は,解剖学に加え技術的要素を詳細に解説し,手術アプローチ法に特化している点である。きれいな良い手術は的確なアプローチから成り立つものであり,一つのアプローチ法しか知らないと対処できる部位は狭められ無理をした手術となってしまう。例えば耳鼻咽喉科医である私は,眼窩底骨折へのアプローチは内視鏡下経鼻内法もしくは経上顎洞法が主であった。しかし本書第2部に記載されている経眼窩法を行うと,驚くほど眼窩底骨折前方の処置が簡単であった。眼窩底後方の骨折に対しては内視鏡下経鼻内法のほうが処置しやすいが,前方に対しては経眼窩法のほうが格段に容易である。病変部位によってアプローチ法を変えることの重要性が実感できる。
『Surgical Approaches to the Facial Skeleton』は,1995年の初版刊行以来,米国で頭蓋顎顔面外科を修める医師にとって教科書的な本となっている。本書は,その第3版(Wolters Kluwer, 2018)の日本語版である。本書の特徴は,解剖学に加え技術的要素を詳細に解説し,手術アプローチ法に特化している点である。きれいな良い手術は的確なアプローチから成り立つものであり,一つのアプローチ法しか知らないと対処できる部位は狭められ無理をした手術となってしまう。例えば耳鼻咽喉科医である私は,眼窩底骨折へのアプローチは内視鏡下経鼻内法もしくは経上顎洞法が主であった。しかし本書第2部に記載されている経眼窩法を行うと,驚くほど眼窩底骨折前方の処置が簡単であった。眼窩底後方の骨折に対しては内視鏡下経鼻内法のほうが処置しやすいが,前方に対しては経眼窩法のほうが格段に容易である。病変部位によってアプローチ法を変えることの重要性が実感できる。
顔面骨格の手術においては,切開する際に顔の審美性,表情筋とその神経支配,感覚神経の走行を考慮しなければならない。そのため病変部位に対するアプローチ法は,引き出しが多いほうが良い。その点,本書はそれぞれの長所と短所を列挙し,ある特定のアプローチ法を推奨しているわけではない。各アプローチ法の長所と短所を理解した上で選択できれば,対処できる部位の幅が広がり,治癒率の向上につながる。そのため本書を頭蓋顎顔面領域の手術に携わる全ての外科医にお薦めする。本書を読めば,顔面骨格のあらゆる箇所に自信を持ってアプローチできるようになり,外科医としてランクアップするであろう。
さらに私は,本書を中堅以上の耳鼻咽喉科医にお薦めしたい。われわれ耳鼻咽喉科医は,鼻閉に対する手術として鼻中隔中央部を切除する術式を伝統的に施行してきた。そして外鼻形成術は鼻閉と関係のない話であり,形成外科医の役割と考えていた。しかし鼻という一つの器官は必要な鼻機能が外鼻形態を形成しており,鼻の手術を行う際には,機能的手術と形態的手術の両方をバランス良く治療することが望まれる。鼻外アプローチ(第7部)の手術手技が求められるようになり,現在では実際に施行する耳鼻咽喉科医も増えている。本書は,鼻外アプローチの手術手技に対しても解剖を基本に置いた上で,豊富なイラストと写真を使用し,丁寧に手術手技の手順を解説している。本書を理解することで鼻閉に対する手術の合併症を限りなく減らし,満足度の高い治療を行えるようになるであろう。間違いなく今後の外科医人生に役立つ良書であり,ぜひ読破することをお薦めする。
A4・頁272 定価:本体20,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03951-2


森本 義晴,太田 邦明 編
《評者》菅沼 信彦(京大名誉教授)
「高齢不妊治療」という臨床現場の最重要問題に答える
 近年の不妊治療において,体外受精をはじめとする生殖補助医療技術(ART)が発展し,多くの不妊患者に福音をもたらしていることは周知の事実である。日本においてもART出生児は年間5万6617人(2017年)に及び,少産化が進むわが国においては全出生児の17人に1人となっている。しかしながらARTによっても児を得られないカップルが存在する。その主たる原因が「高齢不妊」である。特に女性の加齢による卵子の質的・量的変化は著しく,臨床現場では苦慮する場合も多い。本書は「高齢不妊診療」に焦点を当て,基礎から臨床に至るまであらゆる問題点を考察し,まさに現在の不妊治療に必須の項目が網羅されている。
近年の不妊治療において,体外受精をはじめとする生殖補助医療技術(ART)が発展し,多くの不妊患者に福音をもたらしていることは周知の事実である。日本においてもART出生児は年間5万6617人(2017年)に及び,少産化が進むわが国においては全出生児の17人に1人となっている。しかしながらARTによっても児を得られないカップルが存在する。その主たる原因が「高齢不妊」である。特に女性の加齢による卵子の質的・量的変化は著しく,臨床現場では苦慮する場合も多い。本書は「高齢不妊診療」に焦点を当て,基礎から臨床に至るまであらゆる問題点を考察し,まさに現在の不妊治療に必須の項目が網羅されている。
まずは第1章の「高齢不妊診療のための基礎理論」において,加齢による妊孕性低下のメカニズムが統計を含め詳細に述べられている。一般臨床医にとっては見逃しがちな本質が明解に記載されている。続く第2章では,卵子提供も含む「高齢不妊診療の実際」が具体的に示されており,外来現場でそのまま役に立つ情報が満載である。さらに第3章は,本書の特徴ともいうべき「統合医療的アプローチ」が紹介されている。これまでの不妊治療専門書では,サプリメントなどの解説は僅少であったが,実際に患者さんが服用している場合も多く,その説明に非常に役立つ。また第4章の「ケーススタディ」は,このパートのみを読んでも日々の臨床症例として興味深い。
本書は多数の著者により執筆されているが,各領域の専門家が自らの分野を深く詳述している。しかしながらその内容は決して難解ではなく,臨床現場に従事する者にとっても十分に理解できる。それは多くの図表が駆使され,一見による認識を可能にしているためであろう。その点からは医師のみならず,不妊診療に携わる他の医療者にとっても有用である。さらに各単元に置かれた文献の多さにも目を見張る。それはエビデンスに基づく記載を保証するのみならず,さらなる情報の検索にも有益であろう。同時に,著名な執筆者の本音とも言うべき「コラム」は,一服の清涼剤のような味わいである。
このように本書は,高齢不妊診療における高度な医学的知識を供給するとともに,不妊診療専門医,産婦人科や泌尿器科の一般臨床医,研修医,胚培養士,看護師などにとっても読みやすく,重要な知識を享受できる名著である。
B5・頁392 定価:本体8,500円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03957-4


眼内腫瘍アトラス ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
